新しくイングランド王位についたウィリアム公であった。王は、雪で
覆われた目の前の大聖堂をジッと眺めていた。
王は、昨日の戴冠式の後で家臣達と祝宴を張り、葡萄酒を浴びる
ように飲んだが、平常通り暁に目覚めていた。強靱な体力と精神力
の持ち主である。深酒が熟睡を誘い、酔いは短時間で醒めていた。
(純白の大聖堂か・・・・エドワード王は良いものを建てられた。聖ペテ
ロの旗幟を掲げて海を渡って来た余が、聖ペテロに奉献されたこの
大聖堂で戴冠式を挙げ得たのも、何かの因縁であろう。それも、この
大聖堂の竣工一周年記念日である聖降誕祭の祝日に間にあったの
は、まったく幸運というべきか。それともハロルドを嫌っていたエドワー
ド懺悔王の導きか・・・・)
新王は、胸で十字を切って懺悔王の冥福を祈った。亡父ロバート公
の血を受けた冷徹さを持つウィリアム公であるが、妙に信心深い面も
あった。
「天の時、地の利、人の和」
ふと口をついて出たのは、師と仰ぐランフランク僧院長の言葉であ
った。
それにしても、戴冠式の最中に、まさか火事騒動が起こるとは予想
だにしていなかった。小さなボヤではあったが、一時は群衆が反乱で
も起こしたのではないかと心配した。これは杞憂であった。雪の中を
集った人々が暖をとっていた焚火が、近くの小屋に燃え移った事故だ
と報告を受けていた。
(あの程度の騒動で、まだしもましであったわ。むしろ、アングロサクソ
ン人達の大音声の方が、わざとらしく気にかかるな。国王万歳!など
と本心から大声で言える筈はない)
穏やかな朝の雪景色を眺めている所為であろうか、王に即位したと
いう感激と興奮はすっかり治まり、いつもの冷静さを取り戻していた。
動物的な直感力は抜群であった。
醒めた王の耳には、今でも群衆の熱気のない大喚声が、不気味な
海鳴りのように残っていた。
(侵略し征服した余に、国民が反感を持つのは当然であろう。しかる
に、いかにもわざとらしい昨日のあの大喚声は、何なんだ)
不安が消えなかった。ハッと思い当たるものがあった。
(うむ、あの群衆の中には、百姓商人共ではない面構えのものが多数
いたな。ボロを纏ってはいたが、確かに騎士や戦士の眼光だ。生き残
ったサクソン貴族の誰かの手の者達であろうか?くすぶる火種は早い
時期に、一つ一つ確実に消しておかねばなるまい。だが、この王宮で
は、この身が危ない。城が欲しいな。いや、城でなくともよい。砦のよう
なものでよいわ)
仄かに射しはじめた朝日を受けて、ウェストミンスター大寺院は、荘
厳さを増していた。
王は、大聖堂を凝視していた。
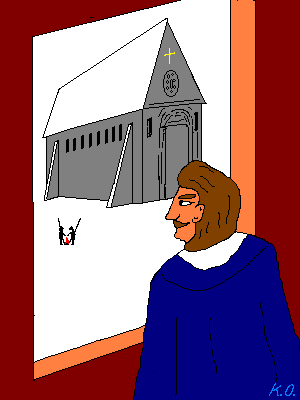
(そうだ!エドワード懺悔王は、この国にノルマン・ロマネスクの大聖
堂を建立し、神の恩寵の下に国家安康を祈念された。が、余は俗人
だ。ノルマンの名城を築き、世を治めよう。最初の城は、この地ロンド
ンに。それも、この雪を頂いた大聖堂のように、純白の塔を持つ城に
しよう)
王は、大聖堂の彼方に、未来の城をはっきりと描いていた。その想
いが、独り言となって出た。
「キープ(天守閣)は『ホワイト・タワー』(眞白き塔)と呼ばせよう。マチ
ルダを呼び寄せるのは、この塔が完成した時か・・・いや、それまで待
てぬな」
(よし、重臣会議を開こう)
ウィリアム王は、側臣ウォルターの部屋に通じる鈴の紐を、力いっぱ
い引いた。
次頁へ