お稲荷さんの思い出(絵:藤沼保夫君(白黒)、酒井(クレヨン))
1 わが家は”美の輪稲荷神社”前
私は次郎長で知られた清水で生まれた。私の家の近くには、次郎長の生家があるため次郎長通りと呼ばれる商店街がある。狭い道を挟んで魚屋と電気屋が向き合ったり、風呂屋の横に花屋があったり、くすり屋と駄菓子屋が軒を並べたり、意外なことに、本屋まであるといった、まあそのころ何処の町にもある商店街であった。次郎長通りと交わる幾つかの通りの一つに、入り口に大きな石の鳥居が立っている、次郎長通りより少し広い通りがある。鳥居をくぐって50mほど入った右側に清水でも一番大きな神社(と私が思っていた)美の輪(みのわ)稲荷神社、通称「お稲荷さん」があった。私の生家はそのお稲荷さんと道路を隔てた真向かいにあった。

なにしろ清水一(?)のお稲荷さんの真向かいにあるわが家であるから、いろいろと御利益があった。お前の家は何処だと聞かれたら「お稲荷さんの前だ」と答えれば良かった。それでも半信半疑でやってきた友達は「本当に真ん前だな」と感心することしきりであった。私が大学時代まで、わが家に金の催促でしか送らなかった父宛のはがきの住所も「静岡県清水市美の輪稲荷神社前」でよかった。
お稲荷さんの御利益は住所だけではなかった。終戦まぎわ、清水市はアメリカの潜水艦による艦砲射撃を受けた。この時お稲荷さんの本殿は直撃弾で滅茶苦茶に破壊された。別の一弾はわが家から3軒隣に落下した。しかしけが人は出ず、わが家はもちろん無傷(と思って)で終戦を迎えた。しかし戦後まもなく2階建てのわが家に雨漏れが見つかった。屋根に上った大工さんが瓦に突き刺さった砲弾の破片を発見した。その頃未だ生きていた祖母は、お稲荷さんの御利益だ、と会う人毎に(といっても大部分は同じ年頃のばあさん達であったが)吹聴していた。
お稲荷さんの境内は広くて我々悪童たちの格好の遊び場であった。正面の石段を上がると、赤い鳥居が拝殿に向かって3列にならんでアーケードを作っている。拝殿の奧に本殿があった。右手に広い社務所があって正月のお神楽などが広間で拝観できた。しかし何と言ってもお稲荷さんの思い出は
,これらの建物を囲む広い境内での出来事であった。思い出すままにその幾つかを書いてみた。2 オートバイ・サーカス
毎年3月14、15、16日の春の例祭にはさまざまな興業師による小屋掛けが境内を埋め尽くした。15日は小学校も臨時のお休みで我々悪童にとっても待ち遠しい日であった。祭りの興業の中でももっとも大がかりなものは、大きな樽の内側をオートバイが走り回るオートバイ・サーカスであった。観客は樽の縁に沿って作られた台から見おろすようになっていた。オートバイははじめゆっくりと樽の壁に沿って地面を回転しているが、やがて次第にスピードをあげながら、樽の内壁を回転しながら登り始める。
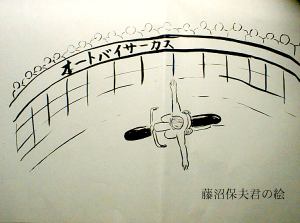
なにしろ垂直な壁をぐるぐる回っているのであるから、上から見ると信じがたい光景である。その内オートバイはさらにスピードをあげ爆音を発しながら内壁を登り始め観客に向かって迫ってくる。爆音と共に鼻をつく油の臭い、オートバイ乗りのダンディーな皮ジャンバーとゴーグルが空に飛び出していきそうに見える。始めてみたときは思わず息をのみ眼をつぶてしまった。気がつくとオートバイはスピードを下げやがて地面におりたち停止する。思わずほーと安堵の息を吐いたものである。
しかしこれで終わったわけではない。次は2台のオートバイが互いに反対方向に廻りながらの曲乗りを披露した。違う高さを保ちながら疾走するかと思えば突然斜めに走り出し壁を上がったり下がったりしながらすれ違うのであった。何時激突するか、爆音と油臭い煙のなかで息をのんで見守った。母が、均がまたうなされていたというのはそんな祭りの日の夜であった。
3 女相撲
オートバイの曲乗りが男の臭いとすると女相撲は私に女の臭いを嗅がせてくれた。若い女力士が腰巻き一枚ではっけよいと押し合いへし合うのである。当然もみ合いになると腰巻きがめくれ上がり
,太股やお尻が曝される。中にはわざと相手の腰巻きをまくる力士もいた。そんな光景を想像しただけで私はどきどきした。とうじの女性は胸を出すことにはそれほどこだわっていなかった。わが家のまわりでも夏の夜ともなると男も女も道ばたに並べた木の椅子で夕涼みを楽しんだ。男はふんどし一本、女は腰巻き一枚、上ははだけたままか薄い襦袢だけだった。しかしスカートめくりとなると別であった。自分より年上の女の子に興味があった。しかし年が上だけに、いざとなると反撃されて目的は達せないことが多かった。だから女相撲はどうしても見てみたかった。ここまで書いてきて、はてと疑問が生じた。実際に女相撲を見たかどうか確かな記憶がないのである。というのは成人してから、もちろん戦後であるが
,女相撲を主題とした映画かテレビドラマかを見た記憶があるからである。どんな内容であったか忘れたが、意地悪な女力士が主人公の若い女力士を負かすために腰巻きをめくりあげる、といったシーンがあったような気がする。

しかし女相撲がお稲荷さんお祭りの恒例の興業であったことは事実である。見た記憶がないのは、或いは小学生は入れて貰えなかったのかも知れない。
どうも考えれば考えるほど記憶があやふやなので、この駄文を小学校の同級生で今でもお稲荷さんの近くに住む藤沼保夫君こと、やっさんに送って彼の意見を聞いてみた。すぐに電話で返事が帰ってきた。女力士は上半身を白地の上っ張りのようなものでおおい、白地の短パンを穿いた上からまわしを付けていたという。私が想像したよりずっと健全で小学生も見ることが出来たという。やっさんが見たことがあるのは言うまでもない。
しかしやっさんでも見ていなかったものを、私が見ていたことも分かった。お祭りの間、女力士達は次郎長通りから鳥居をくぐって入ってすぐのそば屋に泊まっていた。そば屋の息子と仲がよかった私はそんなときは彼の家に押し掛けて、間近で女力士を見ることが出来た。ある日店先で女力士達の餅つきが行われた。横綱級の女力士のおなかに木の臼をのせ、若い力士達が餅をついて見物人に振る舞った。一見華やかではあったが、子供心にうら悲しい風景でもあった。もっとも、そば屋の名前は「朝日屋」(字に自信はない)、息子は我々と同級生であったことはやっさんから聞いた。
4 親の因果が子に報い
「親の因果が子に報い」という文句を覚えたのもお稲荷さんのお祭り興業であった。小屋の入り口の木戸番の口上が、恐いもの見たさの見物人をさそった。因業な親の祟りで、何やら得体の知れない子供が産まれた。親が恐れて殺そうと言うのを哀れにおもい、金を払って買い取ってきた、あわれな子を一目見れば因果応報の恐ろしさが分かる、といったような口上であった、と思うが余り自信はない。とにかく、なけなしの小遣いを払って入ると、10人も入らないような狭くて薄暗い小屋の中に水を張ったたらいがおいてあって、男がもったいを付けてふたを半分くらい開けて見せていた。気持ちが悪いので、そこそこに皆出ていく。私もちらっと見ただけだったが、平らな黒い色の魚とも、大きなかえるとも見える何かがいて、うごめいているようであった。しかしはっきりと見たのは、子供の手のひらのような二本の小さな手であった。
後年私は山陰に長く住み着くことになった。その地方の名物の1つに、”大さんしょう魚”があった。ある時近くの寺の池で飼われていた大さんしょう魚を見る機会を得た。あっと思った。あの時の親の因果で産まれた子供とは、正にこの大さんしょう魚であった。大さんしょう魚の手は4本の指を持ち、子供の手に良く似ていることをこの時初めて知った。いらい大さんしょう魚を見るたびに、気味の悪いあの見せ物小屋の得体の知れない臭いがよみがえるのであった。
5 忍術秘伝の巻
お稲荷さんのお祭りはまた私にとって、忍者の秘伝を授かる絶好の機会でもあった。私は子供の頃からチャンバラが大好きで、特に忍者にあこがれていた。指を十字に組み、呪文をとなえると、あら不思議どろどろドローンと消えてしまう。かとおもうと高い塀も軽々と跳びこえ目指す相手の屋敷に忍び込む。真田十勇士の猿飛佐助や霧隠才蔵はあこがれの忍者であった。もっとも私が忍者になりたかった理由は、何も武勇伝を立てたかったからではなかった。好きな女の子のスカートをまくったり、誰にも気付かれずに女風呂に忍び込んででやろう、などという他愛ないものであった。
お稲荷さんの祭りには、我こそは忍者の末裔であり、先祖伝来の秘伝の巻を譲ってもよい、という男が毎年のように現れた。私はもちろん絶対欲しかった。しかし彼は決して初めからこの秘伝の巻を店先に並べるわけではなかった。まず何か口上をのべ人が集まると、俺の気合いで彼処を歩いている男の足をぴたっと止めてみせるとか、近くの木の枝でさえずる雀をさして、あの雀を落としてみせる、などと見物人の気を引くのである。身ぶり手ぶりの話を聞いていると、今にも気合いが掛かって雀が落ちてくるのではないか、と期待にわくわくするのであった。
ある時はこんなことがあった。見物人の大人の一人が男の腕をとって「でたらめ言おうな」とすごんだ。彼は一瞬男の腕を握りエイと気合いを掛けた。と驚いたことに、その男の腕は忽ち硬直してしまった。呆然と立つ男に向かって男はまた気合いを掛けた。男が硬直が解けた腕をさすりさすり退散したのは言うまでもない。
彼はまた鉄で出来た火箸をとりだし、見物人の男に曲げて見ろと渡したが、もちろんその男が渾身の力を込めても曲がる様子はなかった。しかし彼が薄ら笑いを浮かべながら、火箸の中ほどを左手で握り、右手で軽く手前に引くと、火箸はあたかも飴のように易々と曲がってしまった。
こうして色々な秘伝を見せつけた後、彼は何やら後ろ手に隠し持ちながら、今までの技を書いた秘伝の書を今日は特別何々銭(円だったかな)で譲ることにした、早いもの勝ちで3人までだ、とかなんとか切り出すのであった。雀の落ちるのを待っている余裕はなかった。私はためらわず握りしめていた小遣いを渡した。彼は私を近くに呼び寄せ、薄っぺらな冊子を私の手に押しつけて言った、「うちに帰っても誰にも見せるなよ」
こうして手に入れた秘伝書は、黄色く変質した10pくらいの小冊子であったが、内容は私の期待を裏切るものではなかった。まず音もなく高塀を跳びこえるジャンプ力の鍛錬は、麻の苗を庭に植えることから始まった。育ちの早い麻の苗を毎日何回も飛び越えるているうちに、麻の苗の生長と共にジャンプ力がつくという原理であった。私はいたく納得して早速実行にうつした。もっとも麻の苗は手に入らず、何かあり合わせの若木ですませたようにおもう。毎日毎日同じことを繰り返すのは根気のいることであったが、忍者に近づく道はこれしかないと思って頑張った。しかし壁を飛び越えたという記憶がないところを見ると、何となく終わったのであろう。熱しやすく冷めやすいのは、いまも私の気質である。
これにくらべると、火箸を曲げる術は簡単に会得できた。当時何処の家もお風呂は薪で焚くことになっていた。私は母の目を盗んで風呂の釜焚き用の火箸を持ち出し、秘伝書に従って姿勢を正し真ん中を左手ににぎった。たんでんに力を入れ息を吐きながら、右手の平で火箸の上端をぐっと手前に引いた。なんと火箸がくの字に曲がったのである。びっくりしたが、暫くしてしまったと思った。母に見つかったら大変である。あわてて元に戻そうとした。しかし、曲がった火箸を真っ直ぐにするのは至難の業であることがすぐに分かった。曲がり目の下を握って、上端を引いても押しても、くるっとと回ってしまって力が入らないのである。これには流石の秘伝書も役に立たなかった。私はひそかに火箸をもとの場所に戻し、何食わぬ顔でいた。その日の夕方のことである。案の定、風呂場から母が私を呪う声が聞こえた。「火箸が曲がっていて使えないじゃない、均でしょう、こんなことしたのは!」
6 水銀事件
次の日も祭りであった。忍者の末裔はこの日は何でもぴかぴかに磨き上げるという不思議な粉を売っていた。錆びた鉄瓶や火箸を磨くと、あっと言う間に銀白色に輝くようになった。私はあのお風呂の赤黒く錆びた火箸を思い出し、これで磨けば母も驚くぞと胸がおどった。残った小遣いで1袋買い、針金で試してみた。粉は木の灰のようなものであった。布に取り針金をこすると確かに銀白色に変わっていく。その夜、私は父の前で得意になって粉を披露し、火箸を磨いて見せた。黙ってじっと見ていた父は、やおら母にガーゼのような布きれをもってこさせた。布に粉を包み新聞紙のうえで両手でしぼった。するとガーゼの隙間から銀白色の小さな玉がぽろぽろこぼれ落ちてきた。父はうめくように言った、「これは水銀だぞ」。父は歯科医であった。虫歯に詰めるアマルガムの材料として、水銀は何時も手元に置いてあった。私はこの事件以来、父を尊敬するようになった。大げさな言い方かも知れないが、私が後年忍者の道をすて化学の道を歩み、しかも何時も水銀を使った装置のお世話になることになったきっかけも、この祭りの夜の出来事であったかも知れない。それにしてもあの粉で水銀を擦り付けた火箸を炭火に入れれば、水銀の一部は気化して部屋の空気を汚染するであろう。無知とは恐ろしいことである。
7 神主さんに追われる
美の輪のお稲荷さんには社務所があり、神主さん一家が社務所の隣にすんでいた。神主さんの仕事は朝が早い。確か六時には拝殿の太鼓がならされる。どーん、どーんと初めゆっくりとならし始め、どん、どんと次第に間隔がつめられ最後はど、ど、どーーとなり、ふたたびどーん、どーんと同じことが何回か繰り返された。神主さんは純白の着物に青い袴、それに烏帽子をかぶってさっさとあるいた。私はひそかに神主さんにあこがれていた時期もあったが、その気持ちはある時こっぱみじんに打ち砕かれた。そのきっかけは、彼が私がお稲荷さんの境内のはとをとって食べたと誤解したことにあった。
私は雀とりに熱中したことがあった。私の生家の庭にはグミ、夏蜜柑、などの木があり実のなるころにはメジロがよく訪れた。メジロはもちを塗った木の枝に輪切りにした蜜柑を刺した罠や、口を開いた鳥かごに蜜柑をおき、メジロが入ると遠くから糸を引いて口を閉じる仕掛けでよく捕れた。メジロはもちを脚でつかんでも決してあわてなかった。くるりと反転して頭を下にしてぶら下がるのである。じっとしていると、もちが伸びて枝から足が外れることを期待しているのであろうか。だからメジロがかかるかどうか何時も監視している必要があった。かごの場合も同じであった。糸を充分ながくしておいて、離れの窓から中に引き入れ、窓の隙間から何時間でもじっと待った。こうして捕ったメジロは本当に可愛く大事にした。
雀はメジロより身近な鳥である。しかし意外と捕るのが難しかった。彼らは主として地べたで餌をとった。餌も米粒を好んだ。雀はわが家の庭にも沢山降りてきたり、木の上や屋根でさえずっていた。母にねだって使い古した金網のざるをもらい雀捕りの罠を作った。ざるを地べたにおき、その一端を長い糸を付けた割箸で持ち上げておく。ざるの下に米粒をおき、糸の端を持って物陰に隠れて雀のくるのを待った。しかしなかなかうまく行かなかった。箸が長いと糸を引いてから倒れるまでに時間がかかり、雀は敏捷に飛びさった。短いと隙間が狭く雀は警戒して入らなかった。
ある日、お稲荷さんの拝殿の前でこの罠を仕掛け、灯篭の陰で様子を窺った。境内には何時も鳩と雀がえさを探していた。わが家の庭よりづっとチャンスが大きかった。案の定すぐに雀が寄ってきた。しかし困ったことに鳩も一緒である。鳩がざるにさわれば仕掛けが働いてしまう。何とかならないかと思案していると、突然うしろから怒声がひびいた。「こら! 鳩を捕ってどうする」
振り向いた私の目に、竹のボウを持って走ってくる神主さんの姿が眼に入った。私は鳩なんか捕っていないよ、といおうとしたが神主さんの恐い顔を見てあわてて逃げだした。壮年の神主さんと小学生の私では本来競争にならないはずであったが、私は反ズボン彼は神主の正装である。だから辛うじて竹のボウをかわして夢中で走った。赤い鳥居のアーケードを抜けて、石の階段を駆け下りたが神主さんは追ってくる。わが家の玄関を横目で見ながら、お稲荷さんの石の壁に沿って走ると、田圃に出る路に走り込んだ。田圃の手前に広い空き地があって、いつものように斜めに立てたすだれの上にアジの開きが干されていた。私はその間を縫うように走り、小川に達した。もう大丈夫と思って後ろを振り返って驚いた。神主さんが未だ追ってくるではないか。私は小川を飛び越えイネを苅ったばかりの田圃を走った。畦を踏み越えながら、こんなところをお百姓さんに見られたらまた追っかけられと思った。
何処をどう逃げたか覚えていないが、家に帰ったときは夕闇が迫っていた。いつものように勝手口からはいると、母がしょんぼりと立っていた。その顔を見て神主が来たなとわかった。母につれられて社務所に行き、神主に謝った。私は鳩など捕るつもりではなかった、といいたかったが母に眼配りされて、もうしませんと謝った。悔しくて涙が出たが、神主には悔悟の涙と映ったのか、無事放免された。たしか中学に入ってから漢文の時間に「李下に冠を正さず」と言う格言を学んだ。神主に追いかけられた昔を思いだしおかしかった。
8 猿田彦の祭り
夏になるとお稲荷さんには猿田彦の祭りがやってきた。お稲荷さんと言っても本殿の左にあった小さな社に猿田彦が祭ってあった。猿田彦はににぎの尊が日本に降臨の際、先頭に立って道案内をした神様である。言い伝えによると猿田彦は身の丈7尺余の大男の上に、容貌魁偉で鼻高く天孫降臨の絵には欠かせない神様であった。祭りの日は白衣の神様衣装をつけ、赤い天狗の面をかぶった子供を先頭に御輿や幡をかついだ行列が次郎長通りから現れ、わが家の前の鳥居をくぐって猿田彦を祭った社の前に整列した。

猿田彦のお祭りには春のお祭りのような賑わいや楽しさはなかった。私はむしろ猿田彦の行列を見ると、何時も自分がなんとなく疎外されているのを感じたことを覚えている。実は私も何時かあの赤いお面をかぶって行列に参加してみたい、いやお面などかぶらなくても良いから一緒に歩いてみたいと思っていた。しかし母も祖母もそんなことはおくびにも出さなかった。私の家はお稲荷さんの前にあったが、地名は松井町であって、お稲荷さんの属する美の輪の町とは違っていた。私は子供心に、あれは美の輪の人たちのお祭りであるから、私は参加できないのだなと納得するようになった。こうして私と猿田彦の祭りの間にはある種のわだかまりを生じてしまった。
私の父が歯科医であったことは先にも書いた通りである。歯科医の父をついだ兄は清水に永住し10年以上前にお稲荷さんの前でなくなった。私は次男であったから、大学を出た後は山陰の三朝や東北の山形に65才まで住み、いまは東京に住んでいる。日本は祭りの國である。何処に行ってもその土地のお祭りがあり、はっぴに鉢巻きの土地っ子にかつがれて御輿が練り歩く。そんな土着の祭りを見るたびに、私は土地に根付いて暮らす人をうらやましいと思い、猿田彦の行列を見た子供のころの疎外感をおもい出すのである。
ところが電話でやっさんと話している内に、この話もまた私の一人合点のところが多いことが分かった。やっさんに聞くと、彼は行列に参加したし、私の隣の家の保ちゃんは天狗の面をかぶって歩いたというのである。私は勝手に自分は駄目だと思いこんでいたのである。私には小さい頃からこんな引き込み思案のところがあったのである。
9 トンボ釣り
夏にもなるとわが家の庭にはシオカラ・トンボが沢山やってきた。薄い空色の胸と尻尾のおすと黄色っぽいめすが、庭のあちこちの草や木の葉の先に止まって羽根を休めていた。彼らは近づいてもすぐには飛び立たず、大きな目玉をきょろきょろさせていた。だから彼らをたもで捕らえることは簡単だった。その上、なれると素手でも簡単に捕まえることが出来た。トンボの目玉を中心に片手をはじめは大きくゆっくりと、そのうちだんだんと小回りにスピードをあげながら目玉に近づけ、トンボが眼を回したところをさっと背中を押さえてしまう。この方法は子供の頃誰かに教わったもので、私の子供達にも伝えた秘伝であるが、本当にトンボが眼を回すかどうか実は確信を持っているわけではない。
簡単に捕まえることの出来たシオカラトンボに比べてヤンマトンボは子供達のあこがれであった。

ヤンマが身を翻すのは餌を見つけたときだけではなかった。彼らはそれぞれが自分の縄張りをもっていて、別のヤンマが近づくと身を翻して追い出した。だから彼らは何時もひとりぼっちであった。広々とした田圃で一人じっと縄張りを守るヤンマ。あいつをなんとかこの手にしたい、かごに入れてじっくり眺めることが出来たら、と思うだけでゾクゾクした。しかし、シオカラと違ってヤンマは敏速な上に用心深かった。だからシオカラを捕るようなわけにはいかなかった。だからこそ捕りたかった。こうして私もヤンマ取りにのめり込んでいった。
ヤンマ取りは先ず長くてしなやかな竹竿とそれに塗る鳥もちを買うことから始まった。竹竿は家の軒に立てかけると、先が数十センチも余るほど長かった。もちは使うまで中庭の池に浮かべておいた。いざ出陣となるともちを竹竿の先端20cm位の長さに指で巻き付けた。お稲荷さんの横手をまわって山側に歩くと、すぐに目指す田圃が広がっていた。ヤンマのいる田圃を見つけると畦を選んで近づいた。畦といっても踏めばぐじゃっとなる奴と、少し広くて固いのがあったから慎重に歩く必要があった。肥だめにも注意が必要であった。

こんなわけでヤンマ取りを始めて何日かすると、私なりの足場の良い定点がいくつか出来上がっていた。田圃に出ると先ずこれらの定点を観察し、ヤンマのいるところにしゃがみ込んだ。ヤンマ取りの原理は簡単である。隙をついてヤンマに竹竿を繰り出しもちにくっつけてしまうのである。竹竿を繰り出しながら、竿の端をもった右手首を激しく斜め上下に振るので、もちのついた先端も激しく揺れ動き、逃れようとするヤンマがもちに接触してしまう、という作戦である。ヤンマ取りと言わず、あえてヤンマ釣りという由縁も竿を使う点にあった。
しかしこの作戦は簡単には成功しなかった。ヤンマの動きは私の繰り出す竿の速さより何倍も早かった。それに一旦失敗するとヤンマは二度と竿の届く距離まで近づかなかった。何度も無駄に竿を振るとヤンマは遠くへ飛びさっていった。そこで竿を予め繰り出しておくことにした。しかしヤンマは竿の先から何時も何十センチか離れたところまでしか近づかなかった。そこで竿を目一杯出さず1メートルほど手元に余裕を残しておくことにした。ヤンマが先から50センチ以内に近づいたらさっと繰り出せばよいと思ったからである。この作戦はときどき成功した。何度も失敗した後始めて1匹を捕まえたときの感激は忘れられない、と書きたいのであるが困ったことに正直言ってどんな感動であったか思い出せない。だから恐らく感動したであろうと想像で書いている。
夏の半日或いはそれ以上を炎天下でヤンマと知恵比べ、根気比べをしていたわけであるからおなかも空いた。毎日トンボ釣りに出かけるときは祖母がおやつの袋を腰に付けてくれた。袋の中身は彼女が醤油で炒めたイナゴであった。褐色の炒めイナゴは口にほうばるとこりこりと香ばしかった。このイナゴは私が前日ヤンマ釣りのかたわら捕まえたものだった。トンボ釣りから帰って捕ったイナゴを祖母に渡すと、翌日は私のおやつになって腰の袋に入れられた。

祖母の名はあきといった。由比の漁師の娘で、夫(私の祖夫)を日露戦争で失ったあと、女手一つで父を歯科医にまでしたのであるから、大変気丈で生活力に満ちあふれたばあさんであった。彼女はイナゴだけでなく私たちが捕ってくる魚から雀、時に鳩まであっと今に料理した。私がお稲荷さんの境内で雀を捕ろうとして神主さんに鳩を捕ると誤解され、追いかけられたのも案外祖母の“実績”が遠因としてあったのかも知れない。もちろんこれは今にして思えばの話で根拠はない。祖母の話は別の機会に譲るとしてヤンマ釣りに戻ろう。
長い夏の日のもそろそろ日が傾き始める頃、ヤンマ釣りのクライマックスが訪れる。腕に覚えのある悪童たちが手に手にもち竿をもって田圃の西側を南北に走る土手に集まってくるのである。彼らのお目当ては何処からともなく飛んでくるつがいのヤンマであった。田圃には雄のヤンマしかいない。しかし、この時刻になるとオスが尻尾の先にメスの頭を挟んでつがいで飛んでくるのである。高度が高く田圃では竿が届かないが、土手に上ると辛うじて届くのである。つがいであるから目標が大きい上に、動きも鈍い。だから捕まえるチャンスは大きかった。
つがいが土手にかかると待ちかまえた竿が一斉に繰り出される。5_6人時には10人近い子供が一斉に竿を突き出すのあるから壮観であった。しかし待ちかまえる位置が問題であった。一番腕力の強いものがつがいの進む方向を予測して一番良い位置をとった。しかしつがいは土手にかかる直前に進路を変えることもあったから、列の端の方でもチャンスはあった。誰かが運良くつがいを捕ると歓声があがった。みんながその日のヒーローのまわりに集まり、獲物をうらやましそうに眺めた。やがてまた次のつがいが現れ、皆その方向に走った。私は初めは傍観者であった。低学年では端っこの位置しか取れなかったし、第一背が低くて運良く真上につがいが来ても届きそうになかった。
やがて高学年になるにつれて私も土手の仲間に入るようになった。そうして、何回かの失敗の後、遂につがいをしとめることが出来た。家に持ち帰って羽根についたもちをベンジンか何かでぬぐい取った。メスは緑がかった胸と尻尾が美しかった。羽根は赤みを帯びていた。メスの胸に1mほどの長さの細い糸のはしを回し羽根の間の背中で結んだ。糸を持って軽く持ち上げるとメスは糸をひっぱりながら飛んだ。これで明日の為の準備は終わった。わくわくしながら眠りについた。
翌日は朝飯もそこそこに、イナゴの袋を腰に、糸を付けたメスと虫かご、たもをもって田圃に出かけた。草むらに身を隠し、メスを付けた糸の端を棒に付けた。棒をくるくる回すとメスが草むらの上を羽根をきらめかせて飛んだ。あっと言う間にオスが現れ飛びかかってきた。二匹は絡まるようにして地べたに落ちた。そこをたもで押さえると簡単にオスが取れた。メスを囮にしたこの方法は私が考え出したわけではない。昔から子供達の間で伝えられた秘伝である。この日も面白いようにオスが取れた。やがてメスはぐったりとして動かなくなってしまったが、オスは見境なく飛びかかってきた。いつもなら何日かに1匹取れるという貴重なオスヤンマが1日で虫かご一杯になったのである。しかも、もちがついていないからまっさらなオスであった。
ヤンマをだます戦術は別にもあった。釣りの錘に木綿糸をぐるぐる巻き付け、ヤンマに見えるように空高く放りあげるのである。餌と思ったヤンマはさっと飛びかかるが、これが運の尽きで足を糸に絡められ、錘とともに地上に落下し、たもで押さえられることになる。これも私は試してみた。何回か成功した記憶があるが、メスを囮とした方法ほど感動的ではなかった。
こうして小学時代はヤンマ釣りに熱中した。しかし、囮作戦の成功以来あれほど神秘的に見えたヤンマのイメージにも陰りが生じた。孤高のヤンマにも意外な弱点があり、死んだメスにも飛びかかるとは情けないな!という思いがつのってきたのであろうか、何時しかヤンマ釣りの熱も冷めていった。