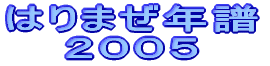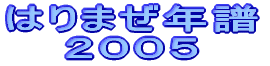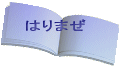|
朝日新聞20050116
[原油産出量が頭打ちとなり横ばいや減少に転じる「石油ピーク」を迎えた産油国が相次いでいる。00年以降に少なくとも11カ国を数える。80年代以降、新規油田の発見が急減し、採掘可能な埋蔵量が減ったためだ。世界の石油開発業界では「地球全体の石油ピークが近い」との説が強まっている。資源問題の研究者や米コンサルタント会社などのまとめによると、00年以降は北海油田をもつ英国とノルウェー、オマーン、コロンビア、パキスタン、コンゴ共和国、オーストラリアの7カ国が減少局面に入った。そのほか横ばいになった国も、大慶、勝利両油田が減退期を迎えた中国、メキシコなど少なくとも4カ国ある。90年代後半にもエジプト、シリア、ガボン、アルゼンチンなど6カ国が減少に転じた。国際エネルギー機関(JEA)の分析では、60年代以降、新規油田の発見による埋蔵量の増加ベースが鈍り、ここ20年間は生産量が埋蔵量の増加を上回る状態だ。地域別では欧州と、中東を除くアジアがすでに生産能力の減少期に入った。旧ソ連崩壊で生産量が膨らまなかった旧ソ連諸国や、新規油田を抱える西アフリカ、南米諸国は今は埋蔵量にまだ余裕がある。ただこれらの国でも今後、他地域の供給減分を穴埋めするため生産増に拍車がかかり、10年以内にはピークを迎えるとの見方がでている。この結果、世界の埋蔵量の3分の1を占める中東への石油依存が一段と高まる見通しだ。ただ中東の大規模油田にはすでに生産開始から50年以上経過しているものも多く、生産能力の大幅な拡大は難しい、というのが石油資源の研究者らの一般的な見解だ。一方で、中国など新興市場の石油需要は今後も急速に膨らむ見通し。業界には「現存油田を従来の採掘技術で生産するだけなら、15年後には需要の半分が賄い切れなくなる」(欧州の石油メジャー幹部)との懸念も出ている。IEAによると、2030年の全需要を賄うには、新規油田の発見や採掘技術の向上などに総額3兆ドル規模の投資が必要という。]
|