その夜、オザワはいつになく饒舌だった。
「君の専門はヒューマノイドと人間の関係史だろう」
「まあな、今サマリーのようなものを書いているところだけれど、人間と彼らの関係は考えれば考えるほど面白いと思うよ、まさに紆余曲折というやつだな」
「彼らの人工知能は人間の精神の働きとは違う、それは明らかだ。けれども彼らが人間によって作られている以上、人間の精神をコピーしているはずだ。いったいどこまでが人間と共通でどこが違うのかわかるかい」
「そんなことを言って、またPAに人間とは独立した人格があるかなんて言うつもりだろう。」
「そう先手を打つなよ、僕にとっては重要なんだ。なんせ非人型ロボットを研究していたからね、やつらの人工知能は人間のそれとは違ってもいいんだ、目的に最適ならなんでもありさ。ところがヒューマノイド、PAはそうじゃない」
「単に見た目が人型だからというだけじゃなないのかい、目的に合えばいいのは同じじゃないか。人間の言うことがわかり正確にそれに応じて、しかも時間と空間的な状況をユビキタスネットを通じて把握して行動できれば十分だろう」
「メカの動作としてはそれで十分だがね、PAの人工知能は、ある意味人間と対等な関係を築くために、人間から学習する能力スペースを与えられているじゃないか。ほら、PAは持ち主に似るっていうやつさ」
「学習するのだから、そりゃ当たり前だろう、動物のペットだって飼い主に似る」
「まさに、そこなんだよ僕が問題としてるのは」
「持って回った言い方だな、何が言いたい」
「PAは一部しか持ち主に似ないということさ、新品のときから同じ持ち主と暮らしていてもだよ」
「なるほど、やっぱりPAに個性が宿ると言いたいんだろう、独立した人格というか精神的コンプレックスを持つとね。その問題はずっと昔のフィクションでテーマになっているのは知っているだろう。人工知能ないしはロボットに意識とか魂はあるのかという。こういうのを僕は人間の心にあるロボット神話と呼んでいるのは話したっけ?」
「聞いたことがある、君のは人間の持つロボット神話だけれど、ヒューマノイドロボットやそれに適合した人工知能にも同じように『神話』的部分があってもおかしくはないと思わないか」
ヒューマノイドの「意識」あるいは「魂」
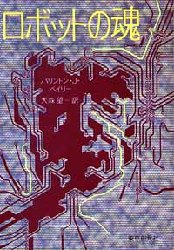 これについては神話時代に数多くフィクション上で議論され、問題提起されてきた。
これについては神話時代に数多くフィクション上で議論され、問題提起されてきた。
その一つが3原則後に、その原則を無視して描かれた、B・J・ベイリーの「ロボットの魂」の主人公たるロボット「ジャスペロダス」である。彼は、起動された直後、生みの親のロボット技師の命令を無視して「放浪のロボット」となり、その次の行動においては、殺人を犯してしまう。殺意はなかったので当時の法律上は傷害致死もしくは過失致死だが、ジャスペロダスの関心は、唯一つの方向に向かう、つまりロボットに「意識=魂はあるか」である。
彼はその世界の中で最もすぐれた、ロボット技術者(彼はジャスペロダスを作った技術者の師匠でロボット製作に関してのマイスターであった)を探し出し、答えを聞くが「ロボットに意識はない、なぜなら意識と言う概念は意識があるものが与えた名称だが、それを持っている存在は人間以外にはありえない」とあっさり否定されてしまう。その一方で彼の生みの親である技術者は再会したジャスペロダスに「自分と妻の魂を半分ずつ取り出して(方法は秘密だそうだ)お前に受容させたのだから、お前には意識=魂がある」と宣言する。
お分かりのとおり、前者は言葉には必ず対応する実在があるという実在論に基づき、後者は人間の魂あるいは意識が実体を伴った再生可能な存在であると言う一種の唯物論に基づいている。
すでに量子物理学の知見が広まり、最も確かなものと思われた物質やエネルギーの世界での不確定性がはっきりした時代でも、意識=魂についてはこのようなまさに神話的な問題意識が主流だったのである。
 このようにヒューマノイドロボットの意識=魂の有無は、一神教文化圏に属する人間にとっては大きな問題だったようで、ジャスペロダスは「魂」を求め、映画の「A
I」の子ども型ヒューマノイドは「愛」を求めてさまよったなど、さまざまなフィクションでの設定が試みられている。
このようにヒューマノイドロボットの意識=魂の有無は、一神教文化圏に属する人間にとっては大きな問題だったようで、ジャスペロダスは「魂」を求め、映画の「A
I」の子ども型ヒューマノイドは「愛」を求めてさまよったなど、さまざまなフィクションでの設定が試みられている。
しかし結論から言うと無意味で不毛な議論であったというしかない。
なぜなら肝心の人間に意識や魂が、物質的存在を超えて存在するのか、ただの脳という遺伝子情報によって形成されたたんぱく質組織が引き起こす電気信号を介した現象ないし機能としてのみ存在するのか、ほとんど議論が成り立たない2律背反的事象であるからだ。
まして魂の永遠性を言うことは、宗教的な教義からも疑問視されている(仏陀ゴータマはこの問題には解答しないという態度をつらぬいている)。もっとも「科学的」あるいは「科学と矛盾しない」ことを教義とする宗教(20世紀後半以降つぎつぎと生滅を繰り返している)では、量子宇宙論的にまじめに物理現象として考察するということまで試みられているが、量子物理学の要は、不確定性原理だと言うことを忘れている。
もう一つ神話時代典型の議論として、意識や魂がヒューマノイドや人工知能に存在しないこと、あるいは人間とロボットとの決定的な違いとして「感情のありなし」があげられたが、実際には、人間と同じ感情表現ができるかいなかと定義しなおせば、技術的にはロボットに組み込むことはできた。ヒューマノイドのプロトタイプの一つの「擬似筋肉による柔組織タイプ」通称は「柔らかロボット」では見事なほどに表情で感情表現し、笑うべきときには笑い、悲しみ、怒り、脅迫、いかなる表現も可能であったのだ。
人間の感情の源泉が「好き嫌い」あるいは「好悪」の心理だと定義すれば、ロボットの知能設計に盛り込み、そこから演繹される「感情」はある意味容易であったとすらいえる。
人間の精神疾患である「統合失調症」の症状の一つに極端な感情の鈍麻があるが、この症状を治療するほうがはるかに困難である。
つまり人間が自らの精神についても、古代ギリシア哲学やインドのウパニシャッド哲学あるいは仏教(中でも唯識学派)に代表される瞑想による考察に、19世紀末にフロイトなどの深層心理学と、20世紀後半の大脳分子生理学の知見を加えた程度しか解かっていないところに人工知能の「魂」の議論を乗せたところで、まったくのアポリアでしかありえない。
ましてデカルト流に「思惟する精神的な個我」と「延長する物質」の二元論に基づいて人間の優位性を主張することなど、再び傲慢な過ちを人間が犯す危険を許してしまう。
感情の中でも喜びや悲しみの状況を感知し、それらの表現として「泣く」「笑う」機能は確かに組み込めたが、「欲望」「希望」「絶望」これらの事象については、研究されはしたが今のところ断念せざるを得ない状況にある。
これらは分析し再現可能な現象というには、あまりにも生命そのものに近かった。感情の中でも「憎しみ」は非常な注意を払って人工知能の状況認知機能から除去された。憎しみを持たせるのは、兵器としての人工知能が「敵」を認識する機能からかなり容易に拡張することができた、感情の中では最も組み込みが簡単な機能だったからだ。
この「憎しみ」除去研究と、3原則研究が重なり合うことで、実はヒューマノイドと人工知能の研究に大きな停滞期間が生じたことは以外に知られていない。
ヒューマノイド=人工知能研究は、人間が分析できる範囲の知性にとどめ、それ以上の機能を追及するのは「神の領域」として禁止されるべきだという主張が人間世界を支配した時代が、実は長く続いたのである。
 そのことによって、昆虫や人間以外の生き物と類似の機能へと大きく迂回し、その成果がヒューマノイドにフィードバックされたことで、皮肉なことにヒューマノイド開発での神経−運動研究として役立った。
そのことによって、昆虫や人間以外の生き物と類似の機能へと大きく迂回し、その成果がヒューマノイドにフィードバックされたことで、皮肉なことにヒューマノイド開発での神経−運動研究として役立った。
何よりそれは、人間が自身を研究するときにはできなかった「検証」が可能だった。外部対象を分析して実験によって再構成するという「科学」方法論がそのまま使えた。
生きた人間を、まして精神や魂を分解するか実験台とすることはできなかったが、人間以外の生物、特に昆虫ならまったく倫理的制約なしに行えたのである。
そのおかげで、トンボをはじめとする飛翔昆虫の研究から得られた飛行制御の成果は、今やあらゆる飛行機械の姿勢制御や飛行形態(昆虫の行う急激な方向転換は、人間の乗る飛行機械の強度や中の人間への加速度重力の問題で完全には再現されなかったが)に及んでいるといえる。もちろんこれらの人工知能制御の機械群はヒューマノイドロボットではなく、単一機能(好例は兵器)を極限まで自動化することに成功したものである。
が、ヒューマノイドの人工知能を、集中処理から分散型処理へ転換すると決断したとたんに、これらの非人間型運動制御や認知機能の制御にたちまち応用されたのである。
3原則を抜きにしても、学習しながら人間の命令を完全に理解し実行するというヒューマノイドの成果と、民生分野への普及の前にいつしか、機械の意識問題は腰砕け状態になってしまった。
ただ、まったく消えたわけではなく、今でも「意識ないし知性を持った機械」に対する強い懐疑が、ヒューマノイドや人工知能ネットワークに何らかの事件があるたびに声高な、時に過激な発言や行動となって現れる。反ヒューマノイド反人工知能のカルト集団は増えもしないが減りもしていない。
いまひとつの、ヒューマノイド人工知能においての問題は、忘却であった。人間には確かに忘却という現象が起きる。しかし忘れたと思っていた事柄が、ある日何の前触れもなしに記憶に呼び出されることがあるのも事実である。人間の忘却とは、表層意識に上らず潜在意識化されることだともいえる。
しかし人工知能の場合は、これと事情が異なる。メモリーの方式とその容量という壁が開発段階で常に立ちはだかったからである。しかも、人間の側にしてみれば、人工知能が「忘れる」というのは、人間に近似した「傑作」を作り出せたと評価されるより、「役立たずのガラクタ」として葬り去られる可能性が高かったのである。
無限メモリーの研究は、一時人工知能研究の主流になったが、結局量子人工知能第3世代に入ってからも実現はできず、不可能であるという証明が相次いで数学者から提出された。
ロボット(=人工知能)にも潜在意識を作ろうという研究もなされたが、人間の無意識領域を含む精神構造が明らかでない以上、それを人工的に作り出すのは最初から無理な望みだった。
人工知能領域に特有の擬似潜在意識を開発した例もあったが、結局、自立学習型人工知能の意識・学習レベルを著しく不安定にするという代償を越えられなかった(当初は「夢を見る人工知能」と華々しく宣伝されたが)。
もっとも、この研究は、人間の精神疾患のひとつである統合失調症研究に大きな発展をもたらすという副産物をもたらした。
ならば、外部ネットワークの中に分散して潜在化してしまえばというアイデアが実行されたが、今度は、ネットワーク化された人工知能が、すべての人間の個人情報を管理記憶し、人間を支配するという、デストピア神話がまたしても立ちはだかった。
妥協としてヒューマノイド自身または人間が消去したいメモリーを消去、または、ネットワーク外の外部メモリーに移し変えるという最も原始的な方法が採用され続けている。今のところヒューマノイドのメモリー容量がとてつもなく大きいため問題は起きていないが、本当に忘却なしに人工知能の安定性が保てるのかどうかは不安視されている。
8ページへ
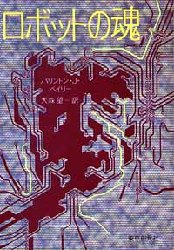 これについては神話時代に数多くフィクション上で議論され、問題提起されてきた。
これについては神話時代に数多くフィクション上で議論され、問題提起されてきた。 このようにヒューマノイドロボットの意識=魂の有無は、一神教文化圏に属する人間にとっては大きな問題だったようで、ジャスペロダスは「魂」を求め、映画の「A
I」の子ども型ヒューマノイドは「愛」を求めてさまよったなど、さまざまなフィクションでの設定が試みられている。
このようにヒューマノイドロボットの意識=魂の有無は、一神教文化圏に属する人間にとっては大きな問題だったようで、ジャスペロダスは「魂」を求め、映画の「A
I」の子ども型ヒューマノイドは「愛」を求めてさまよったなど、さまざまなフィクションでの設定が試みられている。 そのことによって、昆虫や人間以外の生き物と類似の機能へと大きく迂回し、その成果がヒューマノイドにフィードバックされたことで、皮肉なことにヒューマノイド開発での神経−運動研究として役立った。
そのことによって、昆虫や人間以外の生き物と類似の機能へと大きく迂回し、その成果がヒューマノイドにフィードバックされたことで、皮肉なことにヒューマノイド開発での神経−運動研究として役立った。