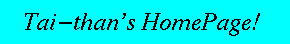|
|
| Linux導入編 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
1.1 ハードウェア環境を用意しよう
1.1.1 わたしのハードウェア環境ですいちばん上へ
1.1.2 これから購入する方へ(*)は以前のマシン部品を流用しています。以前のハードウェア環境はこちらです。
- マシン: 自作PC
- マザーボード: GIGABYTE GA−586STX
- CPU: Intel Pentium 133MHz
- メモリ: EDO 32MB
- ハードウェア: IDE 540MB(*)
- ビデオカード: PV70 2M
- ネットワークカード: ELECOM NE2000互換(*)
- CD−ROM: ATAPIタイプ(*)
- サウンドカード: SoundBlaster16(*)
- キーボード: 富士通(*)
- マウス: 3ボタンマウス(*)
- ケース: ミドルタワー (ATX)
これから購入しようと考えている方は以下の点に注意をして下さい。もっと詳しく知りたい方へ
CUP X−Windowを使うでしょうから、DX4/100MHz以上の物を。
(当然のことながら、CPUが速いほど快適に動作します。)メモリ X−Windowを使うでしょうから、20MB以上必要です。 IDE/EIDE SCSI ハードウェア 大きいほど良いです(500MBが最低ラインです)。 問題ありません。 SCSI−HOWTO参照 CD−ROM . ビデオカード これはちょっと曲者です。新し過ぎる物は注意して下さい。X−Windowが使えない物もあります。
詳しくはXFree86−HOWTOを参照して下さい。ネットワークカード これは、今は必要ありません。ネットワーク編で紹介します。 サウンドカード なくても動作しますが、せっかくあるのだから使いましょう。使えるハードウェアは Sound−HOWTO
を参照して下さい。
もっと詳しく知りたい方はJFのHardware−HOWTOを参照下さい。
1.2 ソフトウェアを用意しよう
1.2.1 わたしの使用しているLinuxはSlackware3.1です。いちばん上へ
Slackware3.1の中身はKernel: Ver2.0.0
XFree86: Ver3.2
あとは面倒だから省略します。
1.2.2 Linuxパッケージの入手方法
一番簡単なのが 本屋 に行くこと! UNIXコーナーのある書店であれば置いてあるはずです。
書店でCD−ROM付きの本を選んで買ってきて下さい。
市販のパッケージソフトがほしい方はパソコンショップに走って下さい。でも、どこにでもあるものではありません。
私の知っているショップでは ぷらっとホーム(株) にありました。
あと、わたしはやったことはありませんが、インターネット上からも得られます。しかし、手間と時間がかかるでしょう。
また、どうせ入門書も必要になるのだから、この際パッケージを買って来た方が良いでしょう。
1.3 インストールをスムーズに行おう
これからのインストールをスムーズに行うために、事前に知っておいた方が良いものをリストアップしておきます。いちばん上へ
1.3.1 決めておくこと
- HDDの分割の仕方(各パーティションのサイズ)
- Linuxマシンのマシン名(ホストネーム)
1.3.2 調べておいた方が良いこと
- HDDのタイプ(IDE?SCSI?)
- CD−ROMのタイプ(IDE?ATAPI?Other?)
1.4 HDDのバックアップとDOSパーティション
1.4.1 HDDをフォーマットしますいちばん上へ
今回は、PCをLinux専用にしますので、HDDのバックアップを取っておいて下さいね。新品の方はべつにとらなくていいよ。1.4.2 DOSパーティションを作成
次にHDDをフォーマットして下さい。つまり、まっさらなHDDにしてしまいます。
フォーマットしたHDDにDOSパーティションを作ります。DOSのFDISKコマンドで、10MB程度のDOSパーティションを作って下さい。
作成したDOSパーティションでDOSを起動し、CD−ROMが読めるように設定しておいて下さい。(注:DOSの使い方は事前に学んでおいて下さい。)
1.5 bootdiskとrootdiskを作ろう
ここからは、わたしの使用しているSlackware3.1をもとに話を進めていきます。いちばん上へ
まず、DOSでフォーマットしたFDを2枚用意して下さい。
1.5.1 rootdiskの作成まず、イメージファイルの選択をしなければなりません。1.5.2 rootdiskの作成
次の3つについて確認をして下さい。この質問によってイメージファイルが変ります。わたしの場合はATAPI(CD−ROM)、IDE(HDD)でしたので、イメージファイル名は上の質問から下の表を参照して下さい。
- SCSIを使用しているかどうか
- CD−ROMドライブの種類は?
- インストールしようとしているHDDの種類は?
*注:非SCSI非ATAPIのCD−ROMを使用している場合はパッケージソフトのBOOTDSKS.144のWHITCH.ONEを参照して下さい。
インストール元
のメディアHDDの種類 IDEタイプ SCSIタイプ HDD bare.i インターフェース名.s SCSI
CD−ROMインターフェース名.s インターフェース名.s IDE/ATAPI
CD−ROMbare.i インターフェース名.s その他の
CD−ROM*注 *注
bare.iでした。
どのイメージファイルを使うかが決まったら、一枚目のFDをドライブに入れてRAWRITEコマンドを実行して下さい。(カレントディレクトリは¥SLACKWAR.1¥BOOTDSKS..144¥です)
すると”Enter source file name:”と聞いて来ますので、決定したイメージファイル名を入力してENTERキーを押して下さい。次にFDを入れたドライブを入力して下さい。
しばらくドライブが音を立てた後に終了すれば、bootdiskの出来上がり。作り方はbootdiskの時とほとんど同じです。
まず、カレントディレクトリを¥SLACKWAR.1¥ROOTDSKS..144¥にして下さい。
次に、2枚目のFDをドライブに入れてRAWRITEコマンドを実行して下さい。
すると”Enter source file name:”と聞いて来ますので、何も言わずにCOLOR.GZを入力してENTERキーを押して下さい。次にFDを入れたドライブを入力して下さい。
しばらくドライブが音を立てた後に終了すれば、rootdiskの出来上がり。
1.6 ハードディスクを分割しよう
1.6.1 パーティションを切りましょういちばん上へ
わたしの場合は、ハードディスクが小さかったので次のように切りました。DOS:10MB切り方は自由です。参考程度にroot用に100MB、スワップ用にメモリと同程度の容量、User用に400MB以上あれば良いでしょう。
root:60MB
スワップ:32MB
User:413MB
1.7 Linuxをセットアップしよう
以上が済んだら、いよいよLinuxパッケージのインストールです。インストールの方法は各パッケージにしたがって下さい。いちばん上へ
1.7.1 ミニLinuxの起動bootdiskをFDDに入れ、リセットして下さい。boot:が現れたらリターンを押します。1.7.2 setupの起動
次にrootdiskに入れ替えてリターン、login:が出たらrootでログインします。
setupコマンドを実行し、後のインストールの方法は各パッケージに従って下さい。1.7.3 ネットワーク機能の設定
ネットワークの設定は、netconfigで設定できますので、とりあえずloopback onlyで設定しておきます。
1.8 カーネルをコンパイルしよう
カーネルのコンパイルの方法は特にテクニックなどありません。ここでは、手順を紹介するに止めます。いちばん上へ
1.8.1 カーネルコンパイルの手順1.8.2 もっと詳しく知りたい方へ
- カレントディレクトリを/usr/src/linuxにして下さい。
- make config の実行
(すでに、X−Windowが使える方は、make xconfigが扱いやすいです。)- make dep の実行
- make clean の実行
- make zImage の実行
(20分ぐらいかかります。お茶でも飲んでいて下さい。)- make zlilo の実行
- あとは、rebootして再起動して下さい
もっと詳しく知りたい方はJFのKernel−HOWTOを参照下さい。
1.9 日本語キーボードを使おう
パッケージをそのままインストールするとキーボードの設定は101KeyBorad用になっています。いちばん上へ
日本語106KeyBoradを使用するには少し設定をかえてやらねばなりません。
(中には、インストールの時点で設定出来るものもあるようです。その場合は読み飛ばして下さい。)
1.9.1 カーネル1.1.54以降を使用している場合
1.9.2 カーネル1.1.53以前を使用している場合(詳しく知りたい方は106keyboard−HOWTOを参照して下さい。)
- テキストファイル106keyboard.mapをダウンロードして下さい
- 106keyboard.mapを/usr/local/etc/にコピーして下さい
- viエディッタで/etc/rc.d/rc.localを編集します
- /etc/rc.d.localに以下の1行を追加して下さい
/usr/bin/loadkeys /usr/local/etc/106keyboard.map
(わたしの/usr/rc.d/rc.localを紹介します。)
- rebootして下さい
わたしは良く知りませんので106keyboard−HOWTOを参照して下さい。
1.10 X−Windowを使えるようにしよう
設定は簡単です。が、それは一度でもXの設定をやったことのある場合でしょう。一度、経験してしまえば簡単です。いちばん上へ
以下にわたしの設定方法を紹介します。
1.10.1 X−Windowの設定(xf86config使用)1.10.2 X−Windowの設定(XF86Setup使用)
- 設定に入る前に以下の事を確認しておいてください
- ビデオカードのチップセット名
- ビデオカードのメモリサイズ(VRAM)
(1、2はSuperProbeコマンドを実行しても調べられます)- マウスのタイプ
- マウスのつながっているデバイス名
- ディスプレイの水平走査周波数
- ディスプレイの垂直走査周波数
- xf86configコマンドを実行して、設定ファイルXF86Configを作成して下さい。
(わたしのXF86Configを紹介しておきます。ヴァージョンは3.3.1です。)- 設定項目を入力し終ったらX -probeonlyコマンドを実行します
(設定項目については、本を参照して下さい)
- ここでエラーが出なければX−Windowは問題無く起動するでしょう。
- エラーが出た場合は、エラーを修正します。たぶん、マウスのエラーがでるでしょう。
(わたしの時はマウスタイプを”PS/2”に修正するだけでした)
- はい、これでX−Windowは動くようになったでしょう。 startxコマンドを実行してみて下さい。
1.10.3 わたしのハードウェア内容
- 設定に入る前に以下の事を確認しておいてください
- ビデオカードのチップセット名
- ビデオカードのメモリサイズ(VRAM)
(1、2はSuperProbeコマンドを実行しても調べられます)- マウスのタイプ
- マウスのつながっているデバイス名
- ディスプレイの水平走査周波数
- ディスプレイの垂直走査周波数
- XF86Setupコマンドを実行して、指示にしたがって進めていきます。
- 終了したら、startxコマンドを実行してみて下さい。
- うまく動いたら、おめでとう。
*注:インストール時に適当に設定している場合はシリアルポートかマウスデバイス名が必要です。
ビデオカード
チップセットPV70 ビデオカード
VRAM2048KB マウスタイプ PS/2マウス マウスの
デバイス名/dev/mouse (*注) ディスプレイ
水平走査周波数24KHz−65KHz ディスプレイ
垂直走査周波数50Hz−90Hz

ご意見、ご質問はこちらまで!
    |