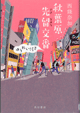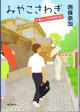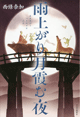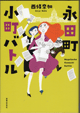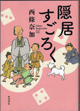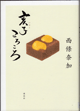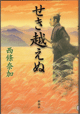| 11. | |
|
「秋葉原先留(さきどまり)交番ゆうれい付き」 ★★ |
|
|
2018年04月
|
秋葉原に復活した“先留”交番を舞台に、凸凹コンビの交番勤務警官2人と足だけの幽霊が活躍する、連作短編風&長編事件ものストーリィ。 下半身が極めて緩く、またもや女性関係で謹慎処分を喰らった警官=向谷弦(むこうや・ゆずる)。その向谷に連れられて再び秋葉原に戻ってきたというのが、足だけの幽霊となり向谷から「足子さん」と呼ばれる渡会季穂、20歳。 その2人を迎える先留交番勤務の警官は、30歳前後の権田、季穂が仇名する処の「メガネトド」。 (もっとも季穂の足は向谷には見えるが、権田には見えない) まもなく足子のことを権田が、メイド喫茶「桃飴屋」のメイドで行方知れずとなったままの玲那ではないかと気づきます。 何故、季穂は足だけの幽霊となったのか。その謎を解く長編ストーリィに並行して、秋葉原を舞台にした幾つかの事件の解明が連作短編小説風に繰り広げられるという二重構成。 風体とアニオタという人物像からは想像できない権田の意外な慧眼と捜査能力も見処ですが、何と言っても惹かれるのは、足だけという抜群に個性的な渡井季穂の幽霊造形。 不器用で頑張り屋だった季穂、何とか元に戻してやれないものかと思うのは、きっと私だけではないでしょう。 でも、事件が解決したからと言って季穂は成仏する訳でもなく、本書はシリーズものになりそうな気配有り。 今後がとても楽しみです。 オタクの仁義/メイドたちのララバイ/ラッキーゴースト/金曜日のグリービー/泣けない白雪姫 |