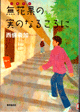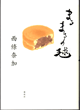|
●「金春屋(こんぱるや)ゴメス」● ★ 日本ファンタジーノベル大賞 |
|
|
2008年10月
|
前からどんな作品か気になっていた本なので、ちょっと空いてしまった時間を潰そうと図書館から借出したのが、やっと読むに至ったきっかけ。
時代は近未来の日本。その日本国の真ん中にありながら、別世界の如くに存在するのが「江戸国」。 その辰次郎が入国した江戸国、そこを差配するのは長崎奉行(入出国管理も必要という点では江戸町奉行より当時の長崎奉行の役割に近いという理由)。 近未来でありながら登場人物たちが走り回るのは昔の江戸そのものという舞台設定の面白さは、井上ひさし「吉里吉里人」等のSF作品に通じるものがありますが、折角の題名にもなっている金春屋ゴメスの存在感が今一つに終わった観あり。そのために、ストーリィとしての面白さが中途半端に終わったという印象が拭えません。 |