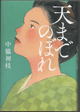| 「天までのぼれ」 ★★★ | |
|
|
江戸末期に生まれ、明治の時代に女性参政権を求めて行動、“民権ばあさん”と揶揄して呼ばれた実在の女性=楠瀬喜多(1836〜1920)を描いた評伝小説。 土佐の高知に富裕な商家の長女として生まれた喜多は、向学心に溢れ、おなごだからという理由で勉学の道を閉ざされたり、男の決めたことにただ従うというような生き方は、どうしても肯んじなかった。 そうした喜多の考え方、姿勢は、当時の社会においてまともに相手にしてもらえるようなものではありませんでしたが、幸いにも喜多には、そうした思いを理解、共感してくれる仲間がいた。 ようやく明治の世界になり、社会の仕組みが変わっても、相変わらずおなごのことは無視されたまま。 そうした中で喜多は、堂々と論を述べ、毅然として女性の参政権を求めていく。 議会の場で、「婦女は脳漿が乏しい」と平気で言い放つ反対派議員に対する喜多の意見陳述は、名演説といって他なりません。 当時は欧米でも殆ど女性に参政権が認められていなかった時代、喜多の先取の精神、その胆力は素晴らしい。 何より喜多という人物が傑出しているのは、決して言論だけの人ではなく、実践の人でもあったことです。 自らの家産をつぎ込んで、育院や学費援助を続けていたという。 同じ土佐出身の板垣退助から“同志”と呼ばれ、一緒に民権自由を求め続た女性。 その胸の内にあった思いは、現代においてもそのまま通じるものだと確信します。 なお、本作は喜多の視点に立った、<板垣退助の評伝小説>という側面も持っています。当時の政争状況がよく分かり、政治史の勉強にもなります。 上記喜多や、その後に続いた女性たちによる参政権を得るための闘いがあったことを思うと、昨今の選挙における投票率の低さは悲しい。 本作は、社会を変えることのできる権利を、変わらないからと実質放棄している人たちへの“訴え”ともなっている作品。 是非、多くの方たちに読んでもらいたいです。 ※ただし、投票といっても、ポピュリズムの甘言に乗せられてしまうのは困りますが。 第一部 天を仰ぐ/第二部 天に唄う/第三部 天までのぼれ |