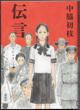|
「魚のように」 ★☆ 坊ちゃん文学賞大賞 |
|
|
|
坊ちゃん文学賞を受賞した「魚のように」は、親から優等生として信頼され、可愛がられていた姉が家を出奔した後、劣る子扱いされてきた弟である主人公もまた家を出て、当て所もなく川沿いを歩き続けるストーリィ。 歩き続ける中、主人公は姉とその親友だった君子との関係を回想していく。 何故に姉は、親友を裏切るような行動をしたのか。親からの信頼という束縛にがんじがらめにされてきた姉は、自暴自棄に走りざるを得なかったのではないか。 だとしても、主人公の孤独感が癒されることもない・・・。 「花盗人」も、「魚のように」と同様、中脇さんが高校生の時に書いた作品とのことです。 姉を愛する一方自分には冷淡な母親との距離感から、同様の想いを抱える友人と共に、家から盗み出した梅の木を持って一晩中彷徨う女子中学生を描いたストーリィ。 2篇に共通するのは、親から疎外されているという孤独感、心の痛みです。と言っても、もはや親が気持ちを改めてくれることを期待する様な年代ではない。それ故でしょうか、冷たい空気が読み手の胸の中に吹き込んでくるような思いがします。その点が印象的。 魚のように/花盗人 |