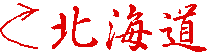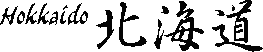 |
逆に、この点は私が再度訪問したり、たまたま気づかないかぎりは情報は更新されていないことになります。 せっかくの旅行計画が題なしにならないように、利用にあたっては最新の情報を直接確認してください。 旅の基本はすべてを自分で行うことにあるし、旅に関する情報の提供は助言を越えることはないと考えるからです。 |
| 当サイト内のリソース | |
| このページでは、北海道全般に当てはまるような情報に限って掲載しています。地域ごとの情報は次のページに分割されています。 | |
| 積丹を訪れる | 積丹 旅の情報 |
| 道東知床半島を訪れる | 知床・道東を旅するための情報 |
| 道央を訪れる | 道央 旅の情報 |
国内旅行の情報を収集するために利用したサイトのリンク集。 | |
| 旅の情報を仕入れる | 旅のリンク集 |
| 北海道に関連したサイト | |
| 鉄道の旅を計画する | JR北海道 |
| 空の玄関 | 新千歳空港 |
| 安く早く北海道入りをするには | 北海道国際航空 株式会社 |
| 北海道の動きを知るには | 北海道新聞社 |
| 書籍 |
| 私が読んだことのある本で、北海道に関連するものを、旅行計画の参考のために拾い出してみました。 |
| 北海道を読んで知る |
| 北海道の旅 串田孫一著 非常に多くの山岳随筆を書いている串田孫一氏の紀行文。昭和30年代に、北海道を歩き回った時の紀行文 である。時間は流れて、旅人の前に広がる現実の風景は大きく変わっているのであろうが、北海道を旅する人の感じる世界はさほど変わっていないというのが、 私がこの本を読んだ後の感想である。 |
| 平凡社 平凡社ライブラリー 1997年刊. |
| 旅を計画する |
| なまら蝦夷 宿主たちの旅案内
私が北海道を旅するとき持ち歩く唯一のガイドブック。それぞれの地域で宿業を営む宿主達の執筆したものであるから、
地元発の鮮度の高い情報となっているはずで私はもっとも信頼している。
改定され現在3号が発行されている。手書き印刷の同人誌に近いスタイルであるから、執筆者の宿や協力店と、
ごく一部の書店でしか購入できない。 連絡先:編集事務局(民宿ぽんぽん船内) 0134-27-0866。 |
北海道なまら宿主43人 2000年(3号)刊. |
| 全北海道公共の温泉がいど もともと、北海道は国内で最多の温泉数を誇る。 近年は、自治体が村おこしのために新たに温泉を掘っているから、これまで温泉としてはまったく 思いつかなかったような場所でも施設に出会ったりする。このような公共の温泉がまとめて紹介されている 本書は、北海道放浪の旅を計画するにあたって必需品であろう。 |
北海道総合出版 2000年刊. |
| とほ ひとり旅を楽しむための宿情報誌 旅の同行者数の調査によれば、ひとり旅行は全体の2パーセント強と取るにたららない数字である。 まだ、家族、職場を単位とした旅行が多数派のようだ。しかし、もし北海道だけで調べたらこの割合 はもう少しあがるのではないか。夏の北海道ではいたるところで見かける単独旅行者の宿泊の場を 提供しているのは、もともとが旅人であった宿主たちである。「とほの宿」といわれているこの本の載っ ている宿は基本的に相部屋制でそれ相応の低価格なのが特徴。 取り扱い店は増えて道内では 入手しやすくなったが、あらかじめ購入したければ、01562−7−3812で確認してほしい。 |
とほネットワーク 年ごとに刊行. |
| 北海道の百名山 道新スポーツ編 北海道の山の多くは、比較的整備されていない登山道から登る。これは山好きはたまらない喜びを感じる点であろう。 100も集めたとなると、私などは山名を聞いてもどこにあるのかまったく検討もつかないようなものが含まれることになるから、 載っている写真を見ながら、山行を練るのは楽しい。 平成10年から道新スポーツに連載されていたようでこれをまとめた本であるとかかれている。 ガイドブックとして作られてはいないから、実際に出かけるためには少し情報不足のようで、 他の山関連の本とあわせて利用することになるだろう。 |
北海道新聞社 2000年刊. |
| 知識を得る |
| 蝦夷北海道の謎 中江克己著 私が学校で学んだ歴史では、北海道は明治になってそれまで蝦夷地と呼ばれていた場所として 急きょ顔を出す。この時初めて政治的に重要なかかわりが出てきたからであろう。しかし、そこには人が住んできたのであるから、その前にも連綿と続く歴史を辿ることがで きるのは当然のことである。北海道の歴史を詳しく紐解いた研究書の類はいくらでもあるのであろうが、旅行を企てる者にとってさしあたって知りたいことを見つけるにはこのような書が有用である。 |
河出書房新社 河出文庫1997年刊. |
| 地名アイヌ語小辞典 知里真志保 著 国策として北海道の開拓が始まると、もともとそこに棲んでいたアイヌ民族の文化はことごとく無視された。 そんな中で唯一取り入れられたのが地名であったといえる。しかし、強引に表意文字である漢字を使った 表記にしたために、語音は不明確になったし、解読には手間を必要とする。 このような目的で使われる地名辞典はいくつかあるようであるが、アイヌ研究第一人者であった知里真 志保による本書は古典ともいえる権威をもっている。 |
北海道出版企画センター 1956初版. |
| きたぐにの動物たち 本多勝一 著 本多勝一氏が、朝日新聞社北海道支社勤務であった昭和36年に、59回にわたって連 載されたものとある。北海道の動物記とあって、この本もヒグマから始まる。大正14年初冬7人の 開拓農民を食い殺した穴持たず熊の惨事からはじまり、猛獣ヒグマは絶滅してほしい動物とし てあげられているのは、まだ日々自然の脅威に立ち向かう生活を求められていた当時の北海道 人々の考えを代表していたのだろう。自然保護を真っ先に考えなくてはならなくなった昨今の北海 道と40年の隔たりは大きい。 |
実業之日本社 1970年初版.(現在は、文庫版が朝日新聞社か ら出版されている.) |