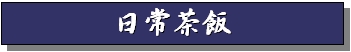
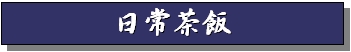
|
御馳走帖 ・ 冷奴 この時季、酒の肴の豆腐は冷奴に限る。 ビールや日本酒や、ウヰスキーにもあう。 豆腐を見ると「火吹き達磨」と渾名されたあの異様な顔を思い出すことがある。 司馬遼太郎の『花神』にでてくる村田蔵六(大村益次郎)のことで、豆腐が好物だったそうだ。 最近は、おぼろ豆腐というのをよく食べる。 綿豆腐の固まる前の豆腐らしいが、旨ければよいので講釈は要らない。 歩いて2分程度の近所に、コンビニがある。 コンビニに縁は無いが、昨日つまらない用で入ったら、「よせ豆腐」というのが目についた。 おぼろ豆腐に薬味とつゆが付いたものらしく、はじめ怪しんでみたが、何となく美味しそうにも見えるので買ってみた。 取り出してみると「一、まずは、そのままで。二、つぎは、にがり塩で。三、最後はつゆで、ゆず、ねぎをかけてお召し上がり下さい。」と書いてある。 箸の上げ下ろしにまで口出するとは小癪(こしゃく)な奴。 試しに云われるままに食べると、因果なことに旨かった。 食べた後で、生姜を足せばよかったと思ったが、 ゆずの細切りに気を取られたせいか、後の祭りなのが残念だった。 閑話休題(それはさておき)。 不在のため、このページ数日ほど休みます。 「用事がなければどこへも行ってはいけないと云うわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪に行ってこようと思う」とは、内田百閒の『阿房(あほう)列車』の有名な冒頭の一節であるが、 用事があって出かけます。 |
|
|
げきを飛ばす 文化庁の日本語世論調査で、「げきを飛ばす」「こそく」「ぶぜん」について、 七割の人が本来の意味とは異なる意味で理解しているという。 新聞記事によると「げきを飛ばす」について、本来の「自分の主張や考えを人々に知らせ同意を求めること」 とした人は15%で、「元気のない者に刺激を与えて活気付けること」が74%に達したとある。 七割とは大きく出たが、これは仕方のないことだと思う。 何しろ、朝日新聞だって誤って使っているのだから。 97年10月、サッカーの加茂監督がクビになった時に、朝日の朝刊三面に、 試合中の選手たちを指さして怒鳴りつけている写真がある。 下に、「4日のカザフスタン戦で厳しい形相でげきを飛ばす前加茂監督」とキャプションがついている。 これは、私が当時この記事を見つけて覚えているのではなくて、 高島俊男さんの『お言葉ですが…③』(文春文庫)からの引用である。 高島さんのコラムから引くと、 「ゲキを飛ばす」というのは、遠くにいる味方に呼応をよびかける書信を発すること。 たとえば鎌倉幕府打倒に立ち上がる決意をした武将が、 「共に挙兵しよう」という手紙を持たせて使者を各地に派遣する。 その手紙が「ゲキ」、漢字で書けば「檄」だ。 目の前にいるやつを叱りつけるのをゲキなんて言うものか。高島さんによると、新聞のスポーツ面はずっと以前(17年ほど前)から、 監督が選手を叱(しか)りつけるのを 「げきを飛ばす」と誤用しているそうである。 ところが、総合面にまで来たので長大息したと書いている。 そこで「げきを飛ばす」をキーワードに Google を検索すると、 テレビ朝日も誤って使っている。 木曜ドラマ「エースをねらえ!」の第三話のあらすじに、 ヨロヨロになるひろみに、コーチは「そこにボールがある限り、お前の足は動く!」とげきを飛ばす。此度のニュースを受けて嘆いてみせる新聞コラムがあらば、笑い者なり。 |
|
|
「ニューズウィーク」 2004.8.4 Newsweek日本語版を、久し振りに読んだ。 以前はよく読んでいたが、この何年かは暇がなかった。 紙面の構成が、以前とは大きく変わっている。 今週号のカバーストーリーは、「おかしいぞ!日本のマスコミ」で小見出しには、 「取材は受け身、リスクは冒さない。一般読者よりも体制側のご機嫌が大事。 「民主主義の番人」という役割を忘れたなれ合いジャーナリズムに、未来はあるのか」とある。 ざっと読んでみたが、特に見新しいことはない。 結局は、問題は日本の記者クラブ制度に行き着いてる。 そうなんだよ。 記者クラブ制度を廃止すれば良いことは、既に分っていることである。 政治も経済にしても、何が問題かははじめから分っていることで、 癌の部分を切り取ってしまえば、健康になるのだが、それが出来ないのが日本の問題なのである。 問題の癌には、いろんな利害や利権が複雑に絡まっていて、切り取ることが出来ない。 誰だったか忘れたが、話で聞いたのか読んで知ったか忘れたが、 この分りきった問題を、下手にいじると世の中不安定になって収拾がつかなくなる。 絡まったままでいる方が、かえって安定しているのが今の日本の状態なのである。 それよりも、アメリカのメディア(マスコミ)につての記事の方が興味深かった。 ひとつは、一部のアメリカの有力紙が結局は、イラク戦争の旗振り役を務める失態を演じてしまったという批判というか反省の記事である。 もうひとつは、ネットの台頭で新聞やテレビの権威は失墜し、ジャーナリズムの存在意義についての危機をリポートしたもの。 お互い様で、病んでいるのである。 あともうひとつ、「ヒラリー大統領への道」。 久しぶりに見るが、写真はなかなか絵になっている。 何だか、ジェフリー・アーチャーの小説を思い出した。 |
|
|
コンテンツ産業 今朝出かける前にテレビのニュースをチラッと見たら、韓国映画の隆盛ぶりを特集していた。 カンヌでグランプリを受賞した『オールドボーイ』が出ていた。 少し古い話になるが、この映画の原作は日本の漫画で、土屋ガロン作、峰岸信明画の同名のものである。 土屋ガロンは、狩撫麻礼の別名だそうだ。 カンヌ映画祭の時、どういう訳かマスコミは、主演男優賞の14歳の少年・柳楽優弥の話題だけで、 『オールドボーイ』のことは触れなかった。 今朝のテレビも同じである。 韓国の中央日報が、それを驚いて見せたので、それで知った。 原作の漫画は、韓国側に2百万円程度で売ったそうで、それをまた日本は2億円で買って、 今秋上映されるらしい。 日本のコンテンツ産業の弱さを象徴する逸話である。 アニメの世界でも、同じようなことがある。 人気テレビアニメの『ドラゴンボール』は、僅(わず)か一本1000ドルで輸出されたという。 問題は、産業としてのインフラが決定的に不足していることにあるらしい。 アメリカなどには、作品を手広く売り込んで歩く専門のプロデューサーがいるそうだが、日本では聞かない。 またリスクを回避するための、映像作品専門の保険会社があるという。 何年も前から、アメリカの映画制作会社は、日本のアニメ技術者の引き抜きをしている。 日本だと10万、20万程度の月収だったのが、向こうでは10倍位になる上、より完成度の高い仕事が出るという。 日本のアニメは長らく一流といわれてきた。 平安時代の絵巻物や江戸時代の浮世絵の伝統があり、感性は一流である。 しかし、それを支えるコンテンツ(情報の内容)産業としてのインフラが弱ければ、やがては沈んでしまう。 |
|
|
映画 『ライト・スタッフ』 何年前だったか、テレビかビデオで映画 『ライト・スタッフ』 を見たのを覚えている。 うろ覚えで恐縮だが、原作はトム・ウルフでアメリカ NASAの最初の宇宙計画「マーキュリー・プロジェクト」の話である。 監督もキャストも忘れたが、宇宙飛行士ジョン・グレン役はエド・ハリスだったと覚えている。 ディスカヴァリー号で、再び宇宙へ出た老人は御存じだろう。 ミッションは、人が宇宙で生存できるかの調査である。 その過程を克明に描いてるのが、この映画の魅力である。 アメリカを代表する一流の科学者が動員されるが、大混乱してしまう。 科学とは積み上げの学問で、先人が達成した成果の肩の上に乗って後人は進むといわれている。 それ故科学は日進月歩、着実に進むとものと思われがちだが、実は違う。 宇宙に出るには、音速をはるかに超える速度の中にいなければならないし、外は真空である。 高名な学者が、真空の中では人は気絶するのではと言う有様である。 さらに、宇宙飛行士としてふさわしい(ライト・スタッフ)のは誰かと迷う。 サーカスの飛び芸人か、それともスポーツ選手か。 結局選ばれたのは、空軍パイロットだった。 なぜか学歴のせいで、最初に音速の壁を破ったパイロットは外される。 映画は、この見捨てられたパイロットを複線にして描く。 先日、NASAの公式日本語ページがあるのを知った。 NASAの公式日本語ページ http://www.hq.nasa.gov/office/codei/japan/nasatoday/index2.html |
|
|
河童忌 今日は芥川龍之介の命日、河童忌である。 芥川は、繊細で神経の細かい性格の人といわれている。 しかし、生活面ではごく普通でむしろ模範的な人だったようである。 大学を出た後しばらくは、横須賀の海軍機関学校の教官として英語を教えていた。 教官ぶりは良く、教師に適任の人だったらしい。 文夫人との間に三人の男児があり、たいへん子煩悩だったという。 教育熱心でもあったようで、子どもたちそれぞれ、別の分野の芸術家に育てようと考えていたそうだ。 その後、長男比呂志は俳優・演出家となり、三男也寸志は作曲家となった。 次男は、確か戦死したのだと思う。 関東大震災では、室生犀星は東京を引払い郷里の金沢に帰るが、 東京生まれの芥川は東京を離れることが出来ない。 そのうち不穏なデマが流れ、噂を信じた芥川は自宅の前に竹槍を持って、終日立っていたという。 文夫人の回想を高校の頃読んだが、よく覚えていない。 覚えているのは、芥川の様子がおかしいので、色々と子どもの用事を作っては、芥川の気をそちらに紛らわせたという話と、 芥川が亡くなったときは暑い日で、氷屋から氷を買ってきて、遺体が傷まないよう気を遣ったという話くらいである。 同じ頃読んだ、漱石と芥川の往復書簡はよく覚えている。 若い頃の芥川が夏に、久米正雄とともに避暑地から漱石を見舞った手紙を出す。 漱石が伊豆の修善寺温泉で「大患」した何年も後の、漱石最期の年である。 この年(大正五年)の二月に芥川は「鼻」を発表し、漱石に賞讃されて世に認められる。 その手紙は溌剌(はつらつ)としている。 漱石は感激のあまり、「あせってはいけません」、「牛のように進め」と激励の手紙を書いている。 |
|
|
「ウイスキー今昔物語」 日経新聞HPの企業PR「C-Style」にある「ウイスキー今昔物語」を見たら面白かった。 ニッカウヰスキーの三代目マスターブレンダーと、銀座老舗のバーテンダーの対話である。 舶来ウイスキーしかなかった戦前、飲み方は二種類しかなかったそうで、 喉の乾いた時はハイボール、そうでない場合はストレート。 ハイボールは、炭酸水割りのことである。 最近、流行のきざしがあるそうだ。 ストレートの方は、チビリチビリとやったのだろう。 水で割っても良さそうだが、水で割ったらウイスキーに失礼だとされていたとある。 「なぜなら、外国人がそうしていないから」というのが可笑しい。 なぜしないかというと、単に向こうでは水が悪いからという事で、 それでハイボールが流行っていた。 戦後1952-3年(昭和27-8年)頃に水割りが現れる。 あるとき誰かが、日本の水の手軽さ、安さ、おいしさ、そういったものにはっと気がついたという。 この「C-Style」というPRのページは、他にクルマや映画の話題があってなかなか面白い。 その中でジョディ・フォスターのインタビュー記事があるが、 『羊たちの沈黙』の頃と比べて顔がまるで別人に見えたので少し驚いた。 NIKKEI NET 「C-Style」のURL http://www.nikkei.co.jp/style/ 
|
|
|
「猛暑警報」を発令しては 7時のニュースは、昨日は甲府で40.4℃、一昨日は千葉では40℃で都心は39.5℃といってた。 気象庁発表の気温の測定は、地上1.5メートルの高さで、風通しの良い日陰で行なうから、 日陰が異常に高いことを示している。 最高気温が25℃を超える日を夏日といい、 最低気温が25℃を超える夜を熱帯夜というから、いまの気温は尋常ではない。 先日テレビで医者が、「体温より高い所に出て行くことは、危険な冒険」 だと言っていたが、大げさではなく本当のことだろう。 熱中症になってもおかしくない。 いくら日差しが強くても日陰に入ると涼しいのが、通常の夏であった。 この猛暑は、気象の原因ばかりでなく、緑のない地表のせいだろう。 アスファルトとコンクリートだらけで、草木の少ない街になったせいだろう。 風の通り道に、ビルを乱立したからだろう。 土木工学は、Civil Engineering のことで本来都市工学を意味する。 なのに、街のつくりは見もせず建物ばかり見ている。 二年前の夏、地方の田舎に行ったら気温が10℃以上も低いのに驚いた。 国土交通省は、ビルの屋上を緑化する施策を考えているようだが、 ちっとも埒(らち)が明かない。 それより、厚生労働省は「猛暑警報」を発令してはどうか。 気象庁が発表しても意味はない。 健康と労働を監督する役所である。 労働を制限すべきだが、靴べらみたいな大臣が拒むなら代わって発令してやろう。 気温が体温を超えたら「猛暑警報が発令されました」、 「生命の危険がありますので、外出は止めましょう。 出勤、登校は止めましょう。 どうしてもというのなら自己責任で」。 冷房のある建物は全部避難所にして、猛暑難民がドット押し寄せて来て占拠して、 誰も働かなくなれば、せっかく回復してきた経済に水を差してはいけないと、 あわてて木をどんどん植えるようになるだろう。 |
|
|
食い意地を張らす 食べるのはいつも腹八分目程度であるから、私は貝原益軒の『養生訓』にある「八九分にてやむべし」 の教えに従っている。 というより、偶然そうなのだから自慢にはならない。 そういうことなので、食い意地を張った人にはかえって関心を持ってしまう。 正岡子規は、三十五歳で結核で死んだ。 カリエスという脊髄の結核である。 六年近く病床にあり、毎日痛い痛いと泣きながら『病牀六尺』を書いた。 それでも食欲は旺盛で、ある時は夕食に焼いたイワシを十八尾食い、間食にはスイカを十五切れ、 桃の缶詰三個を一度に平らげている。 食いしん坊といえば、若い頃の内田百閒である。 夏目漱石の同じ門下生である鈴木三重吉が言った悪口は、 「内田のヤツ、貧乏だ貧乏だとぼやいてゐるが、あの野郎、家で毎晩カツレツを七八枚喰らひ、人が来れば麦酒(ビール)を自分一人で一どきに六本も飲んで、その間一度も小便に立たないとほざいてる。 それを自慢にしてやがる、あん畜生」である。 それに対して百閒は、「そんなにぼろくそに云はれなくてもいいが、しかし丸で身に覚えのない事ではない。」と、とぼけている。 鈴木三重吉は、大正時代に「赤い鳥」を創刊した人で、童話と童謡を掲載した。 漱石の弟子たちに呼びかけ、子供のための良質な童話を書いてもらった。 芥川龍之介の「杜子春」や「蜘蛛(くも)の糸」はそれに応じて書かれたものである。 ただし、三重吉は酒乱だったというから、 食い意地が張っているだけの百閒の方が、よっぽどお行儀が良かったともいえる。 今日は、土用の丑の日。 |
|
|
故・森嶋通夫氏 理論経済学者の森嶋通夫・ロンドン大学名誉教授が13日に亡くなったことを昨日知った。 日本人で唯一、ノーベル経済学賞の候補と噂さていた人で、秋になると書店に 岩波新書の『イギリスと日本』等が平積みされていたのを覚えている。 何年か前から受賞者の傾向が変わったみたいで、見込みは薄れてしまったようだ。 日本人には珍しく相当ラディカルな人だったらしい。 岩波ジュニア新書に『学校・学歴・人生』という教育論の著書がある。 中高生向けの本であるが、はしがきにこうある。 「最後に、お願い。読み終わったら、お父さん、お母さんや兄弟の人たちにも本を回してください。 日本の大学はひじょうに悪いので---まるで高等幼稚園のようになっているので---ぜひ改革しなければなりません。(中略)大声を出して、大学改革を要求してほしいのです。 行動のともなわない読書は無意味です。」また「もしこんな先生がイギリスにおれば、学生につるし上げられて、一日で辞職しなければなりません。みなさんも負けずに、云々」といった調子である。 ただし、この本が書かれたのは二十年前らしい。 『智にはたらけば角が立つ』など自叙伝が何冊かある。 喧嘩ばかりの人生のようで、イギリスに移ったのも喧嘩して日本を飛び出した感がある。 喧嘩して痛快かというと、失う者もある。 渡英は、病身の親の寿命を縮めたという。 五年前、著書『なぜ日本は没落するか』で批判されて腹を立てた日本の経済学者と、雑誌で論争になる。 噛合わず、途中でたち切れになったと記憶する。 |
|
|
御馳走帖 ・ 牛肉料理 内田百閒は、主治医の小林博士に牛肉は食べてはいけないと命じられる。 しかし、すき焼が食べたくて仕方がない。 百閒は、「牛は冬の間はワラしか食っていない。牛の本質はワラである。 ワラを牛の体内に入れて蒸すと牛肉になる。ワラが腎臓に悪いというのはおかしい」と変な理屈をこねる。 それで、牛肉のすき焼のことをワラ鍋と呼んで、ワラを食うと言っては、しきりにすき焼を食べている。 牛肉を食べる習慣は、明治維新の文明開化と共に日本に入ってきたというから、百年以上前から食べていることになる。 百年以上も食べれば和食である。 すき焼はその典型で、 初めは牛鍋といっていたらしいが、昭和のころからすき焼というようになったという。 江戸時代までは、仏教の影響からか四つ足は不浄と考えて、牛は食べなかった。 しかし、肉は食欲の源だから、頭では禁じても口あるいは胃袋が欲したのだろう。 猪、鹿、馬は食べたという。 猪はボタン、鹿はモミジ、馬はサクラと風流な名前をつけて、「薬」と称して食べたそうだ。 何年前だったか江戸時代・長崎の武家屋敷跡地から、ナイフやフォークなどステーキ用の食器を発掘したという記事を新聞で読んだ覚えがある。 奉行所の役人はステーキの味を、出島のオランダ人から教わったのかもしれない。 |
|
|
知的財産と帝国の逆襲 公正取引委員会が米マイクロソフト(MS)に対して、独占禁止法違反で排除勧告した。 日本のPCメーカーとの契約に盛り込んだ、 NAP条項(特許非係争条項:non-assertion of patents)が違法で、条項を削除するよう求めた。 NAP条項とは、MSがメーカーにWindowsの使用を認める代りに、相手企業の特許を「タダ」で使えるというものである。 MSがNAP条項を導入したのは1993年。 当時IBMやNECなどは膨大な特許を持つ。 不注意に特許を侵害する危険すらあった。 そこで一計を案じた。 Windowsの新製品情報をメーカーにいち早く提供、価格も割安にした。 見返りに特許侵害で訴えることを封じる契約を結んだ。 PC市場が飛躍的に成長していた当時、メーカーは黙って受け入れた。 MSは急成長し「帝国」と呼ばれるまでになり、米国を始め海外でも独禁法訴訟で各国政府と争うようになった。 そして昨秋、関西のある大手家電メーカの技術者がWindowsに自社の技術が使われていることに気づいた。 特許侵害で訴えることができないので、経済産業省に相談。 経産省は別のメーカーにも同種の問題があることを知り、公取委に話を持ち込んだ結果が今回の排除勧告である。 以上が、14日の日経新聞のダイジェスト。 MSは排除勧告を受け入れず、裁判で争うとしている。 背景に、PCが以前のパソコンからデジタル家電の分野へ移りつつあることである。 この分野は日本メーカの牙城で、AV(音響・映像)特許を多く持つ。 MSが初めからAV特許を狙ってNAP条項を考えたのかは不明だが、 認めた日本メーカーは当時こうなることを予測していなかったのかもしれない。 第二に、政府の役割。何年か前から政府は、知的財産の保護を言うようになった。 排除勧告には、経産省の強い影響が伺える。 一方で、かつてはMSと係争していた米司法省とは和解し、今や蜜月関係にあるという。 第三に各国政府が採用するOSは、WindowsからオープンソースのLinuxに移りつつある。 MSにとって、AV特許を攻略することは今後の戦略の要となる。 今やMSと米政府の利害は一致している。 これは、日米政府間の争いに発展する可能性もある。 また、NAP条項を違法と認定したのは日本が初めてで、 MSに対する各国の独禁法訴訟にも影響するかもしれない。 勿論(もちろん)、MSは譲れないだろう。「帝国の逆襲」の始まりである。 長くなって面目ないが、この話つづく ・・・(かもしれない)。 |
|
|
梅雨が明けたり まだのところもあるが、私のところは梅雨明けしたらしい。 あまり雨は降らなかったので、水不足が気に掛る。 本来の梅雨は、あまり強くない雨足が長くつづくような雨だった。 あじさいの花を彩り風情があった。 どこから来たか雨蛙(アマガエル)が庭に現れたり、 雨上がりの道ばたでカタツムリに出会ったり、雨の中の散歩も悪くはなかった。 梅雨明けのころには、夕立が通り過ぎると地表が一気に冷えて心地よかった。 気象がおかしくなったのは、十年ほど前からだろうか。 黒澤明の三十作目にして最後の作品『まあだだよ』は美しい映画である。 四季の移り変わりと、雨、夕立、満月の夜、夕焼けといった日本の情景が描かれる。 同時にたくさんの唱歌が出てきて、歌詞の響きと旋律がとても良い。 おつきさま 石原和三郎 作詞 納所弁次郎 作曲 一 おつきさま、えらいな、 おひさまの、きょうだいで、 みかづきに、なったり、 まんまるに、なったり、 はる、なつ、あき、ふゆ、 にっぽんじゅうを、てらす。 二 おつきさま、わかいな、 いつもとしを、とらないで、 くしのように、なったり、 かがみのように、なったり、 はる、なつ、あき、ふゆ、 にっぽんじゅうを、てらす。 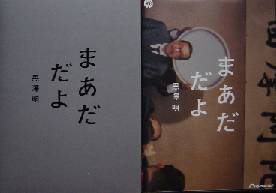
|
|
Copyright(c) 2004 Yamada, K