 日時 平成13年5月23日(水)−25日(金)
日時 平成13年5月23日(水)−25日(金)| 作成者 | BON |
| 更新日 | 2001/05/31 |
 日時 平成13年5月23日(水)−25日(金)
日時 平成13年5月23日(水)−25日(金)標記研究発表会に参加しました。全体に,年々参加者の発表内容及び論文のレベルは向上していると考えますが,特にプレゼンテーションのレベルアップは目を見張るものがありました。時間及び各種用事の都合で全部を聴講できなかったのは多少残念ですが,自分の興味のある分野を中心に,聴講で得たインプレッションなどを紹介します。要稿集をおもちの方は,ページを記述しておきますので,これも参考にしながらご覧くださいませ。
着色した項目は,特に今後の設計計画などですぐに参考になる情報を含んでいるという印象を受けたものです。ちなみに,インターネット活用関係の発表が数点あったが,いまのところは取り組みへの決意表明レベルで,まだまだこれからの印象でした。
| 第52回全国水道研究発表会 水道協会主催の由緒正しい研究会。 |
【参考】
あくまでも私見と印象ですので,ご異議もあろうかと思いますが...請反論,ご意見!図表などは全て要稿集より。ちなみに,夢に見るのはわんこそばです(^o^)。
![]() (3−5)豊平川水系における流達時間予測システムの構築(札幌市水道局 末永氏)p81
(3−5)豊平川水系における流達時間予測システムの構築(札幌市水道局 末永氏)p81
上流域に発電用ダムを有するため,流況の変化の著しい河川を対象とした流達シミュレーションの構築と運用結果。ここまで極端に水源水質変化が発生するケースは限られるが,実際上の応用性は高いと考えられる。流速データをフロートで手に入れているあたりに担当者の苦労が伺える。
【備考】
![]() (9−1)水道施設構造物の耐震診断手法(名古屋市上下水道局 佐藤氏)p654
(9−1)水道施設構造物の耐震診断手法(名古屋市上下水道局 佐藤氏)p654
名古屋市における耐震診断は1次,2次の段階があることが特徴のようで,以前関わった時も液状化現象について2段階の診断を行ったことが思い出される。せん断破壊は危険なので,曲げ破壊モードになるような形状とすべし,という結論のようだが,内容自体は難しくてよくわからなかった。
![]() (9−2)高架水槽を対象とした動的解析に関する一考察(日本上下水道設計 大嶽氏)p656
(9−2)高架水槽を対象とした動的解析に関する一考察(日本上下水道設計 大嶽氏)p656
手間のかかる動的解析を用いなくても十分な精度で耐震構造解析ができるという意見。十分に説得力があったが,動的解析をやったことのない人には,動的解析を要求されて地獄の苦しみを味わっている発表者たちの心の叫びが通じていない可能性も。
![]() (9−3)古地形が地震時の管路被害に与える影響に関する研究(水道管路総合研究所 岸田氏)p658
(9−3)古地形が地震時の管路被害に与える影響に関する研究(水道管路総合研究所 岸田氏)p658
この日の聴講では一番のヒット。古地形図を重ねることで,管路被害の生じやすい地形を相当レベルで予測でき,事故率の補正係数を提案している。古地図は国土地理院で入手でき,コピーも可能とのこと。どこでも平易な努力で適用できる点が特に優れると思うので,是非試してみたい。発表技術にも卓越したものがあった。
古地形を考慮した地域地形・地盤特性については,以下のようにまとめられている。(要稿集,発表より)
| 分類 | Cg 危険度 |
|
| 改変山地 | 1.1 | 基盤岩やその大規模改変地域 |
| 改変丘陵地 | 1.5 | 段丘や断層近傍の大規模改変地域 |
| 谷・旧水部 | 3.2 | 埋立地,池,旧河川,旧溜池,旧海岸 |
| 沖積平地 | 1.0 | 沖積層,崖錘,自然堤防,後背湿地 |
| 良質地盤 | 0.4 | 非改変の基盤岩,段丘,断層近傍等 |
| 埋立地 | 6.6 | 埋立地 |
![]() (9−4)自信による水道管路の被害予測(東芝 平原氏)p660
(9−4)自信による水道管路の被害予測(東芝 平原氏)p660
データベースに対してIF条件式を張り巡らされた論理スクリーニングをかける手法の提案。データの整備が大変なので実用性には疑問がある。(確度の高いデータを集める作業が大変なのだ)手法の紹介だけで計算事例が示されない点にも辛目の評価をしたい。
![]() (9−5)水道管路地震被害予測システムの開発(東京都水道局 岡村氏)p662
(9−5)水道管路地震被害予測システムの開発(東京都水道局 岡村氏)p662
想定する地震の条件を入力することで,都内各地での地震力と被害予測がぱっとでる仕掛け。すばらしいの一言だがブルジョワすぎてよそで同じものを作ることは不可能でしょう。
![]() (9−6)尼崎浄水場におけるろ過池の覆蓋(阪神水道企業団 岡本氏)p664
(9−6)尼崎浄水場におけるろ過池の覆蓋(阪神水道企業団 岡本氏)p664
プレゼン能力はものすごいの一言。ろ過池に蓋をつけた必然性など,手続きを丁寧になぞっている点には手作り感があってよいが,「蓋をつけただけ」という辛口の評価も。
![]() (9−7)大阪市水道における地震モニタリングシステムの構築(大阪市水道局 土山氏)p666
(9−7)大阪市水道における地震モニタリングシステムの構築(大阪市水道局 土山氏)p666
地震データ収集システムの報告。地震計を各地に配置し,オンラインで情報を収集する。大地震時のライン管理は2会社を利用したりメモリで対応とのこと。
![]() (9−8)広域情報ネットワークの構築(阪神水道企業団 本荘氏)p668
(9−8)広域情報ネットワークの構築(阪神水道企業団 本荘氏)p668
用水供給/水道事業体間の情報ネットワークの構築努力。緊急用で整備を開始したが,平時使用まで用途を広げることができたとのこと。2社契約によるリスク分散は9−7と同じ。
![]() (9−9)大都市圏における広域的なバックアップ体制の整備に関する検討(水道技術研究センター 渡辺氏)p670
(9−9)大都市圏における広域的なバックアップ体制の整備に関する検討(水道技術研究センター 渡辺氏)p670
首都圏を対象として,広域的なバックアップシステムのケーススタディを行った報告。3ヶ年の委員会活動をとりまとめたもので,さすがに内容の濃さがにじみ出ている。座長のお褒めあり。
![]() (9−10)災害時相互応援協定にもとづく鳥取県西部自身における災害支援の報告(防府市水道局 福冨氏)p672
(9−10)災害時相互応援協定にもとづく鳥取県西部自身における災害支援の報告(防府市水道局 福冨氏)p672
災害復旧支援の事例。平時より近隣事業体間で勉強会を持っていること,応援協定を持っていることなどにより,復旧支援がスムーズに行った事例で,非常に示唆に富む内容であった。特筆すべき知見として,
などが示された。報道支援については,報道側がストーりーを作ってしまうので,なかなかうまくいかないとのこと。
【備考】
![]() (1−1)今後の施設更新による水道事業経営への影響の検討(大阪府水道局 森本氏)p2
(1−1)今後の施設更新による水道事業経営への影響の検討(大阪府水道局 森本氏)p2
資本調達の手法をいくつか比較検討した事例。株式会社化の最大のメリット,経営の柔軟性について過小評価していると思えたが,怖くて質問できなかった。
【備考】
![]() (1−2)これからの社会基盤整備としての水道施設整備(I)(阪神水道企業団 中安氏)p4
(1−2)これからの社会基盤整備としての水道施設整備(I)(阪神水道企業団 中安氏)p4
企業団における新設浄水場について,PRの重要性を明確に打ち出した事例。プレゼン技術には脱帽。ただ,懇談会に市民参加のない点をつかれた。なかなか厳しいつっこみであった。
![]() (1−3)これからの社会基盤整備としての水道施設整備(II)(阪神水道企業団 小川氏)p6
(1−3)これからの社会基盤整備としての水道施設整備(II)(阪神水道企業団 小川氏)p6
1−2に続き,浄水場の浄水池上部分をガーデニングをテーマとして一般会社に定期借地権契約にて貸し出した事例。これからの水道整備に対して大きな示唆をしめしており,非常に参考になる。プレゼンもすばらしかった。
特に,法的チェックの過程がネックになるため公園にすらしにくかった現状を打破した画期的な取り組みとして高く評価したい。土地借款契約は,「期間20年の事業用定期借地権契約」で締結されているとのことで,地方公営企業法の改訂に伴い可能となった方法であるとのこと。なお,借地の単価は300円/m2とのこと。
同時に,誘致する企業のイメージの絞り込み方にも大きく感心させられた。ガーデニング,クアハウス,スポーツ施設などを比較して,脱水ケーキの活用が視野に入るガーデニングを選定,これを中心としたホーム-センターを事業コンペ方式により選定したとのこと。
![]() (1−4)水道事業におけるユニバーサルデザイン導入への一考察(盛岡市水道部 村田氏)p8
(1−4)水道事業におけるユニバーサルデザイン導入への一考察(盛岡市水道部 村田氏)p8
発表者自身が重度障害者であるためか,非常に説得力があった。なかなか気づかない視点に一石を投じた点を大きく評価したい。要稿集に提案を掲載しているので,実施結果の発表を待ちたい。
![]() (1−10)水質試験年報の電子出版「CD−ROM版の作成」(熊本市水道局 南部氏)p20
(1−10)水質試験年報の電子出版「CD−ROM版の作成」(熊本市水道局 南部氏)p20
CD−ROMによる年報の作成事例。非常にできがよい。是非入手してもらいたいものです。作業は業務の合間に人手で行ったもので,表現技術の継承が今後の課題とのこと。個人的には,今後の報告書などの進化先をみているようで,非常に心強くおもった。
【備考】
![]() (2−4)飲料水としての水道水の使用量に関するアンケート調査(武蔵工業大学 長岡先生)p30
(2−4)飲料水としての水道水の使用量に関するアンケート調査(武蔵工業大学 長岡先生)p30
水道水が飲まれているのかどうかをアンケートによって調べた事例。飲料水としての使用自体が水道に与えるインパクトは限られるものの,品質イメージとして分析する意義はあると思う。30代が水道水を飲まない実態が興味深い内容があった。
![]() (2−5)一般家庭における用途別水使用量(II)(大阪市水道局 瀧川氏)p32
(2−5)一般家庭における用途別水使用量(II)(大阪市水道局 瀧川氏)p32
1−2人世帯よりも3人世帯の方が一人あたり有収水量が大きいという報告で,興味深い示唆があった。また,個別の用途についてもその増減の要因を検討している。サンプルの普遍性には今後の調整余地はあるようだが注目に値する。
![]() (2−6)家庭における節水型給水機器の普及状況調査(神奈川県企業庁水道局 小林氏)p34
(2−6)家庭における節水型給水機器の普及状況調査(神奈川県企業庁水道局 小林氏)p34
アンケート結果からの類推で,節水型(風呂水使用)洗濯機の大きな影響を指摘,分析している。
![]() (2−7)大規模商業地域における土地建物用途別原単位の研究(東京都水道局 藤原氏)p36
(2−7)大規模商業地域における土地建物用途別原単位の研究(東京都水道局 藤原氏)p36
意欲的な研究で,商業用地の使用水量面積原単位はそのまま指針に掲載したいくらいのできばえ。是非ご参考のほどを。全体に大規模高集積事業体としての事例であるので,適用性については少し考慮も必要かも。
要稿集より,面積原単位[L/m2日]について紹介。
| 種別 | 原単位 |
| 事務所建物 | 7.5 |
| 専用商業施設 | 14.0 |
| 住商併用建物 | 10.5 |
| 宿泊施設 | 7.5 |
| 遊興施設 | 21.5 |
| スポーツ施設 | 14.5 |
| 興行施設 | 6.5 |
![]() (2−8)ネパール水道整備プロジェクト評価のためのアンケート調査(立命館大学 大崎氏)p38
(2−8)ネパール水道整備プロジェクト評価のためのアンケート調査(立命館大学 大崎氏)p38
水道未普及の発展途上国において水道の便益を分析した事例で,なかなか国内で仕事をしていても気がつかない点で示唆に富む発表であった。水道整備による便益のアローダイヤグラムが特に興味深い。
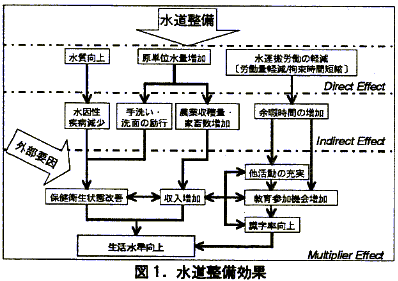
【備考】
![]() (2−9)施設整備指標の策定(東京都水道局 平野氏)p40
(2−9)施設整備指標の策定(東京都水道局 平野氏)p40
東京都版「ふれっしゅ」の策定経緯で,徹底して需用者の視点を取り入れようとする姿勢に好感が持てる。
![]() (2−11)住宅団地計画に対する配水施設整備の1手法(下松市水道局 友森氏)p44
(2−11)住宅団地計画に対する配水施設整備の1手法(下松市水道局 友森氏)p44
配水施設計画としてはごく一般的な団地対応だが,おろそかになりがちな法的矛盾に配慮している点に行政マンらしさを感じた。
![]() (2−13)寿命曲線を用いた施設更新費用の試算(大阪市水道局 田中氏)p48
(2−13)寿命曲線を用いた施設更新費用の試算(大阪市水道局 田中氏)p48
故障確率を取り込んで,将来発生すると考えられる維持修繕費のシミュレートを試みたもの。仮定式によって結果が影響を受けるのは致し方ないが,機材の性能向上の表現など,いろいろ聞いてみたいことがあったのだが...
![]() (2−14)漏水被害シミュレーションの検討(大阪府水道部 永良氏)p50
(2−14)漏水被害シミュレーションの検討(大阪府水道部 永良氏)p50
漏水の被害が発生する前に,法定耐用年数を目安とした予防保全としての更新を行うことによって,最終的は損失を抑制できるというシミュレーションの結果。
![]() (2−15)鋳鉄管路の診断及び更新・更生計画策定手法(水道技術研究センター 舟橋氏)p52
(2−15)鋳鉄管路の診断及び更新・更生計画策定手法(水道技術研究センター 舟橋氏)p52
鋳鉄管更新マニュアルの概要を説明。マニュアルによって,水道管の更新に関する手法の提案ができるものと期待される。鋳鉄管の問題を抱えていなくても,マニュアルは購入しておくべきでしょう。(多少身内びいきとの批判は甘受)
![]() (2−16)地震被害予測システムを用いた老朽管更新計画の策定(釧路市水道部 小田嶋氏)p84
(2−16)地震被害予測システムを用いた老朽管更新計画の策定(釧路市水道部 小田嶋氏)p84
幹線の耐震化の重要性を,数値的に実証した研究。大口径管と小口径管を効果的に組み合わせることを推奨しているので,私的には非常に同感を覚えた。
![]() (2−17)横浜市の老朽管対策(横浜市水道局 代田氏)p56
(2−17)横浜市の老朽管対策(横浜市水道局 代田氏)p56
経年管の定義がなかなか合理的で参考になる。データの蓄積の重要性を再認識させられた。
【備考】
![]() (2−18)京都府営水道各浄水場における環境対策(京都府企業局 菱井氏)p58
(2−18)京都府営水道各浄水場における環境対策(京都府企業局 菱井氏)p58
ISO14001シリーズ取得の経験から。苦労したのは,2500項目にわたる抽出作業とか。手作りだったとのこと。制御の細分化によって薬品注入量を減らすことができたとの報告には参考になる。
![]() (2−19)基本計画での適用を想定したライフサイクルコスト手法の検討(大阪工業大学 松山氏)p60
(2−19)基本計画での適用を想定したライフサイクルコスト手法の検討(大阪工業大学 松山氏)p60
費用便益分析などでの「便益」の評価の一手法として,エネルギーベース(TOE),炭素収支ベース(CO2)の評価を可能とするための原単位の開発に関する報告。観念的な指標でどうしても粗があるが,エコロジーの考え方が市民権を得るなかで,無視できなくなりつつある。コストベースでの収支と同じくらいの精緻な積み上げができるようになればよいが...
![]() (2−20)環境面を考慮した浄水施設の費用・効果の検討(鳥取大学 飯田氏)p62
(2−20)環境面を考慮した浄水施設の費用・効果の検討(鳥取大学 飯田氏)p62
2−19と同じく,エネルギーベース,炭素収支ベースでの便益評価に関する検討報告。
【備考】
![]() (5−50)大規模PCタンク内の水流に関する模型実験(神奈川県内広域水道企業団 織田氏)p414
(5−50)大規模PCタンク内の水流に関する模型実験(神奈川県内広域水道企業団 織田氏)p414
大規模なPCタンク内での水の滞留を防ぐための模型実験による流入・流出管配置方法の分析事例。流入管の形状については私もいままで見落としていたと反省。今後の設計にて参考にさせてもらいます。
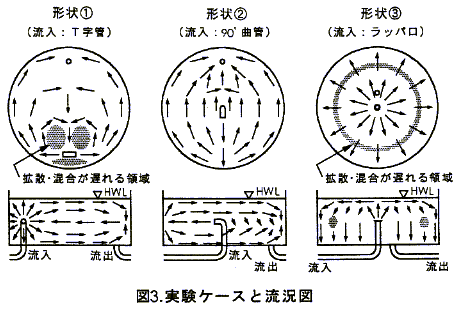
【備考】
![]() (5−37)管路の浅層埋設によるコスト縮減効果に関するフィールドレポート(三重県企業庁 澤井氏)p388
(5−37)管路の浅層埋設によるコスト縮減効果に関するフィールドレポート(三重県企業庁 澤井氏)p388
浅埋によって伏せ越しを削減することで,大幅なコスト縮減を図れたとする報告で,日進量の改善など,事例として興味深い。止めボルトを差し込むため,配管の立ち上がり部分が長いことなど,今後の開発上の問題も指摘。
![]() (5−38)浅層埋設の実施と埋設表示シートの改良(盛岡市水道局 蛇口氏)p390
(5−38)浅層埋設の実施と埋設表示シートの改良(盛岡市水道局 蛇口氏)p390
発表者の名前がいいですね−(^o^)。埋設表示シートの改良とその検証結果を報告。製品仕様として指定してしまうあたり,さすがというべきか。
【備考】
![]() (8−54)紫外線吸光度E260を利用した浄水処理管理への基礎的研究(札幌市水道局 星野氏)p638
(8−54)紫外線吸光度E260を利用した浄水処理管理への基礎的研究(札幌市水道局 星野氏)p638
有機物等の指標として,過マンガン酸カリウム消費量よりもE260の方が指標性や計測の容易などで優れるとの実例報告。濁度の代替指標としての提言も。有機物の性状の違いへの対応や,換算係数に関するノウハウなども今後研究してもらえれば,そのとおりになる可能性もあるかと思われる。今後に期待。
![]() (8−55)味覚センサによる原水及び浄水の水質監視システムの検討(アンリツ 内藤氏)p640
(8−55)味覚センサによる原水及び浄水の水質監視システムの検討(アンリツ 内藤氏)p640
私的には注目度ぴか一の報告。まだ可能性の段階ではあるが,今後も注目していきたい。
【備考】
![]() (8−57)固体硫黄による生物学的脱窒素(武蔵工業大学 横山氏)p644
(8−57)固体硫黄による生物学的脱窒素(武蔵工業大学 横山氏)p644
酸素や温度制御によって,硫黄を水素受容体とした硝酸性窒素除去を目指す手法で,非常にユニーク。酸化還元電位を指標とし,目標とすべき値を-120〜-50と具体的に持っているなど,研究の完成度が非常に高い。個人的には,水道管内での腐食性の懸念が払拭できないが...
【備考】
![]() (8−58)外部支援を利用した水質管理データベースの構築(新潟市水道局 川瀬氏)p646
(8−58)外部支援を利用した水質管理データベースの構築(新潟市水道局 川瀬氏)p646
水質管理情報等をデータベース化した経験の報告。職員酸化,見慣れたレイアウトの活用,直営と委託の使い分け,マニュアルの整備,などのノウハウが示された。システム設計を請け負うSEの苦労は増しそうな気がしたが,自助努力の進展はいいことでしょう。
【参考】