![]() 新着情報!10/22 <お台場のハゼ、100%東京ローカルだぜ!。> by 丸帆亭
新着情報!10/22 <お台場のハゼ、100%東京ローカルだぜ!。> by 丸帆亭
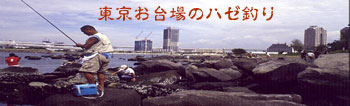
| 釣りはハゼに始まってハゼに終るなどと言いますが、 さてはて丸帆亭の釣りも終りなのでしょうか? いえいえ!それは、初心者にも楽しめるけど、 実は奥深い釣りだと言う"喩え"なのですね。 もう4年程、お台場に通っておりますが、 人様にご報告できるレベルにはなかなか到達できないのであります |
東京港の奥、お台場のフジテレビ前の人口磯でハゼを釣って、キャッチ&ストマックしてしまう。
それは東京ロコの秘かな楽しみ。「えー、そんな所の魚、食えるのかー?」って声が聞こえそうですが、
これが、かなり美味いんですよね。ハゼはかなり水の汚れた水域でも、美味しく食べられる魚だと言う事は、
海釣りをやる方ならご存知でしょうが、お台場のハゼは何故か特に美味しいのです。
水質も近くの浄水場から出ている水のおかげか、実はかなりきれいなのです。
料理としては天プラかカラ揚げが普通ですけど、フワフワホロホロした食感と、口のあとに残る旨味は絶品ですよ。
さて、食欲だけで、通っている訳ではございません。ハゼ釣りの何処が面白いのかを少々。
まず、数を釣るには、その為の技術やノウハウが必要なのですが、たかがハゼ、されどハゼ、で、こと東京港のハゼは
かなり習得が難しい事にあります。梅雨の頃から釣れ始める当歳魚の"デキハゼ"は、バカチョンで釣れますけど、
秋の彼岸も過ぎた頃になりますと、徐々に難しく、特に陸からの手竿での釣りは、腕の差がはっきりと出ます。
名人クラスでは、年末に、お節の甘露煮の素材として、ケタハゼを重箱一杯分揃える、なんて事ができるそうですが、
残念ながら、拙にとっては、当面の目標でもあります。

次に、釣りと言うのは、「魚との対話を楽しむ事だ!」という立場をとる拙としては、
ハゼのひょうきんさと表情の豊かさは特筆すべきものがあります。
魚と言うより蛙の一歩手前と言った感じの顔には、釣り上げる度に思わず
微笑んでしまいますし、これから紹介する釣法の一つである”サイトフィッシング”では
投じられた餌に対して、あるいはソコに繋がっているお馬鹿な人間に対して、の、
すべての反応が目で見ることができますから、思わず擬人化してしまい、とても面白い
ものです。5cm位の子供のハゼが、ほんの数ヶ月の間にいかに、大きく成ると共に、
賢くなって行くかが、手に取るように分かりますから、何だか優しい気持ちになれる
釣りでもあります。(ハゼにとっては生死に関わる迷惑な話しでしょうけどね。)
釣り場については、東京でのハゼ釣りは、臨海部ならほとんどどこでもOKで、
京浜運河や、大井埠頭、江戸川放水路、葛西臨海公園、等、有名な釣場も多く、
また、隅田川のかなり都心部でまで、頑張っている名人の方々まで居るようですが、
では何故、お台場にこだわるのか?と申しますと、人口磯の見事なまでのわざとらしさと、物々しいビル群、
観光お上りさんの団体とか、親子連れや若いカップル、休日はいつもお祭りの様な、世紀末東京の象徴的な環境の中で、
唯一の自然の恵みである、ハゼ君と対話する。と言う、パラドックス的状況が、何ともたまらないのです。
これは東京原住民でないと解らない感覚かもしれませんね。もっとも、自宅から30分で行けるから、と言うのが1番ですけど。

| [ 釣法について ] 陸からの手釣りには大きく分けて4つありますが、 お台場や葛西臨海公園等では、投げ釣りは禁止ですので、1番ポピュラーな チョイ投げの釣法を省きますと、3つになります。順に書きますと、 〔1〕. もっとも普通の渓流竿など、長竿による浮子、シモリ仕掛けで、 竿下を探り釣りする方法。 〔2〕. 1.5〜2m程度の和竿テバネ竿かルアーロッド(ウルトラライト)による、 サイトフッシング(見釣り)。 ラインの長さの調節ができる事が必要ですが、竿の調子はあまり問題ではないようです。 この釣法は、ハゼが見える処に居る事が条件になりますので、10月に入ると 無理かもしれません。 〔3〕. 1m程度のワカサギ竿やテトラ竿を使った、穴釣り。これはミャク釣りですし、 食い込み優先ですので、竿、特に竿先の柔らかさが要求されます。 技術的にかなり難しいのですが、年明けまで良形が釣れます。 |
[ 餌について ] 通常ムシエサのジャリメや青イソ、ミミズ、なんかを使ってる方が多いのですが、
これは諸説いろいろ。( ナイショで教えますと、1番良いのは、現場で採った”カラス貝の身”なのですが、
餌付けに難アリですし、採取もいろいろ問題アリですので、必殺技としてとっておきましょうね。
寄せ餌についても強力な方法がありますけど、一応、禁じ手にして、ここには書きません。)
拙はもっぱらエビ(冷凍のブラックタイガーなんかで充分です。鮮度の悪い方が良い)の刻んだ物を使っております。
これだと、一回の釣行で、¥200以下の餌代で済みます。
[ 仕掛けについて ] ハリはいろいろ試しましたが、普通の袖鉤の6号程度が1番良いみたいで、
赤いハゼ鉤や、蛍光チモト、長軸の物など、ほとんど意味は無いようです。ハリの消耗はかなりですので、
ストックは多めに用意すべきでしょう。数が捕れる場合には、カエシを潰した方が手返しが早いのでオススメです。
ハゼの口は硬いので、掛り所によっては、外すのに往生します。
ラインの太さはあまり気にしないみたいなので、適当で良いでしょう。
〔1〕の釣法の仕掛けに関しては、拙は詳しくないので、〔2〕と 〔3〕について書いておきます。
〔2〕は、もっともシンプル、道糸の先にハリス止めを付けて、ハリスは5〜10cm以内、
ハリス止めの上にカミツブシの中サイズを付けるだけです。
〔3〕は一寸複雑で、オモリはラインが真下に張らなければならない関係で、0.5〜1号位必要ですが、
ナス型を下に付けて、途中の幹糸からハリスを出す方法か、中通しオモリを使うか、
あるいは、ナス型で誘導仕掛けにするか、判断に迷うところです。
拙としては1番食い込み抵抗の少ないナス型誘導仕掛けをオススメします、
ナス型にラインを通してから丸カンで止めて、そこにハリスを結ぶだけです。
根掛かりのリスクは若干大きいかもしれませんが、食い込みは良いはずです。
[ 潮時について ] これが一番問題なのですが、なかなかデータが揃いません。
大潮はダメと言う方も多いのですが、基本は干潮時の両側を狙いますので、
単にその時間が短いって事かもしれません。
当然、潮が止まってる時は喰いませんし、
(2)の釣法は深いと見えませんから、干潮時の釣りになります。
(3)の釣法は、岩と岩の間の穴、場合によっては、既に陸になってしまった岩の間に
残った穴をねらったりしますので、下げの七分位が理想です。上げ三分でも同じと思いきや、
なかなか良い釣果はありません。今後の課題とします。
[ 釣法詳細について ]、(2)と(3)の釣法別にポイントを書いてみましょう。
(2)の釣法は、見釣りですから、水深もせいぜい1m以内で、濁りが少ない事が条件です。
そこで、餌の意味が分かります。エビとかカラス貝は白いので、ムシエサに比べ見やすいのです。透明度が悪い場合、
ハゼ本体の識別は難しいのですが、餌が消えたり動いたりする事で、ハゼが食ったのが分かる訳です。
場合によっては、竿先や手元にアタリが出る事もありますけど、ほとんどは、この餌の動きを見てアワセをする訳です。
鉤が口に入ったか、餌のはじをくわえているだけか、あるいは口に入れずに餌の上に乗っているだけ、って事もありますし、
外道のカニなんかも邪魔しますので、眼力と勘を磨く事が、釣果につながります。
特に、スレてきた彼岸以降のハゼなどは、餌の落しどころと、誘いの技術が別に必要で、
苦労して掛けた(騙した)大物は、格別の嬉しさがあります。この釣法の面白さは、
本来、海底で起こっている魚達の行動が、目の前に見える事と、それと反して、無防備な海底や岩穴に居るときと違う、
人間との関わりのプレッシャーの中での魚達の行動までが、つぶさに見える事にあるわけです。
残念ながらこの釣法は、10月初旬のいわゆる「ハゼが落ちる」(浅場から深みに一斉に移動する)ときまでで、
見える範囲にハゼが居なくなれば、終了で、今年はもうできません。来年のお楽しみとなります。
しかし、「ハゼが落ちる」ってのは、名人達に言わせると、真っ赤な嘘で、「見える所に出てこないだけだよ〜」だそうです。

(3)の穴釣りがこれからの季節のメインです。岩と岩の隙間の穴に仕掛けを落とし込んで、
岩の下に隠れているハゼを狙う訳です。一番のポイントは、釣れる穴を見つける事ですが、お台場の場合、
場所も限られていますから、行けばだいだい分かります。只、波打ち際の穴ばかりでなく、
すでに乾いてしまった陸の大岩の下などにも、プールがありますので、見逃さない様にします。
ハゼの食いが良いときは、仕掛け投入とともに、グッグっと手元にアタリが出ますし、向こうアワセで、
ノってしまう事も多いのですが、食いがシブイときには、仕掛けを上下して誘います。
餌についても、この釣法では餌は見えませんから、動きのあるムシエサの方が良いと言う方もいます。
アワセは、ききアワセの様な感じでゆっくりとアワセます。なんせ竿先が柔らかいので、無理しない様に。
無理なアワセは、根がかりの元ですし、カニも多いので、仕掛けの損失になりやすいのです。
ハゼがノッたら、上手く引き抜かないと、ハゼごと根掛かりにもなりますので、ご注意を。
まったくアタリも出ないのに、餌が無くなったりしましたら、それは、ハゼ君の仕業ですから、
釣り人の腕のせいだと思って、腕を磨く事が必要です。この辺が面白い所以ですね。
見釣りの時期の様に一束(100匹)釣り等は期待できませんけど、これからどんどん大物が釣れますし、
地元名人の話しでは、正月まで、このやり方で超大物ハゼがイケるそうです。
[ ハゼを食べる前に ] なんせ小さい魚ですので、下ごしらえに時間がかかります。コツをいくつか。
まずウロコを適当に包丁でこそぎ落としてから、頭を落とします。
この際、胸びれの付け根まで一緒に落とすと、内蔵もくっ付いて取れます。
そのあと背開きにしますが、背骨がやたら太い魚ですので、若干浅めに包丁を入れるのがコツです。
このキッカケが上手く入れば、綺麗に開けます。背骨は前半分位を果物の皮むきの様な形で包丁を入れて、
切り離します。大きさ次第ですが、背骨の後半分位は天ぷらなら大丈夫です。かえって美味しいぐらいですよ。
一番のポイントは内蔵を抜いた後の腹身の内側にある、黒い汚れを、必ず爪などでこそぎ落とす事。
包丁では、身ごとなくなってしまうので、必ず、指先で落としましょう。これをサボると釣り場によっては、
臭い場合があるそうです。お台場以外での釣果には、くれぐれもサボらずにやった方が良いようです。

*いろいろ思い入れの多い釣りですので、第一報として校了します。
都心にお住まいの皆様、是非是非一度お試し下さい。
この釣りの一番の近道は、地元の名人の指導を受ける事です。
東京ロコはぶっきらぼうですが、実は教えたがり屋です。
拙もこの場所で数人のグル達に教えを乞いました。
求めよ!さらば開かれん!・・・・ってね!。
![]() 萬釣報 過去のログ
萬釣報 過去のログ
1999.5 マエストロの奄美釣行記
1999. 1〜4
1998. 11〜12月
1998 9〜10月