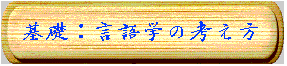
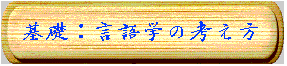
皆さんは、英語がお好きですか? このサイトにおみえになったのですから、多少のご関心は持っていらっしゃるのでしょう。ここでは初心に帰って、英語について考えてみましょう。
私たちは日本人ですから、多くの人は、生まれたときから日本語に囲まれて生活をしてきました。文字も日本語のひらがな、カタカナ、そして漢字に囲まれていたわけです。英語に関心を持ち始めたきっかけは様々でしょうが、幼い私たちは、まずその文字が、ひらがな、カタカナと違う、というところに不思議さを覚えたはずです。
文字というのは、誠に不思議なもので、私たちは今文字に囲まれているので、文字のない生活など思いも寄らなくなってしまっています。文字とは「ことば」そのもの、という気がしてしまうんです。ですが、ちょっと待って下さい。「もじ」は「ことば」そのものでしょうか?
私が「ちょっと待って下さい」と書くと、読むと同時に頭の中でその科白が聞こえませんか?読める=発音できる=聞こえる 文字を読むと言うことは、無意識のうちに「チョトマッテクダサイ」と書くと、日本語に不慣れな外国人の言った科白のように聞こえる錯覚すら覚えることもあります。
聞こえるように思えるのは、皆さんの記憶の中に、その科白を言われた時のことがあって、こう言われるんじゃないかな、という想像から頭の中で声がするだけなのです。実際に聞こえるわけではありません。文字は私たちの頭の中に「音」を想像させるのです。
なぜ、そんなことが起こるのでしょう。これは、まさに訓練の賜物といった感じのもので、文字を目で読み、口で発音をすることを、それこそこれまでの生きてきた間のほとんどに費やしてきたおかげで、私たちは苦もなくそういうことができるようになっているのです。
それで、私たちは、目で文字を追うときに音声としての言葉を疑似体験していることになります。これが、「文字」=「言葉」という思いこみを生むベースになっているわけです。
私たち日本人は、基本的に3種類もの文字を使い分けます。ひらがな、カタカナ、漢字は、見た目にそれぞれに印象を与えます。幼い頃から駆使しているために、何気なく使っているこの使い分け。人によって様々です。好き嫌いがあったりします。「おねがいいたします」という科白を「お願いいたします」と書くのと「御願い致します」と書くのでは印象がかなり違いますから、人によってはワープロを打つときにいつも「致します」と「いたします」との変換にこだわったりして時間を費やしたりしてしまうこともあるようです。
私たちが英語を学ぶとき、私たちに第四の文字が与えられます。それがアルファベットと呼ばれる文字です。
アルファベットとは、ギリシア語の最初の二文字、a、b(アルファ、ベータ)と並べて読んだものがなまったわけですね。最初の二文字で、文字全部を代表させているとも言えます。日本語も、昔は「いろは」と言いましたね。これは、最初の三文字をして、文字を代表させているわけです。
2 「異音について
1. 「音素」:構造言語学理論の最も大きな成果といわれるこの考え方は、様々な認識論にまで応用されようとしています。
一言で言って、ある言語を話したり、それを聞く人間が、単語として認識できる最小限の音の単位の集合。それが音素なのです。
次の単語のそれぞれを、どうやって識別するかを考えてみましょう。
E.g.1 cap, cab, cat, cad, catch, cadge, cam, can 訳1
スペリングの違いから、僕たち日本人は違いを認識しようとしますけれど、もともとは、この違いというのは「発話」される「音」がもとになっているんです。で、他は同じだけれど、ここ!が違えば違う単語と考える、というその違う部分を全部集めます。すると、英語というものが作られる構成要素を全部あげ連ねることになるんです。
上の例では、
が、それぞれ他の単語との違いを決める要素になるのです。
(-t と -tch は、アルファベットの数は違うけれど、「音」の違いは「一つ」と考えるんです。それを発音記号のように表すと、
という風に表されるのです。)
(同様に、-d と -dge も、
のように表されて、区別されるのです。)
他の音は同じですから、それぞれは
という風に表され、区別されることになります。
また、母音の部分だけを変えますと
cap, cat, can と kip, kit, kin つまり 訳2
は、きちんと違う単語だと識別されています。
また、最初の例を
と比べる場合、
cab と scab, cat と scat, cad と scad . . .
のように、「ココ!」と言うところ、語頭の子音部分で識別されるわけです。
まとめてみましょう。
母音、子音それぞれに、識別する音の「違い」というのが確認できます(これを難しく言うと「示差的音単位あるいは弁別的音単位 (distinctive sound unit)」と言います)。そして、英語には、母音の音素体系と、子音の音素体系があり、両者を合わせた「英語の音素」というものが英単語を作り上げているのです。
これでわかることは、英語には英語の音素、日本語には日本語の音素、という体系があって、それは物理的な音に関係ない、「言語学」の枠内に取り入れられる認識現象が存在する、ということです。このことは、次の「異音」の説明へと導かれます。
参考:英語の音素体系へ
人間の耳はどこまで音の違いを聞き分けられるでしょうか? というのが最初の質問です。
音楽の質問ではありません。最近は、絶対音感なるものが話題になってますが、ここでいう音の違いとはは、ドレミの聞き分けというのではなく、音の「質」の違いです。
ゴジラの鳴き声と、ターザンの雄叫びと、赤ちゃんの泣き声をあなたは再現できますか?
ではそれを文字で書くことはできるでしょうか?
聞き分けることと、それを表記したり、再現したりすることとは別かもしれませんね。けれど、人間同士の言葉の場合はどうでしょう。彼はこう言った、先生はああ言った、ということを私たちは日常的に再現できていますね。その時私たちは、言葉を再現しようとしているのであって、別にどれだけ正確に「声まね」をしようと競っているわけではありませんね。
再現するためには、まず「聞き取り」「理解する」ことが必要です。
たとえば、先生が「一本の木」と言うときも「二本の木」と言うときも、私たち日本人は、「ぽん」も「ほん」も同じ意味と理解することができます。けれども物理的な音は明らかに異なっていますね。この場合、日本語の中では、両方とも「ほん」(/hon/) が基本であり、その前に詰まる音「(小さな)っ」が来るとき、日本人は [hon] ではなく [pon] と発音するのです。
この時、(具体的)音声学的には [hon] と [pon] という異なる音を、日本人の耳は、抽象的な音の /hon/ と認識します。この抽象的な頭の中の音を「音素」と呼び、実際に発音された音は、二つともその「異音」であると呼びます。
けれども、もし、先生が「私」というときに、「わたし」と言っても、「あたし」と言っても、私たちはそれを「私」と表記しますね。言葉として「わたし」も「あたし」も区別をつけてはいないことになります。このばあい、「わ」と「あ」とは「異音」であるといえますが、さて、どうでしょう。もし、「あたし」と「わたし」ではやはり意味が違う、「あたし」は女性的な代名詞、「わたし」はもっと一般的な代名詞だと主張したとしましょう。その人は「わ」と「あ」とは単語を区別する別々の「音素」だと認識しているのです。こういう場合もあるのですね。
top さて、英語の場合、どういう現象が考えられるでしょうか。
上記の例 cat, cad, scat を比べてみます。それぞれを音声学的に表したものと音素的に表したものとを比較しましょう。
(Lass (1987) 3.1)
(k の肩の上の小さな h は、気息音を表します)
英語の他の例も考え合わせると、このことから、次の二つの規則が導かれそうです。
規則例 1)語頭の 無声 閉鎖音 /p, t, k/ は、その前に /s/ が来ない限り必ず「気息音」を伴う。
規則例 2)強勢のある短母音は、その後に有声の子音が来るときには長母音化する。
このように、異音というのは、その前後の音声学的な状況から規則正しく導かれるのです。この状況なり、位置なりによって生じる異音を「位置(条件)異音」と言います。
異音にはその他に自由異音というものがあります。異音が互いに入れ替わっても意味に違いがないことです。
わかりやすく日本語の例を挙げましょう。「三本」という語を「さんぼん」とも「さんほん」とも言えますね。このとき、[bon] と [hon] とはともに /hon/ という音素の異音ですが、入れ替えも可能です。こういうのが自由異音といえるものです。
英語の例でよく言われるのは、語末の /t/ の音についてです。たとえば sit(座る)という単語は音素的に /sit/ となりますが、語末を [t] と発音しても、[th] と発音しても意味になんら変わりはありません。これは話しての癖とかリズムとかによって自由に交換可能なんです。
ところで、このように異音同士は同じ音素のもとでは異なる状況でしか存在しないことがあります。こういうものを、「ある音声学的な状況での一つの異音は、それ以外の状況の異音と相互補完的、あるいは相補的である」と言います。
理解を確かめるために、もう一度日本語の例に戻りましょう。「一本」の [pon] という異音は、その前が促音便のときにだけ発生します。もし、「一本」の「一」を [ichi] と促音便にしないで発音する場合、音素 /hon/ は、音声学的にも [hon] というもう一つの異音となって、[ichi hon] という発話になるのです。
このように一つの音素の異音は互いに相互補完的である、という観察が得られるのです。
人間が発音できる音はいったい何種類あるのでしょう。おそらく、詳細に記述していくときりがないでしょう。けれども、一つの言語の中は、使用される音の数は限られています。また、使用される音の組み合わせも限られているのです。その制限とはどのようなものかを論じるのが「音素配列論」です。
最も簡単な例が、bl-, -lb の組み合わせについてです。英語では、/bl/ という音の組み合わせは語頭、もしくは語中にしか存在しません。E.g. blue. そのさかさまの/lb/ という音の組み合わせは、語末にしか存在しないのです。E.g. bulb.
そんなふうに、英語の中には、音の組み合わせで「英語らしくない」音の組み合わせというのが存在するのです。そのような分析から、英語には決して存在しないであろう単語を想定することもできます。たとえば、*stling という語は、英語らしくないのです。一方実際には存在しないけれども、英語らしく聞こえる音の組み合わせもあります。E.g. *kib, *kidge などは、英語らしい音の組み合わせといえます。
その一方で、ある言語とある言語とを比較することも興味深い資料となります。たとえば、英語にもドイツ語にも
の三種類は存在しますが、音素配列は二つの言語では異なるのです。
英語では、この三つの音はどれでも語頭に使われますが、ドイツ語では
の二つしか語頭には現れません。けれども語末では
しか現れないのです。この/z/ の位置の制限は英語には見られないものであり、両者を(歴史的にも)区別する一つの目安になっているのです。
top 4. 急速調(あるいは「カジュアル・スピーチ」)について
言語とは、実際に使われるものである、というのを忘れるわけにはまいりません。
実際に音で表せるとき、それは口から蕩々と流れ出る音の行列になります。当然、私たちは一つの単語を音で表すとき、その音をしっかりと意識しては発音しなくなりましょう。語尾の音は当然弱くなったり、省略されたりしてしまうのです。
音素 ここで大事なのは、音素との関連です。音素はあくまでも理論上、抽象的な音にしかすぎません。
それが実際にどのように発話されるかは「異音」によって説明しましたが、さらに文章の中に現れる「異音」もまた、規則的な条件によって規定されうるのです。
たとえば、in という単語は音素で
という音と認識され、かつまた音声学的にも
と発音されるのが普通です。しかしながら、発話の中では、[n] の音は、そのあとに続く子音によって大きく影響を受けるのが普通です。たとえば後ろに /k/ のような口蓋音がくると、/n/ の音は口蓋化したり(e.g.5)、/p/ のような唇音が来ると、唇音化したりします(e.g.5)。
英語には日本語にはない子音があったり、日本語にも英語にない「音便」などがあったりして、色々と違いがありますね。そこで問題です。
日本語と英語の発音の違いで、最も重大なものは何だと思いますか?
答は、強勢です。この「強勢」というものについていろいろと勘違いをしている日本人が多いので、ここではそれについて記します。
A. アクセントの意味:
この強勢のことをよく「アクセント」と言う人がいます。英語の cattle は、a に「アクセントをおく」などと言ったりします。
「アクセント」というのは、実は意味が広く、英語の場合、上のようなものは本当は「語強勢」といって、幾つかの音節ので最も「卓立」したものを指す言葉なのです。この「強勢」という言葉すなわち 「ストレス(stress)」というのが、俗に言う「アクセント」になります。
日本では「ストレス」というと急に「疲れて」しまうらしく、あまり日常的には「強勢」を指すときには言いませんね。
でも、同時に英語でも、accent という言葉は、日常的には「訛り」を指す言葉ですから、誤解を受けやすいですね。
さて、英語の2音節以上の語が単独で発せられると、卓立のある音節とない音節ができます。
どこに卓立があるか、その位置を示すのが「語強勢」だということになります。
一方、語が単独で発せられると言うのは、実際には極めて稀だと言えます。そこで、文を単位として考える場合、文の中で「強勢」を持つ音節が現れます。そういうものを「文強勢 (sentence stress)」と言います。
「文強勢」はしばしば文意に左右されるので「意味強勢 (sense stress)」とも言われます。
英米差 語強勢は、固定的だと言われます。しかし英米との間に相違があるばあいもあります。
学校では「アクセント」として一種類しか習わなかったかもしれませんが、実は「ストレス」は奥が深いのです。
1. 外来語、特にフランス語からの借用語の場合、英では初めに、米では終わりに第一強勢を置く傾向があります。
2. -ate で終わる2音節の動詞は、英では
、米では
として第一強勢のある音節が異なるのです。たとえば locate, frustrate, vibrate などがそうです。
3. -ary, -ery, -ory, -mony という接尾辞で終わるとき、その直前が弱強勢のとき、これら接尾辞の第一音節に第二強勢が来ることが米では当たり前。英ではこの接尾辞は弱強勢になる。
結果としてたとえばnecessary という語は、英 ne'cessary、米 'necessary という風にストレスの位置が異なります。
強勢 上のように、英米の差などはありますが、英語はいずれにせよ、音節の構造と音節の数に従って、
強勢は厳密な規則のもとに定められていると言えます。
合成語 合成語の強勢にも、よく見過ごされることがあります。
合成語では、英では両方に、米では第一語に強勢が来る傾向があります。
例えば、apple sauce は、英vs米では
という違いがあります。
また、例えば blackbird(クロウタドリ)という語と black bird(黒い鳥)では、英の傾向に従えば
という違いも認められるのですね。ビートルズのblackbirdという歌は、果たしてこの通りに発音されているか、是非一度あの名曲に耳を傾けて下さい。
発音記号は [ ]、音素記号は / / という記号を使います。
訳1:こう言うのは日本語で考えちゃいけないんだけれど、参考のため
(野球の)キャップ;タクシー;ネコ;捕まえる;物乞い;カム;缶
訳2:kip;kit;kin 眠り、下宿;道具一式;親類 戻る
卓立:言語音又は音節の連鎖において、ある言語音又は音節が他のものよりも目立つことをいう。卓立は、音の大きさ(loudness)、音の高さ(pitch)、音の長さ(length)音質(quality)によって決まる。大きさ・高さ・長さが増すほど、卓立は大きくなる。音質に関しては、母音は子音より、有声音は無声音より、[l, r, m, n,
] は有声の摩擦音・閉鎖音より、摩擦音は閉鎖音より、また、母音は広いものほど卓立が大である。 --->戻る
強勢に伴う卓立を重視する考えを最初にはっきりと打ち出したのは Kingdon という学者です。彼は強勢を三つの区分に分けました。動強勢、全静強勢、部分静強勢といいます。この強い順に、第一強勢 (primary stress)、第二強勢 (secondary stress)、弱強勢 (weak stress) の3段階に分けるのが一般的に認められました。
恐らく、多くの日本の学生諸君は上のようにならったはずです。
この第一強勢、第二強勢をそれぞれ
または
という記号で表します。
--->戻る