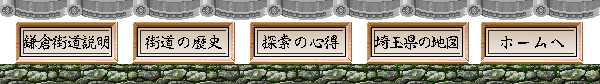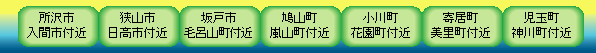◆◆◆◆◆◆◆ 八国山・将軍塚 ◆◆◆◆◆◆◆
八国山
八国山は埼玉県と東京都の境に位置する丘陵をいいます。八国山緑地の白十字病院西側の道は、東村山市の国宝の地蔵堂がある正福寺の付近を通って、ここに至っている鎌倉街道のルートのひとつと考えられています。下の写真はその白十字病院西側の道です。この道は八国山を南北に縦断していて、現在でも古道の雰囲気を感じさせてくれる道です。直線的に南から登りきったところで、東西に交差する道があり、そこを東に少し行くと将軍塚があります。ここ八国山は東村山市と所沢市にまたがり、住宅地の近くにある緑地帯のためか、休日には多くの人々が散策に訪れています。四季折々の息吹を感じられる貴重な森が残されているのです。

八国山緑地内の白十字病院西側の道
将軍塚
将軍塚は新田義貞が鎌倉攻めのときに、ここに陣を置いたところと伝えられています。また鎌倉攻めのときに、ここに塚を築いて白旗を立てたところともいわれています。一方でこの塚は古い古墳であるとも考えられているそうです。塚の碑の前には、いつ来ても徳利が置いてあるのは面白いものです。この塚のところをそのまま南に山を下りた辺りに、久米川古戦場碑がありますが、そのまま下りる道はないので、ここから東に行く道を下りて右に迂回して行けば久米川古戦場碑の前に出られます。久米川古戦場碑は小さな公園の中に建つていて、隣に説明版があります。付近は一般的な住宅地で、今では古戦場であったことはとても想像がつきません。

八国山の将軍塚
元弘青石塔婆所在跡
元弘青石塔婆所在跡は、かってこの場所に国指定重要文化財の「元弘の板碑」があったところで、現在は下の写真のとおり元弘青石塔婆所在跡の碑が建っています。元弘の板碑は現在、東村山市の徳蔵寺の板碑保存館に展示されています。この板碑は上半分が欠けた状態ですが、歴史資料としては実証性に欠ける部分が多いといわれる『太平記』の物語を補足する重要なことが刻まれています。元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉攻めの時に分倍河原や相模の村岡の戦いの時、討ち死にした飽間氏一族3人の供養のために立てられたことがわかっています。飽間斉藤氏は群馬県安中市の秋間村出身の人であるといわれ、飽間の地は里見氏の里見郷と続き、里見・飽間両氏は早くから新田氏に従っていました。板碑の下部には次のように刻まれています。「勧進玖□□陀仏・執筆遍阿弥陀仏」建立者は長久寺の玖阿上人です。またこの板碑以外にも入間市元加治の円照寺の板碑も同じ元弘3年の重要な金石文資料です。

八国山の元弘青石塔婆所在跡碑
武蔵国悲田処跡
悲田処(ひでんじょ)とは古代の平安時代初期に、旅人の救済保護を行った施設です。病気や飢えで倒れる人を救いたいと、下級役人が自分の収入の一部を割いて食料や薬品を備えた施設を造ったのです。遠い昔にこのような人達がいたのかと関心させられます。このような施設の跡がこの付近にあったということは、やはり鎌倉時代以前の古代から、上道に沿った幹線路があった証であると考えられるのです。 なお悲田処跡地としては東村山市内にも幾つかの候補地があります。

武蔵国悲田所跡