|
プロローグ   

「ええ、白石夏美です...
日本でBSE(牛海綿状脳症)が問題になったのは、2001年の晩秋から立冬の頃
でした。私たちが“変異プリオンの考察/第1弾”を編集し、掲載したのが、2001年
12月3になっています。あれから、もう3年近くもたつわけですね...
その後、BSE問題は、どのように推移してきたのでしょうか...日本は、ともかく世
界一の安全基準、“全頭検査”というシステムを定着させました。ヨーロッパの“EU方
式(30ヶ月以上の牛を検査)”よりも、さらに厳しい基準を設定したことで、からくも日本の消費
者の信頼感をつなぎとめたと言えます。
そして、“23ヶ月齢”、“21ヶ月齢”という若い感染牛も順次発見し、このシステム
は世界的にも大きな成果をあげて来ました。また、私たち国民にとっても、この事に関
しては、行政に対する信頼感を回復し、牛肉に対する安心感を醸成しました。その
“全頭検査”という政策が今、政府自身の手によって、大きく揺らぎ始めています」
「さて、今回の“BSE・変異プリオンの考察/第2弾”では、プリオン研究の第一人
者、
S.B.プルシナー博士の論文を参考文献とし、最新の状況なども紹介し、さらに
考察を深めて行きたいと思います。ちなみに、プルシナー博士は、プリオンの発見者
であり、プリオン理論の提唱者です。また、1997年に、プリオン研究で、ノーベル生理
学・医学賞を受賞しています」
「ええ、当時...このページの<第1弾>では、高杉・塾長が急遽担当されたとい
う事情がございます。それから、私と、途中から“クラブ・須弥山”のママ、羽衣弥生さ
んが加わりました。そんな経緯から、今回も同じメンバーで、<第2弾>の考察を行う
ことになりました。
ええ、高杉・塾長...それから、弥生さん...今回も、よろしくお願いします。高杉・
塾長、今回も、リラックスした会話形式でお願いします」
「そうだね...難しい内容になると、つい説明的な、文章を読むような会話になってし
まう。ま、今回は、リラックスした会話形式にしたいということだね」
「はい。前回もそうでしたから、」
「うむ。そう、努力しよう」
「よろしく、夏美さん、」弥生が、首をかしげ、白い歯をこぼした。「このBSE問題は、本
来は誰が担当されるのかしら?」
「うーん...
“資源・環境・エネルギー”の、堀内秀雄さんと、私だと思います。それから、“バ
イオハザード”ということで、“危機管理センター”の里中響子さんも考えられます。
あ、もちろん、高杉・塾長は、統括責任者ですから、最適任者です。“ガイア塾”の塾
長であり、このページ本体も、“ガイア塾”の“生命体・命のリズム”の中に収められて
いますし...」
「これは、“ガイア塾”の方に収められているのですか?」
「そうです。<第1弾>も、そうです...」
「ともかく...」高杉が言った。「あの時は、急にこの仕事が舞い込んできたからね。
あれから、日本は、世界一の“BSE・全頭検査体制”を作り上げたわけだ...
それを“アメリカの圧力”で、日本政府が、あっさりと覆そうというのだから、その真
意が分らない...日本政府は、日本の国民の安全というものを、どのように考えてい
るのですかねえ...」
「11月に、アメリカの大統領選挙がありますし...」弥生が、細い肩を傾げた。「それ
が、ブッシュ大統領の支持基盤である、畜産業界を支援する事になるらしいですわ。
でも、本当に小泉・首相は、そんな事で、日本国民のBSEに対する安全性を、緩め
てしまうおつもりなのかしら?」
「さあ...どうも、小泉・首相は、何を考えているのか、最近はよくわからなくなって来
たねえ、」
「はい...」夏美が言った。
〔1〕
異常プリオンの現状と対策 
 
≪1≫
プルシナー博士の言葉
 
「さて、」高杉が言った。「そのプルシナー博士が、論文の巻頭文で、こう書いていま
す...
“感染牛を早期に見つけ出し、
人への感染を防ぐには、“全頭検査”が最も有効だ”
と...」
「BSEは、異常プリオン・タンパク質の増殖が、病気の原因ですよね、」夏美が言っ
た。「この“タンパク質だけの病原体”というのは、細菌やウイルスのように、DNAやR
NAによって自己増殖するのとは、まったく違うメカニズムで増殖するわけですね?」
「そういうことです...
しかし、そのメカニズムは、まだよくは分っていないらしい。この“プリオン理論”と
いうのは、全く新しい概念だということです。まあ、私は研究者ではないし、門外漢だ
が、まるで“将棋倒し(ドミノ倒し)”のような増殖風景に見えますねえ...いずれにしろ、
まだまだ分からない事が多い。いや、これから本格的な研究が進んでいく、未開拓
の分野だと言った方がいいでしょう。
プルシナー博士は、論文の中で、こうも書いています...
“一見、健康な動物でも、病原型プリオン・タンパク質を持っている可能
性があることを考えれば、全頭検査
こそが、唯一の合理的な政策だ
と、私は信じている。現在の検査法の感度は不十分だ。だが、迅速で、
高感度な検査方法が出現すれば、全頭検査
が標準となるかも知れな
い...”
...ということです。
しかし、日本政府は今まさに、その“全頭検査を放棄”しようとしているわけです。し
かも、こうした“未知の病原体”において、その“安全性”に対し、“無用な政治決断”を
しているように思えます」
「どうしたらいいのかしら、私たちは、」夏美が言った。
「ともかく、後は、国民自身がどう考えるかということが、“最後の防波堤”になります。
まあ、輸入されて来ても食べなければいいわけだが...それでは、“政治決断の責
任”は、いったい何なのかということになる...」
「他に、選択肢はあるのかしら?」
「結局、食べるか食べないか...多少危険でも食べるか、ということになるが...そ
のうちに、慣(な)れてしまうだろうねえ...本当に、危険が無いのなら、かまわないが、
プリオン研究の第一人者が、“危険だ!”と言っているわけだからねえ...」
「つまり、どうしたらいいのかしら?」
「危機管理において、“この程度のリスクがあった場合”、私は“危険は絶対に回避す
べきだ”と考えます。この場合は、“リスクを犯す”必要はないのです。
東海地震や南海地震は、必ずやってくるものだし、様々なリスクを犯してでも、“準
備/予報/決断”は果敢にやらなければなりません。しかし、この場合は、“純粋にバ
イオハザードの問題”として捉えるべきであり、政治決断をするほどの緊急性も無い
わけです...」
「そうですわ、」弥生が言った。「11月の、アメリカ大統領選挙の応援で、国民の命を危
険に晒されては、たまらないですわ」
「うーむ...総理大臣の決断に対して...言いにくいことだが...そういうことだろ
うねえ...これが杞憂(きゆう/取り越し苦労)であってくれればいいが...そもそも、危機
管理などというものは、“杞憂で終わることが最高の結果”なのですからねえ...とも
かく、そのぐらい、“慎重であって欲しかった”と言うことです」
「ええ!」弥生が、冷静に、うなづいた。
≪2≫ 現状 〜 BSE騒動の風景  

「さて、」高杉が言った。「BSE(牛海綿状脳症)は、現在、世界20数カ国で報告されてい
ます。1980年代〜90年代へかけての、イギリスでの大流行は終息したものの、
2001年の末から、日本でBSE・騒動が持ち上がりました。この頃の経緯について
は、私たちが2001年12月3日からスタートした、<BSE・変異プリオンの考察/
第1弾>で、詳しく述べています。
それから、2003年の末に、アメリカで初めてのBSE感染が発表されました。この
アメリカの感染牛の発表は、牛肉の輸出大国であるだけに、再び世界的な大混乱を
引き起こしています...
これは...ええと...アメリカ北西部の、ワシントン州マブトンですね。ここで、ホル
スタイン1頭が、BSEに感染しているというものでした...しかし、ここから、新たに
アメリカでの感染不安が拡大して行ったわけです...」
「このBSEは、カナダから来たわけですよね?」夏美が言った。
「まあ、正確なことは、私には断言できない。プルシナー博士は、アメリカでもBSEは自
然発生していると推測しいるしね...そもそも、イギリスで発生していたわけであり、
それよりもはるかに牛の数が多いアメリカで、自然発生していないと断言するのには、
無理があるのではないかな...
まあ、アメリカでは、カナダから来たものだけに、BSE感染を絞り込みたいのだろう
がね...」
「うーん...難しい話になりますね...」
「あとは、本当にBSEを心配する、アメリカ国内の消費者が、どう動くかです」
「はい、」
「ちなみに...カナダとアメリカでBSEが見つかったのは、最近のことです。2003年
5月20日に、カナダ政府は、アルバータ州とサスカチュワン州で飼育されてきた8歳
半の牛が、BSEに感染していたと発表しています。
この牛は、2003年1月に“と畜”されていました。ところが、手続きが遅れて、当局
は4月までサンプルの検査をしなかった。さあ、その間に、肉がすでに流通してしまっ
ていたということです。そして、その1部は、ペットフードに加工され、アメリカに輸出さ
れていました」
「はい、」
「いずれにしても...それから、7ヵ月後...12月23日...アメリカ農務省は、ワシ
ントン州でBSE感染牛が見つかったと発表したわけです...
“6歳半の乳牛”、で、“4歳の時”に、アメリカに輸入された牛...ということです」
「うーん...」夏美は、大きく体を揺らした。
「まあ、ここからアメリカでの騒ぎが拡大し...ええと...58カ国がアメリカ産牛肉の
輸入禁止措置を取っています。アメリカの畜産業界は、現在、大混乱に陥っています。
まあ、ざっとこんな状態ですが...さあ、日本は、国内基準の“全頭検査の体制”を
緩和し、米国産牛肉の輸入をするべきなのかどうか...」
「アメリカで、自然発生のBSE感染牛が相当数いるようですと、」弥生が言った。「大
変なことになりますわ」
「うむ...」
 
「さて、話を戻すが...
先ほども言ったように、1980年代から90年代へかけて、イギリスでBSEが大流
行したわけです。やがてその原因が、“肉骨粉”である事が分ってきました。
それは、こういうことです...ヒツジ、ウシ、ブタ、ニワトリを“と畜”し、加工処理した
後、残った部分から工業用の油脂などを採取します。そして、さらにその残滓(ざんし)
で、“肉骨粉”を生産するのです。
こうした過程を“レンダリング”と呼ぶそうですが、まあ滓(かす)も残さず全て利用する
わけですね。しかし、ここが肝心です...この過程で、普通の細菌やウイルスなどの
病原菌は、“高温処理によって除去”されるわけです。しかし、異常プリオンは、“熱に
強く”、破壊されずに“残存”し、この肉骨粉の流通と給餌によって、牛にBSEが大感
染して行ったのです」
「ええ...」弥生がうなづき、火のついていないタバコを、唇の先にくわえた。
「もう少し説明しよう...
正常プリオンと異なり、異常プリオンというのは...溶解しにくい、非常に強力な
“凝集塊”を形成します。この複雑な立体構造のタンパク質は、“熱”にも“放射線”にも
“化学物質”にも抵抗性があるのです。タンパク質分解酵素の“プロテアーゼ”でも分
解されないわけですね。まあ、この“プロテアーゼ”でも分解されないという性質が、検
査にも利用されます...
ともかく、細菌やウイルスやカビなどは、数分間煮沸すれば一掃できます。ところ
が、この異常プリオンには効果がないのです。こいつは元々、DNAもRNAもなく、ただ
タンパク質だけの物質であり、より複雑な立体構造に折畳まれ、“凝集塊”を形成し、
“病原体のフリ”をしているのです...いったい、何処からこんな知恵を授かったの
ですかねえ...」
弥生は、細いライターで、カチ、とタバコに火をつけた。
「しかし、プリオンとウイルスには、“変化しやすい”という共通の特徴があるのも事実
です。そして、少しづつ特徴の異なる、“幾つもの株”が存在しているのも、よく似てい
るようです。
この“プリオン株”の違いが、“異常プリオンの高次構造”による事は、はっきりと示
されているそうです。しかし、“株の構造”と“生物学的特長”との関係は、まだ正確に
は分っていないらしいですがね...」
「あの、高杉・塾長...」夏美が言った。「その“プリオン株”の違いによって、違う病気
になるのでしょうか?“在来型・BSE”と、日本で発見された“23ヶ月齢”だった“新
型・BSEの牛”のように...」
「うむ...そういうことだろうねえ...これは、掲示板の方に掲載されているが、もう
一度説明しておこうか...」
「はい」
「この“日本での8頭目の感染牛(23ヶ月齢)”は、“異常プリオン・タンパク質の構造パタ
ーン”が、従来のものとは違う“新型・BSE”だったと言われている。そこで、次の“9
頭目の感染牛(21ヶ月齢)”も、2例目の“新型・BSE”の可能性が指摘されました。とこ
ろが、専門家会議が画像分析の結果、異常プリオンのパターンは、“従来型・BSE”
と診断しました。これは...2003年10月〜11月頃の話になりますね...」
「はい、」
「あ...それから、もう1つ言っておこう...“プリオン株”によって、病気の種類が変っ
てくることについてだ」
「はい」
「“プリオン病”については...人では“クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)”、“変異型・
クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD/BSE感染牛を食べて人に感染)”、“クールー”、“致死性家
族性不眠症”、“ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群”などは、全て異な
る“プリオン株”が原因となっています...
それから、羊では、約20種類の“スクレイピー”が知られている。つまり、BSEでも、
当然様々な種類があることが予想されるわけです。“在来型・BSE”に加え、“新型・
BSE”が登場してきたということは、そういうことでしょう...
ちなみに、“新型・BSE”の牛では、中脳で、大量の異常プリオンが見つかったそう
です。“在来型・BSE”の場合、異常プリオンは脳幹に蓄積する傾向があるといわれて
いますがね...」
「ふーん...はい」夏美が、うなづいた。
〔2〕
プリオン病の本質・・・
 

「弥生さん...」高杉が、口元をこすった。「私にも、タバコを1本もらえるかね?」
「あら、あら、」弥生が、タバコを細い指ではさみ、白い歯を見せた。「どうぞ、高杉さ
ん、」
「うむ...」高杉は、タバコの箱をもらい、1本取り出し、口にくわえた。
彼女が、体を寄せ、細いライターで高杉のタバコに火をつけた。
「夏美さんは、どうかしら?」
「私は、けっこうです」
「ま...弥生さんが、あまりうまそうにタバコを吸っているもんでね、」高杉は、煙を吐
き、苦笑した。「タバコだって、害にならない程度なら、楽しみもある...ま、これは、ボ
スのセリフだがね...」
「うーん、」夏美が、難しい顔をして見せた。
「ほっほっ、私もですわ...」弥生が、灰皿を高杉の方に押してよこした。

 
≪3≫
BSEは、感染ルートだけでなく、
散発的な自然発生
や 遺伝的発生
もある!
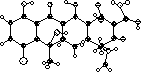
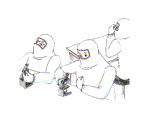

「ええ...
“プリオン病”というのは、“変異が早く/異なる株があり/感染性が高い”というこ
とから、“ウイルス性疾患と似ている”ということが強調されます。しかし、“プリオン病”
には、別の側面があることを忘れてはいけません。つまり、BSEを食い止めるには、
感染症対策だけでは不十分だ...ということです。
感染ルートを潰したり、感染牛を封じ込めたりしているだけでは、“自然発生のBS
E”や“遺伝的に発生するBSE”は、補足出来ないということです。」
「うーん...」夏美が、首を横にした。「感染症なら...抗生物質や熱処理や殺菌消
毒などが有効ですよね...でも、BSEの場合、そうした“感染症対策が機能しない”
ということですね?」
「うーむ...そういうことだろうねえ...従来の感染症対策では、うまく行かないはず
です。また、そうした対処の問題とは別に、発生についても、“感染ルート”だけでは
ないという、厄介な問題があるわけです。つまり、“プリオン病”というのは、散発的に、
“自然に発生”することもあるわけです。感染ルートだけを追っていると、こうした自然
発生するものを取り逃がしてしまうことになります」
「そうですね」
「ここが、“プリオン病”と“ウイルス性疾患”とを分ける、重要なポイントになってきま
す。それからもう1つ、この“プリオン病”は、“遺伝的に発生”する事もあるようです。し
たがって、これは“BSE対策”についても言えることで、やはりこの致死性の奇妙な病
原体から国民を守るためには、“全頭検査”こそがベストだと思いますね」
「やはり、そうなるのでしょうか?」
「そうてすね...
その“全頭検査体制”の中で、“技術革新”をし、“さらなる安全性”を高めていくこと
が必要なのではないでしょうか。日本政府は、アメリカからの圧力で、“全頭検査”の
体制を緩和しようとしていますが、本来これは政治決断するような性質のものではな
いと思います。
それから、いわゆるこうした“バイオハザードの危機”というものは、これでおしまい
という事でもないのです。これを教訓として、“新しいパターン”としてファイルを重ね、
次の危機、更なる大きな危機に、備えておく事が大事なのです」
「はい。それが、私たちの社会を守っていく、“備え”になるわけですね」
「そういうことです」
「あの、高杉さん...」弥生が言った。「基本的なことをお聞きたいのですが、」
「うむ、何だね?」
「プリオン病と、BSEとは、同じなんですか?」
「ああ、はい...
異常プリオンが蓄積するのが、プリオン病ということでしょう。したがって、BSEもプ
リオン病の1種だということです」
「あ、はい!」
「まあ...この異常プリオンというのは“神経細胞に蓄積”するようですが、最近の研
究では、“血液中”や“筋肉中”にもプリオンが見つかっているようです。それから、マウ
スの後ろ足の筋肉中には、“血液中の10万倍もの高濃度のプリオン”が存在するこ
とも発見されています...
こうなって来ると、プリオンというタンパク質そのものが、いったい何なのか、どのよう
な機能を持っているのか、ということが非常に興味深く感じられますね。生物体の中
には、無駄なものは何も無いのですから...一見、無駄に見えても、その無駄そのも
のが、高次元で非常に深い意味を持ってくるわけです。
まあ、最先端では、相当に研究が進んでいるのでしょう...あ、それから、血液中
に観測される微量のプリオンですが、この測定技術が確立すれば、将来的には、生き
ている牛のプリオンを発見することも、可能になるということです」
「ふーん...」弥生がうなづいた。「そうなれば、当然、全頭検査ですよね...」
「時代的な流れとして、そうなるでしょう...」
「ええ、」
≪4≫
最初は自然発生だった...“クールー” 

「弥生さん、“クールー”という、ヒトのプリオン病があります。これは、実は、最初は自
然発生だったと考えられています。20世紀に、この病気によって、ニューギニアのフォ
ア族と呼ばれる集団に、多くの死者が出ました」
「はい、」
「これはフォア族が、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)にかかった人の脳を、仲間の弔
いの儀式として食べた事が、原因だったと考えられています...つまり、たまたま自
然発生だったクロイツフェルト・ヤコブ病の人の脳を食べ、その風習が続いたため、感
染が拡大して行ったというものです...」
「ヤコブ病の人の...脳の異常プリオンが、他の人に食べられたわけですのね?」
「そういうことです...」高杉は、うなづいた。「ヒトの場合は、毎年100万人に1人の
割合で、プリオン病が自然発生していると言われます。そして、これは、牛でも同じで
はないかと言うことです...」
「考えられますわね、当然...」
「まあ、BSEにおいても、最初は、こうした自然発生的なBSEがあったのでしょう...
私は研究者ではなく、推測の話になりますが...そうしたプリオン病の牛が処理さ
れ、肉骨粉が生産され、それを共食いのようなサイクルで、他の牛が食べた。ところ
が、肉骨粉の生産過程で“熱処理”しても、異常プリオンは破壊できなかった。まさか、
こんな“新しい概念の病原体”が存在するとは考えなかったわけですからねえ。とも
かく、ここから、おそらく、BSEの被害が拡大していったものと考えられます...」
「ええ、」
「BSEは、1980年代から90年代にかけて、イギリスで大発生したわけですが、イギ
リス当局は、数回にわたって“飼料禁止令”を出しています。これは、共食いのような
給餌方法を禁止する、厳しい法律でした。まあ、私なども、“人類文明のモラル”という
ものを感じますね。動物愛護だと言い、一方では、こういうことをやっているわけですか
らねえ...」
「その通りですわ」
「さて...
イギリスにおけるBSEの大流行は...1992年あたりがピークだったのでしょう
か...この年は、3万7280頭で、感染が判明しています。そして、“飼料禁止令”の
効果等で、ようやく沈静化したのが1996年だったと言われています。ちなみに、昨年
(2003年)は、612頭が報告されています。
イギリス全体で見つかったBSE感染牛は、累計で18万頭を超えています。これを、
疫学モデルに基づいて推定すると、感染していたのに検出されなかった牛は、およそ
190万頭に及ぶとのことです...」
「まあ...そんなにですの!」弥生が、目を見張った。
≪5≫人への感染...  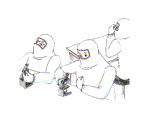 
「あの、塾長...」夏美が言った。「BSEが“人に感染”したことで、騒ぎが大きくなり
ましたよね。そのあたりのデータは、どうなっているのでしょうか?」
「うむ...
自然発生的なヒトの“クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)”と、BSEの牛を食べたこと
によると思われる“変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)”では、脳内での異常プ
リオンの沈着パターンが明らかに異なっています。
1996年、ようやくイギリスでBSEが沈静化した頃...イギリスにおいて11人の
若者が、“vCJD”で死亡していたことが報告されています。また、2004年2月の時点
で、イギリスでは累計146人が“vCJD”と診断され...ええ、すでに141人が死亡し
ていますね。いずれにしろ、現在の所、確立された治療法は無く、死亡率は100%で
す...」
「はい...」
「その他の国では、10人が“vCJD”と診断されていますが...フランスで6名、イタリ
アで1名、カナダで1名の死亡が確認されていますね...アメリカで報告されている1
名の患者は、イギリスでの滞在経験があったようです...それから、香港で死亡して
いる1名は、確定診断待ちということですね...」
「ふーん...圧倒的に、イギリスが多いんですね、」
「そうですね...
イギリスが、日本のように島国だったということが、感染拡大を防ぐ上では、大きな効
果があったようですね...昔は軍事学的に有利だと言われていたわけですが、感染
症対策でも、有利なわけだ。まあ、今回は、それが逆の意味で、“隔離できた”という方
向で作用したわけですがね...」
「はい」
「まあ...
牛への大感染に比べれば、人への感染は、まだそれほど深刻なものではない。ち
なみに、“vCJD”は、主に若者で発病しているようですね...平均発病年齢は...
ええ...29歳ということですね...日本での患者は報告されていません...まあ、
このあたりの、“vCJDの医学的データ”は、最大の犠牲者を出した、イギリスに集中
しているのでしょうか...」
「はい、」夏美が、うなづいた。
「ええ、」と、弥生の方も、うなづいた。「SARS(新型肺炎)は、感染が拡大した中国や台
湾の病院が、最も多くの患者を扱ったわけですわね。だから、SARSに関しては、中
国や台湾に医療情報が集中しているし、BSEは、イギリスということですわね...そ
ういうことでいいのかしら?」
「うむ、そういうことだろうね...放射能の被曝については、唯一の被曝国である日
本が、世界的権威であるのと同じでしょう...多くの犠牲者の中で確立される、医療
技術、医療体制ということでしょう...」
「はい、」弥生が、まばたきした。
〔3〕
BSEの検査方法

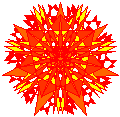
 
「さて...」高杉が言った。「次に、検査方法の話をしましょう。検査方法の話を進めて
いけば、最先端情報にもとづくBSEの実態について、もう少し具体的な姿を描けると
思います」
「はい、」夏美が、うなづいた。
「ええ、何度も言います...、北米大陸では、これまで2頭のBSE感染牛が確認され
ています...
今回の参考文献によると、プルシナー博士は、北米でも“BSEの自然発生”があっ
ても不思議ではないと考えているようです。あるいは、過去において、すでに小規模
なBSEの流行はあったが、察知されなかったという可能性も指摘しています。つまり、
プルシナー博士のこの推測が、北米大陸でのBSE汚染の、危うい実態を予感させま
す...」
「はい、」
「しかし、それにもかかわらず、非常に多くの人々が、2頭のBSE感染牛は、“肉骨粉”
の摂取に由来するものだと考えたがっています...ま、その方が、問題が単純です
からねえ...
しかし、プリオン病は、遺伝することもあるのだし、自然発生することもあるわけで
す。そもそも、最初はそうしたものが、“肉骨粉という共食いのような給餌方法”によっ
て、BSE感染症となり、拡大したと考えられるわけです」
「はい、」
「それにもかかわらず、“肉骨粉”からの感染ルートだけを追いかけていると、“BSE対
策”は、単なる“感染症対策”になってしまうわけですね」
「うーん...そうですよね、」
「その結果がどうなるか...このことについては、日本への輸出問題だけでなく、アメ
リカの消費者も、また生産者自身も、真剣に考えるべきです。結局、間違った対応は、
社会全体にフィードバックされてくるわけです。
壮大なモラルハザード社会を描き、世界に大恥じを晒している日本ですが、ここは
“全頭検査”という“世界1のBSE対策”を持っているわけであり、しっかりと注文して
おきたいですね」
「はい...」夏美がうなづいた。「ええ...牛の世界では、BSEが自然に発生してい
る可能性が、非常に高いということですね。“肉骨粉”による感染ルートの他にも、」
「そういうことです...
しかし、そうだとすると、アメリカの畜産業者にとっては、非常に面倒で、厄介な問題
になって来るわけです。しかも、現在の方法で、“全頭検査”となると、莫大なコストが
かかってくるわけです。
しかし、将来にわたって、“食の安全”を確保するには、必要なコストだと思います
ね。これからも、環境汚染、流通、遺伝子組み替え食品などで、“食の安全”に関して
は様々な難題が予想されます。“食の安全”は、これで終わりではないのです」
「はい」
「ちなみに、今年(2004年)1月に、“新しい規制”が導入されるまで、アメリカでは毎
年“約20万頭へたり牛”が、食肉に加工されていたわけです。しかも、これらの牛につ
いて、BSE検査がされていたのは、ほんのわずかだといいます」
「...」
「しかし今後は、こうした“へたり牛”については、全頭に対してBSE検査を行うことに
なるようです」
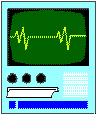
 
「ええと...弥生さん、何か...」夏美が、弥生に聞いた。
「はい。私たちは、“全頭検査”を強く主張していますけど...それは、具体的にどの
ようなものなかしら?」
「そうですね...その話をしましょう...
現在、病原型・プリオンタンパク質(異常・プリオン)の検出には、4種類の検査法が
利用されています。また、他にも色々な方法が開発されつつあります。
その前に、私たちは、<BSE/第1弾>で、2001年当時の検査体制として、次
の2つの検査法を紹介してきました...
***************************************************************************************
《
ウエスタン・ブロット法 .....これまでの検査法
》
“プロテイナーゼK(タンパク質を加水分解する酵素)”に対する安定性で診断
 (
プロテイナーゼK は、このページでは、プロテアーゼ
に改めています...) (
プロテイナーゼK は、このページでは、プロテアーゼ
に改めています...) 
《 SIFT法
/クロス相関蛍光分光法 .....新しい検査法
》
モノクローナル抗体を用い、高感度・共焦点の蛍光顕微鏡を使用
***************************************************************************************
しかし、あれから3年余りがたち、検査体制の様相も変り、BSEにおける新しい発
見も相次いでいます。
ちなみに、上記の“ウエスタン・ブロット法”は、現在も使われています。しかし、最
近の研究で、タンパク質分解酵素の“プロテアーゼ”で分解されてしまう“異常・プリオ
ン”が見つかり、かなりの量がこの検査をすり抜けている実態も分って来ています。
また、この“プロテアーゼ”で分解される“異常・プリオン”は、分解されにくい“異常・
プリオン”に比べ、かなり早い段階で出現していることも分っています。これは、非常
に面白い発見ですね」
「早い段階で...と、言うことは、分解されやすい軟弱な“異常・プリオン”から...分
解されにくい、非常に強力な“凝集塊”に変化して行くということなのでしょうか?」
「さあ、そのあたりは、まだよく分っていないようですね」
「あ、はい...」
「それから、もう1つの、SIFT法
/クロス相関蛍光分光法の方は、現在広く使われて
いる4つの検査法の中には、入っていないようですね...まあ、膨大な量を、効率よく
こなしていくということでは、それぞれ一長一短があるわけです。こうした中で、全体と
して、裾野の広い技術を応用し、常に“より良い検査体制へ更新を続けていく”という
ことですね...」
「はい!」夏美が、うなづいた。
「ええ...では、次に、具体的に、4つの検査方法について話して行きましょう」
「はい、お願いします」弥生が、テーブルの上で、細い指を組み合わせた。
 
 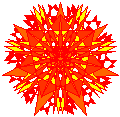

「ええ...現在使われている、以下に示す4つの方法は、いずれも、死んだ牛の脳組
織から、“異常・プリオン”を検出する方法です」
「あの、新しい方法は、開発されているのでしょうか?」夏美が聞いた。
「はい。血液や尿に含まれる微量の“異常・プリオン”を、迅速に検出する方法などの
開発が進められています...ともかく、血液や尿だと、生きている動物での検査が可
能になるわけです。そうなれば“全頭検査”も、それほどコストがかからなくなります」
「はい、」
「また、血液や尿で検査ができれば...ヒトのプリオン病の検査にも道が開けてくる
のではないでしょうか。“異常プリオンの立体構造を解きほぐす分子”が発見されたと
いうニュースもありますしね...」
「あ、そのニュースは、“BSEの掲示板”に載っていましたよね」
「そうですね」
≪6≫ 現在使われている、4つの検査法 
【1】生物学的検査法
【2】免疫組織化学法
【3】免疫測定法
【4】構造依存性・免疫検査法(
CDI )
 
【1】
生物学的検査法 ...........  
<結果が出るまで、36ヶ月> <コストが非常に高い>
「ええ...この方法は...
組織サンプルを、試験動物に注入し、発病した場合の潜伏期間をもとにサンプルの
感染性を評価します...
もう少し具体的に言うと、組織サンプルとは、“異常・プリオン”が存在するかどうか
を調べたい牛の、脳幹などの組織細胞になります。脳幹というのは、脳のうち大脳半球
と、小脳を除いた部分です。これは、逆に言うと、間脳、中脳、橋(きょう)、延髄、をあわせ
たものですね。“異常・プリオン”は、この脳幹に蓄積する傾向があると言われていま
す」
「あの、」夏美が、首を揺らした。「試験動物というのは、何を使うのでしょうか?」
「まあ、マウスです。それから、その他の動物もありますね」
「はい。その他に、この検査法で、何か特徴的なことは?」
「“特定のプリオン株”を明らかにできる、という利点があります」
「はい...」
【2】
免疫組織化学法 .........   

<判定に数日...7日ぐらい必要な場合もある>
<大規模なスクリーニングには、不向き>
「ええ...
アメリカ農務省が、この“免疫組織化学法”を採用しています。まあ、検査が面倒な
上、結果が出るまで数日かかるという古い方法ですね」
「うーん...」夏美が、言った。「アメリカは、どうしてそんな古い方法を使っているのか
しら?」
「まあ...アメリカでは、“異常・プリオン”を検出すめために、最初に行われる検査法
だということです...
これが、他の検査結果を判断する基準になっているようですね。しかし、これは、
専門家が1枚1枚スライドを調べていく作業になり、非常に手間がかかるわけです」
「はい...あの、塾長...ごく初歩的なことを聞きますけど...この“免疫組織化学
法”というのは、そもそも、どういう原理で行われる検査法なのでしょうか?」
「うむ、それを説明する必要があるな...
ええ、まず、この検査法は...組織サンプルに、病原型プリオンタンパク質(“異常・プ
リオン”)を認識する“抗体”を加え、その反応を調べるというものです。それをスライドに
入れ、専門家が顕微鏡で1枚1枚調べていくわけですね...まあ、古いといえば、古
いわけで、まさに手作業の仕事です...もちろん、大量にさばくことは出来ません」
「あの、塾長...“異常・プリオン”を認識する、“抗体”というのは、どんなものなので
すか?」
「うむ...これはよく言う、免疫系の反応を利用しているわけです...つまり、生物
体が、“異常・プリオン”という“異物/抗原”を認識する“抗体”ということでしょう...
まあ、生物体の防御システムである免疫系は、こうした“自己以外の異物”というもの
の侵入を、ミクロのレベルで、しっかりと監視しいているわけです。風邪などで熱が出
るのも、こうした免疫機能化働くからです。
この免疫系システムというのは、脊椎動物で特に発達した、“自己”と“他者”を識
別する、完璧な防御システムです。まあ、それが乱れると、アレルギーや、免疫不全症
候群などになるわけですね...逆に、臓器移植などで、他人の臓器...つまり異物
を、移植する場合などは、これが逆に作用してしまうわけです」
「はい...それで、その“抗体”が反応するのに、数日かかるということですね?」
「そういうことでしょう...」
【3】
免疫測定法 (ウエスタン・ブロット法)...  
<8時間以内に結果が得られる>
<同時に何百ものサンプルを検査>
<高濃度の“異常・プリオン”のみに有効>
「この方法は、現在、“多くの企業が実用化”している迅速な検査法です。ヨーロッパや
日本では、一般的に使われていますが、アメリカでは導入されたばかりです。
ええ...私には、参考文献を頼りに、大雑把なことしか言えませんが、ごく簡単に
説明します」
「はい、」夏美が、首をかしげた。
「ええ...
まず、検体である組織サンプルを用意します。もう少し具体的に言えば、“異常・プリ
オン”があるかどうかを調べる、牛の脳など、ですね。これを試験管に入れ、タンパク質
分解酵素であるプロテアーゼを加えます。
これによって、“異常・プリオン”はプロテアーゼに対して抵抗性がありますから、
“正常・プリオン”だけが分解され、“異常・プリオン”のみが分解されずに残るわけで
す」
「あ...はい、」
「この後、感染の有無を調べるには、プリオンを認識する標識抗体を加えるか、タンパク
質を質量に基づいてゲル上で分離して決定する、ということです...」
「あの、高杉さん...」弥生が、腕組みをした。「もう少し、詳しく説明してただけないか
しら、最初から、」
「うむ...そうだねえ...
1980年代の半ば頃のことです...イギリスで、BSEが発生した頃ですね...そ
の頃、脳内の危険なプリオンを効率よく確認する目的で、“新しい種類の抗体”が作ら
れました。しかし、これらの抗体は、“正常/異常”を問わず、全てのプリオン・タンパク
質を認識するものでした...」
「ええ、」弥生が、うなづいた。
「そこで、“異常・プリオン”を検出するには、“正常・プリオン”を完全に除去しておく必
要があったわけです。つまり、ここで、“異常・プリオン”が、プロテアーゼに抵抗性が
ある性質が利用されたのです。したがって、脳の組織サンプルを、プロテアーゼ処理
すればいいというわけです。“異常・プリオン”があれば、それが残るし...無ければ、
全て分解されてしまうということでしょう...」
「ええ、はい...」
「その後、、このサンプルに標識抗体を加えると、“異常・プリオン”の量が分るというわ
けです。まあ、全体的な流れとしては、こういうことです」
弥生は、コクリとうなづいた。
「まあ、こうした方法を利用して、スイスのプリオニクス社やフランスのバイオラッド社な
ど数社が、“独自の抗体”や“市販のキット”などを開発してきたようです。最初に紹介
した、“数時間で結果が分る”というのは、こうした“検査キット”を使用した場合です
ね」
「日本でも使われているのでしょうか?」夏美が聞いた。
「“全頭検査”の日本は、大のお得意様でしょう...この手法は、同時に何百ものサン
プルを検査できることから、日本やヨーロッパで行われている“大規模スクリーニング”
で使われ、その効果は実証済みということです。
日本では、2001年に1頭目の“BSE・感染牛”が見つかり、2004年4月現在まで
に、11頭が確認されています。全てこの検査が使われていますね」
「つまり、この検査が、これまでの主流になっていたわけですね?」
「そういうことです...
しかし、この方法も、万全というには程遠いものです。まず、脳にある程度の“異常・
プリオン”が蓄積しないと、検出できないという問題があります。“高濃度”でないと、検
出そのものが難しい場合が多いようですね...」
「それで、どのような影響があるのかしら?」弥生が聞いた。
「色々あります...
まあ、BSEに感染しても、発病するまでに、“平均で3〜5年”かかると言われます。
アメリカの食肉用の牛は、ほとんどが2歳以下なので、感染していたとしても“異常・プ
リオン”の蓄積量が少なく、検査では陽性にならないといいます。
こうした牛を、日本の小泉内閣では、何故か、“輸入しようじゃないか!”というわ
けです...非常に危険な臭いを感じますね。
これは、危機管理としては、失政だと思います。後は、国民がしっかりと監視してい
くしかないわけですが、非常に残念です。日本では、“結果オーライなら全てOK”、とい
うような風潮がありますが、これでは未来に向かって、しっかりとした危機管理体制を
築いていくことは出来ません...これは危機管理全体、国家運営全体についても言
えることだと思います。
アメリカの大統領選挙の応援というような意図があるようですが、こんなことで“国
民の命を危険に晒す”などは、まさに“論外”ですね、」
「はい!」夏美が、強くうなづいた。
  
「ええと...」夏美が、言った。「日本では、“23ヶ月齢”や“21ヶ月齢”の感染牛が、
実際に見つかっていますよね。これは、偶然なのかしら?」
「まあ...そうした微妙な所は、現場の人間ではないので分りません...しかし、非
常にラッキーだったというような話は、聞いた事がねあります...
ちなみに、この2頭は...ええと...いずれも、“免疫測定法/ウエスタン・ブロット
法”では陽性でした。そして、2頭とも、“免疫組織化学法”では陰性になっています。
それから、“構造依存性・免疫検査法(
CDI )”では検査されていませんね、」
「はい、」
「ともかく、技術開発は日進月歩です。また、現場では様々な工夫や、直観力が成果
をあげることもあるのでしょう。実は、成果というのは、そうした微妙な所に集中してい
ることが多いようですね。
それから、もちろん、検査技術の優劣や、検査体制全体も、成果に大きな影響を及
ぼすと思います...まあ、そうした文化、それを評価するシステムというものも、しっ
かりと育てていくべきだと思います...」
「はい、」
「ともかく...明確にしておきたいのは、この“
免疫測定法/ウエスタン・ブロット法”
が信頼できるのは、“年長の牛の検査”だということです。そうした中から、BSE・感
染牛を見つけ出す場合ですね...もちろん、“へたり牛”であろうが、なかろうが、で
す」
「でも、アメリカでは、自力で立てない“へたり牛”が、この検査の主な対象になってい
るようですが、」夏美が言った。
「まあ、くり返しになりますが...もう一度説明しておこうかね...
アメリカでは今年(2004年)1月に新しい規制が導入されるまで、毎年約20万頭の
“へたり牛”が食肉にされていました。しかも、BSE検査をされたのは、そのうちのほ
んのわずかだといいます。しかし、アメリカ農務省は、今後1年間で、少なくともこうした
“へたり牛”については、BSE検査行う予定だということです...
と、まあ、これが実態のようですね」
「ふーん...アメリカは、遅れているんですのね」弥生が言った。「大統領選挙では、ま
だ半世紀以上も前のパンチカードを使っているようですし...一方では、NASA(アメ
リカ航空宇宙局)のような所もあるし...」
「そうだねえ...だから、面白い国でもある...
しかし、BSE問題では、アメリカは牛肉の輸出大国だし、ともかく牛の数が桁違い
に多い...それだけに、強力な圧力団体もあるのだろうねえ。ますます事態が事態
が深刻になって来ているようです」
「ええ、」
「今の所は、日本への輸出の話が焦点になっているが、結局最後に問題になるの
は、“アメリカの消費者自身”がどうするかということでしょう。生産者も含めたアメリカ
の消費者全体が、“甘いBSEの検査体制”で、果たして安心が得られるのかという問
題です...
アメリカでのBSEの発生と感染の実態が分ってくれば、私は深刻な事態に陥って
いくと思います。結局、ヨーロッパや日本のように、大規模スクリーニングへ移行するだ
ろうと思います」
「はい...
ええと...それから、BSE感染牛の乳...牛乳が汚染されていないかという点
が指摘されていますよね?かっては、牛乳は安全といわれていたと思うのですが、」
「うーむ...
現在、乳を検査しているという話は、聞いています。まあ、“危険部位”なども、色々
変更されているわけですし、生物体ですから、例外的なものも出てくるのでしょう」
「あの、大丈夫なのでしょうか?」夏美が聞いた。
「現在の日本の体制なら、大丈夫だと思いますね...アメリカのように、年間20万頭
もの“へたり牛”を食べている国だと、牛乳の方もどうかということはありますがね。
これまでは、高濃度の脳の“異常・プリオン”を調べていました。しかし、最近では、
血液や尿などに含まれる低濃度の“異常・プリオン”が課題になっています。したがっ
て、乳はどうかということになるわけです...
まあ、そういう意味では、安全と断言することは出来ませんが、とりあえず、一般的
な危険の範疇に入れてもいいのではないかということです。例えば、交通事故や、飛
行機事故、食中毒、その他の病気にかかる確率などといった範疇です...」
「はい...そうですよね...そのうちに、はっきりしてきますよね」
「まあ、それは次の構造依存性・免疫検査法(
CDI )で話しますが、血液や尿の検査
でBSE感染牛が分れば、生きた動物での検査が可能になるわけです。そうなれば、
乳がBSEに汚染されようがされまいが...“BSE感染牛は全て撤去”となるわけで
す。将来的には、問題はないと思います」
「うーん...“生体での検査”が可能になれば、“全頭検査体制”が敷かれ、感染牛は
全て撤去されるわけですね?」
「まず、そのあたりが、BSE対策のターゲットになるのでしょうかね...ともかく、それ
には、血液や尿がBSE検査に使えるかどうか、最新の検査体制を見てみましょう」
「はい」
【4】構造依存性・免疫検査法(
CDI )...   
<自動化された検査法で、5時間程度で判定できる>
<非常に低濃度の、“異常・プリオン”を検出できる>
<尿や血液が検査に使えるか、現在テスト中...>
「さて...これまで話してきたように、既存の検査法には、限界があります。一方、牛肉
供給の大半をしめる若い牛に対しては、これまでの“免疫測定法(ウエスタン・ブロット
法)”などでは難しくなってきています。
日本での“23ヶ月齢”、“21ヶ月齢”の若い感染牛の発見はラッキーだったが、今
後はこうした若い牛から“異常・プリオン”を検出することが、大きな課題になってきま
す」
「はい、」
「できれば、血液や尿での、生きている動物からの検査が求められます。“と畜”し
て、脳の組織サンプルを検査するというのでは、非常に非効率ですし、時間も費用も
かかるわけです」
「ええ、」弥生がうなづいた。「“と畜”して、脳をの組織サンプルを検査して、それでBS
Eに感染していなかったというのでは、かわいそうですものね」
「あ、その場合は...」夏美が言った。「食肉に回されるわけよね。日本では、これま
で、11頭が例外で、BSE感染牛として、焼却処分されたわけよ、」
「あらあら、」弥生は、白い歯を見せた。
「ふふ、」夏美が、コクリとうなづいた。「それが、普通なわけよ」
「ふーん...」
「さて、話を進めよう...
参考文献によれば、これまで、幾つかの方法が検討されて来たといいいます...
まず、“増幅法”が検討されました。これは、サンプルの中の“異常・プリオン”の量を
増加させ、見逃す可能性を減らそうというものです。まあ、方法としては、オーソドックス
(正統な)なものです。ウイルス検査などでも使われますし、DNAではPCR法(ポリメラーゼ連
鎖反応法)といったような有名な“増幅法”があります。
こうした“増幅法”が完成すれば、生きた検体からの血液から、“異常・プリオン”を
検出できるようになります。これまでの方法では、血液中の“異常・プリオン”は希薄な
ため、検出することが出来ませんでした...
こうした“増幅法”がうまく行けば、生体での検査が可能になり、低コストでの“全頭
検査”に道を開きます」
「うまく行っていますの?」弥生が聞いた。
「うーむ...現在進行中です。この“増幅法”で、成果をあげているグループが幾つか
あります。しかし、それほど簡単ではないようだねえ。例えば、こんなことをやっている
ようです...
正常なハムスターと、感染したハムスターの脳のサンプルを混合します。それから、
この混合物に、“音波パルス”を当て、“異常・プリオン”の“凝集塊”をバラバラにしま
す。すると、“異常・プリオン”の奇妙な作用で、“正常・プリオン”が“異常・プリオン”に
変化するわけです...
まあ、どうしてオセロ・ゲームのように、“正常プリオン”が“異常・プリオン”に変化
し、ひっくり返されていくのかは...そのメカニズムは分っていません」
「ふーん、何故なのでしょうか?」弥生が、首をかしげた。
「さて、この実験では...ええ...“異常・プリオン”を、10倍にすることに成功してい
るようですね...」
「10倍では、ダメなんですの?」夏美が聞いた。
「うーむ...どうなんでしょうか...まだまだ、実験段階ということでしょう、」
「はい」

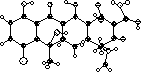
「さて...
もう1つの方法が、4つ目の検査法、“構造依存性・免疫検査法(
CDI )”
になりま
す。この方法は、参考文献の著者/プルシナー博士が、大学の同僚のサファーと開発
した検査法です」
「あ、はい!」夏美が言った。「参考文献の著者のプルシナー博士ですね?」
「そうです...
この方法は、量をふやすのではなく、プリオン・タンパク質の形の複雑さに注目して
います。つまり、“正常・プリオン”と“異常・プリオン”の、“どちらか片方にだけ反応す
る抗体”を利用したものです。
“この抗体”は、プリオン・タンパク質が、特定の構造をとっている時は近づけるが、
別の構造の時は隠れてしまうような部分を、特異的な標的とするということです...」
「うーん...はい...」
「この“正常・プリオン”と“異常・プリオン”を分離する試薬を使えば、サンプルをプロテ
アーゼで処理し、“正常・プリオン”を分解する必要が無いのです。そして、ここが、非常
に重要なのです。
というのは、最近、“異常・プリオン”の中には、“プロテアーゼで分解されるもの”が
あることが分ってきたからです。つまり、“正常・プリオン”を除去する検査法だと、プロ
テアーゼ感受性を持つ“異常・プリオン”の方も、ほとんど、あるいは全て、分解されて
除去されてしまうからです...」
「うーん...」夏美が、首をかしげた。「すると、今までのウエスタン・ブロット法などで
は、プロテアーゼ感受性のある“異常・プリオン”は、“全部分解してしまっていた”の
かしら?」
「どうも、そうらしいねえ...
そうした検査法では、“異常・プリオン”の存在量を、“実際の10%程度に過小評
価”していた可能性が高いようです。まあ、こうしたあたりの話を聞いていると、BSE
の実態や、BSE検査というのも、まだまだ手探りの状態だという感じがします」
「はい」
「日本政府は、“全頭検査”を見直す方向で動いているようだが、拙速は避けるべきだ
と感じます...ここは、急ぐ必要はないし、いくら慎重であってもいいわけです。アメリ
カの畜産業界の苦しい状況は理解しますがね...
規模は違いますが、かっては日本の畜産業界も、そうだったわけですし、」
「はい、」
「ま、ここは、アメリカの消費者全体が、まず自国のBSE対策はこれで十分なのかど
うかを、真剣に考えて欲しいと思います。おそらく、北米大陸の2頭のBSE感染牛の
他に、自然発生のBSEがあることを、慎重に、納得のいく調査を、十分にやるべきだ
と思います。
それにしても、アメリカでは、2004年1月まで、年間20万頭もの“へたり牛”を、ほと
んどBSE検査もせずに食肉に回していたと言います。これは、少々信じがたい話で
すねえ...日本の農水省が、BSE感染が広がっているヨーロッパから肉骨粉を輸
入し、日本にBSEを広めてしまったのと、同じ感性を感じますね...」
「はい」
「ええ、さて...
この“構造依存性・免疫検査法(
CDI )”
ですが、2003年にBSEの震源地だった
ヨーロッパで承認されています。自動化された検査法で、感度も高く、血液中の“異
常・プリオン”も検出できる可能性があるといいます。また、若い牛のスクリーニング
で、有望視されています」
〔4〕
プリオン病の最先端と、治療への道

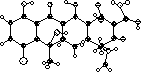
   
≪7≫最先端の状況
「ええ、高杉さん...それでは次に、プリオンに関する新しい展開についてお話して
いただきたいと思います」
「はい...この“構造依存性・免疫検査法(
CDI )”を研究している中で、色々なこと
か分って来たと言います。
まず、“異常・プリオン”はプロテアーゼの分解に対して、異なる反応をする幾つかの
集団があることが分ってきました。ウイルスのように、幾つもの少しづつ特徴の異な
る株(系統)が存在するのです。
それから、先ほども話しましたが、プロテアーゼで分解される“異常・プリオン”は分
解されにくいものに比べ、かなり早い段階で出現するということです。分解されやすい
ものが、分解されにくいものに変っていくのかどうかについては、まだ明らかにされて
いません」
「うーん...」夏美が、言った。「...それは、同じ“異常・プリオン”が...変化してい
く過程かもしれないですよね?」
「でも...別の株かも知れませんわ...」弥生か、夏美を見ながら、タバコを吹かし
た。「こういう問題では...たいがい事態は、複雑にこじれて行くものよ...」
「うむ...弥生さんの言うことも、もっともだ。しかし、素直に考えれは、夏美さんの方
だろうねえ...」
「ふーん...」弥生が、タバコの灰を落した。「高杉さんは、実際に、どちらだと思いま
すの?」
「まあ、両方かねえ...その方がより複雑になる。つまり、変化していく過程のものも
あり、全く別のものもあると...ひねくれたヤツは、常にいるものだ...」
「うーん、そうかもね、」夏美か、うなづいた。
「ええ、さて...
このプロテアーゼで分解される“異常・プリオン”を同定てきる検査法なら、BSEの
症状が現れる前に、その感染が分るわけです。そうなれば、食肉供給の安全性にお
いても十分な処置が取れます。
ちなみに“構造依存性・免疫検査法(
CDI )”では、げっ歯類とヒトの血液から、プ
ロテアーゼで分解される“異常・プリオン”を、低濃度で検出するのに成功しているそ
うです」
「あ、そうなんですか!」夏美が言った。「低濃度で検出するのに、成功しているわけ
ですね?」
「そうです...期待していいと思います。
それから、血液中のプリオンを調べていて、もう1つの驚くべき発見があったといい
ます。それはマウスの後足の筋肉中には、血液中の10万倍の濃度のプリオンが存
在することを発見したことです。それから、他の筋肉中にもプリオンは含まれていると
いいますが、濃度はもっと低いようです」
「うーん...とういうことなんでしょうか?」
「うーん、分らんですね...参考文献によると、そういうことです...
他の研究では、げっ歯類だけではなく、人間にも同様の発見があったようです。何人
かのCJD(BSEによらないクロイツフェルト・ヤコブ病)患者の筋肉中に、“異常・プリオン”が存在す
るのを発見したということです。ええ、他の研究では、患者の25%の筋肉中に“異常・
プリオン”が発見されているということです」
「うーん、25%ですか...」
「そうです...
ええ、他では...尿中にプロテアーゼ抵抗性の“異常・プリオン”が発見されたとい
う、非常に興味深い情報があります。しかし、残念ながら、1例だけで、その後の研究
では確認されていません」
「うーん、尿からは、その程度なのかしら?」
「さあ、詳しいことは分りませんが、そうなのでしょうか...血液よりも、痛みをともな
わない尿の方が、理想的なのですがね」
「はい、」
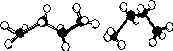   
「他に何か、」
「これもすでに触れてきたことたが、プリオン株の問題があります。前にも言ったよう
に、プリオンにはウイルスと同じような、少しつづ特徴の異なる幾つもの株(系統)があり
ます。
BSEプリオンにさらされたヒツジの研究から、株を調査し識別する必要性が出てき
たといいます。ARR/ARR型という遺伝子型をもつ品種のヒツジは、ヒツジのBSEで
あるスクレイピーに、抵抗性があります...
そこで、ヨーロッパの数カ国では、ARR/ARR型のヒツジを繁殖させて、スクレイピ
ーを一掃しようとしています。つまり、スクレイピー抵抗性のある遺伝子型のヒツジを
増やし、問題解決をはかろうというわけです」
「あの、高杉さん...」弥生が、タバコを持った腕をテーブルに立てて言った。「その、
ARR/ARR型というのは、なんなのですの?」
「ARRの3文字は、ヒツジのプリオン・タンパク質に含まれている、アミノ酸の種類をさ
しています」
「あ、はい、」弥生が、うなづいて、タバコの灰を落した。
「ところが、このARR/ARR型の遺伝子型を持つヒツジは、BSEプリオンを接種して
みると、発病するわけですね。つまり、どういうことかと言うと、このヒツジは、スクレイピ
ーには抵抗性があるが、BSEには感受性があるということです。
スクレイピーは、ヒトに感染することはないようですが、BSEは感染するわけです
ね。BSEプリオンに感染するヒツジがいるということは、ヒツジの肉を食べる人にとっ
ては、危険なことです。
まあ、特定の遺伝子型をもつヒツジの繁殖を試みる前に、ヒツジ由来のBSEプリオ
ンが、ウシ由来のものと同じように、致死性の危険なものなのかどうか調べるべきだ
といいます...」
「あ、ヒツジ由来のBSEプリオンは、牛のものとは違うのでしょうか?」
「違います。人もBSEプリオンを食べて、感染はしますが、人の中に入るとBSEその
ものとは異なるのだと思います。人の場合は“変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJ
D)”といいます。
それぞれ、動物によって、タンパク質が異なるからです。鳥インフルエンザが、人に
感染しないのもそのためです。ただ、インフルエンザなどは変異が早く、それが人に感
染して、“新型インフルエンザ”となるわけです」
「BSEもそうなんでしょうか?」
「分りません...
が、プリオン病というのは、ウイルスとは全く別のものです。まあ、変異しやすいこ
と、株があることなどは、ウイルスに似ていますが、本質的に違います。プリオンの場合
は、DNAやRNAをもたない、タンパク質だけの病原体であり、全く概念の異なるもの
なのです...」
「うーん、はい、」
≪8≫プリオン病の治療   

「ええ、新しい検査法によって、BSEに関する安全性は、今後改善する方向へ向かう
と思います。しかし、潜伏期間が長いために、この致死性の病気は、今後表面化して
くる恐れがあります。特に、対策をとってこなかったアメリカでは、注意が必要かも知
れません。
それにプリオン病との戦いは、BSEでお終いという訳ではありません。ぜひ治療
法は必要なわけです。そこで、“プリオンの形成を阻害”したり、“体内のプリオンを除
去する細胞の能力を強化”するなどの研究がされています」
「はい、」夏美が、うなづいた。
「培養細胞を使った実験では、プリオンを阻害したり、プリオンを除去したりする化合
物が、20種類以上見つかっています。まあ、研究は、これからですね。それに、これ
らの化合物は、大量に投与しないと効果を発揮しないものが多く、毒性への不安が
あるのです」
「うーん、毒性ですか...」
「それに、“血液脳関門”を通過して、血流によって脳組織に送り込める薬を見つけ
なければなりません」
「あの、高杉さん、」弥生が、脚を組んで、タバコを吹かしながら聞いた。「“血液脳関
門”というのは、聞いたことはあるんですが、何だったかしら?」
「“血液脳関門”というのは、脳に“異物”が入らないようにするろ過器のようなもので
す。脳は、微妙な領域ですからね。したがって、分子量の大きい薬なんかは、通過で
きないわけでしょう」
「あ...はい、」
「ちなみに、脳内で作用するある種の薬が、培養細胞でのプリオン形成を阻害するこ
とが発見されています...ええ、参考文献では、プリオン形成とありますが、これは
“異常・プリオン”形成ことでしょうね...その中には、統合失調症(精神分裂病)の治療
に使われる“ソラジン”などがあります。
また、“ソラジン”に似た構造をもつ、抗マラリア薬の“キナクリン”は、その10倍の
効果があるようです。この“キナクリン”は、培養細胞だけでなく、動物実験でも多少の
効果を示したようです。まあ、研究は進んでいるようですね」
「はい、」夏美は、言った。
「もう1つの治療法は、“異常・プリオン”の形成を阻害する“抗体”を使うものです。ま
あ...参考文献からは、その実態はよく分りませんね...」
「うーん...そういう治療薬は、実際に使われているのでしょうか?」
「このような“抗体”を使った薬は、“抗プリオン薬”というのですが、これを受けた患者
は、今のところほんのわずかな様です。
“キナクリン”の方は、“変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)”患者や、孤発生
または遺伝性のプリオン病患者に、口径投与されています。回復した例はまだありま
せんが、病気の進行が遅くなった可能性があり、データを蓄積しているところです」
「うーん...」
「“変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)”患者に、“ペントサンポリサルフェート
(硫酸多糖体)”を投与している医師もいます。普通、“ペントサンポリサルフェート”
は、膀胱の病気の治療薬として処方されるものです。まあ、この薬は、血液脳関門を
通過できないので脳室に直接投与します。ある若い男性では、この投薬によって、明
らかに“vCJD”の進行は遅くなっています」
「はい、」
「ええ...有効な治療法への道のりは、遠いように見えますが、有望な薬や治療法
の候補は見つかっているので、5年前に比べればずいぶん進歩しています。
プリオン病の有効な治療法が開発されれば、“アルツハイマー病”や“パーキンソン
病”、それに“筋萎縮性側索硬化症(ALS)”のような、もっと一般的な神経変性疾患
にも応用が期待されます。これらは、いずれも、“異常な凝集タンパク質”か現れるか
らです」
「そう言えば、最近“BSE掲示板”に、“異常プリオンを“解きほぐす分子”を発見!”
というニュースがありましたよね」
「ああ、そうですね...期待していいと思います」
「はい!」
  
|
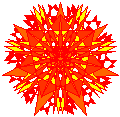





![]()




