配偶者の不貞相手に対する慰謝料の最高額は
弁護士河原崎弘
相談:夫の不貞相手にいくら請求すべきか
私の夫は、もう3年以上、愛人の女性と関係(不倫)が続いています。子供が2人いるので、私は、我慢していましたが、そろそろ限界です。パソコンのメールでも、夫と愛人との間に、肉体関係があることは、はっきりしています。私は、相手の女性に慰謝料請求の裁判をしようと思います。
まず、はがきで、交際禁止と、慰謝料を請求し、次に、内容証明郵便で請求し、次に訴えを提起しようと決めました。
今、いくら請求したらよいか、考えています。このような場合、裁判では、夫の不貞相手(愛人)に対しては、最高額いくらの慰謝料が認められているのでしょうか。
相談者は、うつ状態で法律事務所に現れ、弁護士の意見を聴きました。
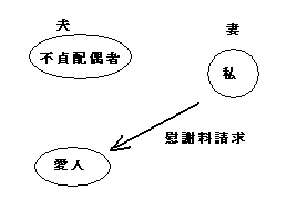
回答:不貞に加担した者が負う慰謝料の最高額は500万円です
不貞行為(不倫)をしている配偶者の相手(愛人)が負う慰謝料は、通常は、200万円前後です。これが基本です。尻軽な配偶者で、夫婦に子供がいないと、愛人の責任は50万円くらい(配偶者の責任が大きく、愛人の責任は小さい)。 自己の配偶者が交際に積極的であった場合は、愛人の責任は100万円〜150万円くらい(愛人は受身であって、責任は小さい)。 夫婦に子供がいて、夫婦に亀裂が入った場合は、愛人の責任は200万円を越える場合があります(愛人の責任は大きい。被害が大きい)。
ときどき、クラミジアの感染などが、云々されますが、それが完全に証明されなくとも、裁判官には、(ひどい人との)強い印象を与えますので、検査の証明書を証拠として提出すると有効です(慰謝料が増える)。
精神的打撃や、慰謝料は証明できませんので、証明する必要はありません。しかし、通常は、 受けた精神的打撃を、陳述書の中で、配偶者の不貞行為により受けた苦しみを説明し、証明します。
さらに、配偶者の不貞で、精神的にストレスを受け、病院に通った人も多いです。そこで、診断書、治療費などの領収書を証拠として提出すると有効です(慰謝料額が増える)。診断書は、心身症、不安神経症、不眠症などだけでなく、精神的なストレスが原因の消化器系統の病気でも有効です。
裁判官は、診断書、領収書を、精神的打撃が大きかったことを認定する証拠として使いますし、損害額(治療費など)を証明する証拠としても使います。
刊行されている文献では、判決上の慰謝料最高額は500万円です。1つの例では、男性ですが、不貞の相手(愛人の女性)の夫の勤務先まで、妻の不貞を知らせたとの悪質な例です。
両方とも浦和地方裁判所ですが、判決を言い渡した裁判官は、違います。
最近の判決では、東京地裁で、弁護士が依頼人と不倫をし、依頼人が離婚したケースでは2000万円の請求に対して300万円を認めた判決がありました。
また、大阪地裁で、金1200万円の請求に対し、300万円を認めた判決がありました。これは、不貞関係が約20年と長かったことが、慰謝料が高額であることの理由の1つでした。
また、不貞期間20年、こどもが2人いるケースでは、妻は、亡夫の愛人に1億円請求しましたが、判決では500万円でした。
以上を概括すると、不貞相手になった愛人の負う慰謝料(相場)は、200万円くらいが標準で、特別の事情があると500万円前後になると言えます。
判決
- 東京地方裁判所平成19年7月27日判決
被告が,Aに原告という妻がいることを知りながら,Aと肉体関係を持つに至り,昭和60年ころ以降,Aが死亡するまでの約20年間もの長期間にわたり,A が毎日被告宅に通うようなかたちでAとの関係を継続し,その間に被告はAが認知した2人の子ももうけていること,被告の住居は原告の自宅と同じ町内ないしは近隣 であったこと,そうしたことから原告は愛人や隠し子がいるなどといった風評にも悩まされたとうかがわれること(甲14)などからすれば,原告は,多大な精神的苦 痛を被ってきたものと認めることができる。
一方,A死亡に至るまで同人と原告との婚姻生活が破綻に至ったとは認められず,Aとの信頼関係を強調する原告の主張・供述(甲14,原告本人)からしても 原告は,Aのことは宥恕しているものと解される。
こうした諸事情も含め,本件に現れた全事情を総合考慮し,さらに,本訴提起よりも前に原告が被告に対して本件に係る慰謝料請求をしたと認めるに足りる証拠 はないので,原告の被告に対する慰謝料請求権のうち,本訴提起の日である平成18年8月11日から20年前である昭和61年8月11日より前の分は除斥期間の経 過によりもはや行使し得ないものと解されることからすると,結局,原告に認容すべき慰謝料額としては,500万円が相当である。 - 東京地方裁判所平成19年2月27日判決
しかし原告とAは,曲がりなりにも共同生活を続けており,婚姻関係が決定的に破綻するに至ったのは,平成16年8月27日,充填料問題での原告の暴言に腹 を立てたAが原告方を出たころと認めるのが相当である。
そして,被告はそれ以前からAと情交関係にあり,それが原告とAの婚姻関係破綻の一因となったことは否定できない。
(2)本件認定の各事実及び被告本人尋問の結果,弁論の全趣旨を総合すれば,被告は,平成6年の離婚交渉後もAに好意をもち,個人的にサポートするなど,その不 満の相談にも乗っていたところ,充填料引き下げ問題をめぐりAの心が原告から離れていく過程で,親密な関係になっていったものと認められる。婚姻関係の破綻につい ては原告自身の問題点もあるにせよ,被告はひとたびは原告の紹介でD及び関連企業の支配権争いに関し民事保全事件,訴訟事件を受任するなどしており,その信頼を裏 切る行為といわざるを得ない(他方,これらの事件での弁護士報酬は原告が支払ったものではないので,慰藉料算定に直接影響するものではない。)。
(3)以上の事情を総合的に考慮し,慰藉料としては300万円を相当と認める。
- 大阪地方裁判所平成11年3月31日判決(判例タイムズ302ー233)
以上検討したところによれば、被告は太郎と不貞関係にあったと認めることができる。そして、不貞行為の期間が長期にわたること、最終的に太郎が原告と別居するに 至ったこと、もっとも不貞関係になるに当たって被告と太郎とのいずれが主導的であったかについては明らかでないこと等、不貞行為の経過、態様及び影響等について証 拠上認められる諸事情を総合的に考慮すると不貞行為によって生じた原告の精神的苦痛を慰謝する額としては金300万円を相当と考える。
- 大阪地方裁判所平成11年3月31日判決(判例タイムズ1035号187頁)
第一 請求
(1) 被告は、原告に対し、金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成10年8月6日)から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告は、原告と甲野太郎との婚姻が継続している間、甲野太郎と同棲又は会ってはならない。 第二 事案の概要
一 争いのない事実
原告と訴外甲野太郎(以下、「太郎」という。)は、昭和50年9月9日に婚姻した夫婦であり、原告、太郎及び被告のいずれ も公立学校の教師である。被告は婚姻していたが、平成元年に夫が死亡した。
昭和54年ころ、被告と太郎は同じ小学校に勤務するようになり、それから間もなく交際するようになり、現在に至っている。 この間、被告は、被告名義の携帯電話や銀行キャッシュカードを太郎に使わせるなどしていた。
平成10年5月17日、原告、太郎及び被告とで話し合いがされ、原告は、被告が太郎と今後交際しないよう念書の差入れを要 求したが、被告はこれを断った。その後、太郎は原告と同居していた自宅を出て、原告と別居するようになった。
二 争点
(1) 被告と太郎との間に肉体関係があったか。
(ア) 原告の主張
被告と太郎は、肉体関係を持っていた。太郎もそのことを原告にしばしば話している。また、太郎は被告宅に泊まるなどしてい る。
(イ) 被告の主張
被告と太郎は、当時の被告の夫の病気や、太郎と原告との夫婦関係がうまくいっていないことの悩みをお互いに相談するうちに お互いに愛情を持つようになったものであり、その関係はいわゆるプラトニックなものにとどまっていた。
(2) 被告に対して太郎と会うことや同棲することの差止めを求めることが許されるか。
(ア) 原告の主張
被告は、太郎の不貞の相手方となり、将来も同様の行為を継続する高度の蓋然性がある。原告は、これにより著しい精神的苦痛 を被るおそれがあるから、人格権又は民法709条に基づき、これを差し止める権利を有する。
(イ) 被告の主張
原告と太郎の夫婦関係は破綻しており、また原告は太郎との離婚を決心している。原告が被告と太郎の交際を禁ずることを求め るのは権利濫用であり、被告と太郎の人格権を損なうものとして認められない。
第三 争点に対する判断
一 争点(1)(不貞の有無)について
(1) 事実経過について
甲具乙1、原告及び被告各本人尋問の結果、弁論の全趣旨並びに後掲各証拠によれば、次の事実が認められる。 (ア) 原告と太郎は、昭和50年に婚姻し、同51年に長女を、同54年に長男をもうけている(甲1)。被告は昭和50年に 婚姻し、同52年に長男をもうけたが、夫は平成元年に死亡した。 (イ) 太郎は、昭和54年に被告が当時勤務していた小学校に赴任し、間もなく、太郎と被告の交際が始まるようになった(甲 5)。
昭和62年4月に被告と太郎が宴会の後に朝帰りすることがあった。これについて被告の夫から原告方に電話があり、被告が太 郎と宿泊したのではないかとの話であったため、原告が被告に太郎とホテルに宿泊したのではないかと電話で間いただし、被告は これを認めた(甲11)。
被告は、遅くとも平成元年ころから自己名義の銀行キャッシュカードを太郎に手渡し、これを自由に使わせていた(甲4、9)。 また、自己名義の携帯電話を太郎に渡し、メッセージを入れるなどもしていた(甲10)。
(ウ) 太郎は、被告と肉体関係があることを原告に対しても述べたり、被告と原告を比べるような話をしたりしていた。 そして、平成9年11月ないし12月ころ、太郎は原告に対し、離婚してほしいと申し向けるようになった。そこで、同10年 3月終わりころ、太郎の両親が来阪して太郎と話しあうなどした結果、太郎は被告と別れる旨述ベた。
ところが、同年5月14日、太郎が深夜になって被告の運転する車に乗って帰宅したことがあり、これを契機に原告は太郎との 離婚を考えるようになった。ただ、原告としては、太郎が原告と離婚した後被告と結婚等するのは許せないと感じ、被告と太郎に おいて結婚等しないならば太郎との離婚に応じるので、被告もその旨の書面を作成するように要求した。しかし、被告は、これに 応じなかった(以上につき甲6ないし8)。
太郎は、その直後から家を出て原告と別居するようになり、原告には居住先も教えていない。なお、被告は太郎の居住先を知っ ており、同人の衣類を被告方で洗ってやるなどしている(甲3)。また、被告は太郎との結婚を希望している。
(2) 原告供述の信用性について
なお、被告は、(1)の事実認定の前提となる原告記載によるノート(甲6ないし8)の内容の信用性について争っている。し かし、ノートの記載内容は非常に具体的かつ赤裸々で、原告自身にとってのプライバシーや名誉に関わりかねないことについても 詳細に書かれている。そして、原告本人尋問の結果とも、よく内容が合致しており、他の証拠から認められる事情にも沿った内容 となっている。また、ノートの記載内容の信用性を疑わせる事情も窺えない。したがって、ノートの内容は信用できる。
(3) 不貞行為の有無について
(1) での認定事実に照らすと、被告と太郎においては遅くとも昭和62年ころから不貞関係にあったものと認められる。 なお、これについて、被告は、太郎との間では肉体関係はおろかキスもしたことがなく、抱擁してもらったことがある程度であ って、いわゆるプラトニックな関係である旨本人尋問で述べている。
しかしながら、前記のとおり、太郎においては、被告との肉体関係を認めていることが認められる。また、交際の経緯を見ても、 被告と太郎との交際は両者が30歳前後の若いころから既に20年近くにわたって継続しており、両者間の関係は深いものになっ ていることが窺える。また、太郎も被告もそれぞれ子どもをもうけた身であっ・て当然に性経験はあり、太郎はそれなりに活発な 性的欲求を持っていること(甲6ないし8)も窺える。そして、被告は太郎との結婚を希望しているところである。
他方、被告は、太郎との交際がプラトニックな関係にとどまっている理由として、原告の家族のことを考慮してのことであると 述べる。しかしながら、交際の経緯や先に挙げた諸事情に照らすと、この理由は納得できるものではない。
そうすると、被告と太郎とには肉体関係があったと認められるのである。
(4) 慰謝料額
以上検討したところによれば、被告は太郎と不貞関係にあったと認めることができる。そして、不貞行為の期間が長期にわたる こと、最終的に太郎が原告と別居するに至ったこと、もっとも不貞関係になるに当たって被告と太郎とのいずれが主導的であった かについては明らかでないこと等、不貞行為の経過、態様及び影響等について証拠上認められる諸事情を総合的に考慮すると不貞 行為によって生じた原告の精神的苦痛を慰謝する額としては金300万円を相当と考える。
二 争点(2)(差止め請求の可否について)
(1) 原告は、被告が太郎と会うことについての差止めも求めているが、被告が太郎と会うこと自体が違法になるとは到底いえ ないから、少なくともこの部分については請求に理由がないことは明らかである。
(2) そこで、次に被告と太郎との同棲の差止めを求めた部分について検討する。
差止めは、相手方の行動の事前かつ直接の示止という強力な効果をもたらすものであるから、これか認められるについては、 後 の゛銭賠償によっては原告の保護として十分でなく 前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情のあることが必要である。
そこで、本件におけるそのような情の有無についてみると、原告と太郎は婚姻関係こそ継続しているものの、平成10年5月こ ろから太郎は家を出て原告と別居しており、原告に居 を連絡してもいない。これに加えて、先に認宀した経緯をも考慮すると、 両者間の婚姻関係が平常のものに復するためには、相当の困難を伴う状態というほかない。そして、原告もまた太郎との離婚をや むなしと考えてはいるものの、太郎が被告と同棲したりすることはこれまでの経緯から見て許せないということから太郎との離婚 に応じていないのである。
そうすると、今後被告と太郎が棲することによって、原告と太郎との平和な婚姻生活が害されるといった直接的かつ目、的な損 害か生じるということにはならない。同棲によって侵害されるのはもっぱら原告の精神的な平和というほかない。このような精神 的損害については、同棲が不法行為の件を備える場合には損害賠償によっててん補されるべきものであり、これを超えて差止請求 まで認められるべき情があるとまでは言えない。
よって、原告の差止め請求については理由がない。
- 浦和地方裁判所昭和60年12月25日判決(判例タイムズ617−104)
1 原告(昭和9年1月3日生)は高校の教科書、大学関係のテキスト等を発行している○○出版株式会社に勤務し、総務部 長の職にあるものであり、昭和39年7月3日妻春子(昭和18年2月26日生)と婚姻し、長女秋子(昭和40年7月1日生) と長男一郎(昭和43年4月2日生)を儲け、長女は短大2年生、長男は高校2年生で、本件が発生するまでは平穏な家庭生活を 営んでいた。一方、被告(昭和3年10月16日生)にも妻子があるが、長男は31歳、長女は28歳で、いずれも別世帯をもつ ている。しかして、被告は中古自動車販売を目的とする有限会社を経営し、従業員4人を使い、年商約3億円を挙げているもので ある(但し、原告が会社に勤め、春子と夫婦であること、秋子、一郎が原告の家族であること、被告が妻子を有し、中古車販売の 有限会社を営んでいることは当事者間に争いがない。)。
2 ところで、被告と春子は昭和58年1月頃ともに町内の自治会役員であつたことから知り合いになり、同年3月下旬から 情交関係をもち、昭和58年8月頃には被告と春子の間柄が噂になつたことから、原告は春子に対し、被告との交際について十分 注意するように戒めた。しかるに、右両名は情交関係を続け、春子は昭和59年6月下旬頃身の回わりの荷物をまとめて被告の賃 借した浦和市下大久保のマンションに移り、被告と約10日間同棲するに至つたが、同年7月2日春子は実母の説得により原告の もとへ戻つた。ところが、被告はその後も春子との情交関係を続けた結果、春子は被告の子を懐妊した。
3 その挙句に、被告は昭和59年12月1日突然原告宅に来て、原告に対し、被告と春子との結婚を認めてほしいと述べた。 原告は春子の親族とも協議し、翌2日に被告と会つて春子と被告の関係について話をすることにし、被告もその旨を了承した。し かるに、被告は翌2日に春子とともに四国へ旅行に出てしまつた。そして、春子は旅先で堕胎し、再び2週間程して同年同月18 日原告の許へ戻つた。
4 原告は春子のそれまでの不貞行為と背信行為を叱責したが、春子の実母の懇願があり、春子自身も今後被告との関係を断 ち切る旨を誓約したので、春子を恕した。そして、同日原告は被告を自宅に呼び寄せて、○○市会議員○○立会のうえで被告に対 し春子との情交関係を叱責し、今後は絶対交際しないように要求したところ、被告も原告に対し、春子との従来の関係を詫びて今 後一切交際しない旨を誓約し、原告の子供たちに対しても陳謝した。ところが、被告は4日後の同年同月22日には春子との交際 を再開し、原告の家庭に頻繁に電話をかけ、その際、春子以外の者が受話器をとると何も言わずに切り、春子が電話に出るまで掛 け直すなどということを繰り返し、その度毎に原告及びその家庭の平穏な家庭生活を乱した。
5 また、被告は昭和60年1月から春子との情交を再開し、しかも、同年4月から5月2日の間に少なくとも3回原告の庭 まで来て、春子の名を大声で叫ぶなど非常識な行動に出た。そこで、5月2日の際には、堪り兼ねた原告の長男一郎が被告を殴打 し、被告は眼部に負傷した。ところが、被告は怪我をさせられたのに原告が誠意を示さないと憤激し、かつ、原告と春子の夫婦関 係を一層悪化させれば春子が被告の許ヘ来るものと考え、同年5月22日から29日の各日付で被告と春子との情交関係を記載し た葉書合計10通を10回にわたり原告の前記勤務先を住所として原告宛に投函し、それらはいずれもその頃勤務先へ配達された。 そして、原告の妻と被告との醜聞が原告の勤務先の文書受付の女性等の目に触れるところとなつた。しかも、右葉書のうち、23 日ないし25日付の葉書3通には、いずれも被告と春子とが寄り添つた姿を撮つた写真を貼付し、また、27日付の葉書2通、28日付の1通、29日付の2通には、いずれもカレンダーを貼付し、昭和58年3月から昭和60年4月までの日付欄に肉体関係 を持つた日を丸印で囲んで明示した(但し、原告主張の日付と回数で被告と春子との淫らな関係を書いた葉書八通を原告の勤務先 に郵便で送付したことは当事者間に争いがない。)。しかも、右の葉書10通には、春子との性関係を淫らな言葉で描写した短文 を書き添えている。また、その頃被告は春子に対し、右葉書と同趣旨のことを記載したカレンダーを渡して原告所有の自動車内に 入れて原告に見せるように言つた。
6 ところで、被告は本件訴が提起された後の昭和60年7月19日から春子と埼玉県志木市○○○のアパートで同棲を始め、 今日に至つている。
他方、原告は今では春子との離婚を決意しているが、原告の家庭では、多感な年頃である高校2年生の長男一郎が自棄的となり、 勉学意欲を失い、成績も低下し、原告が注意すると母春子の生活態度を楯にとつて反抗し、短大2年生の長女秋子の原告に対する 態度までも冷たくなつてしまつた。そのようなことから原告は被告に対し強い憤りを感じている。 以上の事実が認められ〈る。〉
二 前記一2ないし5で認定した被告の一連の非常識極まる不法行為によつて、原告は夫としての権利を著しく侵害されたのみ でなく、原告の妻の不倫行為が原告の勤務先関係者にまで知られて、原告の社会的名誉が著しく毀損されたものである。
右被告の不法行為によつて原告は多大な精神上の苦痛を被つたことは多言を要しないところ、前記認定の諸事情に照らすと、慰 謝料額は少なくとも金500万円を下らないと認められる。
三 よつて、被告に対し、慰謝料金500万円及びこれに対する不法行為の後であることが明らかな昭和60年6月15日から 支払に至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担に ついて民訴法89条を、仮執行の宣言について同法196条を適用して、主文のとおり判決する。
- 浦和地方裁判所昭和60年1月30日判決(判例タイムズ556−170)
二 〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。
1 被告と花江は昭和54年頃、与野市内のスナックで客同志として知り合い、その後次第に懇意となり、大宮市のそば屋 「○○」やクラブ「○○○」などでしばしば会つて遊興、飲食を共にするようになつた。
2 被告は、花江に原告という夫のあることを知りながら昭和55年頃、蕨市内のラブ・ホテルで花江と肉体関係をもち、そ の後かなり頻繁にラブ・ホテルヘ通うようになり、北浦和の天ぷら屋「○○」では、花江の「主人」と呼ばれていた程親密な関係 をもち、また、花江と共に京都、大阪、新潟に旅行した。そして、このような関係は昭和57年夏頃まで続いた。
三 〈証拠〉を総合すれば、次の事実を認めることができる。
1 花江は、昭和56年1月30日頃、原告の実印と土地の権利゛証を無断で持ち出して、原告の土地持分を担保に原告名義 で訴外小菅光雄より200万円を借り受け、昭和56年10月14日には、「緊急に必要だから」と原告をだまして原告に、「日 本エス・アイ・シー株式会社」より100万円を借り受けさせた。更に、花江は、原告の姪の訴外Hをだまして、同人から原告の 株購入資金と称して借金をし、同人に無断でその夫の○○百貨店の口座を利用して被告の背広を買つたり、被告の知人に贈物をし、 原告の姉の訴外甲野高子に無断で同人の名義を保証人として大宮市の「丸井」から借金をし、また子供の一男の名義を無断で使用 して「ダイヤモンドクレジット」から約金20万円を、「オリエント・フアイナンス」から約42万円を借り受け、更に原告の先 祖伝来の刀、書画、骨董品を原告に無断で安価に売却した。その他にも、花江は、家族の誰にも知られないようにして、昭和56 年と57年に集中して「アコム」他多数のサラ金業者から合計600万円以上の金銭を借り受けた。
2 花江は、このようにして取得した多額の金銭を被告との享楽のために費消し、家事を放棄し子供の面倒すら見ないように なつた。
3 原告やその子供達は勤務先にまでしばしば、花江が金を借りたサラ金業者から返金を迫る厳しい電話を受けて困惑し、恐 怖心を抱いた。そのため、原告は、やむを得ず自分の預金300万円を引き出し、訴外甲野高子他二名の親族から合計690万円 を借り、更に土地を担保に日本信販から200万円を借りるなど苦労して花江の債務を弁済1)た。
四 〈証拠〉によれば花江が被告と不倫な関係にあつたことを原告に打ち明けたことを認めることができ、原告と花江が昭和57年9月22日に協議離婚の届出をしたことは当事者間に争いがない。
五 以上の事実によれば、被告は、原告という夫がいるということを知りながら花江と不倫な関係を続けることにより原告と花 江との婚姻関係を破綻させて原告の結婚生活における幸福を追求し保持する利益を侵害し、原告に甚大な精神的損害を与え、その 上多大の財産的損害まで与えたのであり、この行為は原告に対する不法行為となると認められる。
六 〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 原告は、昭和33年2月5日に花江と結婚後同年11月5日に長男の一男をもうけたが、昭和34年5月1日には 訴外Sとの間に女児の美香子をもうけ、同年6月12日にこれを認知した。そのため、花江は原告との離婚を考えたが、子供のた めを思い、原告の母の説得により美香子を養育することとし、昭和39年5月16日に美香子を養子とし、一男と別けへだてなく 養育した。
(二) 花江は、結婚後原告の両親、兄、姉と同じ敷地内に住み、一男と美香子の養育をすると共に、これらの親族の面倒 をみなければならなかつた。その間、原告の海外出張中、一男の高校受験の直前に原告の長姉の子供が精神・神経系統の病気から 自殺し、その後始末を花江が一人でしなければならなかつたり、その翌年原告の姉も同様の病気で長い病院生活の後死亡したが、 入院中の見舞は専ら花江が行わなければならなかつた。そして、これらのことから、花江は自分の子供の精神・神経に異常が出る ことをいつも恐れていた。また、原告の兄は言語障害があり、原告の母は昭和54年6月15日に死亡するまで8か月位病床にあ つたが、花江は良くその世話をし、楽ではない家計を内職までして助け、その他にもその住居の近辺に原告の親族が多数住んでい たので、花江の心身を疲れさせることが多かつた。
(三) これに対して、原告は貿易会社に勤務するため結婚した5、6年位後から海外出張が多くなり、年間通算して約200日も家を留守にすることもあり、休暇も余りとれず、帰宅も夜遅くなることが多く、花江の話相手となる時間がなく、花江の 心中を察することができなかつた。
(四) 原告の母の死亡後、花江の生活態度は急変し、夜間に酒を飲みに外出し、前記の如く被告と知り合い肉体関係まで もつに至り、借金までして金銭を浪費するようになつたが、そのきつかけは原告との結婚生活で生じた心の隙間を埋める欲求から 出たものであり、被告が花江を一方的に誘惑したためではなかつた。
2 以上の事実と二ないし四で認定した事実を総合すると、原告の慰謝料として金500万円が相当である。