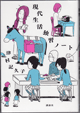|
「まぬけなこよみ」 ★☆ |
|
|
2023年01月
|
「ウェブ平凡」に2012.09.24〜15.09.18まで連載されたという、歳時記エッセイの単行本化。 津村さん曰く、平凡社のスマホアプリ「くらしのこよみ」が優れもので、それにちなんで「まぬけなこよみ」という題にしたのだそうです。つまり、「くらしのこよみ・まぬけ版」との由。 各篇、末尾に「二十四節気」「七十二候」付き。 私も本書で初めて知ったのですが、共に古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、二十四節気をさらに約5日ずつ3つに分けたのが七十二候なのだそうです。 江戸期に日本の風土にあうように改訂され、それぞれに気象の動きや同省物の変化を知らせる短文付き。 内容は日常生活のことを語ったエッセイなのですが、津村さん、自らの生活を評して「無味乾燥な暮らし」と。 でも、一般人の毎日の暮らしなど、津村さんならずともそうしたもので、だからこそ共感を覚えます。 そうした中で、よくぞエッセイを続けたものだと思いますが、そこは、さすが作家さん、と言うべきなのでしょうね。 なお、各篇に挿入されているイラストが、リアルで楽しい。 イラストを見ているだけでも結構楽しめますよ。 新年/冬から春へ/春から夏へ/夏から秋へ/秋から冬へ |