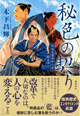|
「秘色(ひそく)の契り−阿波宝暦明和の変 顛末譚−」 ★★ |
|
|
|
宝暦〜明和(18世紀後半、家重〜家治の時代)年間に、阿波徳島藩で起きたダイナミックな藩政改革の動きとその挫折を題材にした歴史小説。 第172回 直木賞候補作ということをきっかけに読んだ次第です。 ちょうど澤田瞳子「孤城春たり」にて備中松山藩の藩政改革を読んだばかりとあって、同じ題材?という興味もあり。 阿波徳島藩、30万両もの巨額の借財を抱え込むが、藩政を担ってきた五家老には危機意識が薄い。若い家臣たちがこれではならじと藩政改革を目指しますが、その中心となったのは小藩の佐竹分家から養子入りし10代藩主となった蜂須賀重喜(1738〜1801)。 渋る重喜をせっつき藩政改革へ重い腰を上げさせたのは、柏木忠兵衛、樋口内蔵助ら「阿波四羽鴉」と呼ばれた若い家臣たち。 しかし、重喜が実施しようとした藩政改革は、適材適所を貫くため身分制度まで崩す、さすがの四人も考え及ばなかった驚愕の改革案だった・・・。 藩主&改革派の若い家臣たちによる、五家老たちとの争い。 そして、改革派と言いながら既存の身分制度を固守しようとする家臣たちと藩主との争い。 歴史小説というより、歴史エンターテインメント、といった面白さです。 そこに加わるのが、足利氏の一族で阿波徳島藩内に百石の領地をもつ<平島公方>一味、阿波徳島藩の名産物である藍の独占販売権を手に入れようと目論む唐國屋金蔵らによる、阿波徳島藩を乗っ取ろうとする巨悪の陰謀が絡み、陰謀との戦いというハラハラする面白さも加わります。 改革といっても、その内容はそれを行おうとする人物の器量、見識に制約されるもの。 核心をついた重喜の改革案に対し、結局内蔵助らの改革案は旧来の身分制度に囚われそれを脱することはできなかった。 そしてその延長として、幕末に向け幕藩体制は時代の変化に応じることができず、弱体化していく定めだったのでしょう。 殿の改革案は正しい、しかし導入するには百年早過ぎる、という言葉はそのとおりだったのかもしれませんが、そこに既に当事者による発想と行動の限界があったと感じます。 藩政改革の挫折例として、興味惹かれる歴史作品です。 なお、題名の「秘色の契り」は、重喜と家臣らの約束のこと。 ※ストーリー中、重喜が語る「心を変えなければいずれ有名無実」「骨抜きにされた法度が害悪として残るだけ」という言葉は今の日本における自民党政治に通じているようです。 1.末期養子/2.五社宮一揆/3.船出/4.明君か暗君か/5.縄取り/6.呪詛/7.謀略/8.密約/9.藍方役所/10.血の契り/11.主君押し込め/12.空の色 |