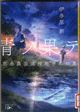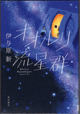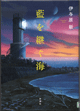| 1. | |
|
「月まで三キロ」 ★★ 新田次郎文学賞 |
|
|
2021年07月
|
題名から察することができるかもしれませんが、各篇いずれとも理系の題材から組み立てた味わいある短篇集。 ・「月まで三キロ」:主人公、残りの人生に絶望。自殺を考えてタクシーに乗る。ぎょっとしたタクシー運転手、自殺に相応しい場所に案内しようと、向かった先は「月まで三キロ」という標識が立っている場所。 ・「星六花」:39歳になる富田千里、知り合いの紹介で奥平潤という気象庁の技術専門官と出会うのですが・・・。 ・「アンモナイトの探し方」:訳ありで東京から北海道の祖父母宅にやって来た小6の朋樹。川原で化石採集を続ける老人と出会いますが・・・。 ・「天王寺ハイエイタス」:かまぼこ店を営む笹野家は、いつも次男が家業を継ぐパターン。伯父の哲おっちゃん、かつてはブルースのギタリストで鳴らしたらしいが、今は問題人物。 ・「エイリアンの食堂」:父親の営む食堂に毎晩定食を食べにくる女性。小3の鈴花は彼女を宇宙人だと信じ込み、「ブレアさん」と呼ぶ。そのブレアさんが鈴花に語ったことは・・・。 ・「山を刻む」:義母の誕生日を放りだし、ある決心を抱えて久々に山に登った主人公。火山を研究している大学の先生と研究生の2人と出会い、これまでの人生と家族のことを振り返る。 会話が理系、科学的なことであろうと、ストーリィの核心はごく普通の出来事。 そんな日常的な出来事も、理系の事実と照らし合わせると、どこか新鮮、自然と答えが導き出されるように感じるところが快い。 斬新さからというと表題作である「月まで三キロ」が抜群。 また同じく宇宙に関する話題となる「エイリアンの食堂」が爽やか。小3の鈴花と研究者であるブレアさんのやりとりに、遥かな宇宙的広がりが感じられて、何とも素敵です。 それに対し、「山を刻む」は山が舞台ですから地に足をつけたストーリィのように感じられますが、その結末が愉快。 清新さが本短篇集の魅力。理系故か、すっきりと感じられます。 月まで三キロ/星六花/アンモナイトの探し方/天王寺ハイエイタス/エイリアンの食堂/山を刻む |