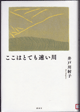| 「ここはとても速い川」 ★★ 野間文芸新人賞 | |
|
2022年12月 2021/07/11 |
「ここはとても速い川」 児童養護施設で暮らす、小学五年生の集。 彼の楽しみは、1歳下の女子ひじりと、近くの淀川にいる亀を見に行くこと。 集たちの送る日々と心模様が細やかに描き出している中篇。 子どもの心は単純と思われがちですが、大人と変わらず、場合によっては大人よりもっと深く、繊細なのかもしれないと感じさせられます。 「膨張」 小説第一作、とのこと。 “アドレスホッパー”の一人である女性=津高あんりが主人公。 以前こうした人たちがいることはニュースで知っていましたが、この言葉自体は認識していませんでした。 アドレスホッパーとは、定住する家を持たずに移動しながら生活する人々や生き方、とのこと。 本篇の主人公は塾の講師で、ゲストハウス等々を転々としながら生活しています。 こうした暮らし方なのかと新たに認識した思いですが、人間関係は普通の人とやはり変わらない、いやむしろ難しいかも。 ここはとても速い川/膨張 |