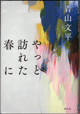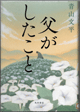| 11. | |
|
「底惚れ」 ★★★ 中央公論文芸賞・柴田錬三郎賞 |
|
|
2024年05月
|
短篇集「江戸染まぬ」の中の一篇「江戸染まぬ」の長編化。 いやあ、こういう見事な仕業をやってのけてくれるから堪らないのですよねぇ、青山文平作品は。 主人公の「俺」、宿で俺を刺して姿を消した元下女兼ご老公想い人だった芳を探し出すため、江戸は岡場処の路地裏を歩き回ります。 その渦中で出会ったのが、評判の高い路地裏番である銀次。 探し回るより「待っちゃあどうだい」(芳の出現を待つ)という言葉と共に、そのための見世買取りを銀次が仲介してくれたおかげで、主人公は芳が選んでくれるような見世作りを始めます。 <客のためではなく、女郎のためになるような見世>−その発想が面白い。 この辺りビジネス小説のような面白さも備えています。 見世が軌道に乗り始めると、屋敷で芳の朋輩、そして故郷も同じだった信が主人公を訪ねてきます。結果的に主人公は信へ、女たちの仕込みと差配を任せることになるのですが、この信の登場がストーリィにさらなる厚みを加えています。 その後も俺の商売は広がっていきますが、依然として芳は姿を現さない。さて・・・・。 いいなぁ、特に主人公「俺」の、自分の損得を全く考えず、無私といって良い姿が何とも透明感ありというか、濁りがない、というか。 また、「俺」意外に、銀次、信という登場人物の人間像が圧巻。 俺、銀次、信のそれぞれが、他人には言い難い過去を抱えているのですが、それでも今いる場所で自分を精一杯務めている。彼らの覚悟ぶりが実に鮮明で確かなものであることを感じさせられます。 異色の時代小説ですが、その面白さも異色。是非、お薦め! |