| 2004年お正月企画「温泉の科学特別コラム」 |
| 2004年お正月企画「温泉の科学特別コラム」 |
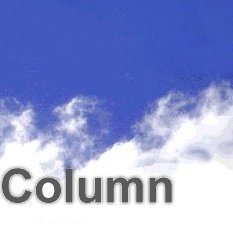 |
明治の鉱泉概念 byやませみ 鉱泉の意義およびその尋常水との区別 鉱泉冷温の区別 鉱泉分類法 附:筆者が考えたこと |
| 明治19年(1886)に当時の内務省衛生局が編纂した「日本鉱泉誌・全3巻」は、全国の鉱泉を網羅的に調査してその全貌をはじめて明らかにした記念碑的な大著です。通常の図書館ではめったに閲覧できない希少本でしたが、ありがたいことに国立国会図書館のサイト「近代デジタルライブラリー」の完成により、手軽に画像ファイルとして見ることができるようになっています。
本誌の第一巻冒頭の「通論」には、鉱泉とはいかなるものかについての当時の考え方が述べられており、これを現在の温泉の概念と比較するときに微妙な差異があることが伺えてたいへん興味深いものとなっています。本文は漢文読み下しなので多少わかりにくいですが、およその意味は理解できるかと思いますので書き写してみました。なお、カナはひらがなに換え、古い漢字はなるべく現用の字体に置換してありますが、筆者の無知による誤りがあればお許しください。 |
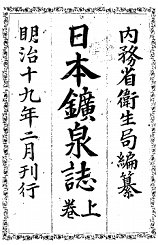
|
すでに鉱泉と尋常水との区別判然せば、更に温度の高低に従い鉱泉の冷温を区別するはまた実地要用のこととす。すなわちこれが区別を定むるには、別に一定不換の温度をもって比較の標準となすものなかるべからず。ただ人々の感触により鉱泉を冷泉、微温泉、温泉および熱泉等に区別するがごときはもとより、また学術上においてこれが限界を定むるの規準あるにあらず。 しかれども強いてこれが区別を為さんには、鉱泉所在地の大気の中等温度をもって鉱泉の温度に比較せば則その規準すこぶる穏当にて一定するを得べし。ゆえに今この比例をもって鉱泉の冷温を区別するの憑據(よりどころ)と為し、その温度該地の中等大気の温に超えざるものを冷泉と云い、そのこれに超越するものを温泉と為す(その超過多少の度に従いて更に微温泉、温泉、熱泉の別を定む)ときは、その冷温の別おのずから判然たり。しかれども熱帯地方に在りては大気温すこぶる高度なるをもって温寒両帯の地方とその比例の同一ならざるは、もとより弁を費さずを明なりとす。 |
|
輓近(近年)通常鉱泉の主成分を記載し、もってその種類の何たるを一目の下に詳にする類別法を採用せり。ゆえに、鉱泉分析は各邦皆精密なる定性および定量試験法を用いてその中に発見したる有力成分につきて分類命名す。 よって一類内の鉱泉はことごとく同一の通性を有するのほか、各泉また特別の副成分に属する特異の性能を有すべしといえども、その主成分の大別によりてはすなわち六七種もしくは九種にすぎず。これを例え、単純泉、食塩泉、苦塩ボウ硝泉、硫黄泉、炭酸泉および鉄泉の六種となし、あるいは鉄泉、硫黄泉、炭酸泉、塩類泉・・・・(中略)・・・等のごとき各国鉱泉の性状と各識者の所見とにしたがいすこぶる差異あるをもって一定の規則なしといえども、各国鉱泉種類の主成分を標準として化学試験法によりてその種類の何たるを瞭然たらしむべき名称を附するは最有益の法なりとす。 しかるに本邦の鉱泉はこれを欧米諸国に比すれば多量の遊離性鉱物酸を含有するもの極めて多し(その主成分と為りて存す)。ゆえに今欧米諸国の鉱泉類別法をもって直にこれを我邦に襲用するは、ただに穏当ならざるのみならず、かえってその実を失うに似たり。よりて衛生局試験所および医司薬場おいて試験したる成績に従い、欧米諸国の類別中に在りていまだかつて見ざるところの特異なる酸性泉の一類を設け、もって全国の鉱泉を左の五種に分類す。 (甲) 単純泉 または温和泉 (乙) 酸性泉 または酸性鉱泉 (丙) 炭酸泉 (丁) 塩類泉 (戊) 硫黄泉 |
|
本誌の冒頭では『地下より湧出する自然泉水に・・・』というのが鉱泉の大前提になっています。もちろんボーリング技術など未発達な時代ですからほとんどの湧水は自然湧出で、ごく一部で浅い掘り抜き井戸や横穴式の掘削が行われていたにすぎません。したがって、『常水より高き温度を保つ』というのは、鉱泉の定義として有効な規準になっていたでしょう。 さて現行の温泉法の定義では、「地中からゆう出する温水、鉱水、及び水蒸気その他のガス」とされており、湧出の形態にとくに限定はありませんので、自然湧出から深層ボーリング井まで同じ規準が適用されるように考えられています。そこでは湧出口での水温25℃以上は成分に関係なく「温泉」であると規定されるため、通常の地下水と成分的には何ら変わらないような深層水が、水温だけで温泉と認定される不可思議な状況になっています。本来は自然湧出の泉水について発した概念を、深層水にまで拡張して当てはめる現在の温泉概念は、じつは根本的な大間違いを犯しているといえるかもしれません。 歴史の古い鉱泉(冷鉱泉)では、現在の規定で「温泉」に該当しないものが数多くみられます。つまり、明治の分類では固形分が0.5 g/kg以上からが塩類泉に含められることになっているため、現在の1 g/kg以上という規定からは外れる冷鉱泉が出ているためです。希薄な石膏泉、緑ばん泉などがこれにあたります。また、炭酸成分の正確な定量は現在でもかなり難しいものですが、明治の定性的な分類で「アルカリ性炭酸泉」とされたものの多くは希薄な重曹泉タイプで、これも現在の規定からは外れるものが相当数あります。 これらの鉱泉は、薬効が高いとして湯治療養にずいぶんと貢献したものが少なくないですが、今は表だって「温泉」の看板を掲げられないため廃業したものが多いのは残念なことに思います。鉱泉の療養効果については未だ不明なことが多く、民間療法の一部にすぎないとして医学の研究対象から除外される形勢になっていますが、解明が充分に試みられないままに多くの鉱泉が消え去っていくことは、後世の人々にとって大きな損失となることなのかもしれません。 |