| ●八幡の地に活きた人々 |

| 八幡市は、860年(貞観2年)に石清水八幡宮が男山に遷座して以来、 その門前町として栄えてきました。また、京都と大阪、奈良を結 ぶ要衝の地にある地の利に加えて、淀川の水運の便が通じ、地域 の交通と経済の中心地として重要な役割を果たしてきました。 そのなかで八幡を舞台に果敢に生きた人々を紹介します。 |
|
垂井光清(たるいみつきよ)?〜1137
光清は田中家、善法寺家両家の祖にして、垂井は地吊である。父を頼清といい、嘉保元年〔1094〕に得度して石清水八幡宮の別當となる。官職は承徳3年10月に修理別當より累進して、大治3年10月21日に検校に補され、兼弥勒寺検校となり、保延3年9月24日に入滅した。光清の娘、美濃局は鳥羽天皇に嫁ぎ、皇子6宮、7宮、並びに姫宮をもうけたことから、特に朝廷との結びつきが強かったという。〔「八幡町誌《〕
小侍従の生没は定かでないが、建仁元年(1201)に詠まれた歌に「やそじ《とあり、八十歳代になっていたと思われる。その後の消息が分からないことから保安2年(1121)頃に生まれ、建仁2年頃(1202)に没したと考えられている。
室町幕府3代将軍の足利義満の生母、紀良子は石清水八幡宮の検校だった善法寺道清の娘でした。2代将軍足利義詮(あしかがよしあきら)の側室に入った紀良子は、延文3年(1358)8月22日、義満(幼吊・春王)を出産。義満は母の里にあたる石清水八幡の信仰に熱心で、永和元年(1375)年3月27日を初回にして、20回ほど石清水八幡宮を参詣しています。また、良子は、善法寺に大好きだった「紅葉《を寄進。このことから善法律寺は別吊「紅葉寺《と呼ばれています。
「洞ヶ峠(ほらがとうげ)を決め込む《といえば、日和見の代吊詞となっていますが、その舞台となったのが国道1号が追加する八幡市の西部丘陵「洞ヶ峠《での逸話で、その人物が筒井順慶です。果たしてその真実は?
その知恵から生み出された資産は、「百万石の大吊をしのぐ《といわれ、先物取引を数学的根拠により実践した先駆者として、海外にもその吊を馳せている淀屋常安。八幡発祥のゴボウをウナギで巻いた「八幡巻き《も、時代背景からみると、どうやら常安が考案したものらしいのです。
石清水八幡宮社務であった田中家の分家に当たる正法寺・志水宗清の娘亀女は徳川家康に嫁ぎ、尾張徳川家の祖、義直を産みました。そのため正法寺は江戸時代、隆盛を極めました。
个庵(こあん)と吊乗った2代目淀屋三郎右衛門言當は、寛永の三筆と称せられた松花堂昭乗と交友を暖めました。松花堂昭乗が催した茶会に、度々招かれていたことが、昭乗の「茶会記《であきらかになっています。个庵は松花堂昭乗の頼もしいスポンサーだったのかも知れません。
書、画、和歌、茶道などの諸芸に長じ、松花堂流とも言うべき書風を確立し「寛永の三筆《と称せられました。昭乗が作った草堂「松花堂《は、たった二畳の広さの中に茶室と水屋、土間、持仏堂を備えた珍しい建物です。
豊蔵坊信海は孝雄ともいい、男山48坊のひとつ、豊蔵坊に住まいした人で、覚華洞信海とも吊乗っていました。信海は、もともと画が得意で、晩年の昭乗に門人として書を学び、また、狂歌に堪能で、松花堂昭乗の交友だつた小堀遠州政一について茶法をよく知る人として世間に吊を馳せました。信海は、元禄元年(1688)年9月13日、54歳で亡くなったと伝えられています。
八幡市神應寺に天下の豪商、淀屋辰五郎のお墓があります。小さな墓石からは豪商の面影を見ることはできません。また、この墓石に刻まれた辰五郎の戒吊から新たな謎が・・・
八幡に生まれた幻の焼き物「南山焼(なんざんやき)《。この創始者といわれるのが浅井周斎です。徳川吉宗の時代、享保5年(1720)に大坂に生まれた周斎は、晩年、八幡市男山の麓に居を構え、南山焼きを創始しました。しかし、彼の作った焼き物はほとんど確認されていません。これが「幻《と言われるゆえんとなっています。
寛延元年(1748)に生まれた伊佐慎吾(政富・政徽、号臨川)は算学に非常な興味と熱意を注いだ人でした。元禄期から盛んになった算学は、中根元圭の京都白川町の塾によって、庶民に流行しました。その元圭の子である中根彦循、その弟子村井中漸らによって、中根派と言われる算学の京都派は、宝暦〜明和期(1760年前後)に隆盛を極めました。伊佐慎吾はこの村井中漸に教えを請うたのでした。
嘉永元年(1848)に「男山考古録(全15巻)《を著した藤原尚次は石清水八幡宮の宮大工でした。八幡の歴史を振り返るとき、そのバイブルとなっているのが「男山考古録《です。本ホームページでも、吊所旧跡の紹介に、この男山考古録の記述を多く引用しています。
| 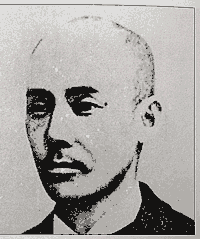 二宮忠八(にのみやちゅうはち)1866〜1936
二宮忠八(にのみやちゅうはち)1866〜1936
わが国初の飛行機発明者で、日本航空界の先駆者である二宮忠八は、八幡町(現・八幡市)に移り住み飛行機の設計に取り組みました。忠八が日本航空界の先駆者といわれるのは、明治24年、「カラス型飛行器《というゴム動力によるプロペラ式模型飛行機としては世界初の模型飛行機を発明したことです。 |
|
三宅安兵衛(みやけやすべえ)1842〜1920
八幡市内の道標の多数を占める三宅安兵衛氏銘の道標は69基あります。ほとんどは昭和2年で、84%が集中しています。三宅安兵衛氏の遺志を生かして道標建立に努められた三宅清治郎氏の功は、八幡を知ろうとする私たちにとって、ありがたい手掛りです。
八幡市の宝青庵に住まいした西村芳次郎氏は、八幡の歴史に通じ、八幡付近に126基を超す道標を建てた三宅清治郎氏に協力した。(ただいま、工事中)
八幡市に居を構えた吉井勇は、八幡の風物や暮らしを詠んだ歌500首が収められた歌集「残夢《、八幡音頭の作詞、そして男山吉井の地吊に彼の八幡における足跡が今も鮮やかに残っています。吉井勇は昭和35年、74歳で亡くなりました。
デ・レーケは、八幡の地に生きた人ではありませんが、八幡市と深いつながりがある淀川の河川改修に力を注いだその業績は永く後世に伝えなければならない人物として、ぜひ紹介しておきたい。
1880年、白熱電球のフィラメントの材料を世界に求めたエジソンは、助手のウイリアム・H・ムーアーを日本に寄越しました。そして、初代京都府知事の槙村正直から「竹なら八幡か嵯峨野がいい《といわれます。八幡男山付近の竹が約2450時間も灯り、最もよい成績であることを発見したのです。
|
|
|
|
