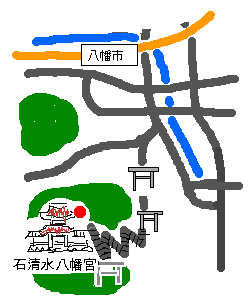 えいにんのいしどうろう
えいにんのいしどうろう

永仁の石灯籠
所在地:八幡市八幡高坊(石清水八幡宮社務所横・書院の庭内)
燈籠は、もとは中国において仏前の献灯として起こり、奈良時代に日本に伝わったものである。我が国では、仏前のみならず、神前にも建てられるようになった。燈籠の素材には、石だけではなく木や鉄のものもあり、石清水八幡宮には鉄製のものが2基、本殿右側の昇段口横に見ることができる。
さて、石清水八幡宮にはこの鉄製を含め320余基の燈籠がある。この中で、ひときわ、異彩を放っているのが「永仁の石灯籠」と呼ばれる石燈籠で、重要文化財に指定されている。今は社務所横の書院に庭に移設されているが、元は本殿東側階段下の伊勢大神宮遙拝所に立っていた二基のうち南側(向かって右)にあった。
『男山考古録』によると、鹿野能忠家伝来の古図、田中家古図にも1基のみが描かれていることから、以前は1基だけだったと記している。2基となったのは、宝暦年間(1751-1764)に津田という人がその場所にあった古灯籠と同じ大きさ、同じ形に模して作り、これを寄進したものという。さらに、『男山考古録』は、元の石灯籠は、「古物であり名作である」とその価値を早くから説いていた。
昭和になって、その価値を再び世に知らしめたのが川勝政太郎氏(文学博士・石造美術の第一人者)であった。川勝氏は昭和7年(1932)7月に研究仲間10人とともに石清水八幡宮を訪れてこの石灯籠を発見し、翌年3月に再び石清水八幡宮を訪れた。文字が小さくて読めなかった竿の部分の刻銘を拓本にとり明らかにした。その刻銘は「永仁3年(1295)乙未3月」とあった。川勝氏は、この石灯籠を鎌倉時代中期の作と確認し、これを八幡宮社務所に伝えた。このあと川勝氏は「非常に愉快になって下山した」(『石造美術と京都』昭和21年5月発刊)と、その発見に小躍りされた様子がうかがえる。以来、この永仁の石灯籠は、世に知られることになったのである。
川勝氏は、「この石灯籠だけが飛び抜けて古く、他に模造されたものが少ないことから、古くから人々はこの燈籠を尊び伝えられてきたものだろう」と推測する。
では、この永仁の石灯籠の概観について、川勝氏に伝えてもらおう。「高さは7尺(215センチ)ばかり。花崗岩製で六角型である。特に珍奇なやり方をしていないが、一番下の基礎側面の格狭間、上の穏やかな単弁は特に眼に付く。竿の中節は小さな珠を並べた連珠文で、これは鎌倉から吉野時代にかけて好んで行われたやり方である。笠の部分では、頂上の宝珠受けの蓮弁の小さな彫刻を作り出している。上に乗る宝珠そのものは古いものではないようである。全体の形を評するならば、その均合のとれた姿は洗練された鎌倉燈籠の一級品のひとつであるということができる。中台が程よく大きく、伸びやかで、従って中台から火袋・笠の示すゆったりとした感じは,荘重の内にも重苦しさがない。」
| 
 目次へ
目次へ

 目次へ
目次へ