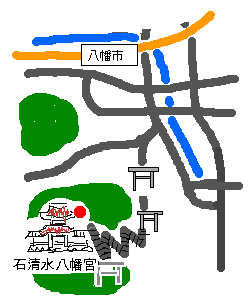 おとこやまよんじゅうはちぼう いしどうろう
おとこやまよんじゅうはちぼう いしどうろう

男山四十八坊の石灯籠
所在地:八幡市八幡高坊
明治元年(1868)の廃仏毀釈前までは、石清水八幡宮は神仏混淆色の強い神社であった。本殿では毎日読経の声が聞こえ、社僧という僧侶が社務を取り仕切ったという。
かつて男山には48もの坊があった。「坊」とは、お寺のことで、今では石清水八幡宮参道の石垣と八幡宮本殿前の参道に並ぶ石灯籠に往時を偲ぶことができる。この48坊、ある時代にすべてが存在したというわけではなく、全盛期で50近く、これが火災や住職の死亡で廃絶などによつて、増えたり減ったりしていたという。
江戸時代中期の古図「八幡山上山下惣絵図」には43の坊を見ることができるように、だいたい40前後の坊が常に男山にあったようだ。その坊も明治の廃仏毀釈直前には23の坊になっていた。石灯籠の竿の部分には「宿坊○○坊」と刻まれている。この「宿坊」というのは、遠くから石清水八幡宮を参拝に訪れた旅人を泊める宿泊施設を持った坊であった。この宿泊費を坊の維持費に充てていたという。
| 
 目次へ
目次へ

 目次へ
目次へ