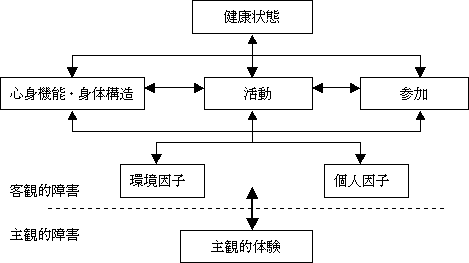第6章 対象論
はじめに
これまで施設の役割等について述べてきた。この章では、そもそも福祉の対象とは何かについて考察をする。施設で働いていると、利用者が施設にいるのかが自明のように映る。虐待されたから、家族でのケアが困難になったからなどその理由は多様にあるものの、なぜそれが施設利用に結びついたのか。普段はそうした問いなど考えずに働いているが、ふと立ち止まったときに頭によぎる問いである。
しかし、その問いを考えることは我々援助者にとっては重い意味を持つ。なぜなら、援助者は、人間のどのような部分を福祉の視点とし、対象化し、「利用者」として扱っているかに突き当たるからである1。それは、その時代の福祉従事者が利用者をどのような文脈で観て、実際に振る舞うのかという根本的な規定がなされている。
本章では、学説的に対象を巡る幾つかの問題について考察し、人間をいかに社会福祉の対象へと捉えていくかについて論じていく。その後、対象化された人々の社会的文脈について特に、障害者福祉分野を中心に考察を加えていく。
第1節 社会福祉の対象とは何か。
はじめに
社会福祉の対象について考える場合、範囲規定がまず重要である。どのような人を社会福祉の範囲(対象化)とするのか。そして、どのようにその人達に作用するかである。最近では、社会福祉の対象が拡散と普遍化したと言われている。本節では、この普遍化について批判を加え、本来の社会福祉の対象について考察する。その上で、いかに対象に働きかけていくのかそのシステムについて論じていく。
第1項 対象の普遍性と呼称の変化
A.普遍性について
一般に福祉の対象は普遍化したと言われる。なぜなら、社会福祉政策(国家)は歴史的に多様な社会問題や生活不安に対応してきた。そして、社会福祉政策はこれからもあらゆる社会問題に対応していく。その結果、社会福祉サービスは全ての社会問題や生活不安をカバーする。よっていまや社会福祉サービスは「だれでも、いつでも、どこでも」を受けることができる(高沢〔2001,PP.7-8〕)。このように、国民全体を対象としている社会福祉は普遍性を持った一政策と言われるゆえんである。
また、普遍性は、社会において排除されている人たちの権利性を侵すスティグマを払拭するための「目標」や「手段」を表している(高沢〔2001〕)。社会福祉は国民全体を包括する政策であるから、今社会的排除によって適用されている福祉サービス受給者を差別したりしてはいけないというわけである。
しかし、本来、社会福祉は「資本主義という社会制度の中にあって、その社会の矛盾が生み出す社会問題、特に生活問題、さらに加えて精神不安、そこから生まれるニーズの解決や克服に、相対的独自的な役割を持ってあたる、社会的歴史的実践」(吉田〔1989,P.5〕)である。相対的独自性とは、社会政策や経済に影響を受けながらも社会福祉には固有の価値がある。歴史的実践とは、人権保障や社会連帯など社会改良的な取り組みから社会福祉は形成されてきたことを指す2。言い換えると、資本主義社会には「冷徹な格差が、つまり、身体的、精神的、経済的、社会的な相違が存在する」(田中〔2004,P.31〕)ことを前提にする。そして、社会福祉はそこ(格差)から出発し、運動体として、個人の生活改善と社会的排除という差別と闘ってきた。
要するに、いくら社会福祉政策の普遍性(国民全体が対象である)を強調しても、社会的な冷徹な格差と社会的排除がある以上、社会福祉が適用するべき固有の範囲が常に存在する。
B.呼称の変化について
時代と共に、福祉対象者の名称・呼称も変化してきた。収容者、入所者から利用者、消費者、顧客へ。関わり方も処遇、援護育成から援助、支援へなどである3。そして、名称の変更は普遍性が目標とする利用者のスティグマの払拭と密接に結びついている。
スティグマの払拭としての用語変更はそれはそれでよい面もある。しかし、普遍性同様、消費者、サービスといった柔らかい言葉は、対象者が担っている個別の深刻で多様・多層な生活問題−社会性から目をそらしてしまう危険性がある。もし仮に、対象者の社会的背景などをまったく考慮せず、対象者の消費能力(金銭の支払い能力)や対象者の要求だけに限定して支援サービスを行うのであれば、社会福祉政策として何が重要か曖昧になる。大枠が曖昧であれば、具体的サービスを供給する際も、どうすれば対象者の生活問題を正しく解決していけるかの認識が曖昧になる(竹原〔2002〕)。あるいは、サービスという一面的な対人関係に置き換えられてしまう。
最終的には、社会福祉が「個別性の重視と対象の担い手(つまり利用者)との具体的な関係性においてのみ成立する」(田中〔2004,P.31〕)点を考えると、一援助者は、この用語や名称の変更について今一度、吟味することは重要である。用語変更に含まれる肯定的側面(人権保障の進展など)や否定的な側面(ソフトな言い回しによる社会的排除の隠蔽など)に目配せし、それでも目の前にいる利用者の社会的文脈について考え抜く姿勢が必要である。
第2項 対象の範囲(カテゴリー)について
では、本来的に社会福祉の対象範囲とはどのようなものなのか。端的に、社会政策的にはつねに社会福祉の範囲は救貧的なものであった(高沢〔2001〕:圷〔2002〕)。そして、金子(2002,P.34)が述べるように、
現代における社会福祉の対象が「貧困者」ではなく、「高齢者」「障害者」「母子」といったカテゴライズな概念を持って幅広く捉えられるように、対象理解の枠組みは社会構造や規範に応じて変化するものであり、また変化すべきものである
と考えられている。
普遍主義における社会福祉は国民全般のものであるとするなら、それは以前に見られた福祉対象の「境界が喪失」がしたと表現できる。そして、社会福祉の対象カテゴリーが、歴史の発展と共に積み上げられてきた結果、対象の生活課題を「拡散」させてきた面が問題になっている(高沢〔2001,P.8〕)。社会改良運動はさまざまな福祉施策を実現させた。しかし、それらの諸政策が整理されないままに、積み上げられた。その結果、生活問題へのアプローチの違いによって、福祉対象者が細分化4され、時にはその背後にある社会問題が見落とされる。岩田(2001,P.29)は、福祉サービスが人に働きかける際、個人の持つ社会問題が細分化されていく過程を述べる。
例えば、社会問題として提起された介護問題は、介護保険制度の対象としては、高齢者の心身の状態のみを基軸とした「要介護度」のランク付けによるカテゴリー区分で把握される。ここでは、このランクから漏れてしまう問題や、障害者の介護問題一般は排除される。
本来「介護の社会問題」は総合的に考えるべき問題である(ジェンターなど)が、その問題は一旦棚上げされ、制度に区分され、介護サービスとして供給される。例えば、知的障害の介護問題は、在宅/施設、通所/入所にカテゴリー化され、在宅でもショートスティ/ホームヘルプ/ディサービスなど細分化され、「介護サービス」として提供される。そして、個別の家族の介護問題は福祉ニーズとして把握され、計画的に測定され、サービスが提供される。結果として、家族の介護問題は、サービスが提供された形で制度上解決されたことにされる。つまり、介護問題はニーズに変換されて薄められている。
そもそも福祉ニーズの概念は、社会問題や生活問題の多様性やその原因を巡る議論などの煩雑性を排除して「政策科学的手法」としてなじみやすいもとさされる(岩田〔2001,P.30〕)。
その理由として、
- ニーズは人間存在に共通する普遍的な「必要に関わる概念」であり、その充足の権利や社会の責務が正当化しやすい。
- さらに、社会問題がある社会集団に関わって想起されるのに対し、ニーズは本質的に個人によって充足されるものである。
- したがって、集団的に共有された社会問題の提起は、ニーズへの転換によって個人レベルに分解することが可能になる(岩田〔2001,PP.30-31〕)。
しかし、何が人間にとって基本的なニーズなのか確定はできないはずである。なぜなら、個人の趣向や価値観、時代的な要請、地域条件など千差万別だからである。よって、福祉政策がニーズの充足のために社会に何を必要とするかという問題は、政策側の価値判断である。それは、人間の必要なニーズそのものではなく、まったく別なものである。
この政策ニーズは、制度上(あるいは政策的)に厳密に測定され(アセスメント、査定など)、需要量と供給量のバランスの上でサービスは設定される。その上で、個別にサービスが提供されるには、前提として利用資格要件による優先順位が付与される。そして、福祉サービスが提供される要件を満たしているかどうかの審査は、対象者が社会の構成員としての資格があるかどうか問うものである。ここに、社会福祉制度がターゲットとする規範や価値基準が存在する(金子〔2002〕)。そして、その背 後には要件を満たせないという理由で排除されている人々が存在している5。つまり、政策的な社会福祉は、生活者が抱える多様な社会問題はニーズの測定によって希薄化され、一面的な充足としてサービスが供給されているにすぎない。
このように施設職員の目の前にいる利用者は、様々なカテゴリーによって選別されていることが分かる。そこには厳密な選別が存在し、さらに限定された形で関わるという制約がつきまとう。仮に、個別性を尊重し、個の状態に従って様々なサービスを組み合わせ、きめ細かに対応していても、そこにはサービスのパッケージが常に用意されている。
施設生活は、排泄、食事、入浴、レクレーションなど利用者の一日の生活を演出している。しかし、その利用者には別の生き方(就労、恋愛、趣味の時間、施設のメニューにない楽しみ、一人での生活)など、多様な生活様式があったはずだし、可能性としては常にあるはずである。そうした意味で、施設生活は利用者の何かを優先順位として取り上げ、限定的に関わっているにすぎない。
次に、こうしたカテゴリー(社会福祉の対象としての範囲)は、結果として、対象者を社会は排除していることを述べていく。
第2節 社会の規範や価値基準について
社会政策としての社会福祉は、ターゲットとなる対象者に社会的に期待する役割や規範へ従わせる面がある。社会福祉もまた社会的な規範や役割が課されている以上、それは仕方のないことかも知れない。しかし、それは対象者の都合ではない。生活問題や社会問題が社会のひずみから生まれているならば、社会福祉が社会の規範や価値基準に従うように対象者へ働きかけるのは本末転倒ではないか。
しかし、援助者は「惜しいかな、いつの間にか支配者層に迎合する専門家本位の論理に甘んじてきた」(松倉〔2001,P.2〕)。例えば、生活問題、社会問題にしろ、援助者は「問題の原因を突き止め、それを取り払うことで社会生活への適応が図られる=問題の解決であると言う定式」(松倉〔2001,P.4〕)が前提となる。とするならば、対象者ははじめから社会の不適応者として位置づけられているのではないか。
なぜ福祉の対象者は不適応者に位置づけられるのか。それは、いくら民主主義や多様性が尊重される社会であっても、「〜でなければならない」「〜であるべきだ」という社会的な規範や形式がある。この「〜であるべきだ」は社会一般に語られ信じられている「見えざる物語」や「大いなる物語」6(松倉〔2001〕)という。そして、この物語は、社会一般の支配的な言説である。例えば、昨今では、競争、市場主義、能力主義などが一般的な言説であり、物語である。そして、この物語に沿うように個人は努力という形で従属される。その上、さらに社会の秩序を重んじる善良な市民としての理性・知性・健康を身につけることが求められる。
その一方で、病気、犯罪、障害、死といった理性で制御できない問題、あるいは、障害者、貧困者は理性を持たない具現者として周辺に追いやり、排除することで社会は成立している(松倉〔2001〕)。逆に言うと、理性や健康を身につけることで、社会秩序と規範が守られる。
しかも時代によって価値観や規範は変遷する。そして、「常にマイノリティの排除や抑圧そのものが福祉国家によって再生産」(金子〔2002,P.38〕)されている。
例えば、これまで男性が一人で稼いで家族を支える性別役割分業モデル(近代家族)が主流であった。しかし、現在は共稼ぎのスタイルが主流(脱近代家族)である。このことは、様々な政策誘導のもと、稼ぎ手が一人に与えられた特権(例えば、所得税控除、扶養手当・控除など)が剥奪され、かわりに男女共同参画と少子化対策が結びついた形で共稼ぎが優遇される。このことは、近代家族の形態は脱近代家族の形態に比べて貧困に陥りやすいことになる。つまり、「性別役割分業を前提にした「近代家族」はもはや社会的に不利な立場に追いやられる傾向が強い」(金子〔2002,P.36〕)といえる。それは善良な市民ですら、物語が意図する価値観や規範から容易に、マイノリティとして作り出される可能性があることを示唆している。
さらに昨今では、アンダークラスという新たな貧困問題がある(金子〔2002〕,渋谷〔2003〕)。ニートやフリーター、あるいは、ワーキングプア、負け組のレッテル、下流社会の形成などむしろ今、貧困は拡大していることを意識する必要がある。
しかし、こうした新たに作り出される社会的排除は状況によって変わりうる。しかし、障害者、貧困者、寝たきりになった高齢者など従来の福祉の対象者は、救済されるべき存在として、「対象者を理解し働きかける人々」7によって歴史的に長く支配されてきた(圷〔2002〕)。よって障害者などには、不利になるとか有利になるというスタイルは存在せず絶えず固定化されてきた。あるいは、対象者自身も、対象であることを甘んじ(受動化し)、社会政策的に規格化され、分かりやすく統一化・一般化されてきた(圷〔2002,130〕)。そして、対象者は改善されるものとして批評され、測定されてきた。
いずれにしろ大いなる物語は社会的排除や競争原理が生活に大きな影響を与えている。しかし、物語の言説はそれだけではない。社会的排除に対抗する形で様々なマイノリティ運動が、社会の位置を巡って「適切なバランス」(堀田〔2005.P.71〕)が模索され、そのパワーバランスの上で言説を形成している。その結果、対象者は生活の保障や生存権を獲得し、これらの権利を押し広げてきたし、多様な視点も生み出している。
さらに言うなら、必ずしも競争原理が悪いと決めつけることはできない。なぜなら、それぞれが自己の能力や目標に従って努力する中で自己実現を図っていくことは悪いことではない。問題は、社会的排除されている人々へのまなざしが、支配−被支配の関係だけで捉える固定的な見方である。
第3節 学ぶべきこと
カテゴリーの拡大(その行き着く、普遍性)によって様々な問題が生じることについて述べてきた。しかし、それでも歴史的に社会福祉は発展をしてきた。例えば、認知症の高齢者や障害者は、福祉サービスが十分でなかった時代は、座敷牢に隔離されてきた人が居た。あるいは、いまよりも劣等な扱いを受けてきた。そこに人権問題や社会要求運動(人間らしい暮らしへの要求など)が結びつき、政策的にニーズとして位置づけられ、社会福祉サービスとして提供された結果、少なくても座敷牢よりはましな生活が提供された人も多いはずである。そこには、家族の介護問題や隔離されてきた人々の社会問題が幾分軽減・解消された一面がある。
施設においても、様々なサービスや社会資源の拡大によって、カテゴリーによっては、昔よりは生活に幅が出てきた人もいるだろう。例えば、軽度知的障害者の就労機会や、少人数で自立生活ができる機能を持った施設・グループホームがサービスとして拡大している。
しかし、カテゴリーは再生産され、増殖すれば広く国民の生活が保障されるという安直な結論に達してはいけない。確かに、カテゴリーが拡がれば、それだけ、メニューの多様化を生みだし、より個別に働きかけ、その人の生活の質を考慮し、生活の幅が拡がるだろう。しかし、カテゴリーの拡大は、選別と不平等を常に孕んでいることも考慮しないといけない。重度/軽度、要介護度5/要支援、できる/できないの選別が働いている。できない人たちをどうするのかという問いかけは援助者である施設職員の課された問題である。
次に、規範や価値基準の側面…社会的排除ではなく、対抗的な視点としての医学的な進歩、社会運動面について、特に障害者福祉を中心に考察する
第4節 障害者運動について
はじめに
第2節では、一般社会には社会的な排除だけではなく、対抗する形でマイノリティ運動や知識・理論・批判があり、それが「大いなる物語」の中に含まれていると述べた。しばしば、現場にいると今の福祉の到達点が、簡単に、あたかも当然のように言われる。例えば、生活の質をあげよう。利用者の立場に立って、利用者の権利を擁護するとかである。その背景には、社会的排除や制限からの解放を求め、積み上げられた歴史がある。
資本社会や市場主義社会に対抗する言説について、これまでの論述を踏まえながらそのエッセンスについて考察をする。
第1項 運動のかたち
運動と聞くと、福祉対象者〜当事者や当事者の親が連帯・行動し、行政へ陳情する姿を想起しがちである。しかし、運動とは当事者だけではなく、学者、施設従事者、メディア、政策的に批判的な者のすべてを含む。
例えば、学者は論文を通じて政策を批判し、望ましい社会を提案する。そして、セミナーや講演などで広く一般市民に訴え、コンセンサス(国民が共通する意識)の向上を図る。さらに論文作成(=理論形成)にあたって、学者は社会情勢や国際的な人権運動への目配せ、福祉対象者の環境(社会)改善へのまなざしなど常に現場と密接に繋がったものとなっている事が多い。
例えば、ノーマライゼーションやICFなどは、多様な理論の結晶であり、これらの思想や概念は広く社会に働きかけている。いずれにしろ、マイノリティの一般社会への異議申し立ては様々な形で投げかけられ、コンセンサスを形成している。
しかし、障害者は高齢者や児童とは違って8、コンセンサスの形成に苦闘している。なぜなら貧困や児童、高齢者は自分(健常者)の身にあり得る問題として認知されやすい。しかし、健常者は障害者になりうるリスクは薄いと考えがちである。また、知的障害、精神障害、先天性の心身障害などは自分には関係ない。よって、障害は自分にはありえないし、将来に渡ってあってはならないと思うのが大半である。そのため、マイノリティの運動〜福祉の運動として、障害者運動は象徴的である。
ところで、障害者運動の歴史は主に身体障害者が起こした自立生活運動が有名である9。本論では、そのエッセンスの概略を述べ、そのことによって、何をマイノリティは社会へ異議申し立てをしてきたのかを明らかにする。
第2項 障害者運動の内容について
障害者運動は、具体的要求を通じて、障害者のニーズを顕在化させ行政のサービスを改善させる。例えば、町へのアクセスを良くした。当事者が政策提言能力を持つようになった。あるいは、専門家への批判、自己決定や自己選択の尊重が社会運動(自立生活運動)で達成されてきたとされる(中西〔2003,P.44-60〕)
これらの要求運動や主張の根本は端的に言って、「支配的文化によって規定され、周辺化されてきた〈障害〉という〈異〉の再解釈であり、…中略…自らのアイデンティティを管理し、慈善や治療の対象者から抑圧的で差別的な社会に対する抵抗者、革命家へと自らを転換させる契機を獲得」(田中〔2005,P.96〕)するためにある。
やや引用が長くなるが、臼井(2001,PP.92-93)は、
我々は、常々、健常者として生活をしており、そこには健常者としての文化が、意識されているかどうかとは別に、確かに存在している。これに対して、障害のあるものが障害者の文化を提起することによって、健常者の文化は「障害のある、無し」という座標軸に基づき相対化されるものであり、障害者にとっては、このような積極的な価値の取り戻しを通して自らのアイデンティティの確立が可能となる。
障害者文化の成立基盤をどこに置くかということは、健常者が決めることではなく、障害のあるものが、それぞれの集団の中で何を文化とするのか、障害のある集団が他の集団に対しその文化を提示するたぐいのものである。
と述べ、障害者文化の提起は、健常者側の支配的な言説や常識を相対化させる契機を与えることを明らかにする。さらに、臼井(2001)は障害者の集団という中にも多様な個別性があり、障害者として単一に捉えてはいけないこと10。また、障害者文化として閉鎖的になるのではなく、「障害者のあるものが健常者に対しその際の承認を求めるために活動すること」(臼井〔2001,P.97〕)を指摘する11。
最近の障害者運動のキーワードでは、自己選択や自己決定、あるいは反専門家、主体、相互依存、消費者などが挙げられる(中西〔2003〕;臼井〔2001〕;金子〔2002〕)。これらを簡単に述べると、
- 障害者は専門家によって客観的に捉えられるものではなく、自身が主体性を持っている。
- 自分自身で何をするのかを選択し、決定することができる。
- 福祉サービス「対象者」と位置づけるのではなく、一般と同じようにサービスを「消費する者」への位置づけを求める。
- 人は根源的に相互依存しており、障害者だけが依存しているわけでもなく、健常者が完全に自立しているとは言えないことを訴える。
次項では、こうした言説がどのようなプロセスで具体的要求へ結びついていくのかを述べる。
第3項 障害者運動の政治性
結論から言えば、障害者運動が求める偏見や差別の解放要求、アイデンティティは簡単に達成されない。そのため、障害者運動は、健常者文化、時には保守主義と妥協や融和などが戦略的に行われ、障害者文化の浸透を図っていく。
例えば、障害者運動は反専門職主義、反管理、反支配を求める意味で「消費者」の重要性を唱える。それに対し、政府は公共部門の支出増大の歯止めをかけたい(専門性の否定−安上がりな労働への転換)の意味(新自由主義−保守主義)で障害者を消費者として位置づけることを承認する。そこには本質的な相違があるものの、障害者運動側は、消費者主義は既に得られた権利として戦略的に有効活用しつつ、より包括的な主権性を主張しうる「市民」としてのカテゴリーへと位置づけ直そうとする(田中〔2005,P.103〕)。
その一方で、「消費者主義の導入によって解放された自分たちを待っているのは、自分たちの〈異質性〉をよりソフトに処理する別のシステムではないか」(田中〔2005,102〕)という危険性が生じる。なぜなら、抑圧的な福祉サービスのシステムから解放されて、障害者が消費者として社会に組み込まれることで、健常者社会の変革(異質性の主張)することが意味をなさなくなる危機を孕むからである。
この一例からも分かるように、障害者運動は常に現実的に勝利を求める政治的なものである。そして、その一方で、差異の承認など障害者としての価値の形成を求める文化的な側面を持つ(田中〔2005,P.107〕)。つまり、消費者主義の獲得(政治的側面)とそれによるソフトな管理への危機(文化的側面)の葛藤が存在する。しかし、こうした葛藤こそが運動の価値形成を創造している12。なぜなら障害者運動において、まず現に生きている障害者の欠乏状態(パン一個の獲得)からの脱却という現実的問題がある。そのため、文化(理想)は現実に引っ張られ妥協を余儀なくされる(政治的解決)。しかし、理想・価値形成への指向性がないことにはただ権力(健常者文化)に迎合し、下位なものと見なされる。かといって、理想が崇高なゆえに、現実から遊離しては問題の解決にならない。結局、政治的なものと文化的なものは障害者運動の両輪であり、どちらも欠けてはならないのである。
いずれにしろ、運動とは単にイデオロギーを振りかざし、よりよい社会を唱え、要求することではない。障害者運動は、権力=健常者文化に抵抗しながらも、自らの文化や価値を浸透させようとする政治的なものである。そして、それ(運動)はいたるところで行われている。
例えば親が障害を持つ自分の子供のことを人に語るとき。施設従事者が一般の人に利用者のことを語るとき。無意識にも、これまで障害者が獲得してきた政治的な言説(生活の質、主体性など)と障害者の価値を含めて人に伝えている。そして、自分の限界とこれからの自分の展望を語るとき、そこには価値(文化)的な側面が影響している。ささやかではあるが、人に伝えることもまた運動の結果獲得した言説の影響と一般社会の接合があるといえる。
次に、障害者運動だけではなく、それに関わる形での生存権・発達権保障のための理論を一つ取り上げる。
第5節 医学の進歩・ICFについて
はじめに
第4節では、障害者の生存権保障を巡る様々な対抗的な言説が紡がれていることを述べてきた。障害者運動に密接に関係する様々な理論がある(インクルージョン、エンパワメントなど)が、本論ではICFの概念を紹介し、それがどのような意味で障害者の生存権保障や発達保障に寄与しているのかを述べる。
第1項 ICFの概念について
障害者と関わる仕事をしている人やその家族は、「障害とは何か」という問いに時々直面する。その答えの一つとして法的定義がある。もうひとつは本人にとっての、また社会にとって障害の「意味」への問いを含む(佐藤〔2002〕)。
ICF(国際生活機能分類)は、法的定義や「意味」の土台となる「障害をどう認識するか」に大きな影響を与えている概念である。さらにICFは、定義や意味だけではなく、さらに政策や個別支援計画の内容に関わる概念である(佐藤〔2002〕)。
ICFの概念の説明に入る前に、従来我々は視覚障害者に対して「めくら」、精神障害者を「キチガイ」としてその人の他の能力を考慮せず、障害者として渾然一体に見ることについて述べる。
例えば、Kさんは精神障害者として医療ケアを受け、福祉サービスを利用している。周りはKさんが精神障害者だと分かっている。そしてKさんは周りの人に時々町で唐突に話しかける時がある。そして、話しかけられた方は常にビックリし、できるだけ関わらないように振る舞う。しかし、Kさんが人に話しかけている時、常に精神症状を呈しているかどうかは分からないし、そうではないことが多い。しかし、周りは「Kさんの話しかけ」は、キチガイの行動として処理する。場合によっては、警察を呼ばれたりする。(鶴田〔2002〕)。
障害がその人の全てとして社会が渾然一体に見る理由は、障害が資本社会からの逸脱〜非理性と位置づけられ〜、秩序を乱すものとして権力に管理されているためである。また、医療が常に障害者(=患者)として役割づけ、治療のしようがない人であっても「治療を要する人」として社会的に包括し管理しているからである13。あるいは近代医学導入以前から生活の中から派生してきた観念である(上田(2002))。
渾然一体に見る観念に対抗するには、障害をひとかたまりのもとして見ず、いくつかの質的に異なるものが関係しあっていることを明らかにする必要がある。障害といってもその中には多様な要素があり、個体を構成している。それは時には社会の整備や制度が障害を生み出している場合がある。また、病気と障害は区別する必要ある。そのため、障害に対し、ある一定の共通言語(共通の概念枠組みと用語)を設定する必要がある(佐藤〔2002〕)。
このような共通言語〜モデル・概念としてWHO(世界保健機構)が1980年にICDIDHを設定し、2001年にICDIDHが改訂され、ICFとして提起された14。そのモデルに、上田の提唱する「主観的体験」としての障害を組み合わせたものを下記に図表化する。
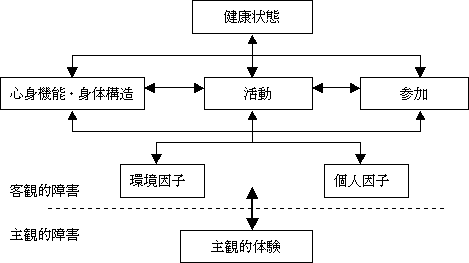
図2-1 ICFの考えを発展させた生活機能と障害構造 出所(上田(2002,P.101)
上田(2002)は障害をトータルに考えた場合、障害がある人の主観的な心情が大きな影響をその人に与えているという点をICFの図に付け加えている。よって、ICFの概念は客観的な障害の部分からなる。ICFの特徴は、それぞれの因子(心身機能・活動・参加など)が相互に結びつき、障害を構成しているととらえる点にある。言い換えると障害とは、単に心身機能・身体構造の欠損だけではなく、日常生活を支える動作(活動)やレクレーションや市民参加などの社会性(参加)が個人的な状況や環境によって著しく制限・制約されている。ICFはその関係15を指し示している。
さらに、ICFは、それぞれの因子に第1レベルから第4レベルまで細かくレベル毎にカテゴライズし、「名前、定義、含まれるもの、除かれるものが述べられ、ある現象がどのカテゴリーに属するのか分類しやすくなっている」(佐藤〔2002,P.10〕)。そして、各レベルを評価し、その人の持っている能力を明らかにし、さらに社会がどの程度障害に取り組んでいるのかを明らかにする。このようにICFは、これまで医療偏重16の障害者福祉施策を、生物・心理・社会があらゆる分野で取り組むべき事として提示している17。
次に障害構造について、ICFの前身である、ICDIHDは疾病(健康)→機能障害→能力障害(活動制限)→社会的不利(参加制約)と、疾患が全ての障害に影響を及ぼしていることを示していた。それは、段階的に治療(疾病→機能→能力)することで障害が良くなると考えられていた。
しかし、ICFは、「参加」(社会参加、コミュニティなどQOL)の改善が「活動」(移動や日常生活動作などADL,ASL,ST)を向上させることもある。例え、「心身機能」(手足の可動域、精神機能など)が改善されなくても、残存する能力を使って「活動」が改善されると生活の質が向上することがある。もちろん、活動→参加、機能→活動の方向で改善されることもある。
つまり、ICDIHDは一方向に障害が形成されていくのに比べ、ICFは障害の諸要素は双方向に影響しあっていることを示している。さらに、主観的な気持ちが家族の状況が良くなるとか社会・経済的に見通しがつくなど、いくらか精神的な余裕が出るようになると、障害に対してポジティブな気持ちになることがある(上田〔2002〕)。
先の例でいう精神障害者のKさんをICFに基づいて解釈すると、周りの偏見やキチガイとレッテルを貼る(コミュニティの成員の態度:環境の阻害因子、コミュニケーションライフ:参加制約の第2分類)、唐突に話しかける行為(対人関係における行動の制御:活動制限の第2分類)などがある。さらにこれらの諸要素は、第3〜第4分類で詳細に区別され、別の障害の要素も加味され、その人の何が障害なのか明らかになる。結果、Kさんには、いろいろな次元での悪循環があることが明らかにされる。さらに細かい分析は具体的な解決の見通しを容易にする。そして障害の一つの因子が改善されるのであれば、悪循環が断ち切る大きな可能性を見いだせる。
いずれにしろICFは、障害は多様な要素で構成されていることを明らかにした。そして、障害は個人の問題だけではないことを明確にした。その上で、障害の改善の見通しを持てるようにした。さらに、ICFは、障害者運動に「参加」の制約の改善要求だけでなく、障害には「活動」や「機能」の視点があることを提示している(上田b〔2001〕)。
次に、ICFとの関連で、医学の役割について述べる。
第2項 医学の進歩と用語の変更について
医学の進歩は、疾病を巡るさまざまな偏見を是正してきた。例えば、自閉症は早い時期の養育環境に問題があり、そのような状態(自閉)に子どもを追い込む問題が家庭に必ずあるはずだと思われた。結果、『「自閉」は心因に対する防衛であり、その原因は家族関係、とりわけ母親のパーソナリティに求められるはずだとする神話が生まれた』(太田ら〔1992,P.2〕)しかし、現在、自閉症は、部位の特定はできないが脳機能のシステム障害であることが定説になっている。(太田ら〔1992,PP.27-28〕)。また、それに併せて、認知療法や自閉症特有のプログラムなどが開発され18、治療や訓練が施されるようになった。もはや、家族は自閉症を生み出す治療対象ではなく、親は、自閉症に対する共同治療者の役割として位置づけられている(佐々木〔1994,P.18〕)。
この他、精神障害者の治療の歴史(蜂矢ら〔2000〕)、心身障害の疾病予防(上田〔2002〕)の進歩など医療が果たしてきた業績は枚挙に暇はない。いずれにしろ、医療は障害者に対し、より適切な治療や原因追及はさらに行われていくだろう。
ところで、そもそもICFは、その前身であるICDIHDからして、国際疾病分類(ICD)から派生した。それまでICDだけで、人々の病気や死因の状況を分析し、医療の効果を計測してきた。しかし、疾病分類だけでは、多様に生じる疾病の後遺症や変調(=疾病の諸帰結)に対応できなくなっていた。そこで、直すべき疾病と改善すべき障害を切り離すことで、より具体的にケアや治療を行うためにICDIDHがモデルとして開発された(上田〔2002〕)。
こうしたモデルは、特にリハビリテーション医学の分野で特に発展し、多くの治療・訓練・療法を生みだしてきた。さらに、ICFは障害構造を明らかにしただけではなく、医学モデルから生活モデルへ医療の持つ役割を拡大していった。そして、医療も病院にきた患者の治療や訓練だけではなく、より包括的に患者と関わること、人権の配慮した取り組みが求められることとなる(上田b〔2002〕)19。このように医療は、単に科学的な原因追及だけではなく、社会的な情勢、国際的な人権や科学水準の進歩、ICFなどの諸理論の影響を受け、前進をしている。
さらに、医療の発展は、それまでひとくくりにされていた障害や症状を微細にわたって明らかにしてきた。例えば、自閉症は古典的に、常に知的障害を伴うものとされてきた。しかし、現在では高次機能(知能は高いまま)の自閉症の存在することが分かる。あるいは、古典的に自閉症と一つに括られてきた、注意欠陥障害、学習障害、アスペルガーなどがそれぞれ特有のものとして細分化され、分類されるようになる(太田ら〔1992,P.334-351〕)。
また、医療の発展はより適切な用語を命名しようと模索する。例えば、ICD-10で自閉症は広汎性発達障害の下位分類である。広汎性発達障害は、それまで「幼年痴呆、共生幼児精神病、自閉的精神病質、非定型児など、小児精神病あるいは小児分裂病とされた状態を、ほとんど全て含む」(太田ら〔1992,P.335〕)と言われていた。つまり、発達障害は、それまで子どもの「精神病」とされていた。しかし、現在、広汎性発達障害はなんらかの脳のシステムに障害があり、他とコミュニケーションが取るのが難しい「状態」として位置づけられている。
これらの用語の変更は、例えば精神分裂病から統合失調症へ。精神薄弱から知的障害へなど多様に存在する。また、用語の変更は、障害に対する不快感を与えるなど好ましからざる語感や印象の改善という面がある。
その一方で、いくら名称を変更しても定義や用語が持つスティグマやラベリングから解放されないという指摘もある20。例えば、知的障害の場合、周りとのコミュニケーションの齟齬によって引き起こされるパニックや暴力行為を「問題行動」としてとらえられることがある。そして、この問題行動は、社会が容認できる範囲での「適応行動」を目指して治療や訓練あるいは、指導が行われる(中村〔2002〕)。それはともすれば、異常と正常の間で把握され、結局、障害=異常という点が強調されやすい危険性をはらんでいる21。
とはいえ、用語の変更、障害の細分化、障害定義の刷新は医学の進歩と共に改善されてきた。また、医学の進歩は法律の障害定義をより具体化させ、新たな法律を生み出す契機をもたらす(例:発達障害者支援法など)。それまで障害がありながらも法律的な根拠がなく、見向きもされなかった人達が、医学の進歩によって障害が発見され、法が整備され、そのことで社会的に認知され、具体的なケアが受けることが容易になる。そういった意味でも、医療の果たしている役割は大きい。
第6節 考察
これまで一般に支配的な言説〜資本主義・市場主義社会に対抗する形での言説について述べてきた。しかし、ICFは実社会では実効性があるのか。あるいは障害者運動をいくら活発に行っても、マイノリティで有り続けることには変わりはないのではないか。障害者の人権保障はヒューマニズムとしては理解できるが、差別や排除は解決されないと考えがちになる。そして、結局社会福祉は支配的な言説(市場至上主義)に絡め取られていると結論づけがちである。
しかし、世界に目を向けると、国連が人権保障の発展と深化を求めて、「障害のある人の権利に関する国際条約」(以下、権利条約)が制定されようとしている。国連は戦勝国中心であるという批判もあるが、国連の人権保障の歴史の根底に「二度の対戦の悲惨な経験に基づく人類の痛烈な反省、すなわち人間尊厳と平和をシステムとしての人権保障によって確立していこうとする意思」(井上〔2006,P.3〕)がある。そして、権利条約は単に超法規的な物である以上に、人権保障の具体化、深化、豊富化、実効化の出発点となっている。そして、つぶさに権利条約を読むと、ICFの概念はもちろんのこと、これまで培ってきた人権保障、科学的知見、医療の業績を集積し、発展させた物になっている22。
様々な国際的な権利条約や規約が国内法規や社会に大きな影響を与えていることを考えるならば、一般的な言説は単に資本主義や市場主義だけではないと気付く。障害者運動にしろ、ICFにしろ、権利条約を大きな対抗言説の武器とすると同時に、現在進行形の人権保障運動は、次なる権利条約の発展的・創造的な側面を生み出している。
かくして、ある特定の人々を排除し、差別し、人権侵害をしている社会への改善要求は、そこにいる一人の対象者から始まっている。確かに、市場主義や競争の論理は強力である。しかし、対象者の現状を良くしていこうとする(人権保障の)行為・思索は、政策的な普遍主義を超えてグローバル・スタンダードである(井上〔2006〕)。
第7節 まとめ
しばしば、我々は市場主義社会(競争原理)が全てで、障害者など福祉対象者への差別は仕方のないこと−解消されないと思っている。あるいは、対照的に人権保障や生活保障は当たり前のことと思うことがある。これまで論じてきた対象論の中にも、この社会政策の視点から差別や偏見をいかに乗り越えるかと論考するもの。一方では、社会運動や理論の側面から、歴史的にも積み上げられたものとして、いかに人権や生存権が守られるべきかが論じられている。
本論では、そのどちらにも目配せをして、確かに市場主義社会の論理は強いものの、それだけでは社会は動いていないこと。人権保障や社会運動の論理はもっともであるが、現実では妥協の中から少しずつ前進していくことを論じた。そして、声高に「差別はいけない」とか「人権は保障されるべき」と理念先行で叫ぶのではなく、すでに社会は多様な見方に支えられていること。そして、差別や生活保障を求めることは「勇気のあること」ではなく、「正しいこと」をささやかながら提示した。
また、本論では、ニーズ、普遍主義、障害者運動などを考察したが、これらの言説は対象論の一端であるし、まだまだ論じるべきことは多くある。とにかく、一般に流布する言説を通り一遍に鵜呑みにせず、一つ一つに距離を取って吟味していく態度が求められる。社会福祉の関わるものはこうした社会的排除や人権に対し、吟味することで、対象者への視点の多様・重層化を試みることが重要である。そしてその吟味は自分自身により豊かな思索と広がりを与えると考える。
註
1 田中(2004,P33)では対象の説明を「…一足的に究極的な概念である“人間”と措定しても、対象論の一つの説明にはなっても、その解明には到らない」とし、結局、障害や高齢を人間の属性として説明することは本質的に社会福祉学の存在理由にはならないとされる。さらに、こうした対象規定がただ単に政策によるカテゴリーの説明に終わるのであれば、社会福祉学としての対象理解には到らないと批判している。
2 吉田(1989,PP.2-5)参照。歴史的社会的実践とは、社会福祉の性格規定、相対的独自性は認識規定としている。本文では、歴史的社会的実践を社会改良的実践を強調したが、唯物弁証法的実践も含まれている。
3 田中(2004)を参照のこと。呼称の変化は、ある事象をどのように呼ぶか、名付けるかは、捉える側の見方、そして価値観に基づくとし、呼称の変化を丁寧に吟味することは、まさに社会福祉学の寛容な細部であると考察する。
4 岩田(2001)によると、たとえば、属性別カテゴリー(高齢者、障害者など)にも、経済的な要件による選別、区分が行われ、障害者を例に取れば、障害種別等級毎の細かいカテゴリー、重度障害、重複障害、重度心身障害を積み上げ、さらに「親の養育にかける子」とか「虐待児童」「一人親」など様々な要件を付与している。これらの対象区分の意味を検討することは、実は我が国の社会福祉の性格全体を解明するキーであると指摘している。それと同様な意味で、田中(2004,P.30)もまた、丁寧に名称の吟味をすることは社会福祉学における《肝要な細部》であると考察している。
5 岩田(2001)によると、人間の全てに働きかけるわけではなく、その中の「何か」を課題として抽出し、働きかける。そして、ある角度から対象として意味づけ、社会福祉のフィールドにその問題を引きずり込むという判断が加わり、その人間は社会福祉の対象として存在しているとされる。その意味で、社会福祉のターゲットとして把握されない問題は、排除されないものの、多様な社会問題や生活問題は社会福祉の外部で発生している。その中でも岩田は「外国人労働者」「家族の解体」等が挙げられている。
6 松倉(2001)の述べる「大いなる物語」とは一般に流布されている支配的な言説を指している。構築主義がよく使う用語である。支配的な言説は様々あり、模範や規範、社会的な帰属の類型などあらゆる場所に潜んでいる。渋谷(2003)は予防とリスク、勤労と怠惰を中心として管理する社会が、大きな物語の言説の一つであると分析している。つまり、民主主義とは緩やかに管理されることであると。民主主義による管理社会の詳細はチョムスキー(2002)を参照のこと。
7 副田(1994,P.31- 32)参照。専門知識をもとにに何がその人々(利用者)の最大の利益になるかを理解した人が、それを決定すること、その事が利用者達の利益・福祉に貢献するという意味でパターナリズムに陥るとされる。それは、利用者の自己決定を否定することではなく、このパターナリズムも人の自律性(行為の選択能力)を侵害するものであるから、その専門的介入には正当な理由がないといけないとされる。つまり、その人のためにと思って利用者を尊重し、介入する手法や援助内容が将来利用者の最善の利益をもたらすかということは誰も分からないという点で、仕事は不確実性や曖昧さを持っている。そのことは、今行われている援助がパターナリズムではないとは言えない状況に常に陥ることを意味している。
8 とはいえ、高齢者では家族の介護問題、児童福祉ではシングルマザーや養育の家族機能の固定化や家族神話による問題がある。
9 この他、代表的なものとして、ハンセン氏病、薬害エイズ、水俣病、古いところでは原爆被災者、傷病軍人など枚挙にいとまがない。これらの運動や訴訟、賠償請求について論じることは本論の範囲を超えるが、常に偏見や差別あるいは存権保障を巡る戦いであることは共通したものである。
10 もちろん、障害者運動内でも退けられた少数意見や、沈黙などにも耳を傾ける必要がある(田中〔2005〕)。
11 とはいえ、障害者運動は単に、社会変革や文化の創出を求めつつも、同時に日々のパンの獲得、いわば目の前の現実的な勝利を求めざるをえなかった。すなわち、障害者は確かに生活の質を求めたが、そこには常に質を問うにはあまりにも不足する量の要求を伴わざるをえなかったことを押さえておく必要がある(田中〔2005,P.105〕)。
12 檜垣(2006,,PP.228-233)参照。正義やローカルティ、マイナーなアイデンティティを自己の根拠として持ち出し、平等と公正を上からの統制で推進するエリート主義的な左翼を否定する。障害者運動は社会的に排除された人への社会の不公正や不平等を憤り、その原動力で、無知蒙昧な他の人たちの意識を改善しようと邁進する正義感がつきまといがちである。しかし、それは弱者の代弁するという発想のもと、自分の正義を他人に強要し、同化を求めるものである。結局の所、自分が正義だと信じるあまり、最も始末の負えない形で管理=コントロール的な視線を張り巡らせる。だからこそ、柔軟に政治的に権力に抵抗していくのかを探っていく必要がある。
13 小泉(2006,PP.204-205)では、パーソンズの社会学の概念を援用し、「社会は、病人を社会の外部に放逐する。しかし、社会は、放逐された病人が、そのままの姿で集団的に社会に立ち現れるのをおそれる。だから、社会は病人を患者として個別的に専門家と親密権の支配下に組み込む。決定不可能なゾーンのただ中で快復の希望を通して、患者役割を担わせる。そこの犠牲の構造が侵入する」とする。医療を福祉に、病人を障害者に置き換えるとその包摂と排除の関係が明確になる。
14 ICDIDHの成立過程やICFへの改訂までのいきさつなどは、上田(2002)や佐藤(2002)を参照する。
15 上田(2002,PP.104-107)では、ICFの図表の他、各因子の関連性について、階層構造があることを指摘している。一つの「活動」を支えるには多様な「機能」が存在し、「参加」の一つには多様な「活動」が付随している。そこには、相互依存と相対的独立性があると上田(2002)は論じる。
16 上田(2002)では、ICFの前身であるICDIDHでは、心身機能・身体構造の分類が一番詳しく、活動は心身機能の分類よりも少なく、さらに参加にしては、7項目しかなかった。このことは、リハビリテーション医学〜病院内での機能回復などに主眼が置かれていた分類であった。また、医療偏重に関しては、基底還元論が有力であり、まず、疾病の根治、それによってさまざまな心身機能が改善され、徐々に活動(日常生活動作など)ができるようになり、活動が改善されると社会参加などができるようになると行った段階的な考え方である(上田b〔2001,PP.62-64〕)。いまでもこうした基底還元論は有力であり、しばしば障害者の自立を阻むことが指摘されている。
17 佐藤(2002)参照。精神障害、知的障害、視覚障害についての簡単な応用が書かれている。
18 代表的なもので、TEACCHプログラム、太田ステージなどがある(佐々木〔1994〕):太田〔1992〕:加藤〔1997〕)など参照。
19 人権に配慮した取り組みとして、インフォームドコンセプトがあり、さらに押し進めるものとしてインフォームドコーポレーションと言う考え方がある。これは患者と共同して障害や疾病の治療に当たるという意味である。さらに、包括的な医療とか生活モデルについては、東雄司ら(2002)等を参照。精神障害者の分野では生活モデルについての考えがより強く主張されている。
20 中村(2002,PP.53-54)参照。知的障害者に特有のニーズがないわけではない。しかし、知的障害としてラベリングされている人のニーズは、本来ラベリングされない人々のニーズとほとんど同じものである。知的障害の疾病的側面と社会的に不利を被っている側面を切り離す必要がある。
21 とはいえ、著しいパニックや暴力行為などの適切な訓練や療法、安定剤の投薬は時には有効である。さらに、精神障害者の場合、幻聴や妄想で引き起こされる自殺企図や反社会的行為は、時には拘束や隔離も必要である。ここで問題にしているのは、問題行動を異常として捉え、正常化する過程で、その障害者の行為そのものの背景や生活のしづらさを考慮しないで治療などが行われる危険性である。
22 例えば、「障害者の差別禁止撤廃と同時に「特別措置」「合理的配慮」など、障害者の権利を実質的に保障する内容が盛り込まれる枠組みとなっている」(玉村〔2006,P.11〕)つまり、普通の人のように扱う部分と障害者が住みやすいような社会に作り替える面のより具体的な方策を義務づける内容となっている。