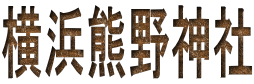
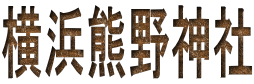
| 弘仁年中(810〜823)紀州熊野の別当尊敬の勧請と伝えられています。この地域は往古より海辺にあって魚、塩の収穫も豊かで、天文年間(1532〜1555)には魚貝の市も開かれて、いつか村名も市場と呼ばれるようになったといいます。村民は、これを熊野権現の加護によるものとして、社殿を造営するなど厚く崇敬したものと言われています。 その後兵火に焼けたり、鶴見川、六郷川の相次ぐ氾濫などにより、社殿が大破して、明和元年(1764)に至りようやく本殿を再建し、天保六年(1835)1月拝殿の改装をおこないました。 明治五年京浜間に鉄道を施設の際、社地がその敷地にあったため現在地に遷座しました。明治6年村社に列せられ、熊野神社と改称しています。 |
 |
 |