書評メモ
まつりちゃん 岩瀬成子 理論社
2010.9 1400円
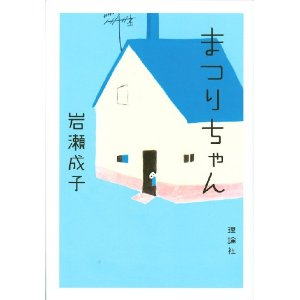
『まつりちゃん』を読む
デビュー作『朝はだんだん見えてくる』以来何作かを読んできた。
その度に「理屈っぽい作家やなあ。」という印象がある。一言でいえば「シンキ臭い」のである。面白くない、退屈の一言。(今回の課題図書に選ばれた時の予感が当たった。)この作品も同様。身辺雑記風の私小説、生活童話。エンドレス作品。飛ばし読み可能。タイトルがその証明。「おどり場」がいい例。「仔ヤギのお母さん」も「わからない」話。「コンクリート」の読者は何処。エンドレスの話に付き合う根気がなくなった証拠か?
同じ身辺雑記風な作品(児童文学ではありません。)を書く瀬尾まいこの作品は読者を「はずませ」ます。清水真砂子の『幸福の書き方』に「いわゆる大人の文学は、幸福よりも不幸に目を凝らしつづけてきたのではないか」という言葉を思い出した。
再度確認したい。こうした作品を今の子どもは歓迎するだろうか。
書店に行く作かの作品が並ぶが果たして子ども読者は手に取るのだろうか。今回はちょっと興奮気味かな?
大藤 幹夫 2011年10月15日
物語性の喪失
「日本児童文学」5・6月号の『特集:子どもの文学この一年』で、野上暁氏は
リーマンショック以降の不況による弱者切り捨てと雇用不安は、子どもを取り巻く環境にも様々な影を落としている。(中略)子どもとは何かを真正面から問い続けてきた岩瀬成子の「まつりちゃん」は、なかなか示唆的だ。
と、述べている。
しかし、この主人公まつりちゃんは全く現実感のない子どもとして読者の目の前に現れる。設定自体がかなり非現実的だが、それを一応置いておいても、観念的、幻想的な存在にしか見えない。
8つの章からなるこの物語はそれぞれの章でまつりちゃんと出会った人々の視点からまつりちゃんの状況が明らかになっていく。
その出会いから、係わった人々の方がまつりちゃんに癒され、支えられていることに気づくという評が多かったが果たしてそうだろうか。
それぞれのしょうの登場人物は奇妙な少女と知り合うことの戸惑いはあっても自分の意識が変わったり、ましてや成長などはまったくなかった。まつりちゃんは単なる町の雑踏ですれ違う他人以上の存在ではなかった。
現実にはあり得ないまつりちゃんの存在が物語の成立そのものを不可能にしている気がする。
この現実感の希薄さのなかでまつりちゃんと係わる人たちの意識の流れが丁寧に描かれている。こうした表現はくどいし、いらいらする側面もあるが児童文学ではあまり見られない手法だ。描かれる内容によっては有効かもしれない。
しかし、野上氏がいうように、今の子どもの状況が描かれた作品にはなりえていないし、子どもその物もネガティブにしかとらえられていないと思う。
血肉を持った子供たちの心躍る物語を読みたいと思う。(信原和夫)
疑問だらけの『まつりちゃん』
『まつりちゃん』はファンタジーなのか?今を問いかけているのか?発信された先は子どもなのか、大人なのか?
読後しばらく考えていたが、わからずじまいだった。
なかでは「仔ヤギのお母さん」が年齢も同じ、友人が集まればとびかう夫の不満も似たようなものなので、親近感はもてたが、あのままごと遊びはなに?
「コンクリート」の章は必要なのか?
ずっと独白が続いていたのに、最終章はあかりちゃんのお母さんから、あかりちゃんにあてた手紙。文字が読めないあかりちゃんに書いた意図は?
すんなりと読めたのは「たまご」。みんな、もっとひびをいれなくっちゃ。そうだそうだと頷いた。
自分にひきつけて読めば、わたしもわたしの子どももそのまた子どもも、五歳では一人暮らしはできなかった。親の言いつけをあんなに守れる聞き分けのよさは、ぜったいになかった。あんなに娘を愛する両親が、それしか考えられなかったことに、疑問を持つしゾッとした。あかりちゃんの愛らしさに、まわりの人間がある種の再生をしたのだとは思いたくはない。 (村上裕子)
『まつりちゃん』(岩瀬成子)を読む
気合いを入れて読まなかったせいもあって、初め短編集と思った。青い透明なガラス箱の中の、生活の匂いを消した世界を外から眺めているような気がした。途中、第4話ぐらになって「これは独立した話ではなく、一人の少女をめぐる話らしい」と気づく。迂闊な読者である。
そう思ったわけは、各話の語り手がばらばらに感じたことにある。第一話は「ぼく」(行夫)、第二話は傾聴ボランティアで女子高生の「松本のぞみ」、第三話はパン屋の娘「奈保」、第四話はまつりの隣家の「空」、第五話はまつりの世話をやかずにいられない老女「わたし」、第六話は「あたし」(まつりであることは明らか)、第七話はまつりの父の同僚の「ぼく」、第八話は「母さん」といったように、複数の人物が語るしかけになっている。
あとで考えればそれほど複雑な構成ではないが、カバーなどにある内容紹介などによる予備知識なしで読み始めると、人物名が出ず一人称呼称だけのせいもあって、短編集と思いこんでしまったようだ。途中から最初にもどって読み返したのだが、ミステリーの種探しのおもしろさがあることがわかった。とはいえ、ここに登場する人物は大なり小なりの孤独をかかえているわけだが、孤独の寂しさや人とつながるふつふつとしたうれしさが複数の視点からとらえられているとは言い難い。
「まつり」「空」といった誤解が生じる名前のためのとまどい、第七話と第八話のつけたしたような話の浅さといった不満はあるが、おとなの小説としておもしろいし、またナイーブな子どもにも受け入れられるのではないかと思った。(向川幹雄)