 図書館が棚卸しの長期休みに入る前に、リクエストしていた「アップデート版 ビル・ゲイツ未来を語る」を借りることができました。以前の版も読みましたが、インターネット関係の章が書き直されているということで読んでみることに。
図書館が棚卸しの長期休みに入る前に、リクエストしていた「アップデート版 ビル・ゲイツ未来を語る」を借りることができました。以前の版も読みましたが、インターネット関係の章が書き直されているということで読んでみることに。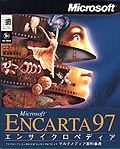 子供がようやく退院することができホットしています。前話の最後に書いたようにモニターに当選したマイクロソフトの「エンカルタ百科事典」を使ってみました。このモニターは主婦仲間を集めて使ってみて、それぞれの感想をアンケートに答えることになっている。アンケートの量は負担になるほどではない。
子供がようやく退院することができホットしています。前話の最後に書いたようにモニターに当選したマイクロソフトの「エンカルタ百科事典」を使ってみました。このモニターは主婦仲間を集めて使ってみて、それぞれの感想をアンケートに答えることになっている。アンケートの量は負担になるほどではない。まず、インストールすると最初に著作権に関する事項についての同意を求められる。同意しなかったら使うことができない。実際この部分を読んで同意しない人なんかいないと思う。法律的には根拠のある問いなのだろうか? 使うには同意するしかないので、同意しインストールを終えた。あっけないくらい簡単にインストールできる。でも、ママのコンピュータに何がインストールされたのかはよく分からない。CD-ROMのソフトだからCDがあれば使えそうなものなのに何かインストールする必要があるようです。
起動するとオープニング時にテーマ音楽が流れたりして、やはり百科事典というよりエンターテイメントソフトのようです。検索のソフトも単なる見出しの検索だけでなく、ガイドツアーや動画や音声、地図が登録されているものだけを一覧したりするメニューがあります。普通の百科事典なら調べたい見出しで探すのであって、百科事典に載っている写真のページだけを探したりしないもの。
以下、ママの独断による感想です。
【いいと思う事】
どちらも友達の自宅にもパソコンがある。でも殆どはご主人が使っているだけのようです。
珍しそうに見てくれたが、あまり興味はわかないようでした。まず、パソコンの操作を覚えないと使えないのと、調べたいときにすぐに使えないのがまずそうです。パソコンの電源を入れて、Windowsが起動されるのを待って、CD-ROM入れてエンカルタが起動されるのを待つ。この時間がもどかしい。
検索する文字もキーボード入力なので、普段からパソコンやワープロを使っていない人には敷居が高すぎるようです。写真も紙のメディアに比べると見劣りするし、動画なんかTVと比べると全然比較にならない。パソコンを使い慣れていない人には受けないようです。15,000円も出して買いたいとは思わないと言われてしまった。トホホ、、、
エンターテイメントソフトというより、子供の教育ソフトだという面をアピールした方が世のお母さん達の財布の紐は緩むんではないでしょうか。
 図書館が棚卸しの長期休みに入る前に、リクエストしていた「アップデート版 ビル・ゲイツ未来を語る」を借りることができました。以前の版も読みましたが、インターネット関係の章が書き直されているということで読んでみることに。
図書館が棚卸しの長期休みに入る前に、リクエストしていた「アップデート版 ビル・ゲイツ未来を語る」を借りることができました。以前の版も読みましたが、インターネット関係の章が書き直されているということで読んでみることに。
前話で書いた「インターネットはからっぽの洞窟」とは全く対照的な内容です。インターネット、PCによって実現されるバラ色の未来象が述べられている。ここまで書かれるとストールさんが、一歩下がって冷静に考えようよ、というのもうなずける。
この本の6章 コンテント革命に「エンカルタ百科事典」のことが書かれている。全項目26,000となっており日本版より項目が多い。リンクが30万件となっているけど、日本版を使ってみた感じでは、そんなにない感覚を受ける。また値段が$60とのことで日本の半額くらいだ。確かに日本語版にするのには経費がかかるうえ、売れる枚数も違うからしかたないのかな。数の面で日本語はハンデがあるな。世界中で1億ちょっとの人しか使ってないんだからなぁ。
ちなみに本に載っていた「ウード」(エジプトの楽器)の音と、大英帝国の国王エドワード8世の退位演説は聞くことができた。このあたりは、翻訳するときちゃんとチェックしているのかな^_^;
しかし、小中学生向けの辞典としては十分使えそうだ。教育ソフトとして売り込んだ方が売れるのではないでしょうかね。我が家の子供たちはまだ百科事典を使う年ではないが、将来はきっとこのような百科事典を使うだろう。これからこのようなコンテンツ製品が増えることを期待したい。
学生や大人向けにはジャンル毎に分冊になったCD-ROM辞典もいいかもしれない。でも、あまり売れないから高いものになってしまうのかな。
以上、勝手なことを書きましたが、エンカルタは基本的には気に入っています。最近発売された?ワールドアトラス(世界地図帖)のCD-ROMも使ってみたいと思っています。最近、内戦やら難民問題その他で小さな国の名前がTVにでたりするけど、その国のことは殆ど知らないのが実状です。そんなとき、少しは役に立つかなと思っています。紙の地図帖でもいいんだけど場所をとるし、やっぱりこれからはディジタル情報時代だと思っているので、、、
アンケートも記入して、ついでにこのページも印刷して一緒に送りました。さて、こんなモニター報告で役に立つのでしょうか???