
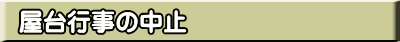
新型コロナウイルスの感染拡大により、令和2(2020)年と令和3(2021)年の秩父神社例大祭は、笠鉾・屋台の曳行などの「屋台行事」及び煙火主催町による「競技花火大会」が行われない事態となりました。
また、秩父神社の神事も、神輿の渡御をはじめ、氏子町会の供物・高張提灯の供奉がないなど、規模を縮小したものとなりました。
令和4(2022)年の大祭は、3年ぶりの復活となりました。
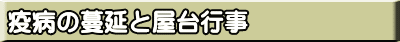
疫病が蔓延したことで、屋台行事が中止の危機に瀕したことは、過去に一度ありました。
明治29(1896)年秋、伝染病が大宮町(後の秩父町)で大流行し、「十一月中頃ニ至リテモ尚全癒ノ模様ナクシテ、イツモノ如ク附祭リヲスルヤ否ヤハ取極メ候訳ニモ不相成居候処」、警察に対して許可の申し入れを再三行うも聞き入れられず、それでも11月29日に「大宮全部衛生組長ノ調印相取リ出願セリ」。遂に、翌30日午後4時に警察の許可が下り、屋台行事は実施されたのでした(「中町記録簿」)。
今回の屋台行事が行われない事態は、大祭の長い歴史の中で、疫病が原因で秩父夜祭が中止となる初めてのケースになります。
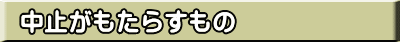
 長年屋台行事に携わり、年齢を重ねてきた者にとって、大祭に参加出来るのもあと何回かとの思いが毎年頭を過ぎります。 長年屋台行事に携わり、年齢を重ねてきた者にとって、大祭に参加出来るのもあと何回かとの思いが毎年頭を過ぎります。
しかし、今回、年配の者より遙かに暗い思いに沈むのは、若年者でしょう。
来春の高校卒業予定者の中には、今年が最後の大祭となるはずだった人も大勢います。それ以外の児童・生徒にとっても、秩父にいる内に大祭を経験する僅かな回数が確実に1回減ることになるのです。
御旅所の夜空に打ち上がる花火に故郷の祭りとの別れを惜しんで涙を浮かべる。多くの先輩達が経験してきたことですが、今年はそれすら叶いません。
いずれは町内の担い手と期待していた若者の多くが秩父を去って行く。秩父は、若者が未来を託せる場所でなくなりました。
屋台行事の中止は、寂れゆく町を一層の悲しみが包みます。
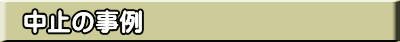
過去に屋台行事が中止になった主な事例は、次のとおりです。
【主な中止の事例】
・徳川幕府の禁止令〔寛政の改革〕 寛政11(1799)年~文化5(1808)年
・徳川幕府の禁止令〔天保の改革〕 天保13(1842)年~弘化2(1845)年
・日露戦争 明治37(1904)年
・明治天皇崩御 大正元(1912)年
・第二次世界大戦 昭和18(1943)年~同20(1945)年
・昭和天皇容態悪化 昭和63(1988)年
・新型コロナウイルス感染拡大 令和2(2020)年・令和3(2021)年
【参考文献】「中町記録簿」中町会 「祭礼日記」 「御祭礼記録」中村町会 |