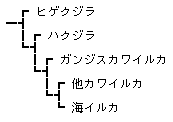◆ かたちと分子からみたクジラの進化 ◆

|
国立科学博物館 自然史セミナー 日時:2000/9/23 13:00-19:00 場所:国立科学博物館 新宿分館 |

|
国立科学博物館 自然史セミナー 日時:2000/9/23 13:00-19:00 場所:国立科学博物館 新宿分館 |
- ハクジラとヒゲクジラが分化した頃のかれらのかたち
ユアン・フォーダイス(オタゴ大学)- 鮮新世以降のナガスクジラ科の頭骨を比較すると
大石 雅之(岩手県立博物館)- イルカの肩と腰、かれらはどのくらい特殊か?
山田 格(国立科学博物館)、伊藤 春香、高倉 ひろか、田島 木綿子- 海棲哺乳類血管系の収斂進化
センティエル・ロンメル(フロリダ海洋研究所)、アン・バプスト、
ウィリアム・マクリラン- 海棲哺乳類の脳と進化
ヘルムート・オェールシュレーガー(フランクフルト大学)- 新たに判明したアカボウクジラ科鯨類の分子遺伝学的発見と かくされている形態学的特徴
メレル・ダウバウト(オークランド大学)、J.G.ミード、
K.ファン・バーレベーグ、J.G.ライエス、
V.G.コックロフト、C.S.ベーカー- SINE による鯨類系統学 〜ハクジラ類は単系統でカワイルカは多系統
岡田 典弘(東京工業大学)- 総合討論
以下、MINEW のコメント(間違いや誤解があるかもしれません):
- はクジラ類の頭骨化石を比較し、ハクジラ類 Odontoceti と ヒゲクジラ類 Mysticeti の共通祖先種について報告したもの。 現世のハクジラ類はエコロケーションを用いて餌を採り、 ヒゲクジラ類はヒゲによる濾し採りで餌を採る。 その採餌方法はそれぞれの頭骨の形にも特徴を与えるが、 共通祖先種である 3000-3400 万年前のバシロサウルス類の 古クジラ Archaeoceti ではエコロケーションもヒゲ濾し採りの特徴も 見られない。化石を年代順に比較してみると、ハクジラ/ヒゲクジラ それぞれにその頭骨が特徴を得て変化(進化)してきたのがわかる。
- は世界中のヒゲクジラ類の頭骨資料を多く収集し詳細に比較したところ、 時代別・地域別・種別にいろいろな形態的特徴が得られたという報告。 時代が進むにつれて、口吻部の骨は長くなり、後ろ側の頭骨部は前後に狭く 左右に広く変化してきた。
- は解剖学的なイルカの筋肉形態を陸棲哺乳類と比較した報告。 イルカは哺乳類なので、その筋肉構成は陸棲哺乳類と基本的には 同じ起源を持つはずである。しかし、海棲となったために その筋肉形状は大きく変化しており、対応関係を見極めるのは難しい。 研究者によって筋肉の有無の報告が異なることが実際にある。 そこで、筋肉の形状ではなく、その筋肉につながっている神経系に 注目して(Nerve-Muscle Specificity)、肩付近、骨盤付近の 筋肉群の同定を行った。
- はアザラシ、イルカ、マナティ類の体温調節機構についての 解剖学的知見報告。 海棲哺乳類は、海水の熱容量が大きいせいで、体内温度を一定に保つために 陸棲哺乳類にはない、優れた血液循環系の適応が見られる。 海棲による大きな変化は、体の大型化、四肢の変化、脂肪層の蓄積 などがある。アザラシ、イルカは陸棲哺乳類に比べ代謝率が 2倍ほど高い。
体表に達した血液はそこで冷やされ熱を失うが、そのロスを減らすために、 体中心から体表へ向かう動脈と逆に戻る静脈は近接して配置されている。 動脈は体表へ向かいつつ静脈へ熱を渡し、静脈はあたためられて 体中心へと戻る。これは対向流熱交換システム Countercurrent Heat Exchange と呼ばれる。対向流熱交換システムは 人間はじめ陸棲哺乳類にも見られる構造だが、アザラシ、イルカ類では さらに効率が高く、静脈が細く分かれ動脈を包み込む構造(PAVR)を 形成している。マナティでは、動脈も静脈も細くホウキのように分かれ、 互いに絡み合う構造となっていてさらに熱交換効率が高い。
静脈系には実は2種類あり、体中心を動脈に沿って走るものと、 体表面近くを走るものがある。体表面を走る静脈血液は熱を奪われ 低温となるので、2系統のどちらの静脈に多く血を通すかを調節する ことによって、体温のコントロールが可能である。 精巣など生殖器官は体温より3度ほど低温に保つ必要があるが、 海棲哺乳類では、陸棲哺乳類と異なり精巣が体内にあるので、 それを冷やすために、前記体表面系の静脈を精巣周囲に導くような構造が 見られる。実際にイルカやマナティの直腸内温度分布を測定した結果、 精巣付近が2〜3度ほど低温となっていることが確かめられた。
- はハクジラ、ヒゲクジラ、カワイルカ、海牛などの頭骨や脳の構造などに ついての報告。特にハクジラ類の頭骨に見られる、エコーを発射・受信する 機構や脳の大きさ・形状について詳しく説明があった。
- は牙を持つアカボウクジラ類 Ziphiidae の DNA 分子情報を用いた 再分類についての報告。 アカボウクジラ類は、成体雄が下顎に2本の牙を持つ種である。 雄のみが牙を持ち、近縁種間で牙の形態が大きく異なっているのは 性選択による特徴多様化の結果と思われる。このクジラは観察個体が少なく 幼体やメス個体は牙の特徴がないため、種分類は非常に難しかった。 そこで、世界各地の収蔵サンプルから得たミトコンドリア DNA を用いて、 再分類を行った。その結果、アカボウクジラ類の系統樹が従来と違った 形で再構成できたほか、誤分類の発見や、未知の新種を発見することが できた。
- Nature 誌にも掲載された、有名な分子情報を用いたハクジラ類の 系統解析についての報告。 DNA 分子の一種である SINE というレトロポゾンは、時代が進むにつれて 一方向に増える(減らない)という特徴があり、系統関係を解析するのに 強力な材料である。この SINE に注目して、ハクジラ類の系統関係を 解析した結果、ハクジラ類は偶蹄目(ラクダ、ブタなど)から分岐した 単系統であり、陸棲哺乳類で最も近いものはカバであるとの結果が 得られた。
従来、古代陸棲生物メソニクスがクジラ類の祖先だと言われてきた。 それは顎と歯の形がクジラ類と共通点があったからだが、メソニクスの 足首の関節骨は滑車状をしており、これは偶蹄目の特徴とは一致しない。 つまり、メソニクスはクジラの祖先ではない可能性が出てきた。
カワイルカ類も含めてさらに系統関係を調べた結果、以下のような 系統関係が得られた。カワイルカ類はガンジスカワイルカのみが 先に分かれた多系統となった。