mori's Page 騒音の対策
3.2.拡張型消音器
管路の一部を拡張して、断面積が大きくなると管路内の流体が膨張し、速度と圧力が減じ、出口管路では拡張により
薄くなったエネルギーだけが出口管の面積に相当する大きさだけ通過し、残りは管路内の反射により減衰する。音波
はインピーダンスが急変する(急拡大・急縮小)ところで反射する。このため図13に示すように拡張室の入・出口や管路
の終端で反射が起こる。
薄くなったエネルギーだけが出口管の面積に相当する大きさだけ通過し、残りは管路内の反射により減衰する。音波
はインピーダンスが急変する(急拡大・急縮小)ところで反射する。このため図13に示すように拡張室の入・出口や管路
の終端で反射が起こる。
この反射波により、管路内あるいは拡張室内で干渉が起こり音のエネルギが消費される。
この型の消音器は比較的低い周波数帯域で使用される。(数100Hz以下から超低周波域)
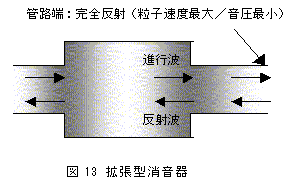
(1)平面波・一次元
管路や拡張室の径が音の波長に比べ小さい場合は管路内での周方向の圧力分布が小さく音の波面はほぼ一定とな
る。このような場合が平面波と呼ばれ、図14の①に相当しインピーダンス変化がある場所では完全に反射する。②や
③の場合(管路径に比べ波長が短い)は完全な反射は発生しない。
る。このような場合が平面波と呼ばれ、図14の①に相当しインピーダンス変化がある場所では完全に反射する。②や
③の場合(管路径に比べ波長が短い)は完全な反射は発生しない。
本テキストで示す計算式はこのような平面波が成り立つ周波数帯域での計算式で、管路径を無視したモデルとなって
おり、一次元的な計算モデルとなっている。このため設計時には注意を要する。三次元モデルも提案されているが入力
の煩雑さ正確さで、まだ実用的ではないと思われる。
おり、一次元的な計算モデルとなっている。このため設計時には注意を要する。三次元モデルも提案されているが入力
の煩雑さ正確さで、まだ実用的ではないと思われる。
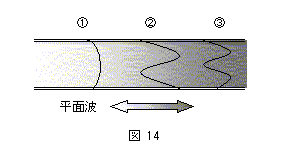
(2)尾管付き消音器
図15は拡張室に尾管を付けた場合を示している。拡張室と尾管の長さが同一であれば長さの4倍の波長に相当する
周波数で最大の減音効果を示し、その減音量は
周波数で最大の減音効果を示し、その減音量は
ATT= 20log(m) dB
maxF =n×C/(4L) n:次数 (1,3,5....)
で表される。
図16は尾管付き消音器の減音特性を示したグラフである。1/4波長に相当する帯域で最大の効果があり、1/2波長
付近では減音効果がなく逆に音を増大する帯域も生ずる。
付近では減音効果がなく逆に音を増大する帯域も生ずる。
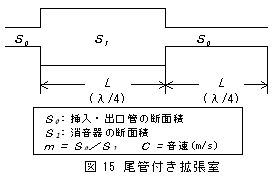
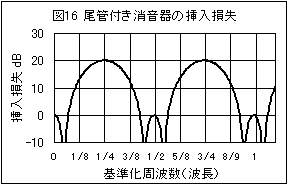
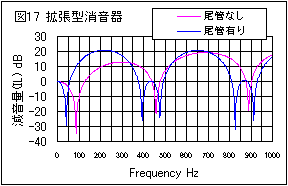
図17は主管路の径が55mmで、拡張室長
さ390mm、尾管長405mmで拡張比m=11の場合の挿入損失を計算した結果で、拡張室のみに比べ、尾管を取りつけた
場合が低域で減音量が大きいことがわかる。
場合が低域で減音量が大きいことがわかる。
(3)内ダクト付き消音器
次式は図18に示すように拡張室に尾管を取り付け、更に尾管の一部を拡張室に挿入した内ダクト型の消音器の減
音特性を表す計算式である。
音特性を表す計算式である。
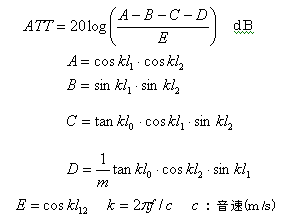
図19に内ダクト有無の挿入損失の比較を示す。内ダクトの効果により挿入損失の谷間が改善される。
図20は入口管、尾管それぞれを拡張室内に挿入した両内ダクト方式で、内ダクトは図21に示すようにブランチとして
扱う、両内ダクト方式の計算は資料消音器計算式の(6)に示す。拡張型消音器の減音効果はブランチに比べ効果のあ
る周波数帯域が広いことである。
扱う、両内ダクト方式の計算は資料消音器計算式の(6)に示す。拡張型消音器の減音効果はブランチに比べ効果のあ
る周波数帯域が広いことである。
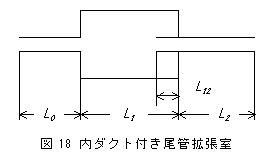
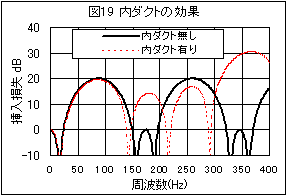
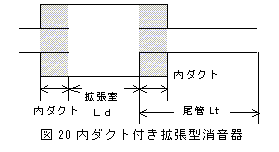
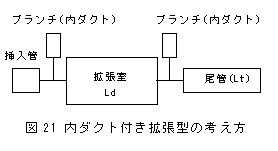
(4)開口端反射
ダクトの開口端では音はインピーダンスの不連続により一部反射されて、開口端より放射される量は減少する。図22
に示す様にその量は周波数が低いほど、また開口が小さいほど放射される量は少なくなる。
に示す様にその量は周波数が低いほど、また開口が小さいほど放射される量は少なくなる。
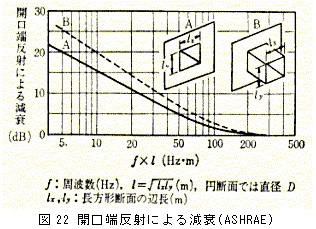
楽器などは消音器と逆で開口端での反射が少なくなるよう工夫されている。
前へ ページの先頭へ 次へ
|

