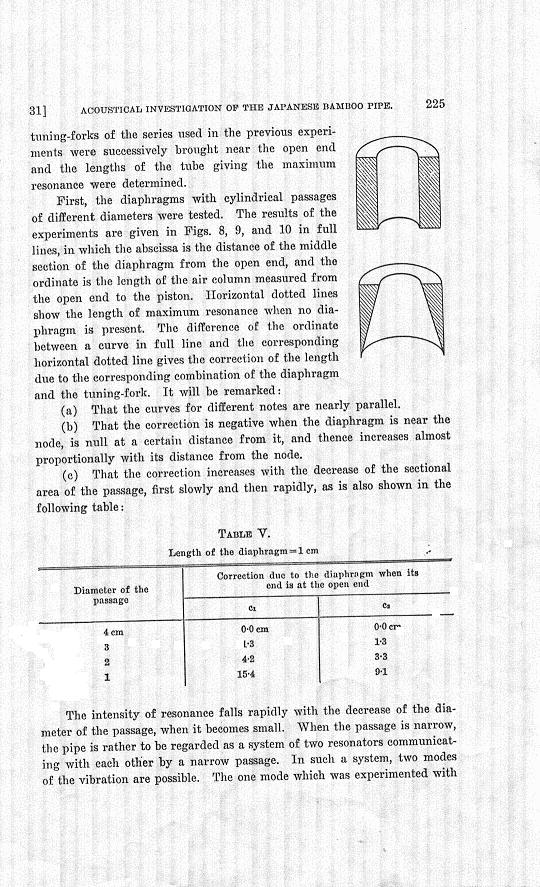寺田はダイヤフラムの中心孔の径を変え、またダイヤフラムの管内での位置を変え、ダイヤフラムの長さを変えて実験を繰り返している。また下の図のように孔の径が円錐状に変わる場合についても実験している。
そして TABLE V はダイヤフラムの孔の径(r)を変えたときの管長さの変化量Δl を示したものである。
寺田はこれを Rayleigh による管長さ補正の理論式と比較した。その理論式によれば、Δl は管の断面積の変化量ΔSに比例する。ここでΔSは、管の断面積の平均値S0と、ダイヤフラムの孔の断面積との差である。
そして寺田はこの関係を
|
Δl ∝ΔS or Δl ∝(R−r)2 where R is the radius of the cylinder and r that of the channel. |
Δl ∝R2−r2
である。