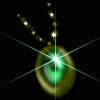エセ占い師
まず頭に浮かんだのがそれだった
長い布をずるずると引き摺って何だか胡散臭さ抜群だ
高価なシルクの筈なのに自分が身につけると単なる布切れに見える
シーツを身体に巻きつけた園児のお遊戯会のようでもある
「……格好悪くないか……?」
せっかく新調した服
しかし―――どうも似合っているとは思えない
今までこんな服を着たことがなかったせいもあるかもしれないが
「宝石も俺がつけると偽物にしか見えないな……」
見るからに豪華な宝石を繋いだアクセサリー
耳につけたり首から下げたりしてみても、どうもしっくり来ない
頭から飴玉をかぶったような、何とも情けない姿に見える
一種の賭けで化粧品にも手を伸ばしてみたが―――不気味な顔になっただけだった
しかも化粧を落としたくてもクレンジングが見当たらない……
俺は鏡の前でずっと自分を睨んでいた
隣の部屋ではゴールドも新しい衣装に身を包んでいるはずだ
今日は二人の初デート…のつもりだ
しかも格調高く超高級レストランのディナーショーに行く事になっている
だから変な格好はして行きたくない
「……でも、絶対変だ……」
馬子にも衣装と言う言葉があるが、限度を超えると見苦しいだけらしい
こんな服、どうやっても自分には似合わない
これではゴールドに恥をかかせてしまうかもしれない
しかし今更予定をキャンセルするのは更に悪い
「…どうしよう…」
俺は鏡の前で盛大に溜め息をついた
「―――ジュン、支度は出来ましたか?」
先に着替え終わったらしいゴールドがドアをノックする
もうタイムリミットだ
意を決して恥をさらすしか道は無い―――のだが
「……なぁ、想像以上に変なんだが……」
「そうなんですか? とりあえず出てきて下さい
ボクでも着付け出来るところは直してみますから」
いや、着付けがどうとか言えるようなレベルじゃない…
そもそもが似合っていないのだから着付けを完璧にしようがどうしようもない
……しかしここでずっと引きこもっているわけにもいかない
「笑うなよ?」
「笑いませんよ。…ドア越しの会話はもう沢山です
早くジュンの綺麗な顔を見て、話をさせて下さい…寂しいです」
さり気無く恥ずかしい事を言われたような気がする
しかしゴールドの言う通り、いつまでもドア越しに話していても仕方が無い
俺は恥を忍んでドアを開いた
「……凄く綺麗なのです。着付けもメイクも完璧で…どこが変なのです?」
ゴールドは俺の姿をまるで芸術品を鑑賞するかのように恭しく眺めている
彼の言葉がお世辞なのか、それとも美的感覚が狂っているのか…理解に苦しむ
いや、そんな事よりも更に俺を苦しませるのは―――
「何かお前、いきなり格好良くないか?」
俺は恨みがましくゴールドを見上げた
黒を基調とした絹のスーツに白と黒のグラデーション模様のマントを身に着けている
いつもは無造作に束ねられている髪も、今日は赤と黒のリボンで硬く結ばれていた
その紳士的な姿は嫌味なほど似合っていて自分をより一層惨めな気分にさせた
「…絶対…つり合わない…」
「そうですね…ジュン、綺麗過ぎます
こんな不細工なボクでは役不足なのです…」
見るからに萎んでゆくゴールドを背後から蹴り倒してやりたくなる
どうすればそんな解釈に辿り着くのだろう
「……お前じゃない、俺がだ」
「え? だってジュンは物凄く綺麗じゃないですか
こんなに素敵になるなんて…何だか人に見せるのが惜しくなってきます
このまま台座の上に座らせて閉じ込めて、いつまでも見ていたい気分になるのです」
ほぅ、っと吐息混じりに俺を見つめるその目は―――ちょっと危ない光を放っていた
彼の場合本当に俺を閉じ込めそうでシャレにならない
「わ、わかった。もういいから、早く行くぞ」
外はもう薄暗くなり始めている
夜闇に紛れてしまえば自分の姿も目立たないだろう
「―――不安なのです…ジュンがもし誘拐されたら……」
そんな物好きは絶対お前だけだ
俺は渋るゴールドを引き摺るようにして城から連れ出した
ディナーショーでは、やっぱり恥をかいた
しかしそれは俺の服装がどうとかいう訳ではない
問題なのはゴールドだった
「―――ふぅ、余計な恥をかいた……」
ディナーショーが終わるなり、俺はゴールドの袖を引っ張って外へ飛び出す
きっと俺の顔は真っ赤に染まっていることだろう
「ジュンは相変わらず恥かしがり屋なのです」
「あのなぁ…ずっと耳元でショーも顔負けの口説き文句を囁かれてみろよ
俺でなくても顔面から火炎放射状態だぞ? 何でお前は平然としてられるんだ?」
そう、俺はディナーショーの間中ずっとゴールドの口説き文句攻撃を食らっていた
肩を抱かれて耳元に唇を寄せられて―――――延々、3時間
恥かしさのあまり何度叫びだしそうになったことか……
「ジュンが綺麗過ぎるのがいけないのです
何か喋っていないと理性が吹き飛びそうで苦労したのです」
「……一度、病院へ行け」
「恋煩いの病も治るでしょうか?」
「……………………。」
駄目だ、俺の敵う相手ではない
俺は早々と白旗を掲げた
アルコールで更に饒舌になっているゴールドは言葉の兵器と化している
「頼むから、もう何も言わないでくれ…」
「そうですか? 残念です…」
俺たちは公園のベンチに腰掛けた
こんな状態のゴールドを部屋に連れて帰ったら―――――想像するのが、ちょっと怖い…
露店で買ったジュースを手渡して酔いが醒めるのを待つ
「こんな風にお前と夜のデートをする日が来るとは思わなかったな…」
少し感傷的な気分になる
見上げた空は星が綺麗だった
輝く星の光りに、俺はこの日のために用意したプレゼントの存在を思い出す
初めてにしては割と上手に出来たと思う、オリハルコンと魔石のペンダントだ
「ゴールド、これ…約束の魔石」
そっと彼の手にペンダントを握らせる
―――照れ隠しにわざと視線を逸らしたまま
「……これ、本当にジュンが作ったのですか?
素晴らしい出来です……感動です。ありがとうございます」
緑色の魔石はゴールドの魔力に反応してキラリと輝いた
細工の際に彼の名前も刻んだのだ
持ち主を指定することで、潜在能力をより引き出すことが出来る
魔石に施した細工は所有者の能力を―――――特に守護の力を高める効果を持つ
もう、ゴールドの傷付く姿を見たくないという願いから選んだものだ
「嬉しいです……ジュンに護られている気がします
身に着けているだけで心が温かくなって……幸せな気分になります」
「喜んでくれたなら俺も嬉しい」
プレゼントをしたほうの俺も嬉しくなってくる
もっと勉強して、もっと強い効果を持つものを早く作れるようになりたい
こういう形でも彼を護ることができるなら努力を惜しまない
「俺だって、お前を護ることができるんだからな」
「……そうですね。…とても心強いのです……」
ゴールドは俺の肩に頭を乗せて目を閉じる
そして口数少なく語り始めた
「…ボクの生まれた家は、とても貧しくて…毎日の食事すらままなりなせんでした
働いても収入は無く…借金も増える一方で……本当に生活に困り果てていました」
意外だった
ゴールドはてっきり裕福な家庭に生まれたのだと思っていた
彼の持つ黄金の輝きがそんな先入観を抱かせたのだろうか
「15歳の秋でしたか―――朝起きると両親は姿を消していて…
家族を探していると、商人が来てボクを知らない土地へ連れて行きました
両親はボクを奴隷商人に売って…そのお金で逃げたのだと、後になって聞かされました……」
「えっ…」
「ずっとボクを捨てて裏切った両親を恨んで生きていました…何十年間も…
それなのに皮肉なものです。ボク自身もスパイとなって主を裏切る生き方を選んでしまったのですから」
「……ゴールド……」
ずっと苦しんでいたのだろう
そして何より―――寂しかったに違いない
自分は彼の傷付いた心を少しでも癒すことが出来ているのだろうか
慰めの言葉も労わりの言葉も口下手な俺の口からは出てきてくれない
今の俺には頬を伝う涙を指先で拭ってやることしか出来なかった
「あぁ、何を言ってるのでしょうね、ボクは…
ただプレゼントを貰って嬉しかったと伝えたかっただけなのに」
無理に作った笑顔は痛々しく涙に濡れている
月の光の下でその姿は何よりも美しく見えた
「……俺が傍にいるから、ずっと……」
「……はい……」
気の利いた言葉なんて知らない
過去の傷を癒す術も知らない
ただ―――傍にいることしか出来ない
それでも俺は願わずにはいられない
黄金の悪魔が受けた傷が癒える日が来ることを
……出来るならば…他の誰でもない、この俺の手によって……
「――――帰りましょうか」
夜の闇は更に深くなって外を出歩くものは誰もいない
民家の窓からも明かりが消え、月明かりだけが街を照らしている
「……そうだな……」
俺はベンチからゆっくりと立ち上がる
着慣れない裾の長い服のせいで気を抜けば転倒しそうになる
しかし気をつけていた筈なのに裾を踏んでしまった
ぐら、とバランスを崩して――――ゴールドの腕に支えられた
「…ど、どうも…」
「暗いですから、足元に気をつけて…」
俺を支えている腕が、そっと背中にまわされる
その体温が布越しにでも伝わって、意味も無く胸が鼓動を早めた
どんなに傷付いていても、俺を支えてくれるその腕が愛しくて堪らない
「――――暗いですし…誰も見ていませんよね……?」
「……え……?」
吐息が瞳を掠める
濡れた唇が、俺の額を啄んでいた
そのまま額から鼻先を滑り伝い、そして唇へ重なる
微かな涙の味に胸が締め付けられた
「何だお前…まだ泣いてんのか」
嗚咽を堪えて肩が震えている
両腕でしっかりと抱きついて俺の胸に顔を埋めた
「ジュンは…ボクを捨てないで下さい…
もう愛する人に置いて行かれるのは耐えられません…
リノライ様に聞きました。貴方は異世界から来た者なのだと
それでも…諦められません。貴方の不幸を願うボクを許して下さい」
ゴールドは知っていたのだ
俺がこの世界の住人ではないことを
「……帰らないで下さい……
貴方にも愛する家族がいるのはわかっています
知らない土地で身寄りも無く暮らす心細さも身を持って知っています
貴方を苦しめるだけだとわかっていても…それでも、引き止めずにはいられないのです」
余計な心配は掛けたくないと、俺は自分の素性をずっと誤魔化していた
しかし、それが裏目に出てしまった
ゴールドはずっと、いつ俺が元の世界へ帰ってしまうのか―――その事に脅えていたのだ
いつも俺に見せていた笑顔は、もしかすると諦めから来ていたのかも知れない
「……ずっと、傍にいると言っただろう?
俺はこの世界でお前と生きていくことを決めたんだ」
「…信じ、られない…どうして…です?」
ゴールドは俺に縋りついたまま離れない
手を離したら最後だとでも思っているのだろう
俺はそんな恋人を安心させようと、必死に言葉を探す
そしてゆっくりと、耳元で囁いた
――――愛しているからに、決まっているだろう?
ゴールドはもう嗚咽を堪えることをしなかった
子供のように泣き声をあげる彼を、俺は母親のような気持ちで抱きしめる
苦しみ悲しみ、そして寂しさはもう忘れてしまえ
……俺が全てを満たしてやるから
俺はそう囁くと、濡れた頬に口付けた
TOP 戻る 進む