●人間がブタになる「千尋」の設定は、世界で受け入れられるだろうか? 2001/05/14
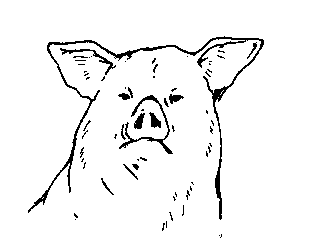 人類の歴史はブタ迫害の歴史であった。 「千尋」でブタの復権はなるか? (イラスト:きばぞうさん) |
ブタのデザイン自体もショッキングであるが、「人間がブタになってしまう」という基本設定の方も気がかりである。「千尋」の制作にはディズニーも資本参加しているから、当然ながら世界配給も考えられていることと思われるが、この基本設定は、果たして世界で受け入れられるだろうか?なぜなら、ブタは歴史的・宗教的に見て様々なタブーを背負わされた動物であり、人間をブタにするということは、それらのタブーに真っ向から挑戦する形になるからだ。
ブタは、家畜として有益であるにも関わらず不潔な動物の代表とされてきた。怠惰な人間を揶揄するときや悪態をつくときに引き合いに出されるほか、蔑視の代用語になっている。英語のPigは強欲野郎、フランス語のCochonはこん畜生、ドイツ語のSchweinはすけべ野郎という意味を含み、まあろくな使われ方がされていない。「お前はブタだ」という言葉が褒め言葉になっている文化圏は存在せず、これからも多分存在しないだろう。
古代エジプトでは、ブタは豊饒神の獣であり太母としてのイシスおよび神ベスの聖獣であったが、悪神セトのテュポンの相を表す悪の動物であるともされていた。後にエジプト人はブタを汚れた動物と見なすようになり、通りがかりにブタに触れるようなことがあると、人々はすぐに服を着たまま川に飛び込んだという。
ヘブライ人もブタを不浄の動物と見なしていた。旧約聖書には「豚を食べてはならない」(レビ記)、「豚はあなたがたにとって汚れたものである」(申命記)、「美しい女に慎みが欠けているのは豚が鼻に金の輪を飾るようなもの」(箴言)など、ブタに関する禁忌の記述がある。偶蹄類ではあるが反芻しないブタは、ユダヤ教徒にとって食べてはいけない動物であった。ユダヤ人に「お前はブタだ」ということは最大限の軽蔑を表す言葉になっている。
地中海世界を見渡してみても、ブタ肉を食べることはタブーであり、ブタを汚れた動物であるとする見方は変わらなかった。ギリシア神話には人間を獣に変える魔力を持つキルケがオデュッセウスの配下をブタに変えてしまうという記述が見られるほか、性欲にかかわる悪夢にはしばしばブタが登場させられる。ローマ帝国でも、ブタの雑食性は貪欲に、多産性は性欲と結びつけられ、それぞれのネガティブな象徴として定着していた。
キリスト教世界では、ブタは悪魔サタン・大食・好色の象徴であり、本質的に汚い動物であると見なされていた。もちろん、決して食べてはいけない禁忌の動物でもあった。旧約聖書と同様、新約聖書にも「真珠を豚に投げ与えるな。豚どもはそれを足で踏みつけたうえ、向きを変えて君たちをかみ裂こうとするぞ。」 (マタイ福音書)、「豚には悪霊が乗り移る」(ルカ福音書)など、ブタに対する敵意をあらわにする記述が見られる。
中世ヨーロッパでは、ユダヤ人とブタを一緒に描いた木版画が広く出回った。ブタとユダヤ人はセットになって迫害されたのである。そのユダヤ人の間でも、キリスト教徒に媚び入った裏切り者をマラノ(ブタ)と呼んで軽蔑していた。ブタはどこまでいっても嫌われ者の代名詞であった。さらに、ブタは魔女や淫夢魔(いんむま)の化身とも言われ、様々な災厄を背負わされて嫌われていた。現在のキリスト教世界においては食の禁忌こそなくなったものの、ブタには汚れた霊が宿るという観念は依然として残っている。
イスラム世界でも、ユダヤ教・キリスト教世界と同じく、ブタは不浄の動物である。コーランに「汝(なんじ)らが食べてはならぬものは、死獣の肉、血、豚肉…」と明記されているように、現在に至るまで食べてはいけない禁忌の動物でもある。「ブタを食べると性格が卑しくなり道徳や精神が破壊される」とも考えられているようで、ブタ食の禁忌は極めて厳格である。よって、ブタ肉はもちろん、ブタに由来する一切の食物を口にすることは禁じられている。2000年にはインドネシアで「味の素」の原料の一部にブタが使われているのではないかという疑惑が持ち上がり、国際問題にまで発展したことは記憶に新しい。
仏教の世界では、ブタは「存在の輪」の中心にあって雄鶏・蛇とともに貪欲・肉欲・憤怒の三毒の象徴とされ、人間をこの世の幻影と感覚と再生に結びつける罪を表す動物であるとされた。ブタは飼い慣らされていない自然の本性を表し、飼い慣らせば有用ではあるが、やはり貪欲で不潔の象徴とされていた。
現在の中国・インド・東南アジアでは、ブタは価値のある家畜と見なされてはいる。とはいうものの、純粋な食用あるいは儀礼における捧げものとしての役回りしか与えられておらず、家畜以上のものでも以下のものでもない。中国では、トイレの中でブタを飼っている(人間の排泄物を餌として与えている)地方もあるほどである。例外的に、中国の占星術でブタは人のためによく尽くし良心的であるともされている位で、全般的にブタがプラスのイメージで語られることはない。
このように見ていくと、ブタの評価は総じて散々なものであり、マイナスイメージの代名詞として世界的に定着している。人類の歴史は、ブタ迫害の歴史でもあったのだ。
ユダヤ教・キリスト教・イスラム教に代表される一神教の人々は、「すべての動植物は人間に搾取されるために作られた」という世界観の中で暮らしている。多神教の文化圏ならともかく、彼ら一神教の文化圏では、人間が動物の姿にさせられてしまう、あまつさえブタの姿にさせられてしまうシチュエーションというのは人間否定以外のなにものでもない。特に、人間は神の似姿であると考えるキリスト教徒にとっては想像を絶する世界であろう。
したがって、人間がブタの姿に変えさせられてしまうという「千尋」の設定が世界的に受け入れられるかどうかは、ひとえに宗教的な寛容にかかっているといっても過言ではない。「千尋」の作品としての芸術性がいかに優れていようとも、人間がブタになるという宗教的なタブーを刺激するものであるならば、神および人間に対する冒涜として相当の反発を招いてしまっても不思議ではない。これは、単なるデザインの醜さから想起される嫌悪感とは次元が異なる反発であり、もしかするとブタを理由として「千尋」の上映が許可されない国が出てくるかもしれない。
もっとも、人間が動物一般の姿に変えさせられてしまうという設定なら、グリム童話など海外の子供向け物語でもよく見られるものである。ブタの宗教的な意味があまり強調されることなく、人間が動物にさせられえてしまう設定の一派生形として寛容的に受け入れられることを期待したい。
多神教の国・日本で制作された「千尋」は、世界人口の大半を占める一神教の文化圏で受け入れられるだろうか?世界中に蔓延するブタにまつわる様々なタブーを超克することが出来るだろうか?ブタは名誉を回復することが出来るだろうか?
ディズニーが、このあたりをどのように判断して世界展開を図るかが注目される。