前ページをご覧になっていない方は、まず「日付」というデータ型の説明があります。
まず、データ上の「日付」がどういうものか理解して下さい。
セル上の「日付」は書式に左右されて、和暦表示だったり、西暦表示だったり、月日だけだったりしますが、「日付」として認識されているなら数式バーには日本語版Excelなら「2000/1/1」という形式で表示されるはずです。
しかし、「日付」というデータ型の実体はこのような視覚的に「年」「月」「日」が認識できるようなものではなく、「シリアル値」というものなのです。
この点の説明を「年・月・日を指定し、その日付を取り出す」の先頭に用意しましたのでご覧下さい。
この点の説明を「年・月・日を指定し、その日付を取り出す」の先頭に用意しましたのでご覧下さい。
- 元の日付から「年」を算出します。(D2セル)
-
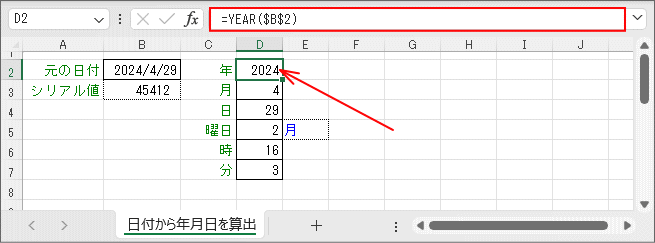
(画像をクリックすると、このページのサンプルがダウンロードできます)
「年」の算出には「YEAR関数」を使います。
関数 概略説明 YEAR関数 日付に対応する年を返します。 引数は日付(シリアル値)です。
- 元の日付から「月」を算出します。(D3セル)
-
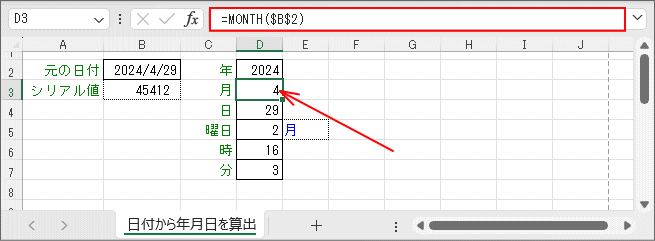
「月」の算出には「MONTH関数」を使います。
関数 概略説明 MONTH関数 日付に対応する月を返します。 引数は日付(シリアル値)です。
- 元の日付から「日」を算出します。(D4セル)
-
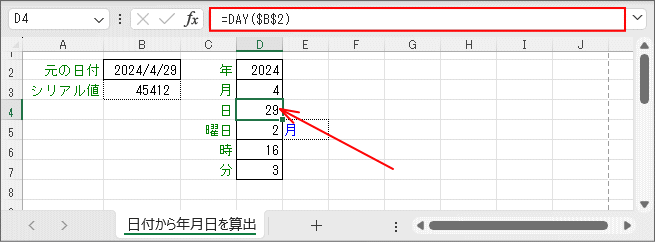
「日」の算出には「DAY関数」を使います。
関数 概略説明 DAY関数 日付に対応する日を返します。 引数は日付(シリアル値)です。
- 元の日付から「曜日コード」「曜日」を算出します。(D5セル、E5セルは曜日の文字)
-
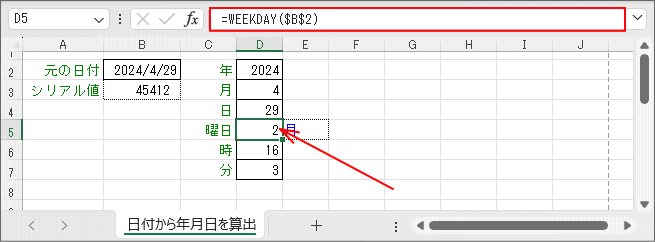
「曜日コード」の算出には「WEEKDAY関数」を使います。
関数 概略説明 WEEKDAY関数 日付に対応する曜日を返します。 既定では、戻り値は 1(日曜) から 7(土曜) までの範囲の整数となります。
引数は次の通りです。
① 日付(シリアル値)
② 週の基準(省略可、省略時は上記の既定になります)
数値で返された「曜日コード」を日本語の「曜日(文字)にしてみます。
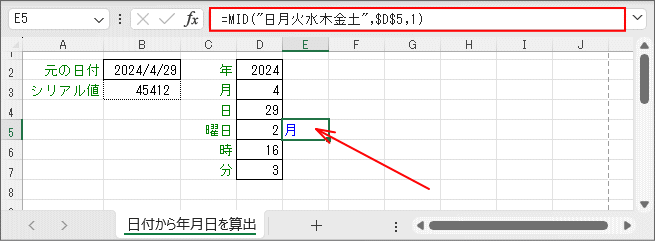
「日月火水木金土」の7文字を並べておいて、「曜日コード」に当たるn番目の文字を取り出す方法で、「MID関数」を使います。
関数 概略説明 MID関数 文字列の指定された位置から指定された文字数の文字を返します。 引数は次の通りです。
① 文字列
② 開始位置
③ 文字数
この画像では「開始位置(曜日コード)=2」「文字数=1」なので「月」が返ります。
※これは曜日の値を表示させるようにしていますが、書式上の操作で曜日だけ見えれば良いのであれば、単に日付を参照して、そのセルの書式をユーザー設定の「aaa」にするだけでも構いません。
- 元の日付・時刻から「時」を算出します。(D6セル)
-
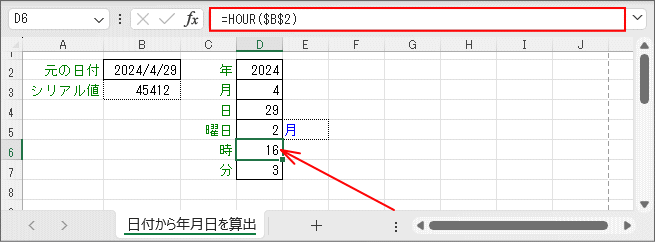
「時」の算出には「HOUR関数」を使います。
関数 概略説明 HOUR関数 時刻から時間の値を返します。 戻り値は 0(午前0時) ~ 23(午後11時) の範囲の整数となります。 引数は日付・時刻(シリアル値)で、日付部分は使用されません。
このサンプルの「元の日付」には「NOW関数」が入っており、ワークブックを開いた時の日時が算出された状態になっています。 書式で日付部分のみを表示させていますが、時刻部分も含まれています。
- 元の日付・時刻から「分」を算出します。(D7セル)
-
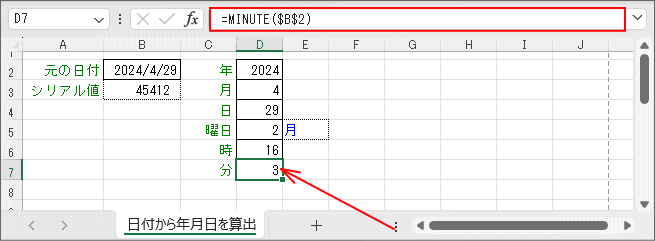
「分」の算出には「MINUTE関数」を使います。
関数 概略説明 MINUTE関数 時刻から分の値を返します。 戻り値は 0(分) ~ 59(分) の範囲の整数となります。 引数は日付・時刻(シリアル値)で、日付部分は使用されません。