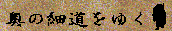
<白河の関>
(しらかわのせき)福島県白河市
旅行日 '96/07 '09/09
地図を見る(ここをクリック)
 元禄二年四月二十日(1689年6月7日)、芭蕉と曽良は現在の栃木、福島県境を越え、いよいよ陸奥(みちのく)へと足を踏み入れました。
元禄二年四月二十日(1689年6月7日)、芭蕉と曽良は現在の栃木、福島県境を越え、いよいよ陸奥(みちのく)へと足を踏み入れました。
陸奥の玄関口が白河の関。関址公園内の資料から抜粋させていただくと、
白河の関は7世紀頃、大化の改新による新政府によって陸奥国と下野国の境に設置されたものと思われる。旅行者を検問し、農民が諸国に流入することを防止する施設であった。(中略)古代律令国家の衰退と共に関としての機能はうすれ、その後は歌枕の関として多くの歌や句に詠まれ、文学の中に生き続けている。
能因法師(988〜1058?)の有名な歌。
都をば 霞と共に 立ちしかど 秋風ぞ吹く 白河の関
 右写真は旧・奥州街道、現在の国道294号線沿いにある境の明神。関東(栃木県)側と奥州(福島県)側各々に社が建ちます。ここが俗に白河関の跡だと思われていました。
右写真は旧・奥州街道、現在の国道294号線沿いにある境の明神。関東(栃木県)側と奥州(福島県)側各々に社が建ちます。ここが俗に白河関の跡だと思われていました。
300年前の芭蕉さんも、ここが白河の関だと思って来てみたところが・・、実はそうではないらしい・・。里の知識のある人にでも聞いたのでしょうか。真の関址と思われる所が二里(8km)ほど東にあるとのことを・・。
曽良と二人、2時間ばかり歩いて、やっと旗宿(はたじゅく)という宿場へたどり着きました。ここで一泊した二人は、翌日、宿の主人に場所を尋ね、かつて白河の関があった場所だと思われる神社を訪れます。なんの変哲も無い社(やしろ)が二社並ぶだけで、拍子抜けだったことでしょう。
 実は「白河の関」のあった場所について、当時は諸説がありました。この旗宿の地を「白河の関」のあった地だと断定したのは、寛政の改革で有名な白河藩3代藩主松平定信で、『奥の細道』の旅の100年余りも後のこと。芭蕉と曽良とにとって白河の関を訪ねるのは今回の旅の最大の目的のひとつ。しかし、関がどこにあったのかという肝心な事が当時の二人には分からない。「白河の関を通過したのだ」と無理やり納得して、北への旅を続けるのでありました(と、勝手に想像)。
実は「白河の関」のあった場所について、当時は諸説がありました。この旗宿の地を「白河の関」のあった地だと断定したのは、寛政の改革で有名な白河藩3代藩主松平定信で、『奥の細道』の旅の100年余りも後のこと。芭蕉と曽良とにとって白河の関を訪ねるのは今回の旅の最大の目的のひとつ。しかし、関がどこにあったのかという肝心な事が当時の二人には分からない。「白河の関を通過したのだ」と無理やり納得して、北への旅を続けるのでありました(と、勝手に想像)。
現在ですと白河の関までは、JR白河駅からバスで30分ほど(バス便僅少)。鬱蒼とした森のなかに土塁空濠などの遺構があり、古を偲ばせます。学術調査も進み、一方で関址に隣接して立派な公園も整備され土産屋なども立ち並び、休日には観光客や家族連れなどで(そこそこ)賑わいます。現代でこそ観光・行楽地ですが、芭蕉が旅した頃は、地元の人や一部の研究家に知られているだけの地と化した、寂しい場所であったに違いありません(これまた勝手に想像)。
 心もとなき日数重ねるままに、白河の関にかかりて、旅心定まりぬ。
心もとなき日数重ねるままに、白河の関にかかりて、旅心定まりぬ。
<現代語訳>心が落ち着かない日数が積もってゆくうちに、白河の関に差し掛かってようやく旅の心も落ち着いた。
長旅にでると、それまでの日常の暮らしと旅の暮らしとのギャップでしばらく、ちぐはぐな思いをすることがあります。私も芭蕉はここ白河の関まで来てようやく旅の生活に慣れてきたとのことでしょう。
この一文の言うところ、学生時代にずいぶんと無茶な旅を繰り返した私にも良く分かります。
続けて、曽良の句(↓)をどうぞ。
 <曽良の句>
<曽良の句>
卯の花(ウツギ)と言えば初夏を告げる花。これが咲くと鬱陶しい梅雨の季節も間近です。
卯の花を かざしに関の 晴れ着かな
(うのはなを かざしにせきの はれぎかな)

<句意>
- (この関を越えるとき、古人は冠をかぶり直し正装に改めたそうであるが、いま私には冠や着替えの用意はない。せめて道端に白く咲いている)卯の花をかざしにして(それを)関越えの晴れ着にしよう。
三省堂・新明解シリーズ「奥の細道」(桑原博史監修)より
先にも記したよう、芭蕉の『奥の細道』の目的の第一はこの“白河の関”を越えることでした。しかし本文中、ここでは芭蕉の句はありません。
司馬遼太郎(あまり好きじゃないけれど)『街道をゆく/第33巻(奥州白河・会津のみち、赤坂散歩)』(朝日新聞社刊)に、芭蕉の歩いた道をたどり、白河の関近辺を巡った模様が著されてます。私も参考にさせていただきました。

 遊行柳の頁へ
遊行柳の頁へ
スタート頁(地図)へ
ホームページへ |「奥の細道」目次へ | メールはこちら
![]()
 元禄二年四月二十日(1689年6月7日)、芭蕉と曽良は現在の栃木、福島県境を越え、いよいよ陸奥(みちのく)へと足を踏み入れました。
元禄二年四月二十日(1689年6月7日)、芭蕉と曽良は現在の栃木、福島県境を越え、いよいよ陸奥(みちのく)へと足を踏み入れました。 右写真は旧・奥州街道、現在の国道294号線沿いにある境の明神。関東(栃木県)側と奥州(福島県)側各々に社が建ちます。ここが俗に白河関の跡だと思われていました。
右写真は旧・奥州街道、現在の国道294号線沿いにある境の明神。関東(栃木県)側と奥州(福島県)側各々に社が建ちます。ここが俗に白河関の跡だと思われていました。 実は「白河の関」のあった場所について、当時は諸説がありました。この旗宿の地を「白河の関」のあった地だと断定したのは、寛政の改革で有名な白河藩3代藩主松平定信で、『奥の細道』の旅の100年余りも後のこと。芭蕉と曽良とにとって白河の関を訪ねるのは今回の旅の最大の目的のひとつ。しかし、関がどこにあったのかという肝心な事が当時の二人には分からない。「白河の関を通過したのだ」と無理やり納得して、北への旅を続けるのでありました(と、勝手に想像)。
実は「白河の関」のあった場所について、当時は諸説がありました。この旗宿の地を「白河の関」のあった地だと断定したのは、寛政の改革で有名な白河藩3代藩主松平定信で、『奥の細道』の旅の100年余りも後のこと。芭蕉と曽良とにとって白河の関を訪ねるのは今回の旅の最大の目的のひとつ。しかし、関がどこにあったのかという肝心な事が当時の二人には分からない。「白河の関を通過したのだ」と無理やり納得して、北への旅を続けるのでありました(と、勝手に想像)。 心もとなき日数重ねるままに、白河の関にかかりて、旅心定まりぬ。
心もとなき日数重ねるままに、白河の関にかかりて、旅心定まりぬ。


 遊行柳の頁へ
遊行柳の頁へ