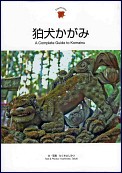続・弘前市周辺の狛犬(8)
鬼神社
さて、いよいよメインメニューその1です。
鬼沢村の鬼神社。ここの鬼伝説は非常にユニーク。昔、干ばつに困っている村人を見て、山から下りてきた鬼が「じゃあ、助けてやろう」と言って、用水路を開いたというんですね。それ以後、村の人たちは豊かな水を利用して農業にいそしめたと。そこで、鬼に感謝して、村の名前を鬼が造ってくれた水路で「鬼沢」とし、鬼神社に鬼を祀り、今も節分のときは「鬼はうち、福はうち」とやるんだそうです。
この鬼神社には5対の狛犬と不思議な石像?がありました。まずは
クイズ「これはなんでしょね?」を出題しましょう。

↑さて、これはなんでしょう???
……この神社、とにかく怪しすぎです。まず、鳥居が変。神社なのに卍マーク。↓

鳥居をくぐると、小さめの狛犬が3対いるんですが、2番目の狛犬がかなり傑作です。
名付けて「親子でびっくり狛犬」↓

この「親子でびっくり」の対になっているほう(吽)も不思議で、玉を手の甲にのせています。↓なんで?
確か、「円丈本」に、大阪の「砲丸投げ狛犬」というのがいましたね。

鬼神社本殿前には、巨大な狛犬がいます。どのくらいでかいかと言うと、このくらいです。↓

昭和6年の建立ですが、目玉が青く塗られています。なぜか、弘前周辺の狛犬は、目玉が青く塗られているものが多いのですが、なぜなんでしょう。
鬼=異民族という説があります。鼻が高い天狗や毛むくじゃらのなまはげなども、大柄な白人系民族の特徴を表しているのではないかという説ですね。青森には、「キリスト渡来伝説」がある戸来もありますし、弘前の保食神社には、鼻が高く目が青く塗られた「天狗狛犬」もいました。狛犬にもそうした「異民族」「鬼」の特徴を持たせているのでしょうか?

「吽」を後ろから見たところ↑尾の流れかたが阿吽で違う。

目が青く塗られていて、ぎろりと見下ろされている感じ。↑かなりの迫力。幼児なら泣き出してしまうかも。

特に尾の迫力が秀逸。↑この角度から見るとなかなか。
本殿には、巨大な鉄の農耕具が飾られています。鬼が使った農耕具ということで、鬼のおかげで農業ができるようになった村人たちの感謝の気持ちが表れているんですね。
また、岩木山北側は、古くから製鉄を生業としていた人たちが住んでいたそうで、もしかすると、「鬼」とは製鉄技術や用水路の設置技術を持った少数山岳民族のことだったのではなかろうか。

鬼神社本殿。↑巨大な鉄の農耕具が額に納められている。
さて、鬼神社にはまだ狛犬がいます。本殿裏、奥宮の前に小形の狛犬が一対。↓こんな感じです。
両脇を向いてしまっていますが、本来は横位置に置くべきものでしょうね。この狛犬も、目が青く塗られています。

Data:鬼神社(青森県弘前市鬼沢村):
その1:
ο建立年月・明治12(1879)年5月29日。ο石工など・不明
その2(親子でびっくり&逆玉のせ):建立年・石工など不明
その3(狛魚):ο建立年月・昭和53(1978)年旧3月29日。ο奉納者・藤田重次郎 80歳 建立
その4(巨大狛犬):ο建立年月・昭和6(1931)年旧5月29日。ο石工・赤石?誠磨、三浦慶次?郎
その5(奥宮):ο建立年月、石工など不明
ο撮影年月日・01年9月22日。
さて、次のページへ進む前に、
冒頭のクイズの答えを。
なんだか分かりましたか?
まだ答えが出ていない人は、考えてからこの下↓を見てくださいね。
なんだろな~?(考え中)
■答え■ 実はこれでした。

昭和53年に建立。奉納したのは藤田重二郎さん80歳。よほど魚が好きだったんでしょうか? 阿吽にはなっていませんが、参道の両脇に一対あります。狛魚?
う~~~む。
 「弘前市周辺の狛犬」次のページへ進む
「弘前市周辺の狛犬」次のページへ進む
 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ

『神の鑿』『狛犬ガイドブック』『日本狛犬図鑑』など、狛犬の本は狛犬ネット売店で⇒こちらです
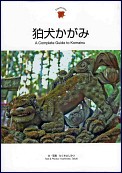 |
『狛犬かがみ A Complete Guide to Komainu』 全128ページ A5判 オールカラー(バナナブックス 2006年9月15日発売 1700円税込)
狛犬文化を体系的に解説・解明。全ページカラー。収録画像400点以上。日英両国語完全対応。日本が誇る狛犬文化・狛犬芸術の全貌を初めて全世界に発信! 詳細情報は こちら こちら
■アマゾンコムでの注文は こちらから こちらから |
|---|












 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ