サクソンの全面降伏まで、徹底的に戦い続けることを全軍に告げた。
ヘイスティングズの砦には、戦の反響について最新の情報が続々と
報告されて来た。
ハロルド王亡き後のイングランドの実力者は、ノーザンブリアの領主
モルカール伯と、マーシヤの領主エドウィン伯の兄弟であつた。彼
らは、ノルウェー王ハラルド・ハードラダがヨークを攻めた時、ハロル
ド新王の急援によって、ハードラダ苛烈王の野望を潰えさせ、ヨーク
をヴァイキングから護って貰った恩義があった。
しかしハロルド王とウィリアム公の決戦には、その恩返しをしていない。
いや、むしろハロルド王には手を貸さずに、自らの勢力の温存を計ろ
うとした。
保守的な田舎貴族であったモルカール伯とエドウイン伯は、ノルマン
ディのウィリアム公の器量や軍事力について、的確な情報を握ってい
なかった。ウィリアム公がハロルド王を斃したところで、北の大貴族で
ある自分達まで倒すことはできまいと、高を括っていた。
北の人間にとつては、テームズ河の南は他国同然に考えられていた
時代である。
彼らの妹アルドギーサは、ハロルド王と再婚していたが、それはハロ
ルド王の同情結婚であるとともに、両者の打算の上に立った政略結
婚であつた。無理をして南の海岸まで出向き、ウィリアム公と鉾を交
える必要はないと両伯は考えた。
ハロルド王の敗因の一つは、北の大貴族の軍事力を、自らの統制下
に置く時間的余裕がなかったことであろう。
ゴッドウイン家のハロルド兄弟が全滅した今、サクソン貴族には大物
はいなかったが、兎も角、イングランドの危機だとばかり、主だった諸
侯がロンドンに集まった。
「ノルマンの揉革屋の孫の野郎めが!このイングランドを蹂躪しおっ
て」
「罵ったって今更どうにもなるまい。それより、誰を新しいサクソンの王
に選ぶか」
口では大きなことを云って論評しても、この難局を自ら背負って立ち、
イングランドの礎になろうと申出る者はなかった。
新王は、国内随一のハロルド軍団を一蹴したウィリアム公の、次の標
的になるのである。
この時、カンタベリー大寺院のスティガンド大司教が進み出た。
彼は、庇護者であるハロルド王が戦死した後も、権力の座に執着して
いた。
「各々方。エドガー・ザ・エセリング王子を新王に推戴されてはいかが
かな。衆知の通り、王子は無力ではあるが、アングロサクソン王朝の
血統を受け継いでいる。他に適当な候補者があれば別だが」
と弁じて一座を見廻した。
「いや、異存はござらぬ。名案でござる」
「しかし、戴冠式はいかが致そうか。王冠や宝剣はエディス前王妃の
手許にあるが?」
「火急の場合だ。王冠はなくとも、我々の賢人会議で選ばれた者が王
だ」
こうしたスティガンド大司教の強い後押しによって、少年エドガー王子
の即位はすんなり決まった。体のいい贅(いけにえ)の小羊であつた。
だが、最大の問題は、ウィリアム公とどう対決するかであった。ロンド
ンで何回となく会議が持たれた。
ウィリアム公は、何時ロンドンに攻めて来るのか、皆目見当がつかな
かった。
落着かぬ気持で評定を繰返しても、なかなか妙案は出なかった。強
力なリーダーのいない、無意味な小田原評定であった。
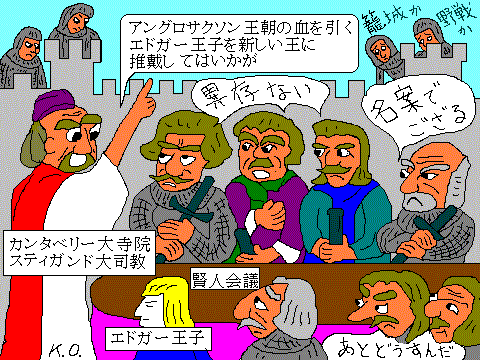
ウィリアム公は、豪胆にして細心だった。それは権力を握る者の必須
条件である。
彼は、残存するサクソン大貴族の勢力とどう対決するか、側臣ウォル
ターと相談した。
激戦に勝利を得た諸侯達の意気は軒昂(けんこう)たるものがあった。
戦には士気が必要であった。しかし、勝利のあとの軍略は冷静に決
めねばならない。ウォルターの情報と情勢分析が非常に役に立った。
「ウォルター、ロンドンの様子はどうか?」
「モルカール伯、エドウィン伯の軍団は、ロンドンに滞在しております。
ただこの両軍は戦意がなく早晩ロンドンを離れ北へ帰ると考えます。
スタンフォードで戦ったハロルド王の歩兵達は次々とロンドンに帰り、
市民軍に合流しております」
「戦力はどうか?」
「新王エドガーは、名目だけの王です。軍事指導力は全くありません。
烏合の衆ではありますが、ロンドン市内は戦意に溢れております」
「このまま直ちに攻撃することはどうか?」
「それは回避した方がよろしいでしよう。モルカール伯、エドウィン伯
の両軍を北へ帰らせるように策略中でございます」
「各個撃破か?」
「そうです」
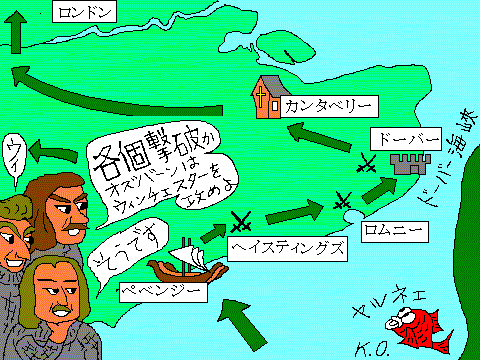
もともとウィリアム公とウォルターは、イングランド侵攻を長期戦と考
えていた。長期戦に勝利を得るためには、各個撃破の積み重ねこそ
必要なことを、少年の頃から骨身に沁みて会得していた。
ハロルド王とウィリアム公の軍団は、拮抗する勢力であった。ノルウェ
ー王ハラルド・ハードラダとトスティ卿の連合軍も、これに相応しいカ
を持っていた。ところが、ノルウェー軍団もハロルド軍団も二度の大会
戦を連勝することは出来なかった。二者は潰しあった。
漁夫の利は、ウィリアム公が占めた。
しかし、大会戦は一度で十分だ。
もしハロルド王が無疵でウィリアム公に立ち向かって来ているのであ
れば、彼は、ヘィスティングズの砦に陣を構えて、進退自在、和戦両
様の覚悟であった。それだけに戦略は予想以上に有利な展開となっ
たが、こういう場面でも浮かれずに冷静でいられるのが、ウィリアム公
の特徴であった。
ウォルターが言葉を続けた。
「母国ノルマンディからの補給、連絡、退路には、ドーバーが最も好
ましい港でしょう。
ケント地方を制圧するのに適した要害の地でもありますから、まず、
ドーバー城を手に入れる必要があります」
「ロムニィの町はどうする?」
「みせしめのために、徹底的に―――」
「この地には?」
「若干の兵を残し、沿岸警備にあたらせれば十分でしょう」
「わかった」
「ノルマンディからの増援軍2千名が、ワイト島に着いておりますから、
一軍を分けてこれと合流させ、前王妃エディスのいるウィンチェスター
城を攻撃させてはいかがでしょうか」
「よしっ。それにはオズバーンをあてよう」
信頼の厚いフィッツ・オズバーン卿が別動隊の司令官に任命された。
チュロルの騎士ハンフリー卿が、沿岸警備隊長としてヘィスティング
ズに残留し、この辺一帯の海岸線を守ることとなつた。
ハロルド王との大会戦では勝利を得たものの、まだサクソンの貴族豪
族はもとより、一兵も白旗を掲げてはいなかった。いや町民村人です
ら、じっと様子を見ていた。
大激戦から一週間、軍属として従軍して来た鍛冶屋達は、鎖帷子や
剣の修理に忙しく立ち働いた。負傷兵の傷の手当も十分できた。
「よしっ。全軍進撃!本隊はロムニィへ向う!」
どっと、喚声が上った。
時に10月20日、天爽やかに晴れ、サウスダウンズの森に、ようやく
秋の気配が深まりをみせようとしていた。
ヘィスティングズからドーバーまでは、約40マイル余りの行程である。
その途中、20マイル(32粁)ほどのところに、ロムニィの町がある。
砂丘が発達していったために、現在は内陸の村落となっているが、当
時は五大港の一つで、
海岸沿いの賑やかな港町であった。
ウィリアム公が、まずこの町に向かったのには理由があった。
9月28日の朝、彼の船団が無事ペペンジー湾の大上陸を終えた頃、
潮と風に流されて船団を見失った二隻の輸送船がこのロムニィの港
に辿り着いていた。しかし、彼らには悲惨な運命が待ちうけていた。
ロムニィの町民は、二隻の船に襲いかかって火を放ち、兵士、船員
約100名全員を虐殺したのである。
ウィリアム公は、この悲報に胸を痛めたが、ハロルド王との大会戦を
目前に控えて、どうすることもできなかった。
だが、その大会戦に勝利を得て、次の目的地ドーバー城へ向かう今、
彼の心は報復の炎で燃えていた。
側臣ウォルターには、別の、冷やかな計算があった。
戦争は、「喰うか、喰われるか」のいずれか一つである。勝つことが正
義となる。勝つためには、まず敵の気勢を削がねばならない。抵抗す
るものは徹底的に抑え、危害を加えたものには、それに倍する復讐を
加える方針を固めていた。
ウィリアム公はロムニィの町に到着するや蟻の這い出る隙間すらない
ように包囲して、町に火を放った。彼の部下が炎の中で無念の死を遂
げたことに対して、炎をもって報復したのである。老人も子供も全員焼
死した。
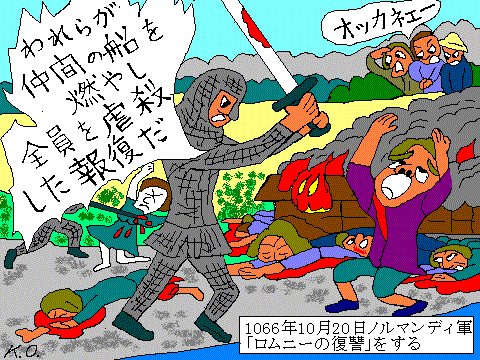
この恐ろしいニュースは、ウォルターの諜者達によって、すぐにイング
ランド全土に拡められていった。イングランド国民は震えあがった。
後に伝わる「ロムニィの復讐」であった。
近隣沿道の百姓達が、村長(むらおさ)を先頭に、臣従を誓うために、
幕舎を訪れて来た。
ウォルターの思惑は成功した。
ドーバーは、古くから「イングランドの鍵」と呼ばれてきた。海峡を隔
てたフランスの対岸カレーからは、僅かに30粁余りである。航空機
のない時代は、大陸からの玄関口はドーバーであった。「イングラン
ドの鍵」とは旨い表現である。
チョーク質の白い崖上の丘には、古く鉄器時代から集落があった。
紀元1世紀には、ローマ軍団渡来の軍港として栄え、当時としては
画期的な大燈台がその
丘に築かれた。ドーバー城内の聖メアリー教会に接して残っている
遺構が、その燈台跡である。この大燈台の灯を目当に、多くの船が
ドーバーを目指して集って来ていた。
当時、町の中心は丘の上にあった。
古代ローマの時代には、町や部落を城壁や柵で囲むのが通例であ
った。ロンドンも、ヨークも、カンタべリーも、シティ・ウォールと呼ばれ
る城壁で囲まれていた。
1064年までのドーバーの町は、城壁というよりも、丸太の柵をめぐ
らした砦といったほうが妥当であろう。ところが、ハロルド伯がノルマ
ンディの漂着から無事帰国して、直ちにドーバー城の補強に着手
したのである。
彼は、パイユー城の神殿でウィリアム公に臣従を誓った際に、ドー
バー城を自らの費用で頑丈に改築し、ウィリアム公渡来の際は献
上すると約束していた。
ハロルド伯は、ノルマンディに滞在している間に、各地の名城をつぶ
さに見学していた。
ノルマンの石造りの城は、サクソンの丸太の柵の比ではなかった。
ドーバー城は、ハロルド伯によって相当に補強された。ケント州の東
端にあって、ケント州を制圧する難攻不落の名城の趣があった。ハ
ロルド伯が、全軍団をこの丘に集結すれば、一兵すら上陸できなか
ったであろう。
ウィリアム公が、最短距離のドーバー上陸を回避し、比較的守りの
薄いと見られたペべンジー湾を上陸地点に選んだ最大の理由はこ
こにあった。
史書は、ドーバーの無血開城を伝えるけれども、秘話がある。
時の城代は、ヘイスティングズの北、アッシュバーナムの領主パー
トラム卿であった。
バートラム卿は、ハロルド王からドーバー城を後詰めの城として、僅
かばかりの兵で留守を護るように命ぜられていた。
ハロルド王は、ヘイスティングズで決戦がつかぬ場合には、ドーバー
城に退くことも考えていたからである。
パートラム卿は、大部分の家臣達をヘイスティングズの戦に送り込ん
でいた。二人の息子と、僅か十数名の手兵で 城を守る卿の許に、ヘ
イスティングズの敗報が届いた。
「父上、ウィリアム公はどう動きましようか」
「ハロルド王が戦死されたのだ。直ちにロンドンに向かうであろう。空
屋同然のこの城などには目もくれまい」
しかしながら、ウィリアム公東進との情報が入った。
「父上!やはりこのドーバーに――」
「ウム、ここは腹を据えてかからねばのう」
「直ちに兵を集めましょうか?」
「いや、もう遅い。それに、たとえ声をかけたところで、農民共は武器
をとって集まりはしない。我等で戦う他はあるまい」
ハロルド王が城代に見込んだ男である。泰然としていた。
ドーバー城には、ロムニィの悲報とともに、多くの難民が逃げ込んで
来ていた。町民達は生きた心地もなく、バートラム卿の出方に一命を
託していた。
卿は、町民の主だった者達を集めた。
「皆の者、よく聞くがよい。ロムニィの町は、ウィリアム公の手によつて
焼かれ、住民は、老若男女全て虐殺された。
もし、余が、この城に立籠って皆の者と共に抵抗すれば、同じ運命に
暴されることは目に見えている。さればとて、武人の余は、恩顧を受
けたハロルド王の仇も討たずに、みすみす降伏することはできぬ。
ウィリアム公は刃向かう者には厳しいが、臣従する者は罰していな
い。
そこで、余は昨夜ウイリアム公に使者を送り、『余は城を出て戦うが、
城に残る町民の命は助けて欲しい』と申入れたところ、公はこれを承
諾された。騎士に違約はない。
皆の者は、余が打出た後は、すみやかに大きな白旗を掲げ、城門を
開き、ウィリアム公を迎え入れるがよい」
「バートラム様、それでは余りに――」
「いや、これでよいのじや。騎士道というのはかようなものなのじゃ」
鳴咽が城内に拡がっていった。
翌日、ウィリアム公配下の槍騎兵軍団が、威風堂々と押し寄せて来
た。
「皆の者!さらばじゃ!」
と、バートラム卿は剣を抜き放ち、拍車をかけた。二人の息子と僅か
の家臣達も、馬に鞭を当て、丘を駈け下って、その大軍団に突入し
ていった。
ドーバーの市民達は、彼らの壮烈な死に、声をあげて泣いた。
ウィリアム公は、何の抵抗も受けずに、ドーバー城に入った。
「ドーバーの市民よ!余が、ノルマンディ公ウィリアムである。余は、
汝等の城代であったパートラム卿との約により、汝等の命を奪うこと
はしない。しかし、このドーバー城を当分の間、わが軍団の基地とす
る。よつて、全員直ちに、城外へ退去せよ!」
と、宣言した。
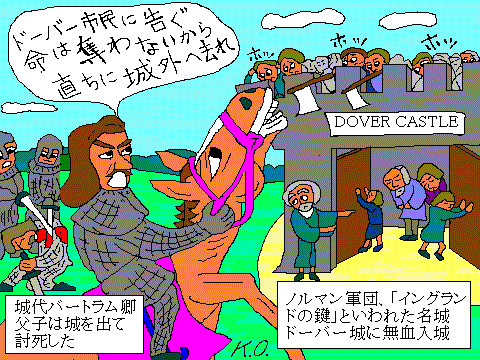
一命を保障された市民達は、先を争って城門を出て行った。
ウィリアム公は、直ちに部下に命じて、市民の家々を壊し、石垣を補
強し、城砦として縄張りからやり直した。彼は城作りの大工石工達を
も引率れていたので、築城工事は容易であった。
8日の間に、ドーバー城は驚くほど装いを新たにした。
今や、「イングランドの鍵」を完全に入手したのである。大陸との連絡
は容易となった。
全軍に、安堵の雰囲気が出た。緊張がほぐれた所為か、あるいは食
当りのためか原因不明の腹痛が流行した。
「気を引締めねばならぬ。なあウォルター」
「左様でございます。後詰めはできましたからカンタベリーへ本営を移
しましよう」
10月29日、ウィリアム公は、軍を教会勢力の拠点、カンタベリーに進
めた。
用心深いウィリアム公は、イングランド侵攻に際して、ローマ教皇の勅
許を入手していた。
軍団は、その時下賜された聖ペテロの旗職を行軍の先頭に高々と掲
げていた。
カンタベリーの大司教は、ハロルド王の恩寵を受けていた政僧スティ
ガンド師である。しかし、彼はずっと前からカンタベリーを離れロンドン
に居住していた。したがって、大本山に残っているのは、地位の低い
聖職者達ばかりであった。
彼らは、世俗の荒波には無力である。
カンタベリー大寺院は、何ら抵抗せず、ウィリアム公の進駐を認めた。
聖ペテロの旗幟、すなわちローマ教皇の威光は絶大であった。
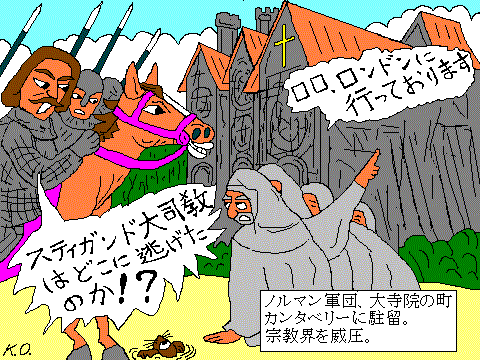
ウィリアム公は、暫くの間カンタベリーに滞在して、身心の休養を摂っ
た。不死身を誇ってきたウィリアム公であったが、胃から十二指腸にか
けて、激痛に襲われたからである。
一説には赤痢にかかったとも伝えられているが、神経性胃炎であった。
「ロムニィの虐殺」がまだ彼の心の奥底にわだかまりを残していた。
ウィリアム公は、聖職者に命じて、その犠牲者達の冥福を祈らせた。
第20章 征服の鐘音(その2)へ
いざないと目次へ戻る
「見よ、あの彗星を」Do You Know NORMAN?へ戻る
ホームページへ戻る