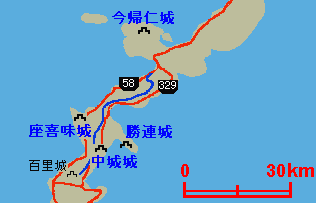
琉球では14世紀ごろに、北山、中山、南山と三つの勢力が対立した三山時代に島内にたくさんの城(グスク)が築城されました。その後、覇権を握ったのは中山の尚把志(しょうはし)王で、百里城を拠点に琉球国の礎を築きます。
明国との冊封体制(明国から琉球王として認めてもらう)により、明国との交易が活発に行われ、正使を迎え入れる儀式が百里城の御殿で行われました。
1609年、薩摩藩の侵略により薩摩の植民地時代を迎え、琉球では日本文化の影響を受けた独自の文化が栄えます。明治12年に明治政府は軍隊を琉球に送り、首里城の明け渡しを迫ります。これに屈した琉球王が城を出て、琉球国は滅び沖縄県が誕生しました。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |





