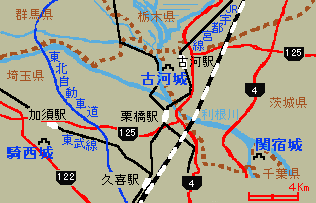
1455年鎌倉公方の足利成氏が、関東管領の上杉憲忠との対立により、古河へ落ち以後、五代130年に渡り、古河公方としてこの関東平野のほぼ中心に勢力を伸ばしました。
五代目の義氏に跡取りが無く、娘の氏女が喜連川の小弓公方足利国朝に嫁ぎ、喜連川公方が起こり維新まで続くこととなります。5千石程度の家ですが、参勤交代の免除、御三家、大々名との同席など、別格な待遇を受けたということです。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |
古河公方の城
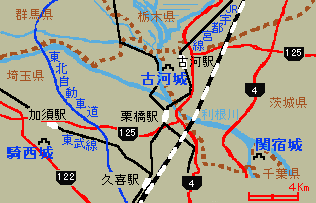
1455年鎌倉公方の足利成氏が、関東管領の上杉憲忠との対立により、古河へ落ち以後、五代130年に渡り、古河公方としてこの関東平野のほぼ中心に勢力を伸ばしました。
五代目の義氏に跡取りが無く、娘の氏女が喜連川の小弓公方足利国朝に嫁ぎ、喜連川公方が起こり維新まで続くこととなります。5千石程度の家ですが、参勤交代の免除、御三家、大々名との同席など、別格な待遇を受けたということです。
1つ前に戻る ホームへ戻る
鴻之巣館 古河城
|
所 在:茨城県 古河市 鴻巣
地図[MapFanWeb] 交 通:JR宇都宮線 古河駅 バス10分(総合公園内) 種 別:中世 平城 古河藩主の土井利勝が桃木を植林した庭園が総合公園として残っており、南端の鴻之巣に上写真の鴻之巣館跡(古河公方御所跡)があります。 古河公方が、渡良瀬川沿いの沼地に古河城を構えるまでの御所で、写真の碑の後ろにわずかですが、土塁の遺構が残っています。 古河公方は史料が乏しいため謎が多く、近年になって本格的研究が始まり、公方の歴史的役割が見直しされているとの事です。 隣には江戸時代初期の豪農の家が移設されており、茅葺き屋根の立派なこの家はなんと重要文化財になっていました。 古河城の城主はその後、北条氏など転々として最後は土井氏に収まり、最大規模に拡張されました。かつて渡良瀬川の沼地(中州?)に、観音寺曲輪、丸の内、三、二の丸、本丸と構えた広大な城で、御三階櫓もありましたが、今では河川工事により大部分が川底に沈んでいます。 下写真は出丸の遺構で、堀が少し残っています。 立派な古河歴史博物館もあり、古河藩の家老であり洋学者の鷹見泉石の出展を中心に、土井家、古河公方のものなどなかなか充実しています。 隣には鷹見泉石の家も残っています。近くの福法寺には、古河城の乾門が移設されていますがたいした門ではないです。 古河は城下町でありながら、日光街道の重要な宿場町でもありました。(本陣跡しかありませんが..) |
騎西城
|
所 在:埼玉県 北埼玉郡 根古屋
地図[MapFanWeb] 交 通:東武伊勢線 加須駅 南へ3km 種 別:中世 平城 別名、私市城とも呼ばれ築城は定かでないらしく、最初に歴史に登場するのは、深谷上杉氏が守るこの城を、古河公方の足利氏が1455年に攻め落としたのが最初で、その後は古河公方の前線基地となります。 北条氏治下時代には、成田氏が守るこの城を、上杉謙信が二回にわたり攻め、徳川時代には松平氏、大久保氏と一万石で入封したが、関ヶ原後は廃城となり陣屋が営まれました。 上写真は唯一の遺構である土塁です。土塁の上には私市城跡の碑が立っています。 下写真は本丸跡に建つ三層の模擬天守で、かつてこのような天守は無く平屋の屋敷がせいぜいのようです。 このあたりは沼になっていたらしく、それなりに要害になってたみたいですね。 土塁近くの真新しい道路を敷く工事の際に、障子掘りの遺構が出てきたらしく、看板で紹介していました。その辺の資料は、模擬天守の資料館に行けば展示されているんじゃないかな? >休館だったので私は入場していません。 |
関宿城
|
所 在:千葉県 東葛飾郡 関宿町
地図[MapFanWeb] 交 通:4号線バイパス菱沼の交差点を東に、関宿橋を渡る 種 別:中世〜近世 平城 1457年に古河公方重臣の簗田成助が、この地に最初に築城し以後、古河公方の前線となり、北条の支配のあと徳川時代となります。 徳川時代になって、利根川本流を太平洋へ向け、江戸川を合流させる河岸工事が行われました。(詳しい内容が、千葉県立関宿城博物館に展示あり) 江戸への船運管理の拠点として重要視され、船関所が設けられた関宿藩には、歴代の譜代大名が入封しました。 上写真は関宿城跡の近くの土手に建てられた模擬天守で、千葉県立関宿城博物館として、利根川の治水、船運産業の歴史の展示、関宿藩についての展示があります。残念ながら、古河公方に関しての展示は一切ありません。(本当は”古河公方の城”には、ふさわしくないんですけど..) 関宿城には、江戸城の富士見櫓を模した御三階櫓があったそうで、この模擬天守もコピーして建てたみたいですね。 下写真は博物館近くの土手の下にある、本当の関宿城跡です。 小さい土塁に囲まれた広場に、関宿城址の碑があります。この土塁に御三階櫓が建っていたかどうかは分かりません。 古河城といい関宿城といい、今では河にバカでかい堤防があるので、沼地などなくなってしまいました。当時はそれらの沼地を、そのまま水堀に利用したと絵図から推測されます。 |