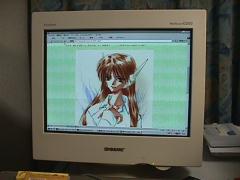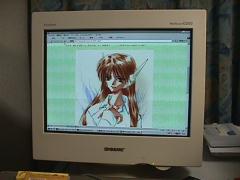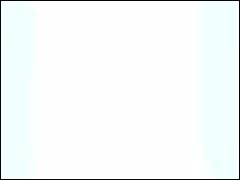SONY CDP-G200J
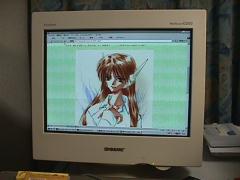

1999年の7月に発売されたSONYの低価格17インチモニターです。最近流行の完全フラットタイプで、SONYが独自に開発したFDトリニトロン管を採用しています。
私にとってはiiyama A702から乗り換えとなりますが、価格や性能面から最も競合する製品であるにも関らず、実際の使用感ではかなり違いがあるなと感じました。
実際、SONYのモニターは初めてというのもある訳ですが、その点も踏まえての相違点などを独自の観点から述べてみたいと思います。
SONYのモニターといえば「トリニトロン」と想像される様に、その名称は従来からのフラット管に対する高画質のイメージを常に確立してきました。
大勢を占めるフラット管に対し、垂直方向が完全に直線、従来のフラット管が持つシャドウマスクによる球点表示に対して視認度の良い長方点表示、さらにはそのドット(点)ピッチ(幅)をより狭く取れるアパチャーグリル方式の採用と、見ただけでその高性能さを実感出来るトリニトロン管は、やがて標準となるだろうグラフィカルユーザインターフェース(GUI)の示唆的存在であった事もまた事実です。
それはGUI表示が未だ釈明期であった時代、Apple社が逸早く自社の13インチモニターにトリニトロン管を採用し、手軽な販売価格もさる事ながら、その表示内容の秀逸さ/素晴らしさを広くエンドユーザーに知らしめた事からも伺えます。
その後、その優位性に気付いた三菱は同じアパチャーグリル方式を用いたダイアモンドトロン管を完成させるに至るのですが、登場したばかりの当時の表示内容はお世辞にも素晴らしいとは言えず、むしろ技術的に馴れていなかった事によるデメリットが目立つ(線の崩れ等)内容だった為に、それまでトリニトロン管を使い続けていたユーザにとって、登場当時のダイアモンドトロンは物笑いのタネでしかありませんでした。
しかし、そうした技術的問題も時間と共に解決し、今では1ガン(トリニトロン)/3ガン(ダイアモンドトロン)のハードウェアの違いはあるものの、その表示性能はほぼ拮抗するレベルにまで達しつつあると言えます。
そうした両者の次の目標は管面の完全フラット化であり、松下電器が世に初めて製品を投入したのを皮切りとして、ダイアモンドトロンもいち早く同じフラットモニターであるダイアモンドNF管を開発/発表。安定した大量生産によるOEM化の促進にて、モニター市場ではもはやスタンダート的なポジションを占めつつあります。
無論、SONYとしてもこの状況を黙ってみつめていた訳では無いのでしょうが、歩留まりの影響からかFDトリニトロン管の出荷はあまり思わしく無い様で、これまでの様にトリニトロン管をOEM製品化しているモニターメーカーにおいても、FDトリニトロン管を用いた製品は現在まで(99年8月)には1台も出ていない事から、完全に出遅れてしまっている感は否めません。
こうした現状となっては、FDトリニトロンの存在意義はもはや無いと考えるべきでしょうか?
私がそう聞かれたなら、多分「いや、そんな事は無い!」と応えるでしょう。
自ら購入したSONYモニターはこのG200Jしか無い私ですが、これまで長々と述べてきた中での「守るべきブランド」としてのSONYの意気込みをこの製品から十分に感じられる点がその大きな理由です。
CDP-G200Jは、数あるSONYモニターの中で最も低価格帯な製品です。
SONYの場合、製品の分け方として、その頭がCDPで始まるものは「より価格を抑えて最新技術を投入した製品」であり、その頭がGDMで始まるものは「民生品の中でもプロ用途を対象とした高級機種」と2種類に分類されていますので、多くのエンドユーザに購入される条件が一番揃っている製品とも言えるでしょう。
さらにCDP-200Jの様な従来型モニターは、今後の主流である液晶モニターの影響を価格面からもモロに突き上げされている存在であり、それだけに「安かろう悪かろう」の側面が最も出やすい(笑)製品とも言えます。
オープン価格で販売当初は6万弱を想定していた様ですが、実際には5万を切る所が多く、中には4万台前半にて販売している所もある様です(私はヨドバシカメラ新宿店で47,800円にて購入しました)。
それだけに、実際手にするまでは「かなり手を抜いた作りじゃないか?」とも邪推したのですが、実際にその予想は半々という感じでした。
一言で表すと、「SONYらしく、見た目を損なわずに手を抜いている」と言った感じでしょうか。
これだけで「ああ、成る程」と思われた方は、かなりSONY製品に馴れ親しんでいると言えると思いますが(笑)



フロントパネルのスイッチ類は非常にシンプルです。メイン電源用のスイッチ、全ての設定をクリアするリセットスイッチ、画面の調整等、モニター全般の調整をするメニュースイッチの3つしかありません。
こうした部分は本当にSONYらしい手抜き(笑)の成果であり、iiyamaのA702H同様、少ないボタン数で最大限のオペレーションが出来る様に(俗に言う「鉄人28号のコントローラー状態)工夫されています。
今回、こうしたスイッチ類を前面パネルにあえて納めなかった理由がよく判りませんが、単にデザイン面を考慮した結果(フラット感をより出す為?)なのでしょうか。だとすれば、正直これは頂けません。
特に電源スイッチは小さくて押し難く、質感も見た目よりかなり安っぽいものに感じました。ON/OFFの感触もあまり良くありません。この点はiiyamaのA702Hの方がはるかに質感も高く、安定しています。
また、特にユニークと思ったのがメニュースイッチでした。写真からも分かると思いますが、モニター下部に下向きに取りつけられており、モニター正面からは目立ち難いポジションとなっています。ボタン自体は直ぐ手前に配置されているので、操作が奥まってやり難いという事はありませんが、全体的にグラグラした感じでこれも操作性は決して良いものでは無いと言えます。
さらにこのボタンは、ゲーム機によくあるマルチファンクションのコントローラーに似た感触を持ち、実際その様な操作にて各種機能が呼び出せる様になっています。

メニューボタンは上下左右の4点とボタン全体を押した時の1点計5点の接点構成/1ボタンとなっており、4点接点のいずれかの場合はブライトネス/コントラストの設定が行えます。
これら設定は次に説明するメニュー画面上からも行えますが、比較的頻繁に使う機能だけにそうしたメニューを経由しなくて済む点からも便利な機能です。
このメニューが表示されている時は、先の4点はブライトネス/コントラストの設定モードとなります(一目瞭然ですね)。

メニューボタン全体を押した場合、左写真の様なメニュー画面が表示されます。
画面の調整項目は以下の通りです。
コントラスト、ブライトネス、水平位置、水平サイズ、垂直位置、垂直サイズ、糸巻歪み、台形歪み、平行四辺形歪み、弓歪み、傾き(回転)、水平コンバージェンス、垂直コンバージェンス、モアレ補正、消磁
水平同期周波数:30.0〜96.0kHz
垂直同期周波数:48.0〜120.0Hz
この他、モニター情報関係としては、
色温度調整(デフォルト、カスタム)、OSD水平位置、OSD垂直位置、周波数表示、言語選択(9ヶ国)、リセット
などがあります。
iiyamaのA702Hではそれぞれページ毎に各機能がまとまってという感じでしたが、このG200Jではトップメニューから目的の機能が項目として選択出来る仕様となっている為、いずれの調整機能も少ない手順で呼び出せる点ではこちらの方に軍配が上がります。
さらには、A702Hで問題だった現在の解像度や水平垂直同期周波数の表示も、このメニュー表示時に同時に表示されるので便利です。ゲーム仕様ボタンでのオペレーション方法としては十分納得出来る内容と言えるでしょう。
また、他社には無いユニークな「ヘルプ」機能というものがあり、モニターの問題からその解決(調整)方法をWindowsのヘルプ形式で教えてくれるものです。初心者にとっては優しい機能だと思います。
未調整での表示内容については、A702Hと違い若干の調整が必要でした。私のモニター固有の問題だと思いますが、1024×768にて若干の台形歪みがあり、垂直方向にコンバージェンスズレが見られた程度のものです。いずれも調整可能の範囲内の問題でした。
画面歪みの程度としては比較的軽いものですし、予想以上に初期調整は成されているなと思います。
さて、恒例となりましたが、これまでの簡単な紹介に加えて、実際に画面を見て感じた点を箇条書きにて紹介していきます。多くの方にとって長々と本文を読まれるよりも、この部分だけ読まれて「ああそうか」と思われる方が時間の節約かなあと思いつつ、以下の通りです(笑)。
良い点
- 発色/コントラストの秀逸さ。画面再現性の高さ。
- 上記に加えて価格の安さ。5万以下でこれだけの表現能力を持った17インチが買えるとは驚き(笑)。
- 中心部0.24mmAGピッチによる表示能力の高さ、絵や文字がクッキリと見易い。
- ハイコントラストARコート。従来ARコートの発展型。昔はこの価格帯ならシリカコートが....(^^;)。
- A702H同様、歪み感の少なさ。以前使ったA702Hよりトータルで少なく感じた。
- 色温度の正確さ。左右縁部分で若干目立つが、殆ど気にならないレベル。
- 一年間の出張修理(実際にはメーカー引き取り/搬入)サービス。メリットとしてはかなり大きい(^^)
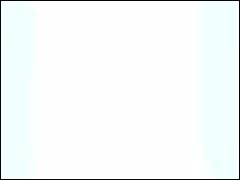
実は、今回もこのモニターを通電するまでは、色温度による差が多少は目立つレベルで存在するのではと少し心配していたのですが、その画面を見た瞬間、そんな杞憂はあっという間にふっ飛んでしまいました。
実際には右図に示す通り、左右の縁に沿って青にシフトする形で色温度の違いが直に見い出せたのですが、画面の半分が赤黒く色変わりしている事例から比べれば殆ど変化が無いと言ってもよい位のレベルであり、同価格帯のモニターの中でもかなり正確な色温度特性を有していると言えます。
余談ですが、これまで私が見てきた17インチモニターではかなりな確立で先のA702H同様の色温度特性を持つものが多かっただけに、このメリット一点だけにおいてもG200Jは買いと言っていいでしょう(笑)
悪い点
- 入力が1系統しか無い。価格的に仕方ないのかもしれないが、A702H同様2系統にして欲しかった。

販売価格面から仕方ないのかもしれませんが、その表示品質から言わせて貰うと1系統では勿体無い限りです。
どうしてもという事ならモニター切替機を使う手もあるにはありますが、接点が増える関係から画質が落ちる点は否めませんし、今後DVDやビデオキャプチャー専用表示やビデオカードのVGAマルチ出力化を考えると2系統入力はむしろ必須と言えるのではないでしょうか。
SONYモニターでどうしてもそれを望むのであれば、現状ですとGMD-F400しか無い(型落ち機種は省く)のも辛い所です。
スペースに余裕がある人であれば、もう一台モニターを購入して横に並べるのが方法としては一番良いのかもしれませんね(^^;)
さて、駆け足でCPD-G200Jを紹介してきましたが、如何でしたでしょうか?
今回、購入値段の安さもあって、実際に画面をきちんと見るまでは大して期待もしていなかった(店頭でチラと見た程度でしたので)のですが、実際に自宅に搬入してその画面を見た瞬間「これは違う!」とピンときた程、A702Hとの絵作りの違いをはっきりと認識させられました。
SONYのこうした製品は、昔からの傾向としてパッと見を派手に見せる傾向にある訳ですが、ご多分に漏れずこのG200Jもその傾向を多分に含んでいると思います。
中にはこうした鮮烈で明瞭な画面は「目が疲れる」と感じられる方もおられる様ですので必ずしも万人向きという訳では無いのかもしれませんが、少なくとも店頭でA702HとG200J双方の画面を比べた時に「..G200Jの方が値が少し張るけど、それでもいいかな?」と感じたのであれば、素直にそちらを購入した方が良いと思います。後から「やっぱりあっちにしておけば」と悔やむ事はまず無いと思いますので(笑)。