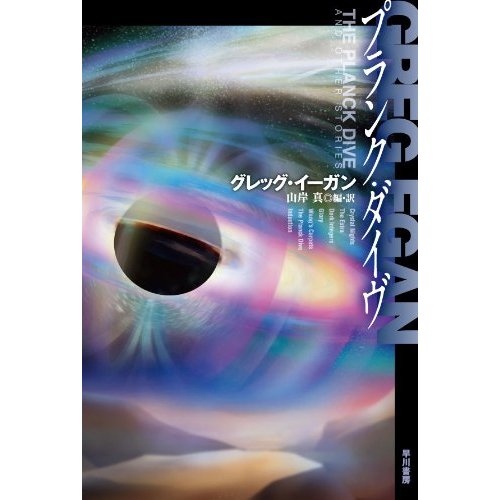
グレッグ・イーガン/山岸真 訳
『プランク・ダイヴ』 解説
大野万紀
ハヤカワ文庫
2011年9月20日発行
(株)早川書房
THE PLANCK DIVE AND OTHER STORIES by Greg Egan (2011)
ISBN978-4-15-011826-6 C0197
現代最高のSF作家の一人、グレッグ・イーガンの日本オリジナル短編集。これまでの中でも、とりわけハードSF度が高い短編集である。
というわけで、ハードSFにポイントを置いた解説を依頼され、大喜びで引き受けたのだが、実際に書く段になって、困ってしまった。イーガンのハードSFのアイデアは作品内容と密接に関係しているので、その解説をすることはそのまま作品のネタバレにつながってしまう。さらに筆者は確かに理系の出身でハードSFが大好きではあるが、科学の専門家ではなく単なる科学好きにすぎない。イーガンの作品に描かれる最先端の科学や数学について語るには全く力不足だ。何といってもイーガンの科学はとても本格的なものなのである。それをきちんと語ることなどとてもできそうもない。
そこで、収録作のそれぞれについて、科学的な解説というのではなく、一人のSFファンとして面白いと思ったポイントを語ってみようと思う。とはいっても、どうしても作品内容に触れないわけにはいかないので、読者のみなさんへは警告です。
以下の文章には作品のネタバレを含む部分があります。本文をお読みになった後でご覧になることをお勧めします。
でも、イーガンの作品を読んで、ぼくのようにわくわくしながら面白がる人も多いのだけれど、同じSFファンであっても「難しくて何が書いてあるのかわからない」と投げ出す人がそれ以上に多いのも事実だ。
大森望さんは『ディアスポラ』の解説で「わからないところはばんばん飛ばす」という読み方を勧めている。それはその通りで、ぼく自身もわからないところは飛ばし読みしている。確かに長編はそれでいいのだが、短篇だと大まかなストーリーしかわからず、途方に暮れてしまう場合もある。やっぱりそれではもったいないと思うのだ。
以下の文章がその助けになるかどうかはとても心許ないのだけれど、一個人の感想として、こういう読み方ができるという参考になればと思う。興味がわけばネットで検索するなどして調べてみてほしい。現代の科学の深さと広がり、それがSF的想像力にどう結びついているのか、細かいところはわからなくても想像が膨らんでいくのではないだろうか。
「クリスタルの夜」
近未来。主人公の男は全く新しい結晶ベースのプロセッサを用いて、ヴァーチャル世界を構築し、そこで生命を超高速に進化させて意識を持つ知的存在を生みだそうとする。
ハミルトンの古典「フェッセンデンの宇宙」から繰り返されてきたテーマである。ヴァーチャル世界での進化も、外部からの進化への干渉も、加速された進化も、多くのSFで繰り返し扱われているものだ。
イーガンがそこに付け加えたのは倫理的な側面である。知的生物(例えソフトウェア存在であっても)を好き勝手に扱っていいのか。勝手にある種を絶滅させたり、進化圧を上げるために苦痛に満ちた環境を与えたり、つまり人間が神のような振る舞いをすることが許されるのか(詳しいいきさつは編・訳者あとがきを参照)。
ここではハードSF的な細部はさほど重要ではない。ただ、ポケット宇宙の創造は、最先端の宇宙論でも議論されている内容である。
「エキストラ」
これは本書の中でも最もわかりやすい話だろう。
自分のクローンに脳を移植して、新たな肉体に生まれ変わることにより、事実上の不老不死を実現しようとする話であり、SF的なアイデアとしてはごく普通の、古めかしさすら感じる作品である。因果応報のホラー的な作品として書かれており、倫理観についても常識的で、イーガンによくあるような大きな変化は描かれていない。
だがここでのポイントは、自分というものが、本当に脳というウエットウェアに局所的に存在しているのか、ということだ。さらにいえば、自分、自意識、アイデンティティとは唯一、一つだけのユニークな存在なのか、という問題意識がある。
イーガンの結論は、自意識は単純に脳だけで成り立つものではなく、また排他的でユニークな存在でもないというものだ。このテーマは彼の他の作品でも繰り返され、移植用クローンという意味で〈エキストラ〉という用語が使われている作品もある。
「暗黒整数」
数学SF「ルミナス」の続編である。まずは、抽象的な存在であるはずの数学が、逆に現実世界に影響を与えるというアイデアを理解、というか少なくとも納得しないといけない。でないと、本当に何を書いているのかわからなくなる。そしてわれわれが知っている数学体系とは別の数学、2+2が5になり、しかも首尾一貫した数学〈オルタナティヴ数学〉が存在するということも。そこからもう一歩、数学体系が違えば、それを基盤とする互いに両立しない別の現実世界が、こことは違うどこかに存在するということ。つまり多世界、並行宇宙の存在である。それはわれわれ自身の世界と同じ場所に存在するかも知れない。すぐそこにありながら、目に見えない、手の届かない幻の世界。
イーガンはその並行世界にインタフェースを持ち込む。〈不備〉と名付けれたそれは、まだ未確定な定理で、矛盾した結論を導くようなものである。それをどちらかの体系から証明すれば、矛盾は解消し、片方の体系が(そのローカルな局面においては)勝利する。逆に相手側から証明されればこちらの負けとなる。負けた場合、数学的な問題だけでなく、物理的なこちらの世界も最終的には消滅してしまうのだ。
すごいと思いませんか? 「ルミナス」を読んだ時、ぼくはこのアイデアにびっくりし、大喜びしたものだ。イーガンは、超巨大整数の問題のような、想像はできるが実際に計算したり証明したりするのは難しそうな(宇宙的な時間がかかりそう)問題を持ち出すことで、いかにもそれがありそうに思わせてくれる。
ストーリーはというと、まるでギブスン流サイバーパンクのパロディのような、アクションやギミックたっぷりのパニックSFとして展開する。〈暗黒整数〉という言葉も暗黒物質や暗黒エネルギーの数学版として面白い。舞台は現代なので、店で売っている安物のパソコンで宇宙間の存在を賭けた戦争を行うというのも、何だか楽しくなる。
「グローリー」
これはイーガン流のスペース・オペラといってもいい。古き良き宇宙SFのテーマを現代科学の言葉で語っているが、ハードSF的なガジェットと描写を除けば、ほとんど五〇年代のSFといっていいようなストーリーだ。
最初の五ページにわたり延々と続く描写は、相対論的時間効果を利用したプローブで恒星をぶち抜き、その向こうの惑星にナノマシンの構造体を作り上げるという離れ業を描いている。めちゃくちゃかっこいいのだけれど、ハードSFオタク以外にほとんど意味のないような描写だ。こういうことをやってしまうのが、イーガンの困った(嬉しい)ところだ。遙かな遠い未来の話なのに、超光速は登場しないことにも注目しておきたい。
異星人の遺跡で発見される未知の数学定理を記載したタブレット。それが、数式のような記号ではなく、可換な超立方体で、まさに数学的にコーディングされているというのも面白い。
本編ではイーガンが繰り返し描く、知識・情報の〈探求者〉というテーマも扱われている。さらにここでは、知識の探求を単純に賞賛するのではなく、その先にあり得る退廃と喪失についても言及されており、より深みを増しているといえるだろう。
「ワンの絨毯」
本編こそ、まさにイーガンのハードSFとしての面白さが爆発している大傑作である。後に長編『ディアスポラ』に(一部を削除して)そのまま組み込まれた。
〈ディアスポラ〉とは、民族集団がその本国から離散して暮らすこと。こちらでは長編版と違い、〈人間宇宙論者〉への批判のため、その反例を探すための探査の旅としてディアスポラが実施されたことになっている。
〈人間宇宙論〉とは、長編版では現れない観点だが、本編では重要である。宇宙論でいう人間原理を発展させ、「もし物質宇宙が人間の思考によって創造されたのであれば、それを仮想現実より上に位置づける特別な理由はない」というものだ。もちろん物質宇宙の方が人間より先にあったわけだが、すでにここまで進化した人間にとって、物質宇宙も仮想現実も変わりはないという考え方である。本編の主人公たちは、それに反対し、物質宇宙をより重視する立場だ。実際の宇宙に人間以外の(人間が作ったものではない)知的生命を見つけることで、それに反証しようとするのだ。だが、そこで見つかったのは〈ワンの絨毯〉だった。
というわけで、〈ワンの絨毯〉である。以下、本当にネタバレ大爆発です。
それはオルフェウスの海に住む巨大な海藻の集合体のように見える生物だが、実は全体が折り重なった一個の高分子だった。その表面は非常に複雑な構造をしており、それが〈ワンのタイル〉という数学的な構造をもっていることがわかる。検索すればわかるが、ワンのタイルというのは実際に存在する数学の問題で、ある規則に従って空間にタイルを並べる充填問題の一つである。さらにそれが〈万能チューリングマシン〉となっているというアイデアがある(このあたりになると、ぼくなどは「そうですか」というしかない。板倉充洋氏のサイトに詳しい解説があるので、参照してほしい)。
〈万能チューリングマシン〉とくれば、コンピュータである。つまり〈ワンの絨毯〉は自然にできた生体コンピュータであって、それがタイルの並びの成長によって毎秒何十億回もの計算を行っているのだ。しかもそれはほ乳類のゲノムと同様に、進化の過程によってプログラムされた、意味のある計算を行っている。イーガンはそれを理由づけるために〈カウフマン・ネットワーク〉という理論に言及している。そして一見単純に見えるその計算が、〈一千次元周波数空間の十六次元切片〉にフーリエ変換してみると(こういう専門用語がみな意味をもっており、イーガンのアイデアに対し、SF的なもっともらしさを非常に高い次元で与えているのだ)、そこは外部とは切り離されたコンピュータ上の〈シミュレーション宇宙〉であり、別次元の生物が存在していたとわかる。さらにその中にはイカと呼ばれる明らかに知性をもつ存在さえ!
この目くらめく論理展開と、皮肉。ちなみに、本編に〈シミュレーション宇宙〉という言葉は出てこないが、これは現実に議論されている多宇宙の考え方のひとつである。
要約してしまえば、他の惑星の海に絨毯みたいな生物がいて、実はその生物は生体コンピュータで、そのコンピュータの中に別の仮想現実世界があった、という話なのだが、それをここまで知的に面白く描き、さらに〈宇宙における人間存在の意味〉という、いわば小松左京的なテーマにも肉薄している。これぞ現代SFの到達点のひとつだ、とぼくは思うのである。
「プランク・ダイヴ」
本編も「ワンの絨毯」と同様の背景をもっているが、とりわけハードな作品で、これぞイーガンのハードSFの最右翼といっていいかも知れない。
一番のポイントは、どんな素晴らしい発見があってもその情報を持ち帰ることのできないような探求(ブラックホールへの突入)を行うことの意味だ。本人しか結果を知ることのできない実験。決して他者による検証のできない、探求者の自己満足にすぎないような実験を行うことは、果たして科学といえるのか。そこにどんな意味があるのか。
もちろんイーガンは科学的好奇心を、探求心を断固支持する。誰にも結果を知らせることができなくても、どうしても自分の目でそれを見てみたい。イーガンの読者なら、きっとそのことに同意するに違いない。
ただイーガンは、それに対立する軸として、露骨に戯画化された吟遊詩人を持ってくる。事実を伝えることができないなら、物語を伝えようというわけだが、これが何というか捏造されたネットのデマ情報のたぐいなので、あまり説得力がない。ここは〈物語〉というものを、SF的に、もっと真剣に扱って欲しかったと思うところだ。とはいえ、ここで描かれる父と娘の物語は、本編に小説としての奥行きを与えている。
ブラックホールはSFのガジェットとしてすでに手垢の付いたものとなっているが、まだまだ科学的には面白く謎に満ちた存在である。ブラックホールにダイヴすると、事象の地平線の向こうでは時間と空間が逆転しており、外部の視点からは無限にそこに留まっているように見える。しかし内部から見ると、特異点を通り抜け、時空がカオス的に振動する様を目にするだろう。それは宇宙終焉のビッグ・クランチとよく似た光景だろう。
本編でダイヴするのはソフトウェア化された人格のクローンだが、その乗り物は物理的な存在であり、ナノマシン群によって構成される光そのものである。内部の時間ではどうしても有限時間で特異点まで行ってしまい、そこで空間そのものが押しつぶされてしまうのだが、プランク長(物理的に意味のある最も短い長さ)スケールでの時空の構造を知るためには、そこへ飛び込むしかない。もしかするとそこではほとんど無限の計算リソースが得られるかも知れない。だとすれば、思いがけない脱出の可能性すらあるのだ。
といったことが本編では物理学と数学の言葉を使って詳細に語られるのだけれど、専門家以外にはほとんど無意味だろう(イーガンのサイトへ行けば、コーディリアのブラックホール・ツアーをCGで見ることもできる)。だが本編のポイントが科学的探求心にあるのだとすれば、それをイメージや安易な比喩で語るのではなく、実際の科学の言葉で語ることは、とても意味のあることだろうと思う。
「伝播」
今世紀の終わり。月面から二〇光年彼方の惑星へとプローブが発射される。それは「グローリー」の冒頭で出てくる遠い未来のプローブの、原型となるものといっていい。光速に近い速度で飛翔し、到着先の恒星で再調整した後、目標の惑星でナノマシンを放出し、そこでロボットを組み立てる。その百二十年後、今度はそのロボットに、人間の意識を送信し、ダウンロードする話が持ち上がる。ソフトウェア化されてはいても、人間の目でリアルタイムに異星を眺めようとするのだ。
ハードSF的アイデアは「グローリー」とほとんど同じだが、ここでは未知への挑戦を絶え間なく続けていきたいとする〈探求者〉の思いがとてもストレートに表現されている。あまりにもストレートで単純に見えるかも知れない。でもぼくはそこに共感する。
この原稿を書いていた時、小松左京さんの訃報を聞いた。小松さんの本格SFには、イーガンと共通するような方向性があったと思う。もしお元気だったら、イーガンに負けないようなサイエンス・フィクションが書かれていたかも知れない。
2011年8月