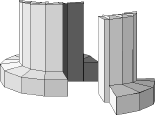「ええ、星野支折です。この夏は、私は目の回るような忙しさでした...
それにしても、この秋最初の仕事に、“インターネット時代の新文化創出”とい
う、たいへん重い、革新的な課題が回ってきました...うーん...どうしましょうか、
塾長、」
「そうだなあ...」高杉が、うなづいた。そして、ゆっくりと腕組みをした。「...実際
に、ネット社会では、どういう動きになっているのだろうか?」
「分かりませんねえ...」津田が言った。「専門ではないですから...しかし、まあ、
それはそれとして、この国の文化は、空洞化が起こっていますね...一見、一生懸
命にやってはいますが、全体が白けてしまっています。文化勲章や叙勲などを見て
も、何のことか意味がわからない。まあ、こんなものは、止めてしまえという意見さえ
聞こえてきます...」
「はい」支折が、うなづいた。
「その一方、インターネットの中で、新しいネット文化が成長しつつあります。今は、こ
うした新文化へ移行する、過渡期なのではないでしょうか?」
「うむ、」高杉は、静かにうなづいた。「確かに、そうした状況だと思う...」
「さて、問題は、インターネットの中です。
インターネットの中の膨大なコンテンツ(contents/内容物、本の内容)に、どうやって知的
所有権を認め、価値を判定し、代価を与えるか...ここが、新文化展開の大きな問
題点になってくると思います」
「そうだね。まさに、そこだと思う。このままでは、上のステージへ飛躍できない」
「はい。我々の、この “人間原理空間の仕事”
にしてもそうなのですが、いくばくか
の代価を得るのが非常に難しい。まあ、大勢の人達が、ただそれが好きだということ
だけで、無償で頑張っているのが現状だと思います。
まあ、商売が好きな人は、水を得た魚のようなところもあります。しかし、こういう
人達は、いわゆる実業家肌なのです。文化や芸術の本流は、むしろその対極にある
ような人達によってが支えられているわけです。
また、何よりも、伝統文化を経済原理や実業家のソロバンで動かしてきてために、
日本文化の本質が空洞化してしまったわけです。また、伝統文化の安易な保護政
策によって、それが単なる既得権になってしまい、国民と乖離してしまっているもの
もあります」
「こうした現象は、医療活動と病院経営の関係と似ているねえ。今問題なのは、文化
と経済の関係だが、こっちの方は、命と経済の関係だ...いずれにしても、経済が
前面に出すぎると、数値で扱いやすいが、“物欲”が勝ってしまう...」
「そこで...現在の状態では、インターネット文化はですねえ...“質・量”ともに、
限界だと思うのです。新しい日本の文化を創出し、その日本文化を大きく飛躍させる
には、ここに、まさにこの場所に、新しい“新世紀・ルネッサンスのシステム”が必要
だと思うのですです...」
高杉は、深くうなづいた。
「...一方、既存のルートで流れている書籍や各種のディスクは、しっかりと代価が
支払われているわけですよ...まあ、だから、今は過渡期だと言ったわけです。し
かし、いずれにしても、インターネット社会は、もう後戻りは出来ないでしょう?」
「そうだね。車が、個人機動力としてなかなか手放せないように、インターネットも個
人情報発信力として、もう国民は二度と手放さないだろうね。文明の発展のベクトル
も、まさにこの方向にあるのだし...」
「しかし、このままでは、なかなか革新的なものが出てこないですね。次のステージ
へ変容するには、ボランティアだけでは無理なのです。おそらくは、それが分かって
いると思うのですが、なかなかやろうとしない...」
「うーむ...」高杉は、ゆっくりと腕組みを解いた。「まさに...過渡期なのだろうね
え...ここをどのように加工していくか...まさに、現在の日本としては、千載一遇
のチャンスだと思うがね」
「すでに、何か、大きな問題が起こっているのでしょうか?」支折が、津田に聞いた。
「もちろん、矛盾は広がっている...まだ、コンテンツの“価値基準”が確立されてい
ないわけだから、世界中で、大勢がただ働きをしている...大儲けをしている人と、
ただ働きをしている人が、混在しているのが現状だと思います...
まあ、人生観、価値観の相違もあるでしょうが...素晴らしい学術的なデータをた
だで公表している所もあれば、がっちり稼いでいる所もある。莫大な資金と労力がか
かっているのなら、それに報いてやるべきですよ。報いてやらなければ、いずれパン
クしてしまいますし、第一不公平です。同じように、社会的に貢献をしているわけで
すからね...」
「でも、ただ働きと言っても、好きなことをしているという、もう1つの側面もありますよ
ね。スポーツは、体を激しく動かすけど、お金は求めないわけでしょう...」
「まあ...欲望の1つを満たしているとは言えるね...しかし、どうも、このままでは
うまくない。
一方では、旧来のシステムで、それが商売になっているわけだから。そ
れに、誰だって、プロ・スポーツの選手のように、それでお金を稼ぎたいわけだしね」
「うーん...はい...」
「何か、いい知恵がありますか、塾長?玉石混合のインターネットのコンテンツに、価
値基準を導入し、代価を支払うというのは、容易ではないでしょうが...」
「うーむ...その前に、逆に音楽ソフトなどでは、インターネットの無断・大量コピー
で、喰われてしまっている側面もあるわけだ...ビデオなどの映像ソフトもそうなの
かな...これまでの旧来のシステムなら、相当に稼げるはずのものが、ただでバラ
撒かれてしまっている。これでは、クリエーター(創作者)はたまったものではないだろ
う。
しかしだ...旧来のシステムに依存しない、ネット・クリエーター達もまた、好きで
勝手にコンテンツを創作している状況に甘んじているわけだ。これはこれで、欲望の
一端を満たしているとはいえ、クリエーターは食べてはいけない。
それに、いま津田・編集長も言ったように、このままの状況では、ネット文化は質・
量ともに、次のステージへ飛躍することは出来ない。やはり、何らかの形で、一般的
なコンテンツに、それなりの代価を与えるべき段階に来ていると思う」
「うーん、」支折が、首を横にした。「このままでは、“旧来のクリエーター”も、“ネット
・クリエーター”も、食べていけないわけよね...」
「そういうことだね」津田が言った。「いずれにしても、ネット社会がさらに拡大していく
と、この矛盾は、いずれパンクします。それが分かっているなら、その前に、どうする
かということです」
「この問題は、結局、“著作権”の問題になるわけかな?」高杉が言った。「この間、
アメリカで、“ディズニー”や“インテル”が、著作権問題で大論争しているテレビを見
たが、」
「まさに、著作権の問題でしょうね...世界中を巻き込むような、著作権全般の問題
でもあると思います。しかし、別の種類の問題のような気もします。まあ...そうは
言っても、著作権の問題ですがね...」
「うーむ、」高杉は、うなづいた。「いずれにしても、権利を主張しなければならんわけ
だな。黙っていては、一文にもならんと、」
「うん、」支折が言った。「私たちにとっても、一番苦手な種類の問題よねえ、」
「そう、」津田が言った。「ともかく、問題は、現在の日本の状況です...文化の空洞
化、モラルの空洞化、政治の空洞化、経済の空洞化、これに、どう対処するかという
ことです」
「そういうことだね。ともかく、大きな展望の開けているネット文化に、どのように経済
システムを組み込み、これを育てていくか。ここに、日本の将来が、大きくかかわって
来ると思う...
この巨大容量の新しいネット文化を、いかに公正、透明、風通しのよいシステムに
していくか...ここに、日本の将来がかかっていると思う...」
「何とかしないと、ゆがんだ形で進化していく恐れがありますね。私は、それを最も危
惧しています」
「うーむ...“ゆがんだ形での進化”か...」
「もう一度聞きますけど、」支折が言った。「それは、日本で考える問題なのでしょう
か。それとも、インターネットだから、全世界共通のステージで考えるべき問題なの
でしょうか?」
「どうなのでしょうか、塾長?コンテンツを価値基準で評価し、クリエーターに代価を
支払うというシステム作りは、日本だけで可能なのでしょうか?」
「まず...日本という国があり、日本文化という枠もあるのだから、日本という国単
位で考えてもいいのではないかな。海外のコンテンツに対しては、その後で機が熟し
てから対応して行くという事でも...とりあえずは、やってみると...」
「なるほど...日本という枠の中なら、話はしやすいですねえ。それから、どうなりま
すか?」
「そうだねえ...まあ、“ネット内の価値評価システム”のようなものを創出できれば
いいのだが...それと、“ネット財団”ですね。代価を支払う財団...しかし、私は、
経済の方は明るい方ではないのでね。こういう場合は、どう作るわけですか?」
「うーむ...まあ、こういうケースだと...まず、インターネットを構成している基幹
産業が、財団を設立することになりますかね...そして、優良で有益なコンテンツ
に、代価を支払うということかな...面白いと思いますよ...
また、インターネットで商売している所から、“税金”のようなものを徴収してもいい
ですね。オークションや店などは、大いに儲かっているわけですから。つまり、そこか
ら上がってくる税収で、各種のネットを構成している必須なコンテンツに、富を再配分
するシステムです...
それから、もともと“国や行政”の関与もあるわけです。犯罪は当然、法の網がか
かってくるわけですし、サイバー・テロなどは、場合によっては軍事的対応になりま
す。ともかく、国や全国の行政機関も、ネット文化に相当な資金を投入してもいいは
ずです。
まあ、こうした意味では、実社会と同じですね。ともかく、新たに創設するネット社
会は、自由な社会として、のびのびとやって欲しいですね。一攫千金のような話も、
面白いですからねえ、」
「なるほど、」高杉は、かるく膝を叩いた。「それじゃあ、ニュース性の高いスクープ映
像なども、しっかりと審査し、それなりの代価を支払うというわけですね?」
「まさに、そのとおりです。ネット全体を統括する、財団を設立すればいいわけです
よ。そこで、犯罪防止なども強力に推し進め、道徳や倫理を復活することも可能だと
思います。
しかし、まあ、それは、ネット文化が花開いて、新世紀ルネッサンスが実を結んで
いけば、当然の果実になりますがね...」
「うーん...」支折がうなった。「そんな風になれば、いいですね。でも、コンテンツは
膨大な数になるんじゃないかしら。実際に対応出るのかしら?」
「まあ...」津田が言った。「とりあえずは、敷居を高くしておけばいいでしょう。そし
て、自己申告制にでもしておけば、コントロールは出来るでしょう。そして、ポイント制
にでもして、優れた検索エンジンやリンク集、貴重な学術的データや論文などには、
ポイントを重ねていけばいい。
まあ、最初はヨチヨチ歩きでも、いずれは膨大な機関になり、“日本文化の基幹的
な評価システム”に育っていくかも知れません」
「スクープ映像には、金一封よね!」支折が、体を揺らして言った。
「うーむ! いいねえ!」津田も、支折を真似て、体を揺らした。「我々の
My Weekly Journal でも、ぜひ金一封を出したいところだ!」
「ただ、その金がないわけよね、」支折が、上を向いて笑った。
「まあ、ともかく、」高杉が言った。「コンテンツの質を向上させるには、それに対して
それ相応の代価を支払い、“その価値に誠実に報いる”ことが一番だと思う。それが
正しいネット社会の姿だと思う。そして、そこに、“日本の将来像”も見えてくるのでは
ないかな」
「はい!」
「それから、いま津田・編集長が言ったように、My Weekly Journal だって、スクー
プに対して、金一封を出したっていいわけだ。そうした、“自由・公正・透明”な、我
々のネット社会を構築していきたいものだ」
「はい...小学生のコンテンツには、それなりの支援団体が賞を付けたっていいわ
けです。あるいは、ネット内の企業が、自社を宣伝するために、賞を作ったっていい
わけですから、」
「そう...」高杉は、窓の方を見て、明るく笑った。「シミュレーションをして行けば、話
はどんどん広がっていくものだな...まあ、本当にいいものかどうかは、さらに検討
を重ねていく必要はあるが、」
「はい。いずれにしても、まず、全体を取り仕切っていく、“ネット財団”が必要でしょ
う。そして、ここは、スピードが大事です。まずは、やってみるということです!」
「はい!」支折が、力強くうなづいた。「小泉首相も、アクセルをグッと踏み込んだよ
うですから、いよいよ“新世紀・維新”が動き出すのではないでしょうか!」
![]() インターネット時代の 新文化創出
インターネット時代の 新文化創出 


![]()