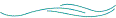
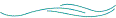
支折は、雨の降りしきる窓の外を眺めていた。白い雨糸が滝のように落ち、庭の樹
木も見えない。かすかに見えるのは、窓の下の、水に沈んだ芝生だけだった。彼女
は、雨の中に手を差し出し、降りしきる雨を掌で受けた。それから、横にいるポン助に
言った。
「ポンちゃん、お茶の用意をしておいてくれる?」
「おう!」
「すごい降りだなあ...」高杉が、部屋に入って来て言った。「さあ、ともかく、始めよう
かね、」
「はい」支折は、窓を閉めながら言った。窓を閉めると、雨音はずっと遠くなった。
「最近...」支折は、窓ガラス越しに、天空の白い雨糸を眺めた。「電車内の些細なこ
とから、殺人事件に発展したようなケースが頻発しています...何故、このような、
“粗暴犯的殺人事件”が急増して来たのでしょうか?」
「うむ...」高杉は、テーブルの椅子に掛け、ゆっくりと脚を組んだ。「マスコミでもよく
言われているように、“日本人の心”が、非常に“キレやすく”なっているのは確かだろ
う。若い男性が、ストレスの溜まりやすい電車の中で“キレる”というのは、こうした社
会的背景の、1つの象徴的な現象だと思う...
つまり、キレやすいのは、別に彼等だけではないということだ。最近では、子供がキ
レるというし、大人だってキレる。また、こう言っている、自分自身ですら、思い当たる
ふしがある。みんな、それをギリギリの所でこらえていたりするわけだ...
大阪の小学校で、8人もの児童が殺された事件の後は、類似犯が続々と出ている
しね...まさに、この国の社会は、相当に病んでいると思う...」
「はい...それにしても、何故、“キレる”などという現象が、社会的にこれほど顕在化
してしまったのでしょうか?」
「私が今回、この問題を“緊急課題”としたのも、まさにそこを考察してみたかったか
らです。こうした、日本の社会全体をおおう異常心理状態は、非常に危険だと思う。
“平和憲法”や、“安全保障問題”という器の話も大事だが、肝心の中身の日本人自
身が“キレた”というのでは、話にもならない。国家や社会が、外交問題で“キレた”な
どということになっては、それこそ戦争前夜に逆戻りしてしまう...」
「はい。最近は、教科書問題や、靖国神社参拝問題などもありますし、」支折は、よう
やくテーブルの方へやって来て、自分の椅子を引いた。
「まあ、外交では、そんなことはないと思うがね。しかし、バックにいる国民の方がキレ
てしまっても、困るわけだな」
「あの...高杉さん...こうした現象は、日本固有の問題なのでしょうか?」
「世界の文化が一元化してきているから、完全に日本固有の問題とも言えないだろ
う。しかし、それは、たてまえかも知れんな、」
「と、言うと、?」
「日本固有の問題だと、私は思う...つまり、日本が自国の文化の問題として、解決
が可能だということだ...もちろん、他の国でもそうだがね」
「はい...それでは...この“キレる”という原因は、何なのでしょうか?」
「うーむ...
私は、“日本人全体の精神”が、巨大ななストレスを受けているからだと思ってい
る。しかも、そうした巨大なストレスを、日常的に常時受けているのではないかな...
それは、つまり、“テレビ文化”であり、“トーンの高い映像文化”であり、“マスコミ文
化”だと思う。まあ、特にテレビの影響が、非常に大きいと思っている。他にも色々と、
意見はあると思うがね」
「うーん...大きなテーマですねえ...それでは、高杉さんは、日本の“テレビ文化”
の最大の問題点は、何だと思っているのでしょうか?」
「一口で言えば...
テレビというメディアは、視聴者である国民を、大切に扱っていないということだ。い
や、むしろ、積極的に、“プレッシャー”をかけていると感じる時さえある。ガンガンとコ
マーシャルを流し、緊張感のないタレントの下品な会話を、ダラダラと流す。明らかに、
故意に、そうしているフシがある...
何故、彼等は、この国の“国民の心”というものを、もっと大切に扱わないのか!
何故、かけがえのないこの国の同朋のために、気品のある、より次元の高い文化を創
出して行こうと努力しないのか!
...」
高杉は、やや興奮している自分を押さえるように、両手のコブシをグッと握りしめた。
「...」
「ともかく、能力が低すぎる!」
「あの...それは、“志”(こころざし)が低いのではないでしょうか?」
「うむ、」高杉は、緊張感の中で、ほくそえんだ。「うーむ...そうかも知れん...
しかし、テレビというメディアは、何か勘違いしている所がある。彼等はメディアで
あって、文化を創出する力がないのに、文化そのものを創出し始めた。このあたりか
ら、この国の文化全体が、ダメになってきたように思う...
まあ、こうした問題は、今後、じっくりと考察していくつもりだがね...」
「はい...あの、テレビが、視聴者を大切に扱わないというのは...それは、何故な
のでしょうか?私には、意味が分らないのですが...」
「それは、官僚や役人が、国民を大事に扱わない感性と、似ているものがあるかも知
れない...
まあ、 “国民を大事に扱わない”、と言うと奇異に感じるかも知れない。しかし、あ
の“薬害エイズ事件”を見ても分るように、官僚の顔は、もともと国民の方へは向いて
いないのだ。彼等は、エイズが発症するのを承知で...それこそ平気な顔で...同
胞であるこの国の民に、エイズ感染の犠牲を強いたのだ。幾ばくかの製薬会社の利
益のためにだ。彼等は、それほどの悪事を、平気でやってのける。つまり、この感性
だな...」
「うーん...どうしてでしょうか?“公僕”であるはずの役人が、何故そんなことをする
のでしょうか?」
「“公僕”という言葉はあるが、彼等自身は、そうは思っていないのじゃないかな。現在
の役人は、かっての武士階級そのものだ。したがって、下の階級の者を支配する気
風が、歴史的に継承されてきているはずだ。それが、現在も残っているから、あの薬
害エイズ事件のようなことが起こったのではないかな。まあ、これは、私の考えだが
ね...」
「はい、」
「しかし...もう一度
くり返すが、厚生省の官僚も、現在裁判中の医療関係者も、明
らかに“血友病患者の命”よりも、“製薬会社の利益”の方を優先した。まあ、なんと
も、恐ろしい話ではある。しかし、これは命にかかわる極端な例だが、例外的な事例で
はないと思う。もともと役人は、伝統的に、国民よりも産業界の方を向いていると言わ
れている。最近は、多少変わって来たというがね、」
「はい...マスメディアが国民を大切にしない感性も、こうした官僚支配に似たものが
あると言うことですね?」
「もちろん、官僚でも、医者でも、マスコミ人でも、立派な人々は大勢いる。いつも言うこ
とだが、」
「はい。それは分かっています。問題は、古くなったシステムと、既得権と、感性という
ことでしょうか?」
「うむ...まあ、そのあたりだろうねえ...マスメディアというものは、昔は存在しなか
った。せいぜい瓦版ができて、新聞が発展してきた程度だった。当然、現在のように、
社会を左右するほどの巨大な力もなかった。
ところが、20年程も前になるかな...正確なところはよく承知していないが、その
頃から、マスコミは“第4の権力”と言われるようになった。“司法”、“立法”、“行政”
と“3権分立”の日本の権力構造の中に、第4の権力が加わったと揶揄されるような
存在になってきたわけだ。そして、どうもこの頃から、マスコミがおかしくなり始めたよ
うな気がする...」
「と、言うと、具体的には?」
「他の権力機関と同じ様に、この国を“支配”し始めた...というかな...むろん、彼
等は、とんでもないと反発するだろうがね...まあ、ともかく、そうした歴史的経緯は、
確かにあったわけだし、」
「ふーん...だから、“第4の権力”なのね」
「うむ...しかし、こうした“支配”は官僚やマスコミの特権意識に限ったことでもない
のだ。この国では、医療機関も、金儲けのために、平気で同胞である日本国民の体を
傷つけて来たしね」
「はい...あの“薬害エイズ事件”も、基本的にはそうでした...」
「うむ。それから、歯科医療もだ。治療と称して国民の歯を壊し、イジメ続けて来た歴
史がある。これは、私自身も経験しているがね、」
「うーん...こういうのって、“命を削る”ことになるのではないでしょうか?」
「うむ。そういう犯罪を、平気でやるところが恐ろしい。しかも、罪に問いにくいわけ
だ。恐いのは、ナイフを持った精神異常者だけではないという事だな...
それにしても、この国では、何故、何もかもが、同胞である日本国民を大切に扱わ
ないのかね...」
「うーん...この国では、主権者である国民は、大切にされていないのですね」
「まあ、ともかく、今後はこの国の“主権者”として、その権利を、有効に使って行くべ
きだと思う。その権利をうまく使えば、こうしたあらゆる弾圧や横暴は、すぐにも排除で
きるはずなのだ。」
「はい...ええ...それでは話を先へ進めたいと思います」
《 お茶を一杯... 》
<
トーンの強いコマーシャル映像の氾濫に、
あの“ポケモン事件”の様な効果は無いのか?
>

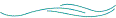
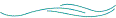

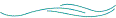
「さてと...」高杉は、茶碗を片手に持ち、雨の降りしきる窓辺を離れた。「支折さん
は、テレビ漫画の“ポケモン事件”を覚えているかな?」
「あ、はい!あの“ピカチュウ”がやった?」
「うむ、そうだ...
あれは、テレビ画面から出た激しい光の発振で、それを見ていた多数の子供たち
が失神したり、気分が悪くなったりした事件だったな。あれと似たようなストレスが、も
う少し緩やかな形で、しかし大規模に、日本のテレビ文化の中で起こってはいないか、
ということだ...
津田編集長が、OPINIONで、“コマーシャル映像のトーンが強すぎる”と言ってい
たのも、確か、この“ポケモン事件”の直後だったと思うが...」
「はい、私も覚えています、」
「ともかく、日本の社会全体が、この種の巨大なストレスに晒されているのではない
かと危惧している」
「コマーシャル映像の氾濫で、“日本人の精神”は、“キレやすく”なっているということ
でしょうか?」
「うむ。私はそう見ている。だから、衆知を集め、この種のことを本格的に調査した方
がいいのではないかということだ。しかも、緊急に!」
「はい、」支折は、コクリとうなづいた。
「さて、“何故、キレるのか”ということだが...私は社会心理学や精神医学の専門
家ではないので、その方面の学問的な分析はできない。ただ、文化全体を見渡すひ
とりの文化人として見た場合、この原因は明らかに、荒廃した日本の文化全体から
来ていることは分る。もちろん、日本で暮らす日本人である以上、それは当然かも知
れないがね」
「はい...原因は、荒廃した日本の文化全体ですか...うーん...」
「それから、1つの現象面に関して言えば、テレビのコマーシャルが、非常に強く影響
しているのではないかということだ。
ともかく、津田・編集長も言うように、1つ1つのコマーシャルは良く出来ている。迫
力もあるし、面白い。しかし、“トーンが強すぎる”ということだ。つまり、そうしたコマー
シャル映像に連続的に晒されている方は、たまったものではないということだ...
しかも、それらは“統一性”もなく、“量的”にも、まさに氾濫しているということだ。こ
うしたことに、“日本人の精神”は耐えられなくなり、“心”が壊れ始めているのではな
いかな」
「それじゃ...大変なことが起こっているのでしょうか?」
「うむ...私は、そう見ている...
もっとも、映像のトーンが強いのは、コマーシャルだけではないがね。民放テレビと、
埼玉テレビや千葉テレビなどの地方テレビとを比較すれば、一目瞭然だろう。民放テ
レビの方は、技術的な蓄積もあり、はるかに洗練されているが、どうにも心の落ち着き
が得られない。それに比べて、地方テレビの方は、はるかに素朴で、人間的な味がす
る...」
支折は、黙ってうなづいた。
「まあ、電卓でもそうだ。この種のものは、いくらでも小さく出来るが、人間の感覚器官
や掌のサイズというものがあるわけだ。これと同じだと思う。つまり、テレビというメデ
ィアにも、“人間のスケール”というものがあるということだ。あるいは、文化的な“感受
性の焦点”と言ったらいいかな、」
「ふーん...」支折は、首を斜めにした。「あの...もう少し具体的に言うと、どういう
ことでしょうか?」
「うーむ...
まず1つは...テレビの画面において、様々なシーンから、突然予告なしに強いト
ーンのコマーシャルに切り替わるだろう。まず、あれがよくないね。また、コマーシャル
によっては、それこそ爆発するように、劇的に変化する。この、“いきなり変わる”、“爆
発するように変化する”というのは、いわゆる“キレる”という状況と、非常によく似てい
るのではないかな。こんなものを、日常的に何年も見ていれば、“キレる”という状況
は、当然起こりうることではないかね...」
「うーん...そうかも知れません」
「まあ、こうしたコマーシャル・ベースの文化というのは、世界的な潮流だと思う。しか
し、こうした文化も、市場の経済原理だけに支配されているかというと、そうでもない。
つまり、その国に住む人々の意思によって、指導者や、メディアや、それこそ伝統的
な文化によって、その国の独自の文化が保たれているわけだ」
「はい、」
「さて、問題は日本のマスメディアだ...
特に、その中心的な役割を担うようになった、テレビで問題が噴出していると思う。
しかも、テレビは、視聴者でる国民を、“粗雑に扱っている”気がするね」
「“粗雑”に、ですか?」
「うむ。私は、そう感じている。つまり...
そうでなければ、現在の様なひどいコマーシャルの流し方を、するはずがない。視
聴者が一番盛り上がっている所で、プツンと番組を切り、全く関係のないコマーシャル
映像をガンガンと流す。2つ、3つ、4つと...まるで、視聴者の精神の限界まで流し
ているようだ...
ま...腹の立つ時もあるが、たいがいは諦めてやり過ごす。つまり、それしかない
からだ。“失礼”にもほどがあるが、どうしようもない。一方、テレビ局の側は、まるでそ
うすることが自分達の特権でもあるかのように、どんどんプレッシャーをかけてくる。こ
うなると、この国の文化は、一体誰のものかという気がしてくる...」
「でも、コマーシャルも必要なのではないでしょうか。NHKのように、聴視料を取らな
い以上は?」
「まあ...国民は、そう理解してきたわけだ。しかし、精神が“キレる”までかき回され
ては、黙ってはいられないだろう」
「はい、」
「ともかく...日本人は、日常的にトーンの強いコマーシャル映像に晒されてきた。そ
れで、心に“感動”というものが湧いて来なくなった。それに、“落ち着き”もなくなった
気がする。それから、じっくりと“物事を考えること”も出来なくなった...
つまり、“心の落ち着き場所”がなくなったわけで、心は常にどこかイライラしてい
る。
一体、伝統ある日本の文化は、何処へ行ってしまったのかということだ」
「はい...では、高杉・塾長...一体私たちは、どうすればいいのでしょうか?」
「うーむ...まず、この現状を、自覚することだと思う...
それから、この国は、“国民主権”の国家なのだと言うことを思い出して欲しい。そ
して、“国民主権”ということは、政治ばかりでなく、“文化”や“福祉”にもその権限が
及んでいるのだということを自覚して欲しい...
現在のように、文化面においても、あらゆるレベルで権威が喪失しまったのは、そ
れは“国民の信”を失ってしまったことだと思う。だから、逆に“国民の信”を回復すれ
ば、権威も回復するということだ...
つまり、言い換えれば、この国の文化は、国民自身が作っていくのだということだ
な。むろん、テレビという影響力の非常に強いメディアも、当然この範疇に入ってくる
わけだ」
「はい...ええ、それでは、今回はこのあたりで、一度話をまとめておきたいと思いま
す。あの、何か、まとめの言葉はあるでしょうか?」
「うむ...
司法、立法、行政...それから、マスコミ、医療...そして、文化...
そうしたあらゆる面で、“国民主権”が確立されていく必要がある。その総合的
な国民運動の中から、“新世紀・ルネッサンス”がスタートしていくものと思います」
「はい...ええ、それでは...次回の展開に、どうぞご期待ください!」

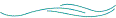

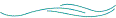


![]() 【緊急課題】
【緊急課題】
何故、私たちの心は
キレるのか!
![]()

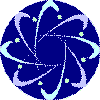


![]()

![]()