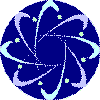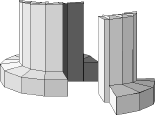プロローグ 

「“文芸”担当の星野支折です...
ええ、今回、“新世紀・ルネッサンス”の提唱
という非常に重い課題を担当すること
になりました。“ルネッサンス”とは、フランス語の“Renaissance”のことで、日本語
では“文芸復興”と訳されています。そこで、“文芸”ということなので、文芸担当の私
の仕事になった次第です。
実は、最近購入したデジタルカメラを使い、“デジタルカメラ講座”の方をバッチリや
ろうと思っていたのですが、当然こちらの方が優先されます。あ、でも、“デジタルカメ
ラ講座”の方もしっかりとやっていきますので、よろしく...
うーん...今まで、私だけがのんびりとやってきたのですが、いよいよ私の方も忙
しくなってきたようです。
ところで、このルネッサンスというのは、広い意味では、14世紀末から16世紀にか
けて、イタリアで始まり、ヨーロッパ全土に広まった社会運動です。中世のヨーロッパと
いうのは、キリスト教の絶対支配が長く続き、その時代的閉塞感は想像を絶するもの
があったと言われます。
例えば、教会に逆らって“地動説”を唱えたコペルニクスは、処刑されました。また、
望遠鏡を発明し、木星を観察したガリレオは、神が中心にいる“天動説”は間違いで、
“地動説”の方が正しいと主張しました。すると、それは神の名において、厳しく弾圧
されたのです。その時、ガリレオは、“それでも、地球は回っている”、という有名な言
葉を残しています。うーん、ガリレオの気持ちが、良く分ります。
一方、教会では、“免罪符”を発行し、これを買えば悪事を働いても罪が許されるとい
うような仕掛けを作っていました。うーん、とんでもない話です。そして結局、宗教改革
が勃発し、カトリックは追われることになりました。カトリックのフランシスコ・ザビエル
が、布教の新天地を求め、自らはるばる極東の日本にまでやってきたのも、こうした
地球規模の時代背景があったのです。
さて...それはそれとして、狭い意味での“ルネッサンス”は、文芸復興という意
味になります。これは、
“古代のギリシャやローマの文化を再現して、神の絶対支配の
もとで失われていた、人間性を回復させようとした運動です。”
...」
≪コメント≫
「ええと...」星野支折は、高杉・塾長と津田・編集長のいるテーブルの方へ、ゆっくり
と歩いた。
「高杉・塾長...今回の“新世紀・ルネッサンス”の提唱
は、21世紀という時代背景
の中で、どのような意味が込められているのでしょうか?」
「うーむ...」高杉は、コーヒーカップを脇へ押しやった。「...小泉内閣が発足して
約1ヶ月...津田・編集長...この内閣は、非常にうまく行っているのではないで
しょうか?」
支折は、二人を交互に眺め、そっと自分の椅子を引いた。
「おっと、こっちの方の話でいいかね?」高杉は、支折を見上げて聞いた。
「あ、どうぞ、」支折は椅子に掛け、自分のノートパソコンを引き寄せた。
「まあ...そうですねえ...」津田が、腕組みをし、首を斜めにした。「いよいよ、構造
改革すべき実態というものが浮かび上がってきましたねえ...今までは、議論に乗
せるのさえもタブーだった課題が、当たり前のように表面に出てきています...
それから、外務省と、田中真紀子外務大臣の確執ですが、これは外務省の官僚の
側に非があることは明らかです。国際会議の場で、本来表面に出るはずのない非公
式の会話が、外務官僚の側から暴露されたのには驚きました。それをやってはいけ
ないのを、誰よりも一番よく知っているのは、彼らですからねえ...」
「ええ。あれは、私も本当に驚きました」
「これは、国益を損なう行為ですよ。背後で糸を引いているのは、どうやら橋本派のよ
うですが、これは国家を危うくする行為ですねえ...まあ、もともと彼等の主張は、国
家よりも自民党、自民党よりも橋本派と言われてきましたので、整合性は取れている
のですが...当然ながら...国のためにはなりませんねえ...」
「改革に反対する、抵抗勢力ということになるのですか?」
「はい。官僚機構も、小泉内閣によって特殊法人を全廃されてしまえば、天下り先がな
くなってしまいます。したがって、彼らも、総力をあげて抵抗してくるでしょう。そして、
その発火点になっているのが、外務省と田中真紀子外務大臣の激突のようです。し
たがって、ここで負けてしまっては、その先はないということですね。そうなってしまって
は、これまでのような、掛け声だけの改革になってしまいます。
ここは、国民がしっかりとサポートし、田中外務大臣を守って行かなければならんで
しょう。そうしなければ、改革に対する反対勢力に負けてしまうことになります...」
「そうですねえ...私から見ても...」高杉は、進行役の支折の方を眺めて言っ
た。「...田中外務大臣の適格性が追求されていますが、問題の本質は外務省にあ
りますね。機密費問題も含めて。いったいこの伏魔殿は、シビリアンコントロールの下
にあるのかどうかということこそ問題にすべきです。編集長は、この点はどう思われま
すか?」
「はい...そもそも、大臣の適格性を言うのなら、これまでのたらい回しの大臣人事
は、首相も含めて、全員が問題アリでしょう。およそ、数十年間、適格性ではなく、派閥
の順送り人事で大臣を決めてきたのですから...だから、まさに、現在の国家存亡
の危機に至っているわけですよ。
それから、田中真紀子外務大臣ですが、彼女は政治家として、非常にいいものを
持っています。ここは、田中大臣の足を引っ張るのではなく、イギリスのように、素質
のある政治家を、しっかりと育てていくべきではないでしょうか。ここは、私たち国民
が、しっかりと監視していくべきだと思います。それから、アメリカが田中大臣に対し
て、少し態度を渋っているようですが、これはアメリカ自身の国益を考えてのことです
からねえ、」
「はい...まさに、私もそう思います」
「ええ...」支折が、割って入って言った。「...はい...お二人とも、どうもありがと
うございました。このへんでよろしいでしょうか?」
「うむ」津田がうなづいた。「言いたいことは、まあ、先に残しておきましょう」
支折は、目尻に微笑を浮かべてうなづいた。
「ええ...それでは、さっそく、本題の方へ移りたいと思います。
まず、No.1の、“緊急課題”ですね。さっそくそちらの方に移りたいと思います」
新世紀・ルネッサンスの提唱
![]() <プロローグ>
<プロローグ>
![]()