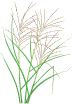無門関・第1則“趙州狗子”で出てきた趙州(じょうしゅう)和尚がまた出てきました。中国
唐時代の後期、禅宗の創造時代に活躍されたこの祖師は、「唇皮上に光を放つ」と
いわれたほどの人物です。一喝する祖師もあれば、棒を振るう祖師もあり、また一指
を立てる祖師もありました。しかし、趙州和尚は、精妙な言句に鋭い機鋒を現した禅
風と言われます。なお、この公案は、日常生活に即した禅の真髄を、端的に示したも
のです。
この公案も、表面的な会話の意味は、小学生でも分かるものです。では禅的な意
味はどうなのでしょうか。
そもそもこの僧は、新参者と自ら名のっていますが、僧堂に入ったのは新参であっ
ても、禅修業においては新参者ではありません。本当の新参者がこの程度の2、3
の会話で悟れるなら、誰も修行などは必要ないのです。六祖・慧能の頓悟(修行の段階を
経ずに、一挙に悟りを開くこと )にしても、それなりの下地はあったのです。ここに、“悟り”と言
うものの一つの風景があるわけです。
公案で趙州和尚は、「朝ご飯は食べたか。」と、聞いています。“ 師よ、どうか指示
をお与え下さい。”と、僧が言っているのに、趙州和尚は何故朝飯の事などを聞いた
のでしょうか。さあ、あなたなら、これを何と受け止めるでしょうか...
和尚は、即下には何があるか...眼前には何があるか...日常の中にある即今
とはどのようなものか...と指し示しているのです。ところがこの僧は、それに気付
きません。私たちと同じようにボーッとしていて、“はい、食べました。”などと答えて
います。そこで和尚は、同じ意味のことをたたみ掛けて言います。“それでは持鉢(じ
はつ)を洗っておきなさい。”と...
そこで、ようやくこの僧は、「はっ」と、趙州和尚の真意を汲み取ります。その、ある
がままの日常的動作の中に、即今の呼吸があるのだと知ったのです。“悟り”とは、
特別な所にあるのではない、一切がそのまま、真実の結晶世界なのだということで
す。蛇足になりますが、趙州和尚がこの僧に言いたかったのは、“そなたがすでに体
得した、無心に生きてゆくがよい”ということです。
 趙 州 洗
鉢
(じょうしゅうせんはつ)
趙 州 洗
鉢
(じょうしゅうせんはつ)

![]()


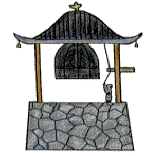

![]()