|
<1> 公案   
六祖を追って明上座(みょうじょうざ/明は、慧明の略)は大庾嶺(だいゆれい)に来た。六祖は
明がやって来るのを見て、衣と鉢を石の上に置いて言った。
「この衣は信の象徴である。力をもって争うべきものではない。君が持ち去ろうとい
うのなら、そうしたらよかろう...」
明は衣を持ち上げようとしたが、まるで山のように動かなかった。明はためらい、
おののいた。彼は言った。
「私は法を求めてきたのであって、衣のためではありません。行者(あんじゃ)よ、どう
か教示して下さい!」
六祖は言った。
「善を思い、悪を思うことをやめよ。この時、明上座の本来の自己とは、どのよ
うなものか?」
これによって明は直ちに大悟した。全身に汗が流れた。涙を流しつつ礼拝して、
彼は尋ねた。
「この密語密意のほかに、まだ何か別の意旨がありましょうか?」
六祖は言った。
「私が今、あなたのために説いたところは、秘密ではない。自己の真面目に目覚め
るならば、秘密とするものは、かえってあなた自身の中にあるのだ」
明は言った。
「私は黄梅山で、他の雲水たちに従って修行してきましたが、自己の真面目に目
覚めることができませんでした。今あなたに適切な御指示を頂いて、人が水を飲ん
でその冷暖を身をもって知るように、自知することができました。行者よ、あなたこ
そ私の師匠です」
六祖は言った。
「あなたが、本当に本来の面目に目覚めたのならば、あなたも私も共に五祖の門
下なのだ。体得した“這箇(しゃこ)”を、大切に護持して行ってほしい...」
さて...前回取り上げた、<無門関・第十九則/平常是道>で、“頓悟”という
概念が出てきましたので、六祖/慧能やその時代背景についてはすでに多少触れ
てきています。ここでは、これらについて、さらに深く掘り下げて考察していきます。
言うまでもなく...仏教は釈尊が生まれた、インドが発祥の地となります。このイ
ンド文化はきわめて哲学的傾向が強く、一方、中国文化はきわめて実践的傾向の
強い文化といわれます。
この二つの文化が...“仏教の中で・・・最も実践的な禅という・・・宗教体験
の形で結合”...しました。そして“インド臭さ”を捨て去り、“禅宗という・・・真の中
国仏教”を確立したのが、六祖/慧能の時代といわれます。これは、唐/玄宗皇帝
の頃であり、妃/絶世の美女/楊貴妃(ようきひ)のいた時代ですね。
それまでは中国においても...伝教大師(最澄)が日本に持ち帰った天台宗や、
弘法大師(空海)が日本に持ち帰った密教などが主流だったのです。つまり、後に菩
提達磨が伝えた...“釈尊の宗教体験を重視する・・・実践修行・・・禅宗”...
とはだいぶ違うものだったのです。
むろん、中国で大きく開花した禅宗は、日本の仏教世界にも大きな影響を及ぼ
して行きます。日本の曹洞宗の開祖・道元が中国に渡ったのは、宋の時代です。
日本では、鎌倉時代・初期ということになります。この時代になると、遣隋使や遣
唐使の時代に比べれば、造船や航海技術も格段に発達し、かなり多くの学僧が
入宋(にっそう)していたようです。
もう1人有名な人物をあげれば...日本における臨済宗の開祖/栄西がいま
す。道元は出家した後、その栄西のもとで学び、入宋し、日本の曹洞宗の開祖に
なったわけです。
栄西の方は...二度入宋していて...最初(/27才の時)は天台教学を学んでい
ます。二度目(/47才の時)は、天竺(てんじく/インド)行きを計画していましたが、断念し
ました。もしこの計画が実現していたら、玄奘三蔵をしのぐ壮大な旅行記が後世
に残っていたかもしれません。いずれにせよ、天竺行きを断念した栄西は、禅修
業に励み、帰国して臨済宗の開祖となったわけです。
<2>公案の解析  
この<無門関・第二十三則>は、公案としては、かなり長いストーリイになって
います。しかし、この公案で肝心なのは、明上座が、慧能の一言で大悟する部分で
す。むろん、大悟するには、明上座の長年の修行があったわけであり、機が熟して
いたというのは、大きな要素になります。しかし、彼はまさに、慧能のこの一言で大
悟したのであり...ここがこの公案の命です...
「善を思い、悪を思うことをやめよ...この時、明上座の本来の
自己とは、どのようなものか...?」
...これによって明は直ちに大悟した。全身に汗が流れた...といいます。さ
あ、公案の全文を、何度も読み返してみてください。そして、この慧能の一言を味
わってみてください。そして、もし...機が熟していれば...あなたも慧明(えみょう
/明上座/明)のよう、に大悟できるでしょう。
さて...“善を思い悪を思うことをやめよ”...とは、どのようなことを指してい
るのでしょうか。“善”と“悪”とは、正反対の両極端の概念を指しています。これは、
愛と憎とも同じ関係ですし、高と低、右と左も同じです。つまり、リアリティーを二つ
に分割し、そのそれぞれの一端をあらわしている対の概念です。
したがって、これらの中から...“善”と“愛”と“高”と“左”...のみをかき集め
て来ることなどは不可能なのです。磁石のS極とN極のように、必ず対になってい
るわけです。そして、こうした概念構成は、これまでにも何度も説明しているように、
二元論と言います。
この二元論を究極的に応用しているのは、0と1という、二進法で構成されてい
るコンピューターです。コンピューターはまさに、二元論の権化のようなマシンです。
この公案については、小説・『 唯 心
』でも詳しく説明していますので、そちらの方をご覧下さ
い。また、“頓悟”については、“特別道場/第2ステージ・まほろば”の方で考察していきます。
<3> 無門の評語  (2000.7.28) (2000.7.28)
六祖は、緊急の場で、とんでもないことをしでかしたと言わなければならない。まこ
とに老婆親切である。新しい荔枝(れいし/琵琶(びわ)の類、)の殻をむき、種を取り除いて
相手の口に入れてやり、ただ呑み込みさえすればよいようにしてやったようなものだ。
この評語は、あえて説明する必要はないと思います。無門禅師は、相変わらず揶
揄を含んだ調子で、こき下ろしながら、実は若い六祖/慧能を大いに賞賛している
わけです。また...
“口に入れてやり、ただ呑み込みさえすればよいようにしてやったようなものだ”
...と、赤ん坊の口に含ませるより簡単なようなことを言っています。しかし、ここ
が実は...“無門関・・・無門の関”...であり、容易ではない関所です。ともかく、
これによって慧明は大悟し...“全身に汗が流れた”...となります。
慧明はこの後、ひとり山中で禅の境涯を深め...やがて袁州(えんしゅう)の蒙山(もうざん)で
活躍したと言われます。
<4> 無門の頌(じゅ) (/頌は偈(げ)と同じで、詩の意味です
) 
それは描写しようにも描き得ず、絵に画こうにも画けない。
詠ずることも、たたえることもできない。
一切の模索分別をやめよ。
本来の面目は、どこにも隠す所がない。
世界が崩壊する時、それは朽ちない。
...この無門禅師の頌は...
「善を思い、悪を思うことをやめよ。
この時、明上座の...本来の自己...とはどのようなものか?」
...というこの公案の核心部分にある、“本来の自己=本来の面目(/原文)”に
ついてのみ、述べています。さあ、この禅における核心中の核心、“本来の面目”
とはどのようなものなのでしょうか。
それは、無門禅師がこの頌で、懇切丁寧にうたっています。繰り返し読んでみて
下さい。また慧能が慧明に言った、上記の一言、“明上座の本来の自己”につい
ても、深く考えてみて下さい。結局、慧明は、これによって何を悟ったのかと。
それから、前章の<無門関・第十九則/平常是道( へいじょうこれみち
)>の解説
の中で、私はこう言ってきました。
****************************** <一部抜粋>
阿頼耶識( あらやしき
)にある...“分別する心・・・自我”...を捨てよ、
そして...“ただ・・・無心となれ”...そうすれば、おのずとそこに、全
てが明らかになるということです。
自我を捨て...自我を忘れ去り...
この世の一切の柵(しがらみ)を、両腕と両脚から放下し...
ただ無心に、眼前の風景を見つめる時...
...まさに、それが南泉のいう、“平常の心”なのではないでしょうか。
ここには...
主体もなく、客体もなく...
時間もなく、空間もなく...
生もなく、死もない...
すなわち、一切の二元性のない世界...
********************************
...これが、いわゆる慧能の言った、“善を思い、悪を思うことをやめよ”と言った
時の、真意の風景です。このような時、あなたの“本来の自己”とはどのようなもの
かと問われ、慧明は大悟したのです...
さあ、禅は実践宗教です。“本来の自己=本来の面目”も、頭で理解しただけで
は、小さな一歩/スタートでしかありません。このことを、自分の全人格で体現してい
くことが、“悟り/覚醒”への道になります。
|
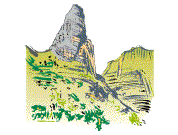 不
思 善 悪 ( ふしぜんあく )
不
思 善 悪 ( ふしぜんあく ) 




