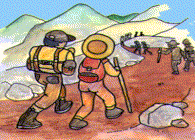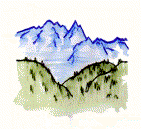|
<1> 公案  
趙州(じょうしゅう)がある時、南泉(なんせん)に、
「道とは何ですか?」と問うた。
「平常の心が道だ...」と南泉は答えた。
「それでは、どのように、それに向かうべきでしょうか?」と趙州は尋ねた。
「向おうと努めれば、道から離背してしまう...」と南泉は答えた。
趙州は更に問うた。
「もし努めなければ、どうして平常心が、道であることが知り得ましょう?」
南泉は答えた。
「道は知にも属さないし、不知にも属さない。知は妄想であり、不知は空虚である。も
し本当に不疑の道を体得するならば、それはちょうど太虚が廓然として限りのないよ
うなものだ。そのとき、道に是非の分別の沙汰があろうか...」
この言葉に、趙州は頓悟(とんご)した。
さあ、この公案は...<無門関・第十四則/南泉斬猫>と同じく、再び南泉禅師
と趙州禅師の話になります。
時代はだいぶ遡り...南泉が五十歳ぐらい、趙州の方は、二十歳をやや過ぎた頃
です。したがって、趙州の方は、名前もまだ従諗(じゅうしん)と呼ばれていた修行僧時代
の話になります。しかし、“頓悟(とんご)した”とありますから、彼はここで悟りを開いてい
るわけです。
“頓悟”とは、修行の段階を経ずに、一挙に悟りを開くことを言います。これに対し
て“漸悟(ざんご)”という言葉があり...これは長い修行の時間をかけて、ゆっくりと悟
りを開いていくものです。
どちらが、いいというものではありません。五祖/弘忍の門下に慧能(六祖)と神秀
(門弟中の最上席)がいて、後に...慧能が頓悟(/南宗禅)、神秀が漸悟(/北宗禅)と言われ
るようになりました。
当時...禅宗の初祖/菩提達磨(ぼだいだるま/インドより海路で渡来・・・北方中国の魏国/崇山
(すうざん)の少林寺に入る)に続く...五祖/弘忍(ぐにん、こうにん)は、北方中国は蘄州(きしゅ
う)の黄梅山にあり、そこは常時七百余名の門弟でにぎわっていたと言われます。ま
さに禅宗の黎明期であり、ここから禅宗は無数の枝葉を伸ばして開花し、やがて日本
にも伝わってくることになります。
さて...激しい情熱だけで、身ひとつで南方/新州から北方/黄梅山にたどりつ
いた慧能(六祖)は、いまだに僧侶の身分さえありませんでした。さらに、貧しく無学で
あり、字も書けなかったと言われます。しかし、ようやくここで米つきの仕事を許され、
約八ヶ月間、毎日米つきをしていました。
ところが、そうしたある日、五祖/弘忍が全山に布告を出しました。自分の力量を
示すために、各自それぞれ偈(げ/詩のこと)を作ってみよと言うのです。そして、ここで
慧能は、古参の超エリート集団を追い抜き、まさにその力量を示しました。しかも、字
を書けなかった慧能は、それを童(わらべ/寺に住む小僧で、慧能と同じように雑役をしている)に書
いてもらい、首座の神秀の偈の横に張り出したのです。優劣は一目瞭然でした。
その後、五祖/弘忍からこっそりと“衣鉢”を受けた慧能は、さっさと南方へ帰って
しまいます。禅宗において衣と鉢を受け継いだということは、法嗣(ほっす)ということで
あり、この場合は、禅宗世界に六祖/慧能の誕生を意味していました。
さあ、まだ僧侶でさえもない、米つき行者(あんにゃ)の新参者に衣鉢を持っていかれ、
黄梅山は一大事になりました。また、黎明期の禅宗世界にとっても、五祖/弘忍の
“衣鉢”は何をもっても代えがたい象徴的な宝だったのです。
その象徴が、何故それほど大事かといえば...“仏教とは・・・悟り/覚醒という
・・・真理の体験的伝承の大河”...であり、禅宗においては、それが特に強く出て
いたようです。仏教は、他宗教に見られるように、たった一冊の聖典に帰結するもの
ではなく、真理の体験によって伝承されてきました。
したがって...五祖の“衣鉢”はそれほど大事な宝でした。むろん、弘忍もそれを
承知していたからこそ、こっそりと慧能に与え、南方へ逃がしました。“頓悟”の慧能
の出現は、新しい時代を予感させるものだったのでしょう。そして、この五祖/弘忍
の行為もまた、禅宗の黎明期における、歴史的なすがすがしい話です...
...この禅宗史に残る大事件と“頓悟”については、
<無門関・草枕...第二十三則/不思善悪>
<特別道場/...ステージ2・まほろば>
<小説/唯心>
...等で詳しく考察していく予定です。いずれにしても、これが慧能の“頓悟”の威力
であり、このような悟りのあり方は、後の禅宗の展開に大きな影響を及ぼしていきます。
公案の末尾に...若い趙州が“頓悟した”...とあるのは、この慧能のような悟
り方をしたということになります。いずれにしても、<無門関・第一則/趙州狗子>
から度々登場する大禅匠/趙州が、悟りを開かれた時の光景です。また、“頓悟の
光景の一例”が示されているわけでもあり...しっかりと学び取ってください。
<文化的背景・・・>  
さて、公案の冒頭で、青年・趙州は、「道とは何ですか?」と問うています。これに
対して師/南泉は、「平常の心が道だ!」と答えているわけです。
この“道”という語は、古来東洋思想においては、非常に深い重要な役割を担って
来ています。まず、仏教よりも古い道教において、その中心的な教えとなっています。
話は少しそれますが...そもそも中国文化というのは、歴史を記録する文化と言
われます。誰が、いつ、何処で、何をしたか、ということを克明に記録することを得意
としています。一方、仏教の生まれたインド文化は、こうした傾向とは対照的で、哲学
的な傾向の強い文化です。したがって、仏教においては、涅槃(ねはん)、般若(はんにゃ)、
空(くう)、などの概念が多用されます。
しかし、もともと中国には、このような概念は発達していませんでした。そこで、“極
めて実践的な臭いのする・・・道/タオ(Tao)・・・という一語”...をこれに当てはめた
と言われます。
むろん、中国には、この菩提達磨系の禅宗以前に、すでに密教が伝わっていて、
大きく花開いていました。またその密教は、学僧/空海(弘法大師)らによって、日本に
も伝来しています。
<日本では、これ以前に聖徳太子の時代にも、仏教文化が大きく花開いています。いずれも中国から伝わってきたも
のですが、禅宗はこうした中では、一番最後に日本に伝来した仏教ということになります。>
中国における禅宗は、唐時代の末期から宋時代にかけて隆盛してくるわけです
が、日本に伝来するのは宋時代であり、日本では鎌倉時代ということになります。ち
なみに、道元禅師が海を渡ったのも、中国では宋の時代でした。また、道元禅師が
日本に帰った直後あたりの時期に、無門禅師が『無門関』を編集しているようです。
ところでこの...“実践的な臭いのする道”という概念が...“実践的性格の強
い禅宗”と結びついた時...ようやく...“インド伝来の仏教が・・・中国文化の大
地に根付いた”...と言われます。
つまり、菩提達磨によってもたらされた“禅”という一粒の麦は、“禅宗”となって中
国の大地で大きく花開し...それは、“中国独自の仏教文化”して完成して行った
ということです。いずれにしても、この禅宗において、仏教はインド臭さが抜けたとい
われます。日本の仏教も、唐・天竺(から・てんじく)から伝わっているわけですが、唐は
唐時代の中国であり、天竺は当時のインドのことです。
<思えば、菩提達磨は、その後の中国及び日本の文化に、計り知れないほどの影響を
及ぼしているわけです...そしてまさに今、原稿を書いている私自身も、その影響下に
あるわけです。むろん、私としては、そのことを誇らしく思っています...> 高杉 光一
<2>
公案の分析  
青年・趙州が、
「道とは何ですか?」
...と尋ねていますが、ここで言う“道”とは、“禅の真髄”というほどの意味です。
これに対して南泉は、
「平常の心が道だ!」
...と答えているわけです。しかし、そう言われても、青年・趙州には私たちと同様
に、理解できませんでした。それで、更に問います。
「それでは、どのように、それに向かうべきでしょうか?」
これは、“平常是道”の境地に心眼を開くには、どの方向を向き、どのような努力
や工夫をしたらよいのか、という意味です。まさにこれは、私たちの知りたい疑問そ
のものではないでしょうか。後の大禅匠/趙州でさえも、私たちと同じように、右も左
も分からない時代があったのです。そして、この問いに対し、南泉はこう言います。
「向おうと努めれば、道から離背してしまう...」
この真意は、どのようなものでしょうか...一生懸命に何かに向かおうとしている
その心...それそのものが、即ち“分別心”であるということです。どの方向、どのよ
うな努力、どのような工夫...それらの全ての“分別心”が二元的概念であり、仏の
教えとは、まずそうした“はからい”を捨てよということなのです。
阿頼耶識(あらやしき/唯識説で説く、八識の第八)にある、あれこれと考える“自我”を捨て、
“無心になれ”とは、まさにこのことなのです。道元禅師も『正法眼蔵』の中でこう言っ
ておられます。
仏道を学ぶということは、自己を学ぶことである。自己を学ぶということ
は、自己を忘れることである。自己を忘れるということは、総てのものごと
が自然に明らかになることである。
総てのものごとが自然に明らかになるということは、自分をも他人をも
解脱させることである。悟りのあとかたさえ残さないのである。そのことを
いつまでも行いあらわしていくのである。
< 『正法眼蔵』/現成公案より
/再度、記しておきます>
さあ、こう言われても、青年・趙州はまだ分かりません。もともと彼は、仏教の学
問的研究を断念し、北方中国の故郷を捨て、南方の南泉禅師の門を叩いたほどの
人物です。
したがって、単に分からないと一言でいっても、私たちのように軽い気分のもので
はなかったのです。時代は前後しますが、あの“洞山三頓”の洞山禅師のように、
故郷を捨て、まさに悶々と求道の修行を重ねてきていたわけです。そこで、もう一度、
血の出るような問いを発します。
「もし努めなければ、どうして平常心が、道であることが知り得ましょう?」
この意味は、努力や工夫もせずに、どうして“平常是道”の境地に、心眼を開くこ
とが出来るのでしょうか、ということです。うーむ...もっとも質問です。また、自分自
身がそのために、壮絶な努力や工夫を重ねてきた者の言葉です。これに対し、南泉
禅師の答えは懇切丁寧です。
「道は知にも属さないし、不知にも属さない。知は妄想であり、不知は空虚である。も
し本当に不疑の道を体得するならば、それはちょうど太虚が廓然として限りのないよ
うなものだ。そのとき道に是非の分別の沙汰があろうか...」
“道”は、知にも属さないし、不知にも属さないと南泉は言います。さらに、知は妄
想であり、不知は空虚であると...
さあ、この説明を聞いて、スッ、と理解できるでしょうか。これはやはり、多少なりと
も禅修業の体験をしたことのない者には、なかなか難しい所だと思います。しかし、
分からなければ、このときの青年・趙州のように、更にもう一度重ねて質問すること
です。しかし、それでも分からなければ、再び修行の場に戻ればいいのです...
今までの二人の会話を要約してみると、こうなります。
********************************************
「道とは何ですか?」
「平常の心が道だ!」
「それでは、どのようにそれに向かうべきでしょうか?」
「向おうと努めれば、道から離背してしまう...」
「もし努めなければ、どうして平常心が道であることが知り得ましょう?」
********************************************
「道は知にも属さないし、不知にも属さない。知は妄想であり、不知は空虚
である。もし本当に不疑の道を体得するならば、それはちょうど太虚が廓
然として限りのないようなものだ。そのとき道に是非の分別の沙汰があろ
うか...」
この言葉に趙州は頓悟した。
********************************************
前にも言いましたように、“道”とは禅の真髄のことです。それは、知にも属さない
し、不知にも属さないといいます。また、それは“平常心”だとも言っています。しか
し、この説明では、一般常識的な解釈では理解できず、どうしても禅的な修業が必
要です。
これは全ての公案に通じることですが、禅の本質は私たちの分別心の根源であ
る阿頼耶識を離れることにあるからです。阿頼耶識にある“分別する心”、“自我”
を捨てよ、そしてただ“無心となれ”...そうすれば、おのずとそこに、全てが明ら
かになるということです...
自我を捨て...自我を忘れ去り...
この世の一切の柵(しがらみ)を、両腕と両脚から放下し...
ただ無心に、眼前の風景を見つめる時...
...まさに、それが南泉のいう“平常の心”なのではないでしょうか。ここに
は...
主体もなく、客体もなく...
時間もなく、空間もなく...
生もなく、死もない...
すなわち、一切の二元性のない世界...
...しばらくは、このような“平常心/禅の真髄”というものにじっくりと接し
てみてください。
<3>
頓悟の風景・・・ 
さあ、この公案のもっとも肝心な部分です。最後に、青年・趙州は何を理解し得て、
“頓悟”に到達したのでしょうか。南泉は、こう言っているわけです。
「道は知にも属さないし、不知にも属さない。知は妄想であり、不知は空虚である。も
し本当に、不疑の道を体得するならば、それはちょうど太虚が廓然として限りのない
ようなものだ。そのとき道に是非の分別の沙汰があろうか...」
この言葉に趙州は頓悟した。ともかく、この一文は難しい文章ではありません。何
度も読み返し、その大意をしっかりと把握してください。それから、一語一語の意味を、
しっかりと自分自身の知恵で検証していってみてください。
これは、大禅匠/趙州が“頓悟”した文節ですから、そうしてみる価値は十分にあ
ります。いずれにせよ、悟りを得るということは、結局は先人の指し示した所を、自分
自身で気付き、それを掴み取る以外にはないのです。
“道”というものは、知にも属さず、不知にも属さず、また知というものは妄想であ
り、不知は空虚であるといいます...ここには、私があえて言葉をさしはさむ余地は
ありません...つぎに...
「もし本当に不疑の道を体得するならば、それはちょうど太虚が廓然として限りのな
いようなものだ...」
...ここでいう不疑の道とは、疑いや疑問のない道ということであり、これまで述べ
てきた“道”と同じ意味です。つまり、“禅の真髄”、“大道”、“至道”ということです。
したがって、これを体得したなら...それはちょうど、太虚が廓然として限りのない
ようなものだ...ということです。うーむ...では、太虚が廓然として限りのないとは、
どのようなことを言うのでしょうか。これこそまさに、これまでの公案でずっと述べてき
た、“趙州の無”であり、“倶胝の一指”であり、無門禅師の“内外打成一片”の風
景なのです。
つまり、南泉が趙州に示した“平常の心”とは、一般的な相対世界におけるもので
はなく、悟りによって体得された絶対主体的な“平常心”だったのです。繰り返します
が、“悟り”とは、阿頼耶識における自我の分別心によって理解するものではなく、そ
の自我を捨て去ることによって実現するものなのです。したがって、“慧能の頓悟”と
は、“この核心を・・・グイと掴み取ったもの”...だったのです。
ちなみに、南泉の師は馬祖であり、その師は南岳であり、更にその師が慧能になり
ます。慧能の南宗禅の“頓悟”は、このように引き継がれ、趙州に至っていたわけで
す。
<4>
無門の評語  (2000.6.1) (2000.6.1)
南泉は、趙州の問いにあって、まるで瓦は崩れ、氷は消えるように見苦しい有様
で、何とも言い開きの余地がない。趙州はたとえ悟りを得たとしても、さらに三十年修
行して初めて、本当にうなずき得るであろう。
例によって、ここでも無門禅師は悪口雑言を並べ立てています。しかし、いつもの
ように真意はここにあるわけではなく、実は南泉をほめたたえているのです。そして、
趙州の“頓悟”をまだまだと奪い去り、本当にうなづきうるには、さらに30年(長い年月)
の修行が必要であると言っているのです。
これは、一体どういうことなのでしょうか...察するに、趙州には確かに、“頓悟”
はありましたが、ここではまだ単なる“知解”であるということです。したがって、それ
は観念論であり、“真の実践的な禅心”には至っていないと言うことなのでしょうか。
また、言うまでもなく、“真の実践的な禅心”などと言うものは、本来言葉で説明で
きるようなものではないのです。したがって、この“頓悟”がスタートであり、さらに長
い年月の修行の中で、真にうなづき得る時が来ると言っているわけです。“頓悟”と
いうものの、ひとつの風景を示しているわけです。
さあ、ここにもまた...公案というもの...“悟り”というものの・・・熟成されて
いく姿”...が端的に示されています。そして、まさにこの...“熟成されていく過
程の・・・悟りの真髄”...こそが...“平常是道”と私は理解しています。
<5>無門の頌 (じゅ/...口語訳)  
春に百花あり秋に月あり
夏に涼風あり冬には雪がある
もし心につまらぬ分別の雲がかからぬならば
君にとってまさに好時節である
これは一読して分るように、四季の風情をほめたたえている歌です。そして...
もし心につまらぬ分別の雲がかからぬならば...
...と言っています。つまらぬ分別の雲とは、無限に拡大していく様々な煩悩の
ことを指しています。例えば、四季にも別の側面があります。春には花の散る寂し
さがあり、秋の月は雲に隠れるむなしさがあります。また、夏には耐えがたい蒸し
暑さがあり、冬には極寒の厳しさがあります。
しかし、二元的対立を超え、ひとたび“真の実践的な平常心”に至れば、“すなわ
ち是れ・・・人間の好時節”というわけです。したがって、生老病死(人間の持つ4つの基本
的な苦しみ)もその二元性を超え、人間の好時節として生き抜くということです。
花と言えば花になりきり...月と言えば月になりきる...のです。また、ひと
たび、生と言えば生を生き抜き...老といえば老を生き抜き...病といえば
病を生き抜き...死といえば死そのものを生き抜く...のです。
しかして...死そのものを生き抜くとは、どのようなことかといえば、つまり...
花は花であり...月は月である...のと同じことです。本来、二元的対立を超えた
所には...いわゆる...生もなければ死もなく、花もなければ月もない...のです。
あるのは...“唯心・・・ただ一つの心”...なのです。それは...“部分や切
れ目のない・・・全体が一つのもの”...なのです。これは裏返せば、自分などという
部分系は何処にも存在しないということであり...“無心”ということなのです。
|
 平
常 是 道 (へいじょうこれみち
)
平
常 是 道 (へいじょうこれみち
)